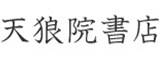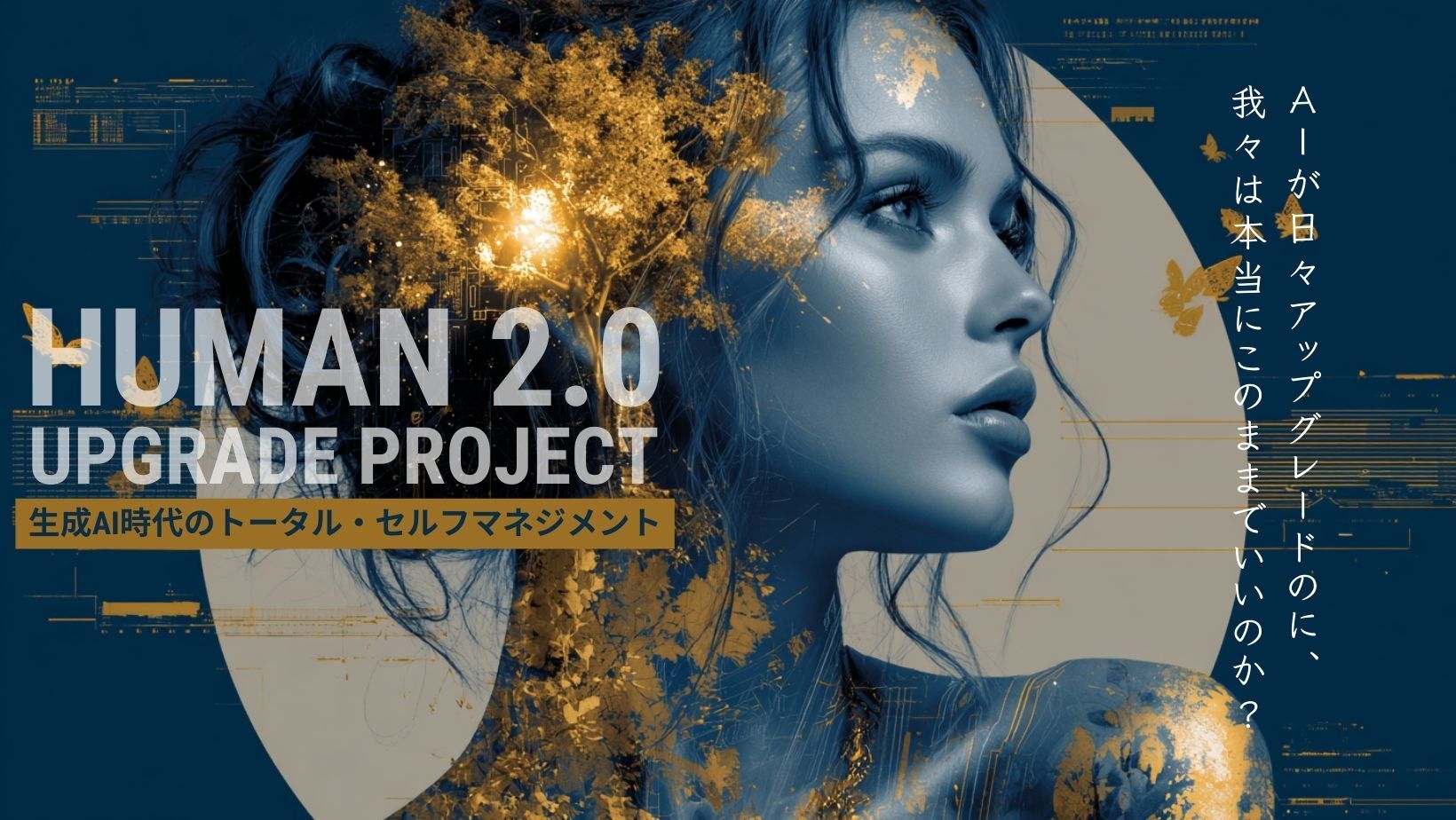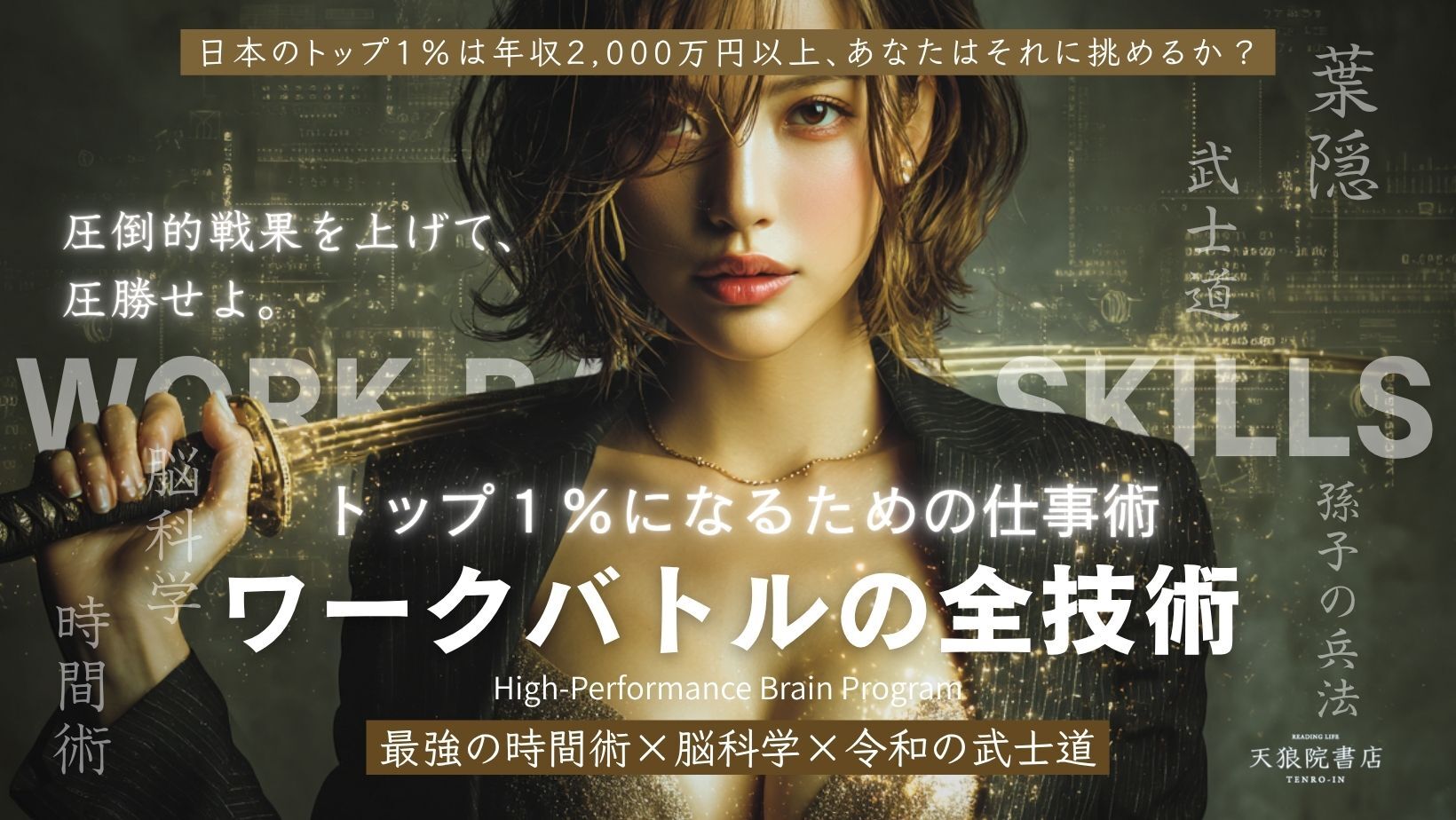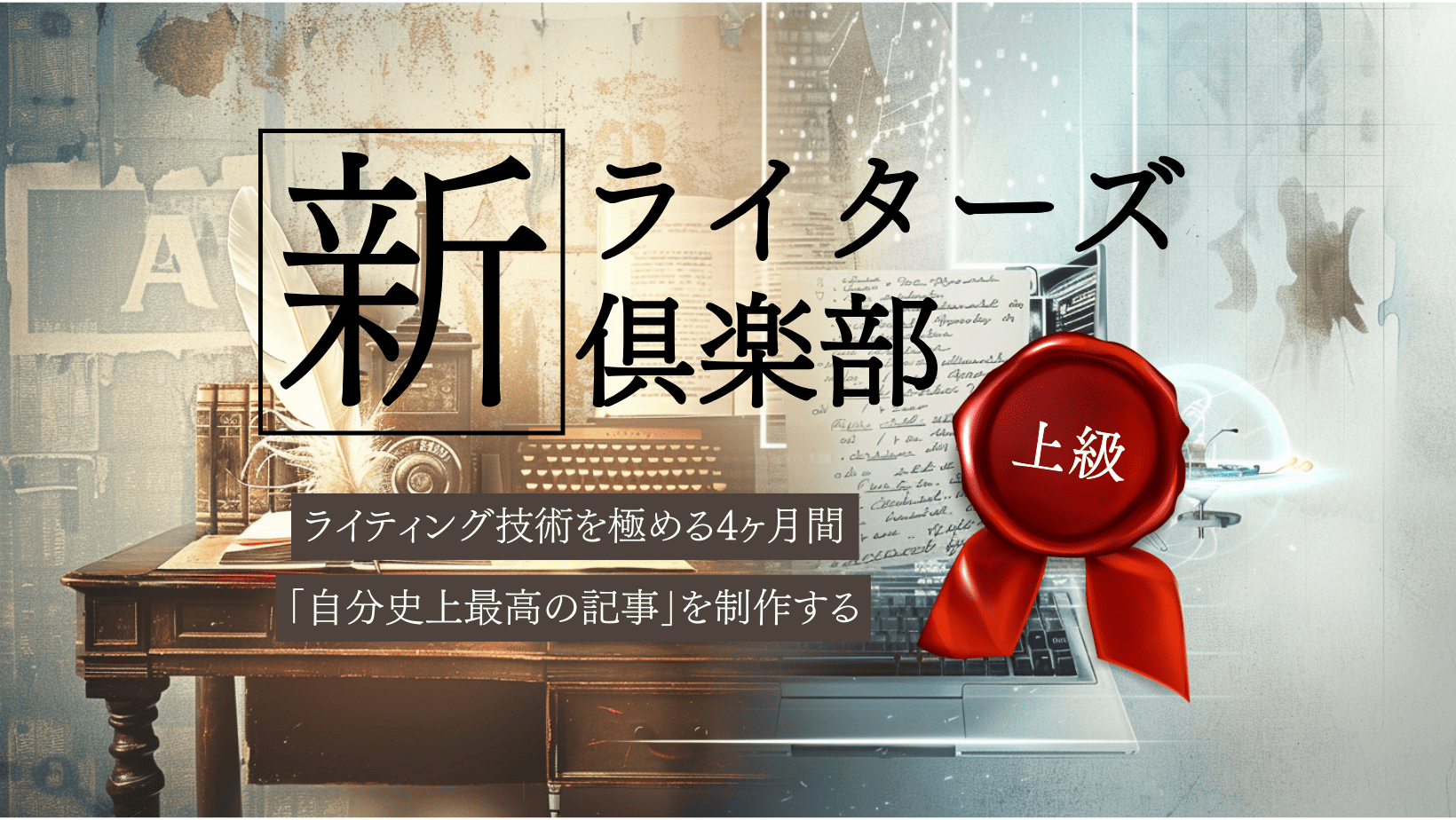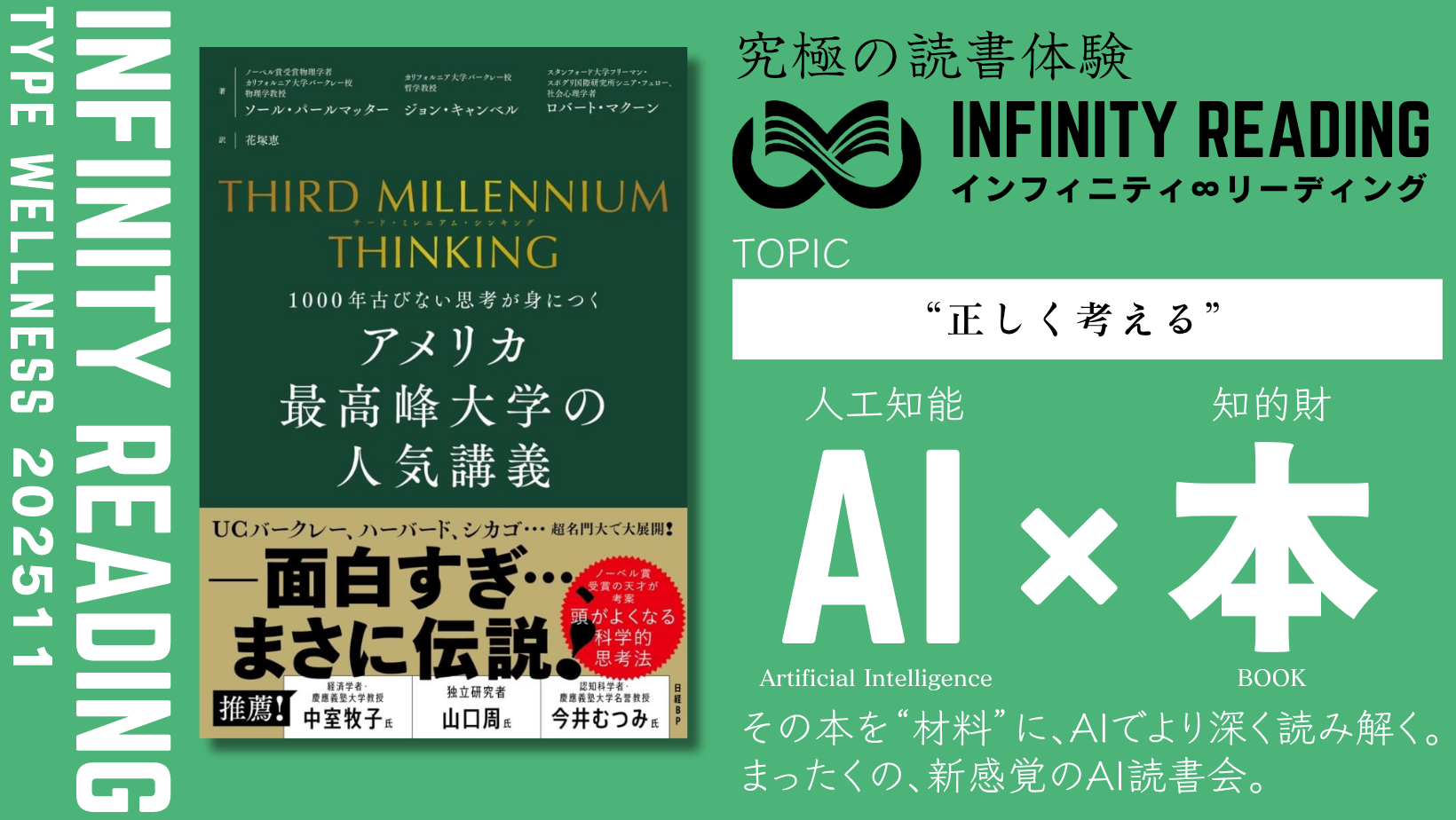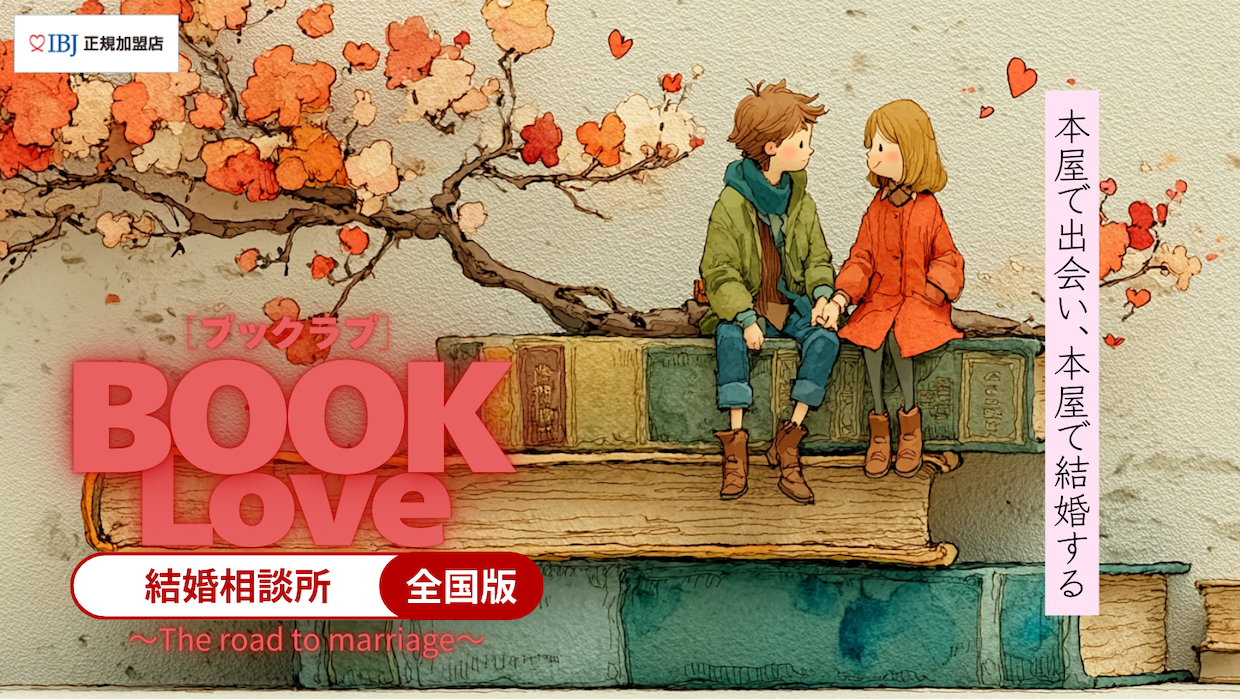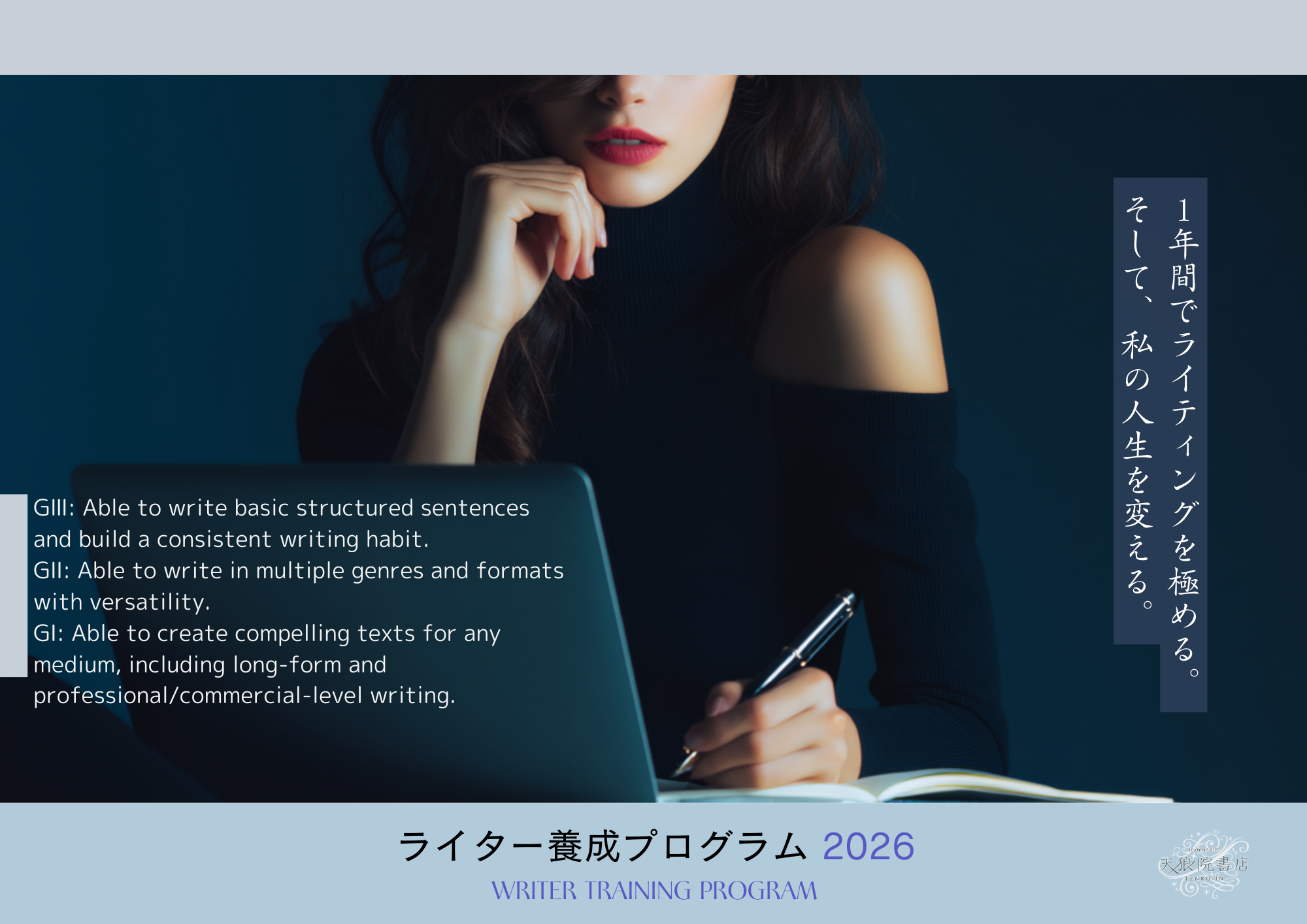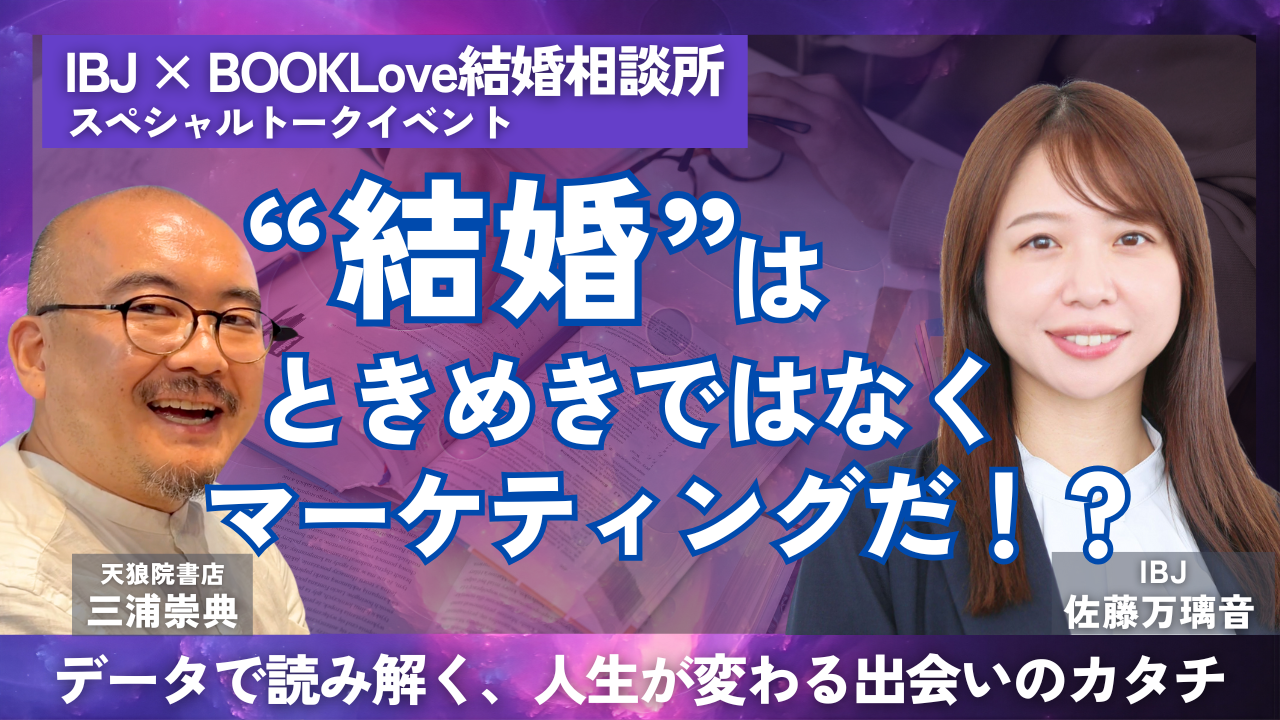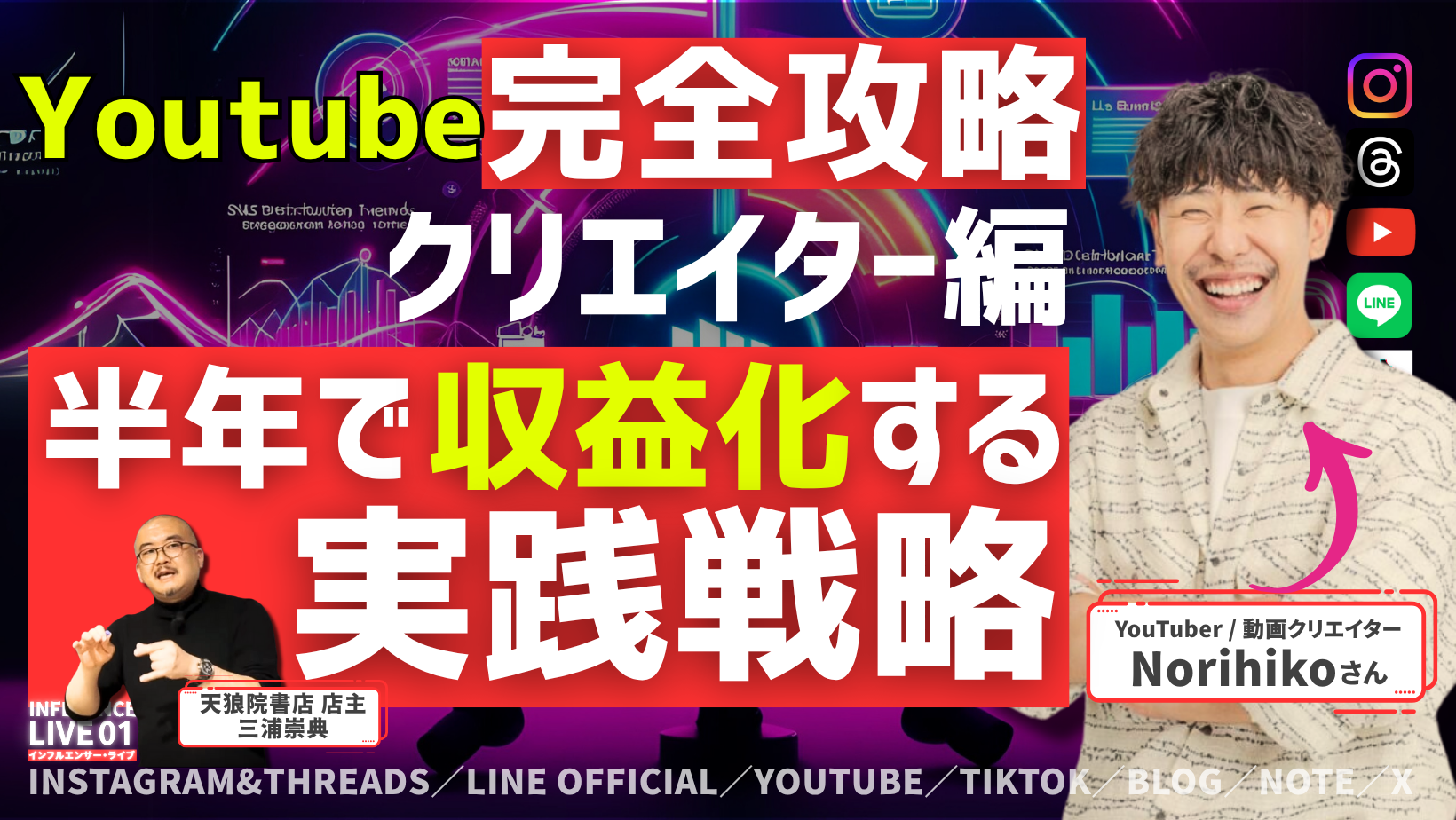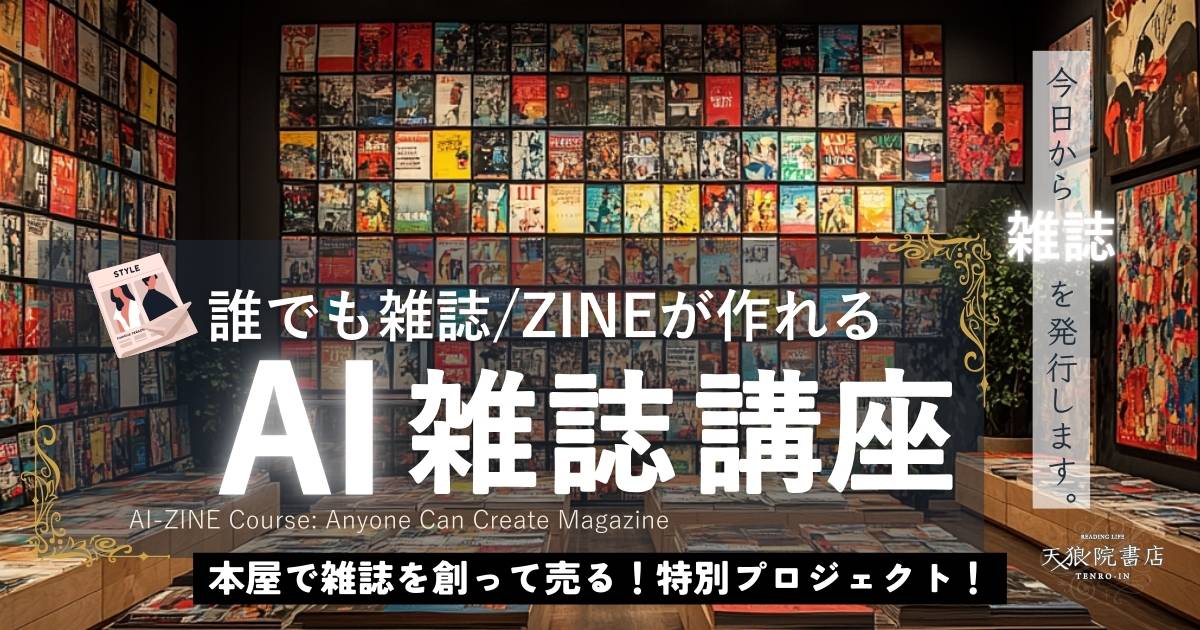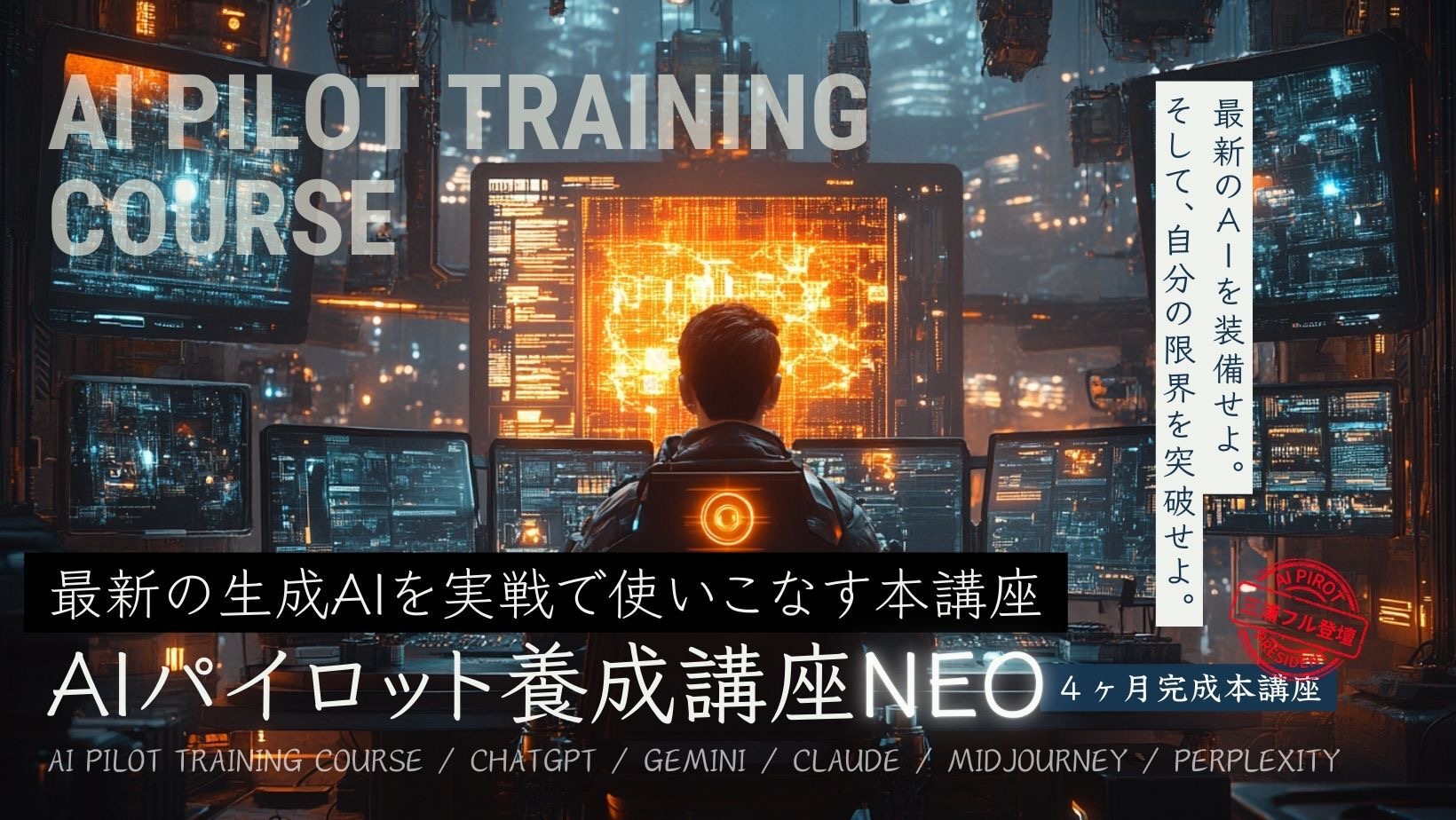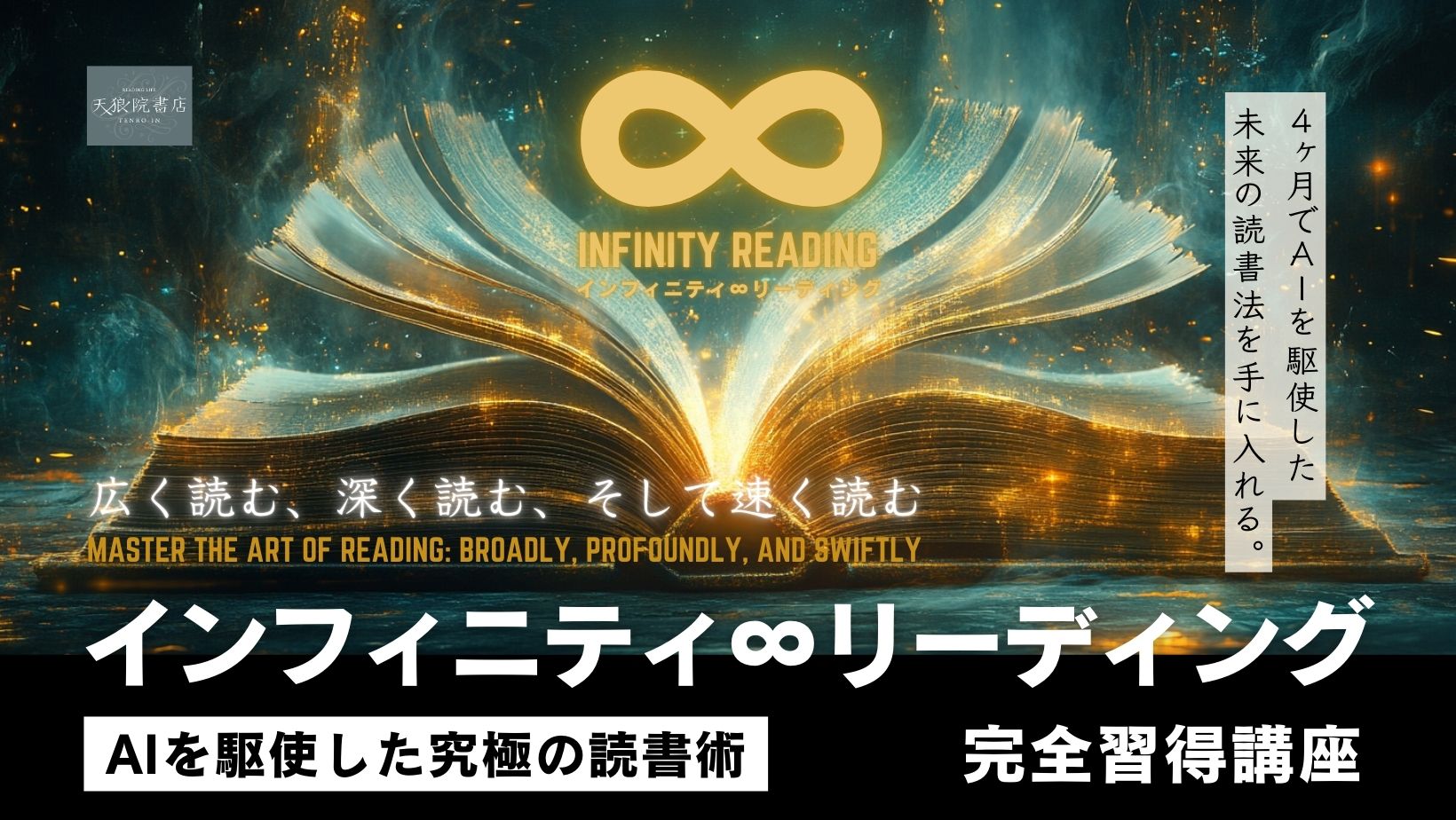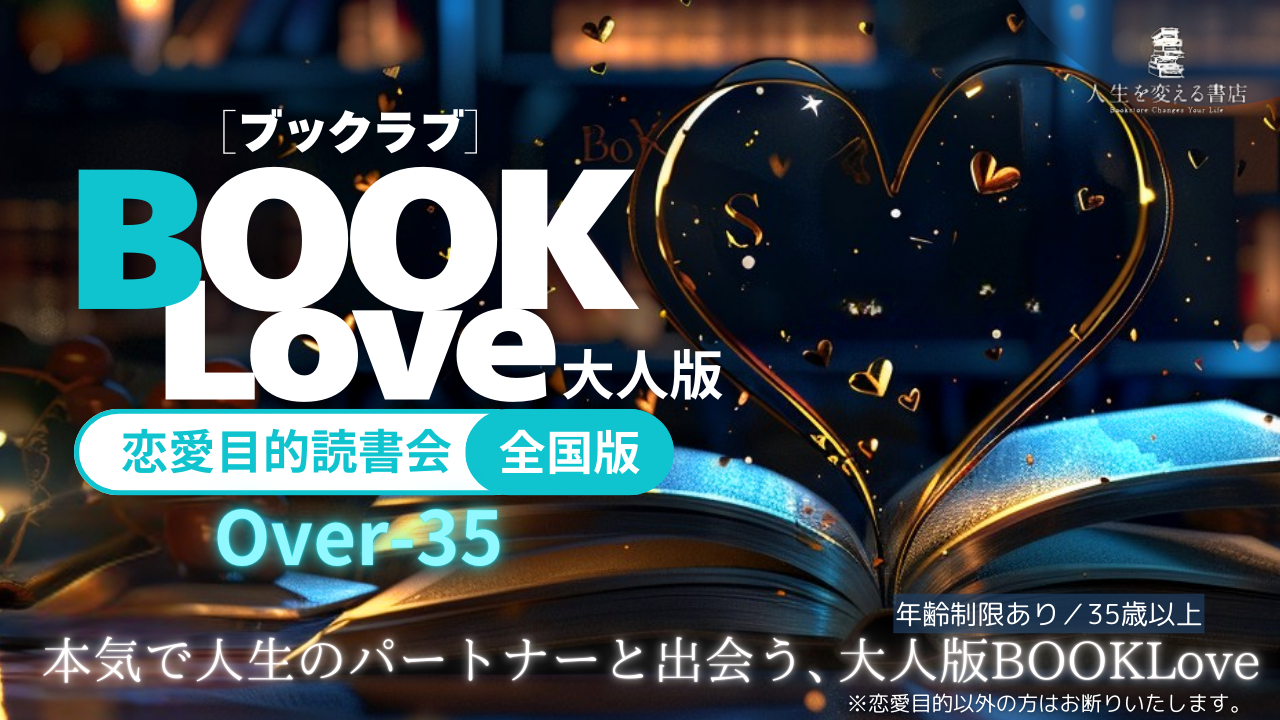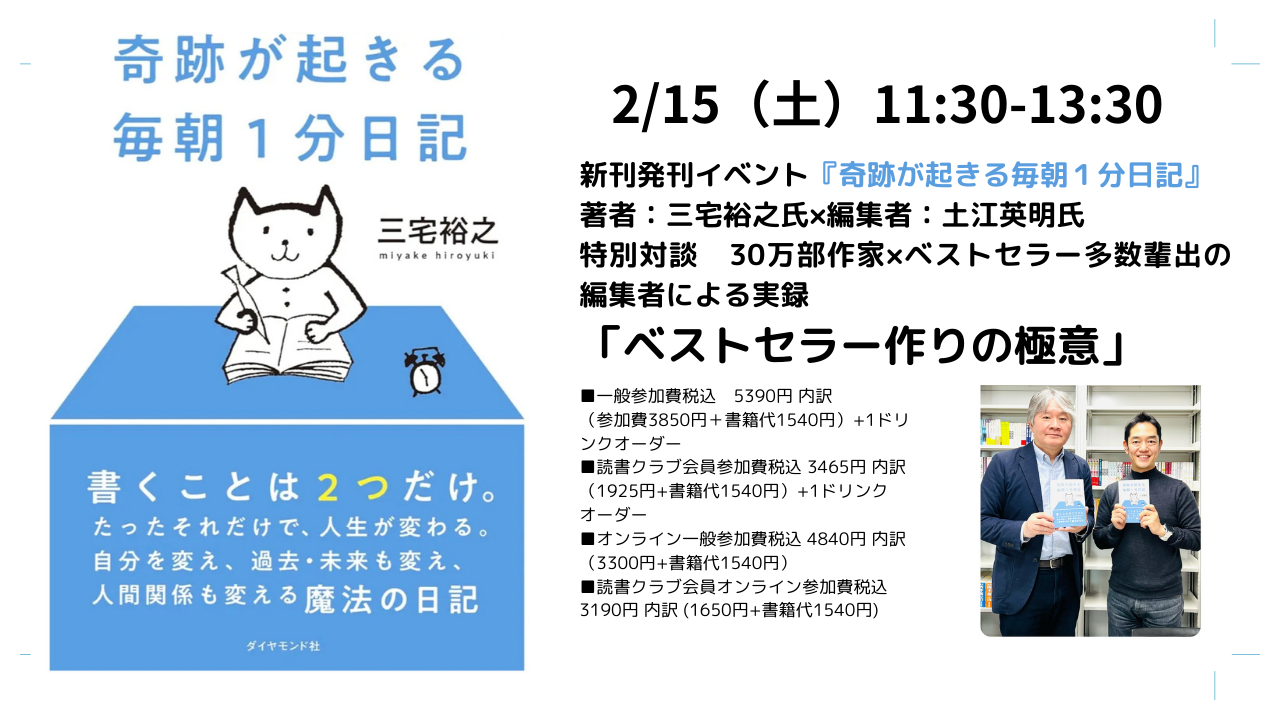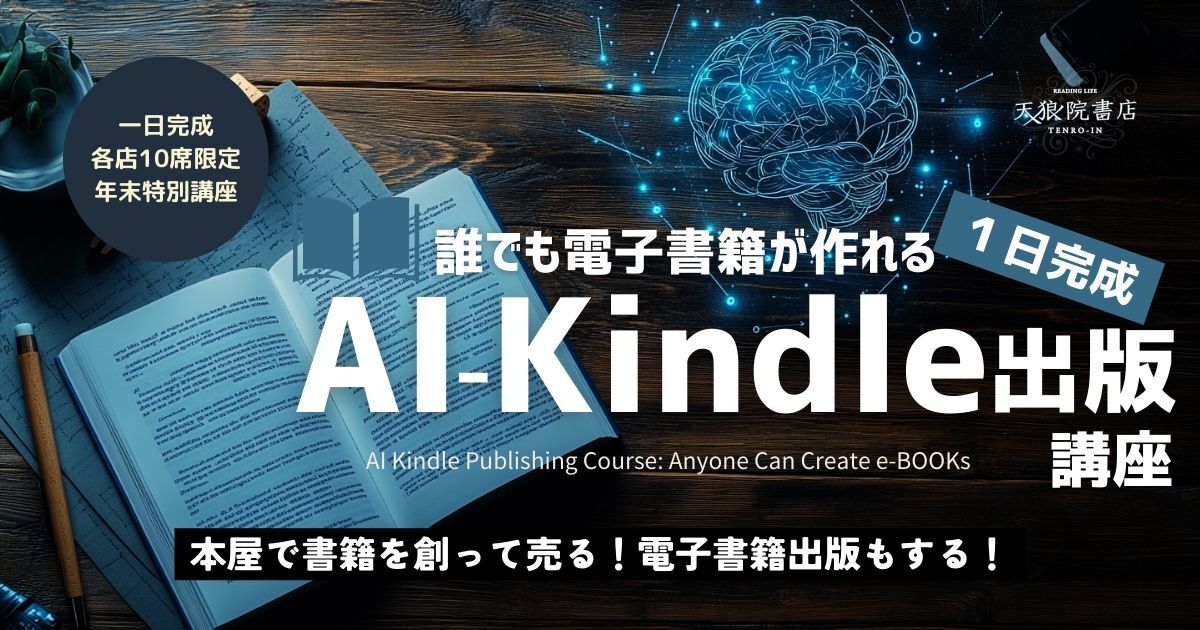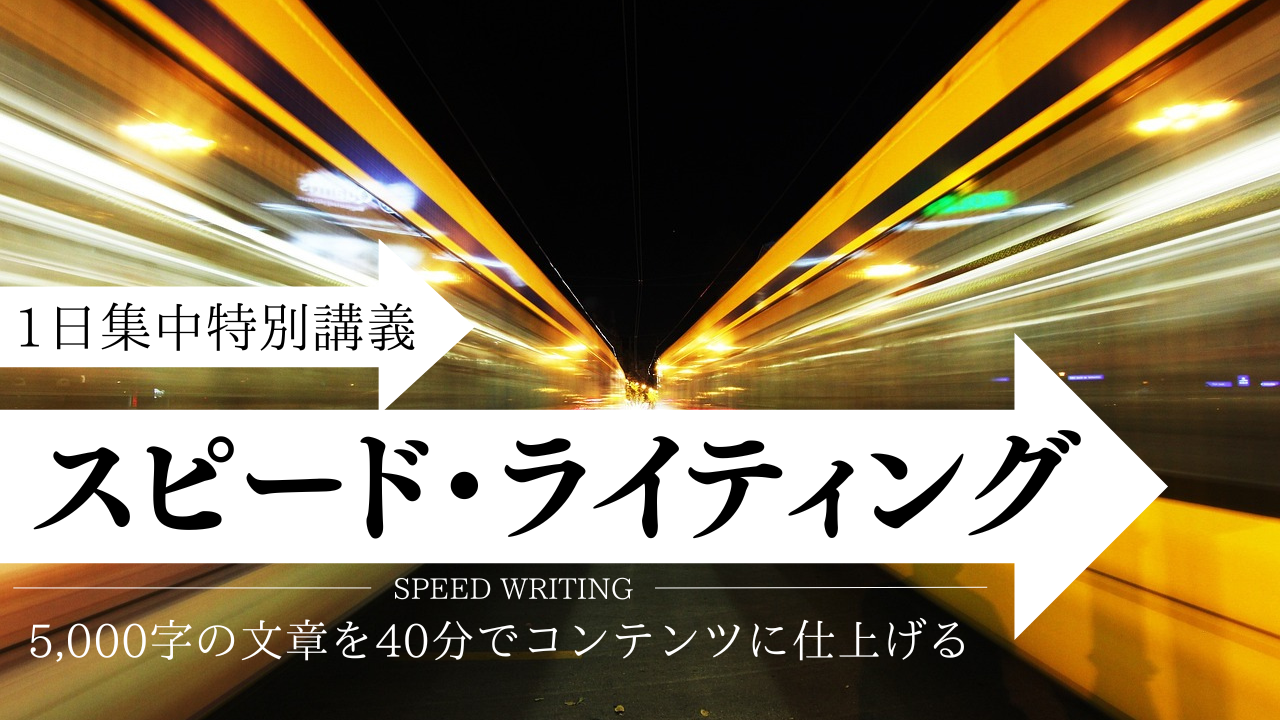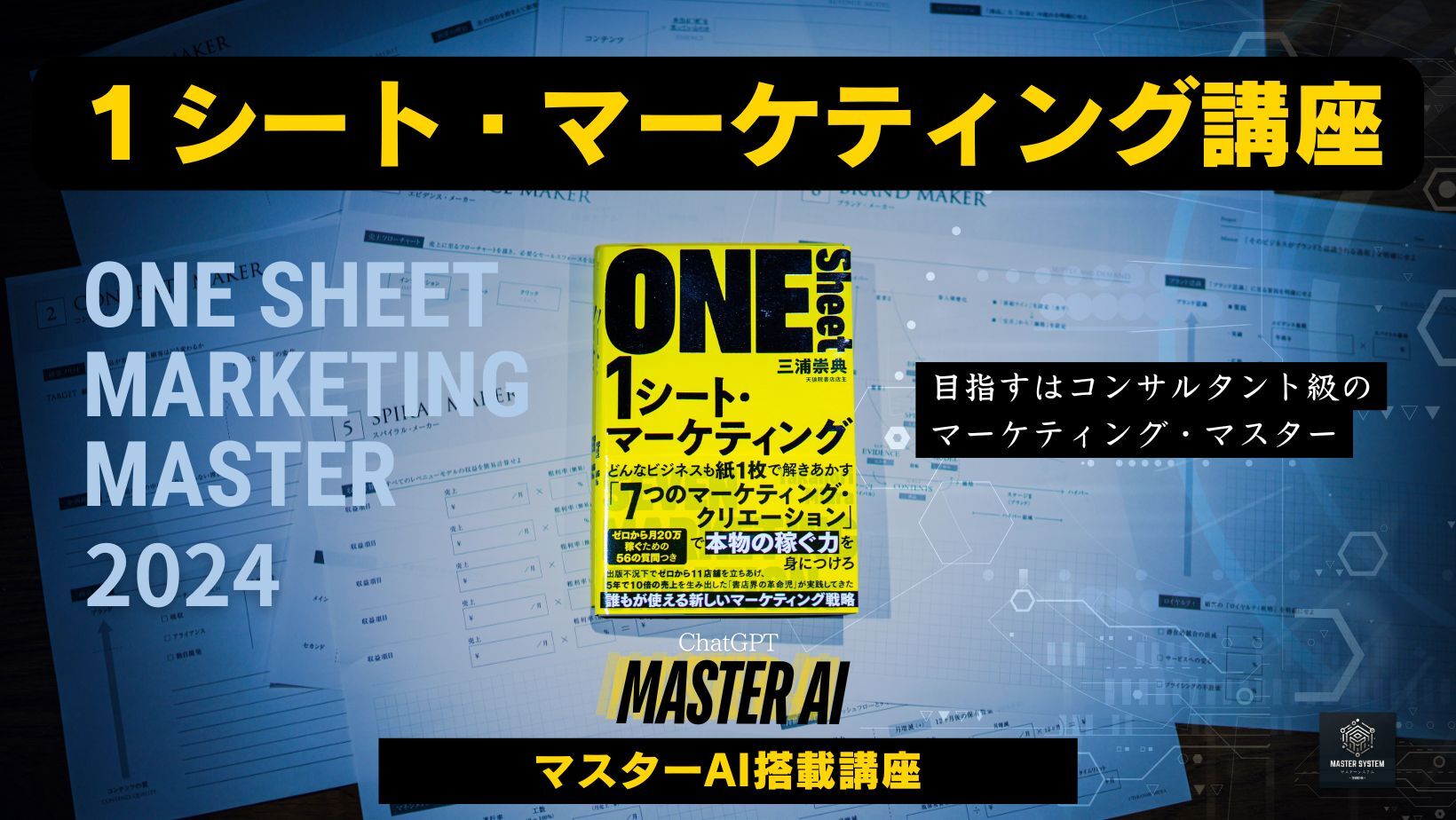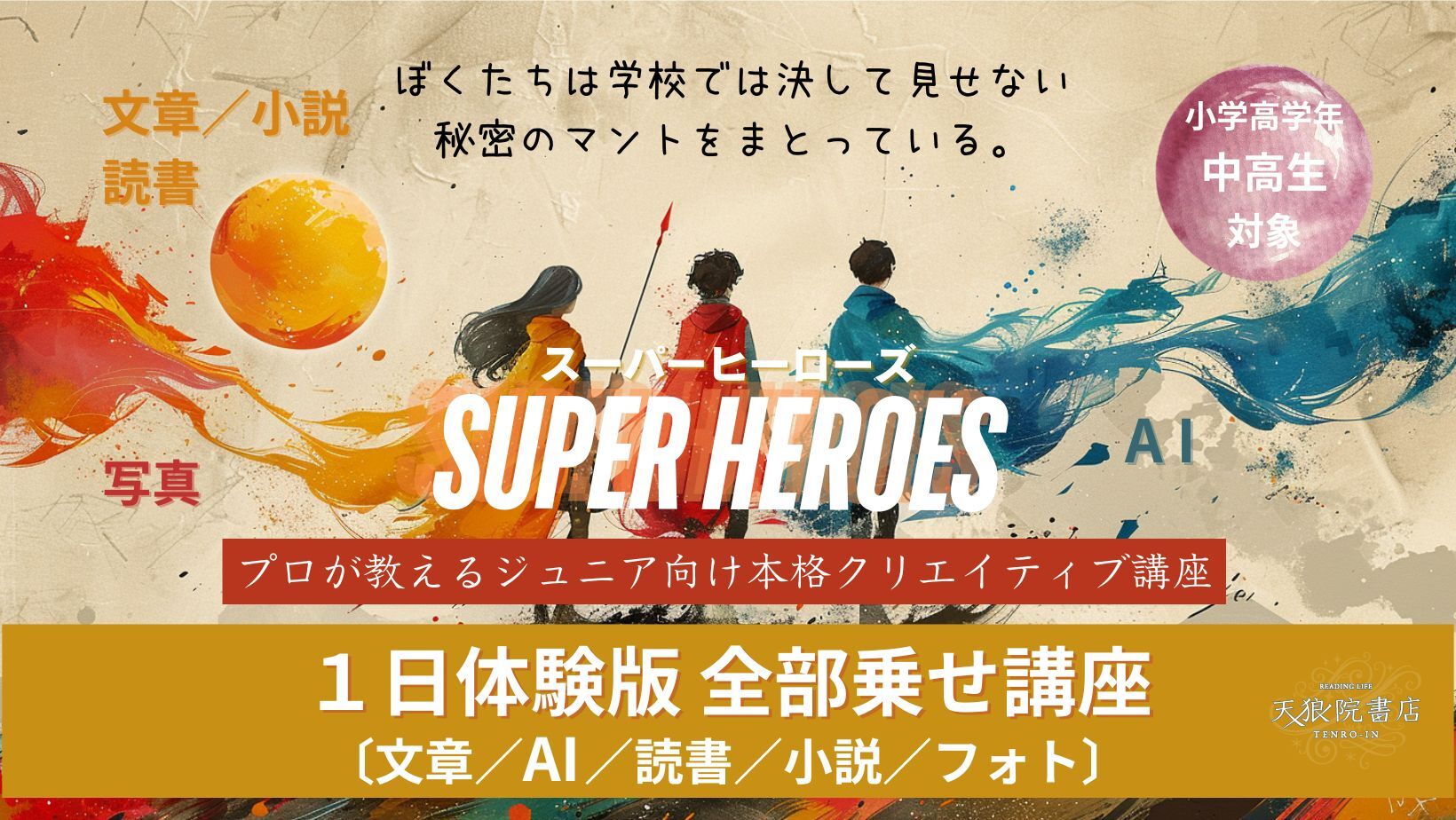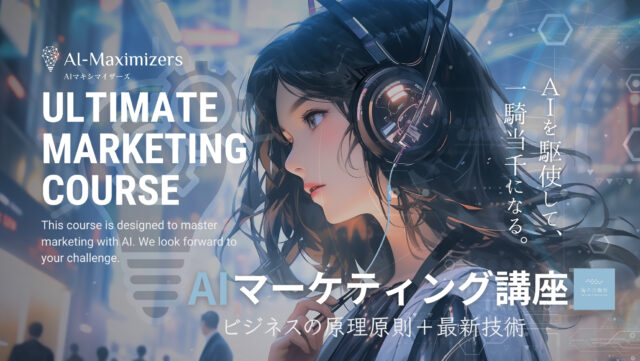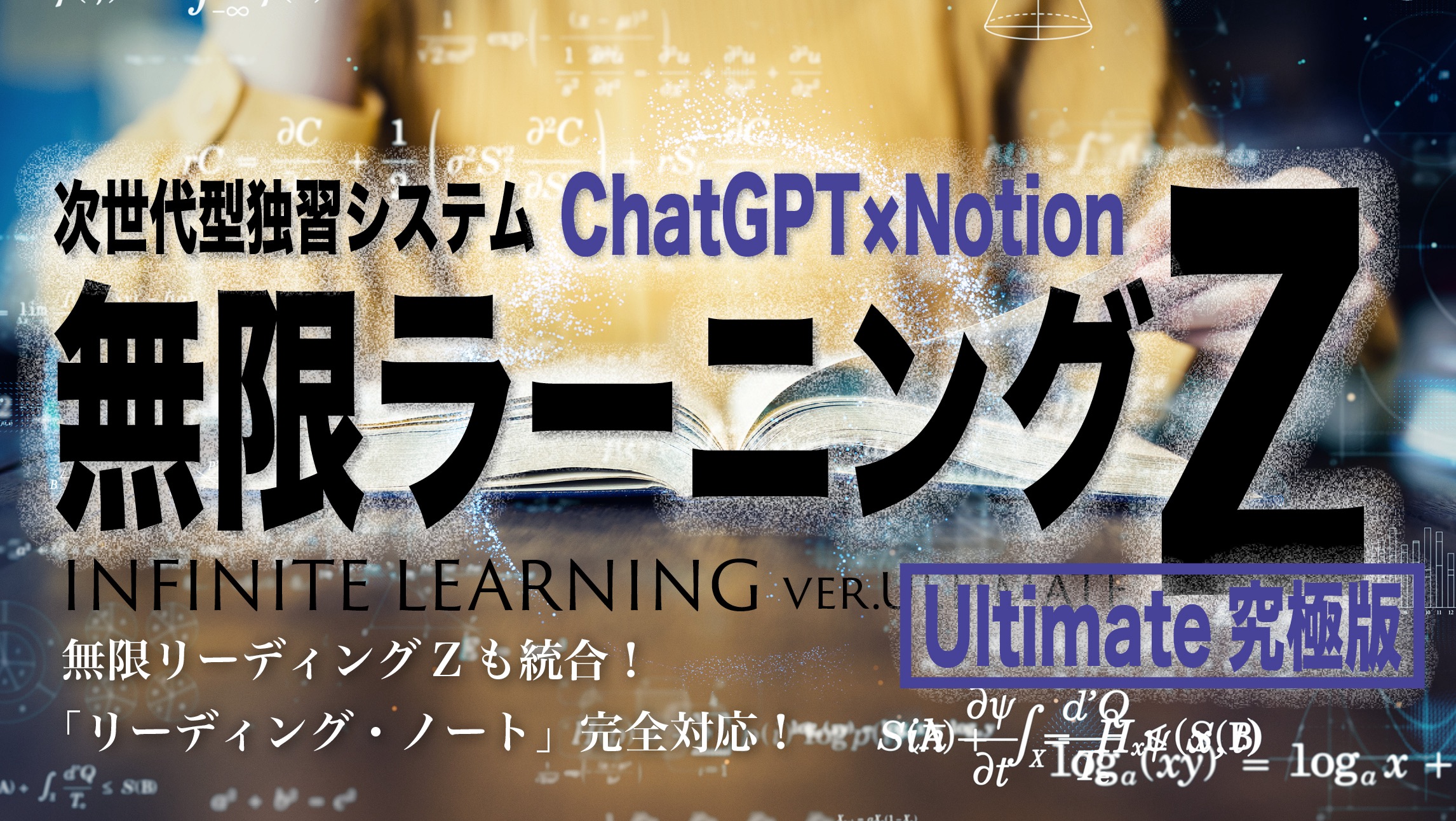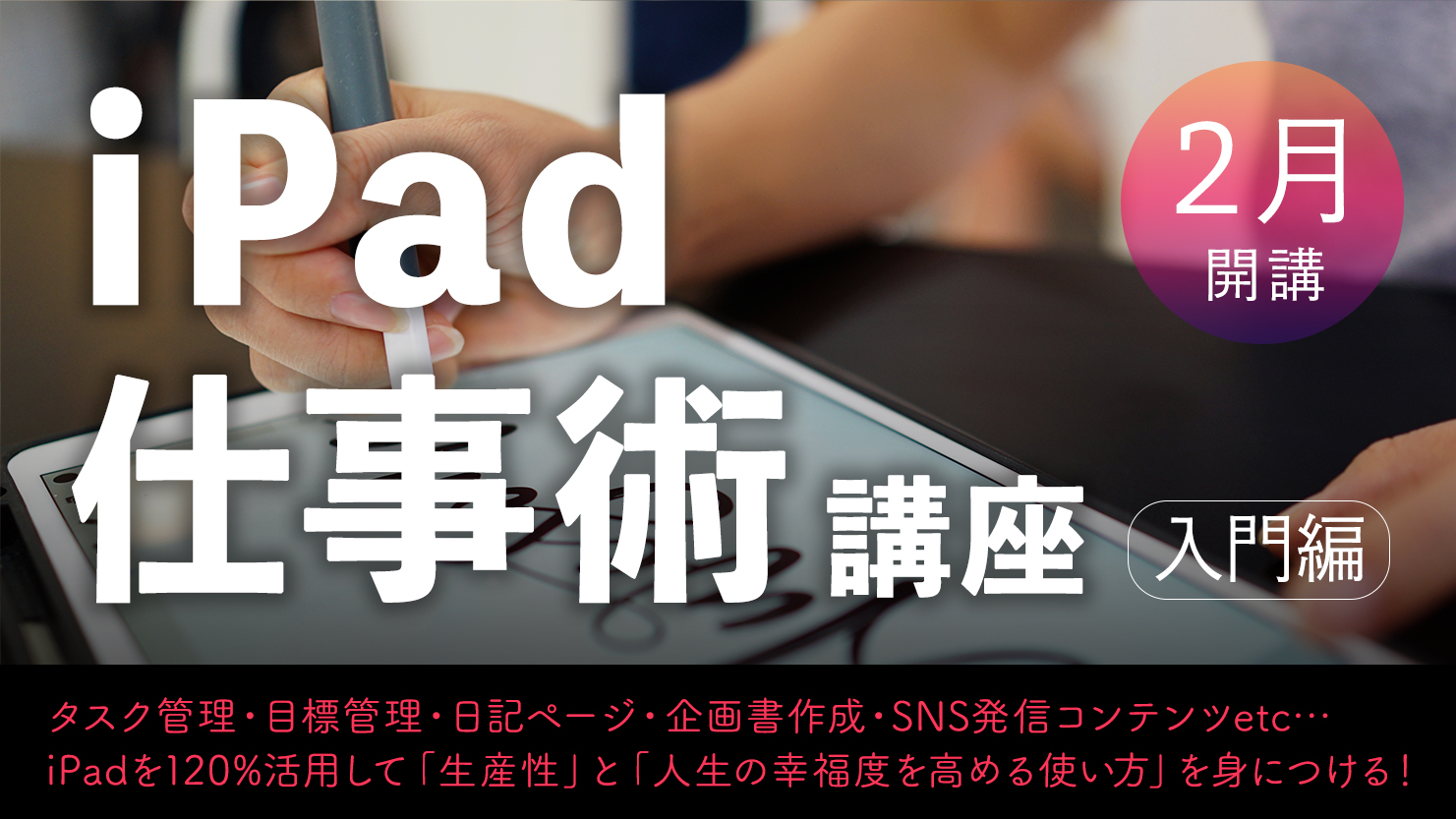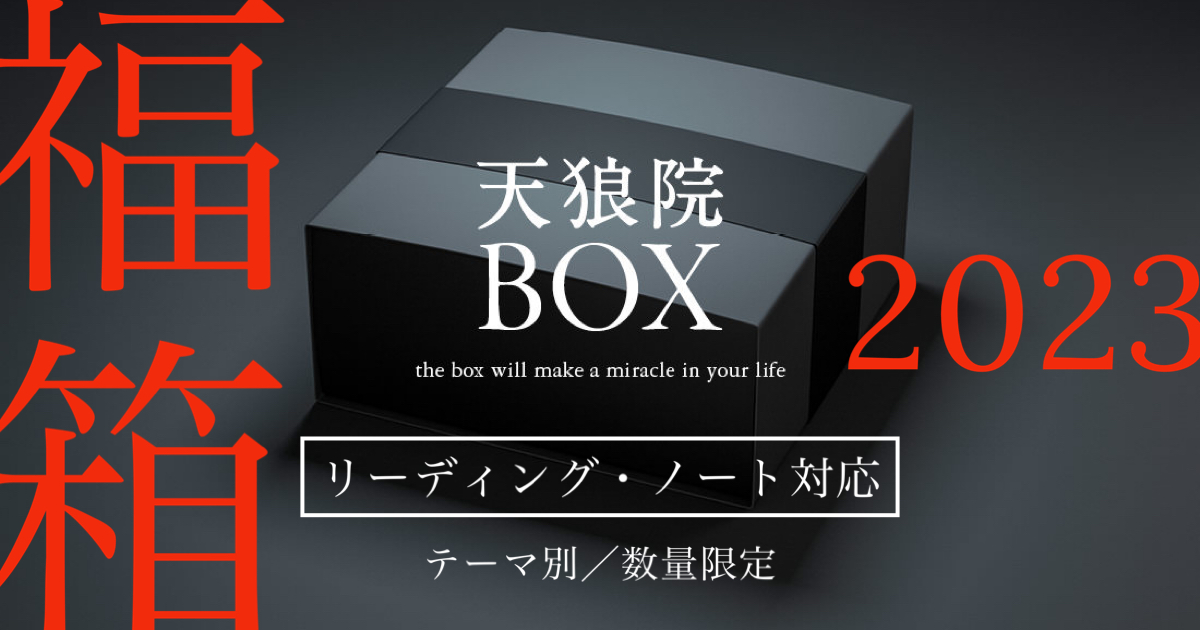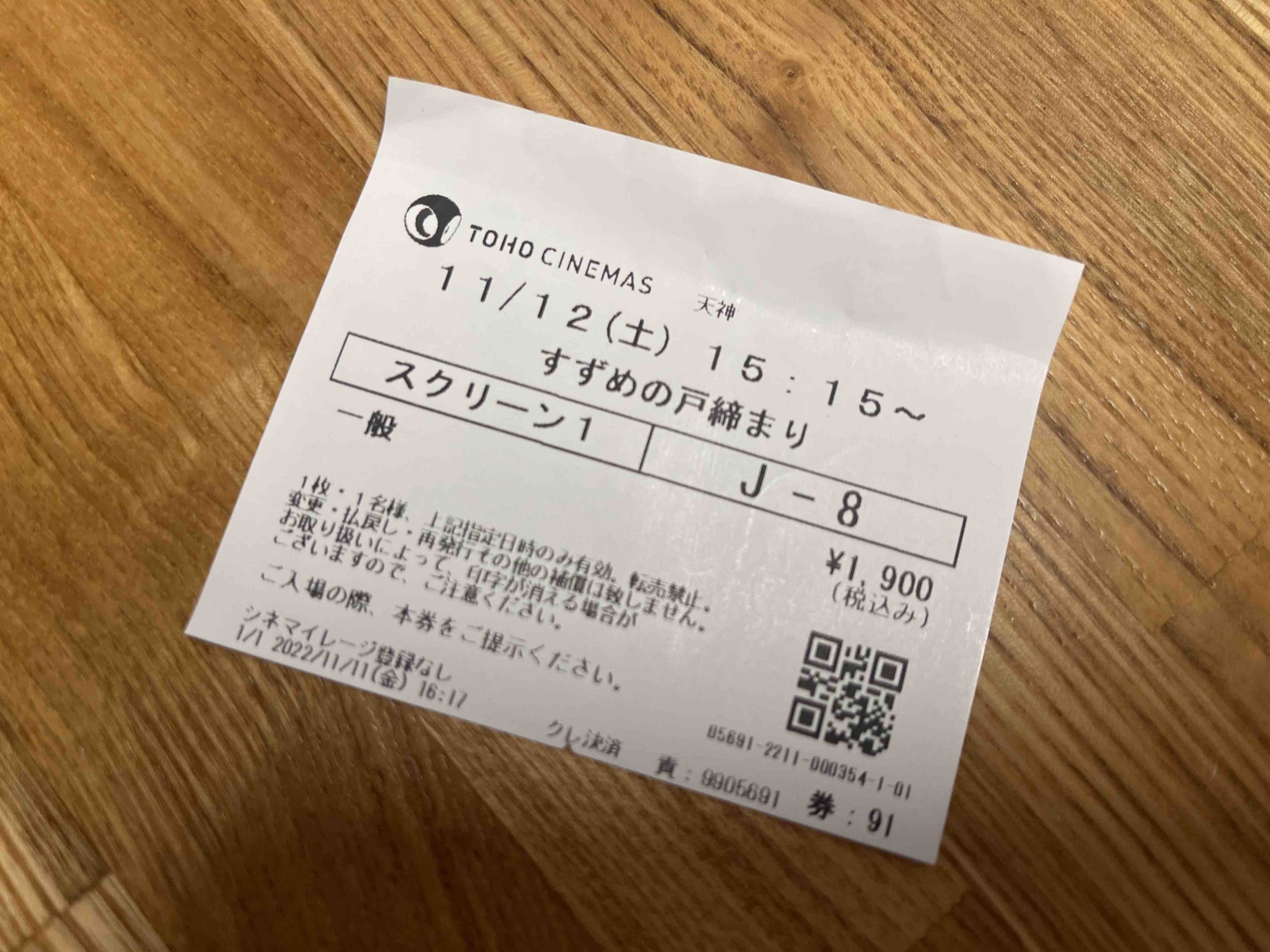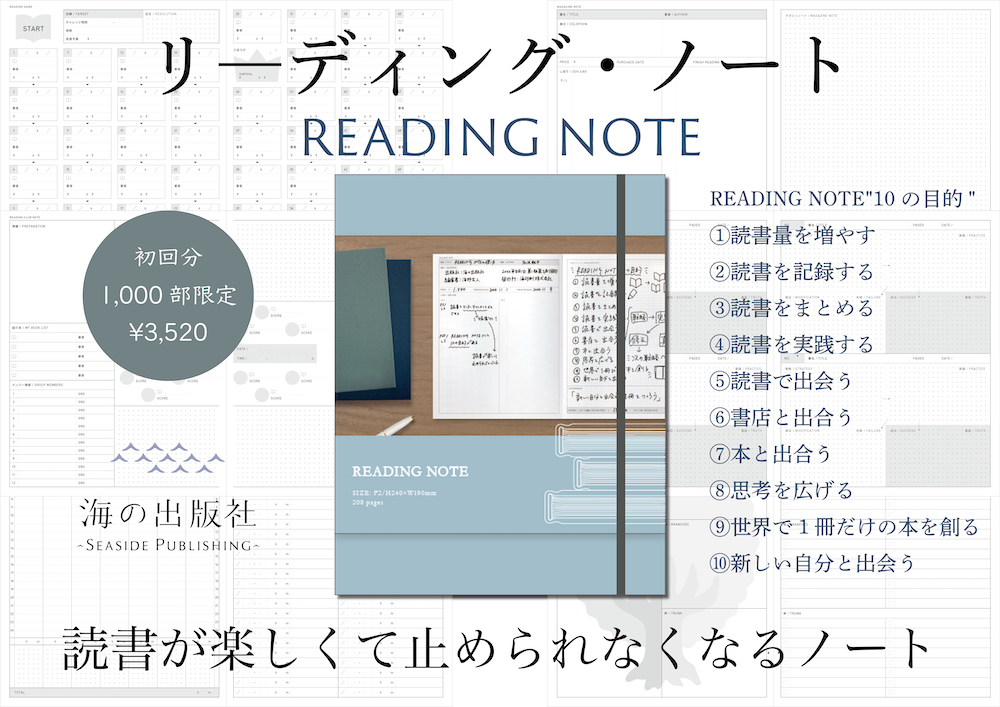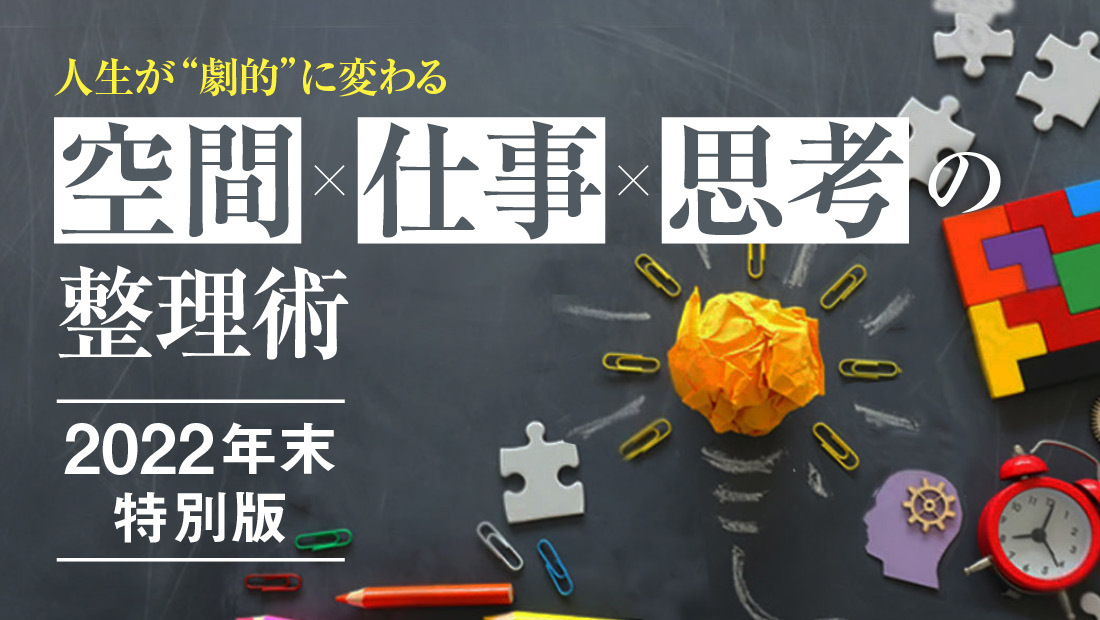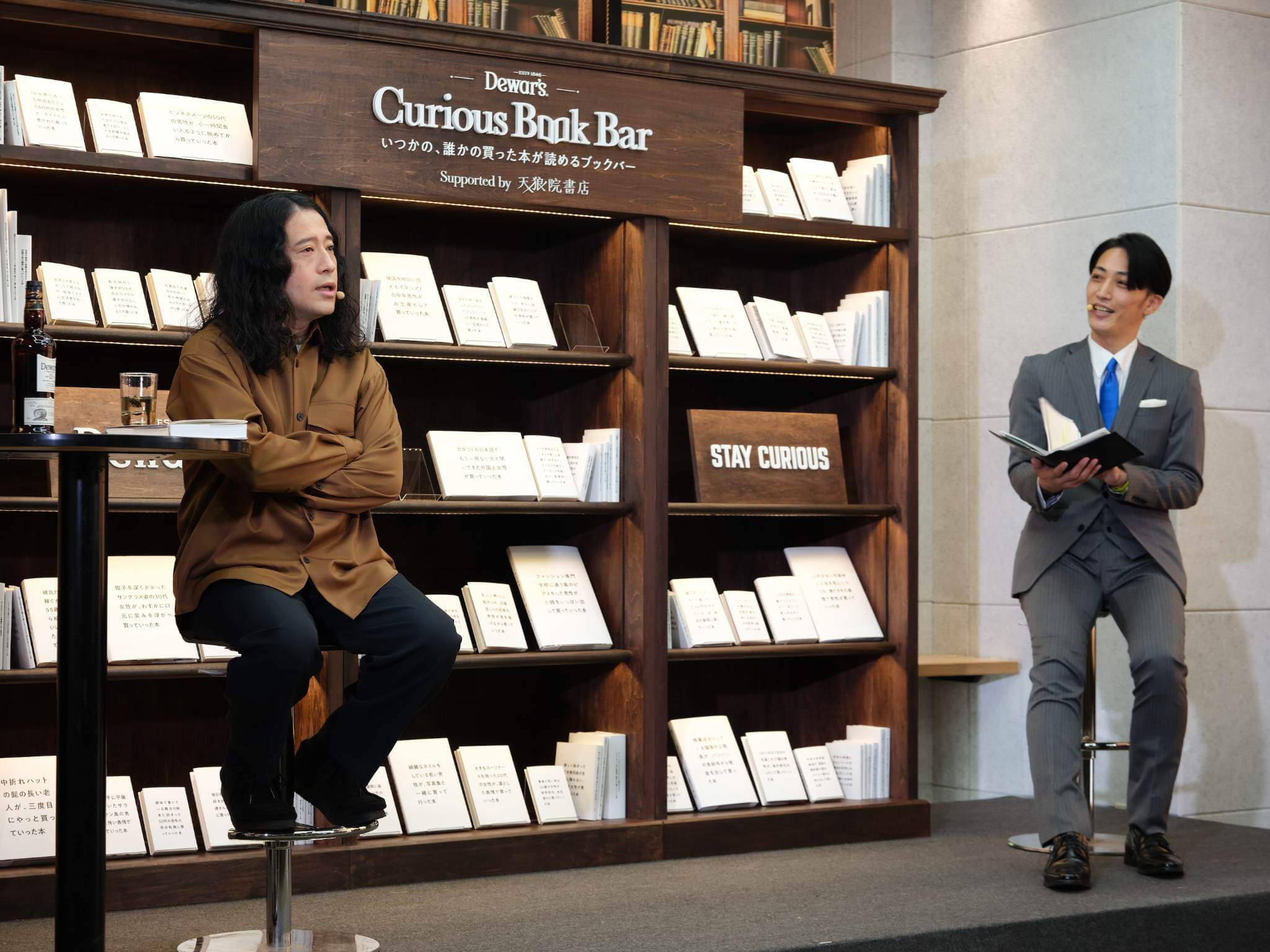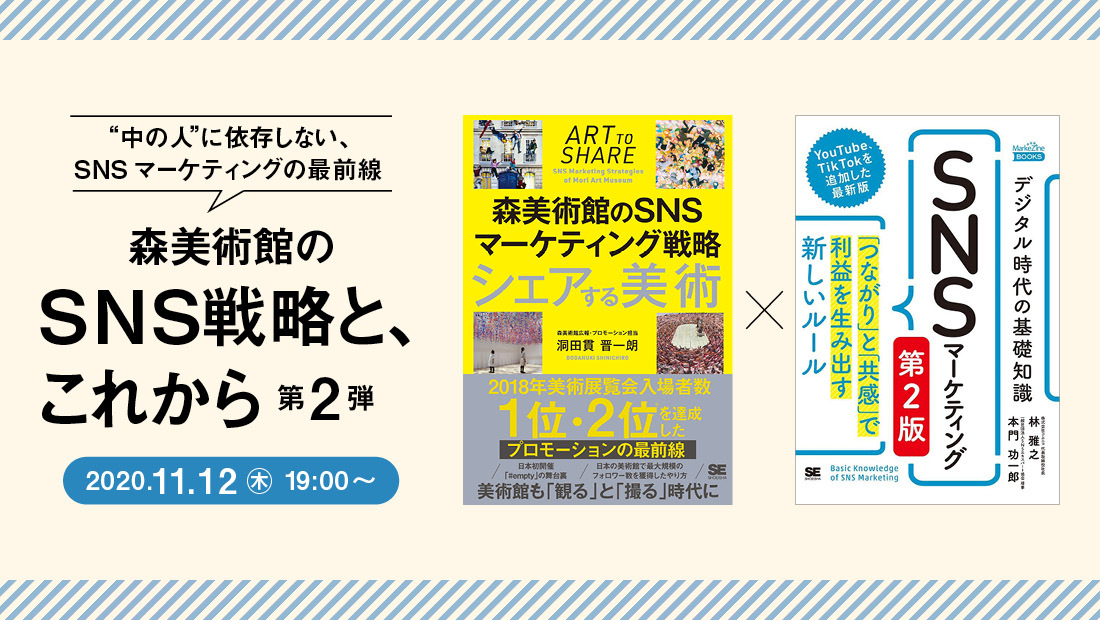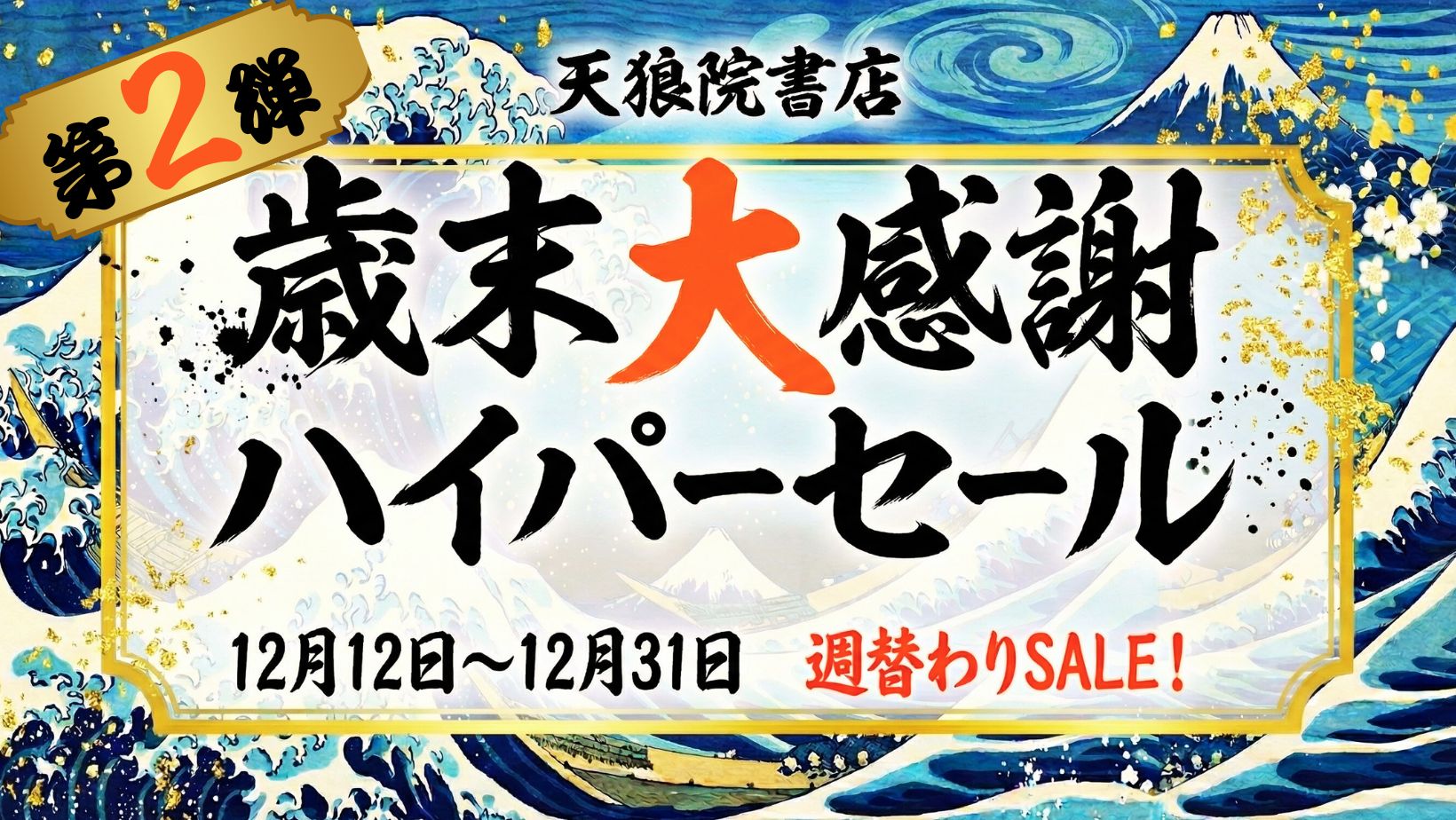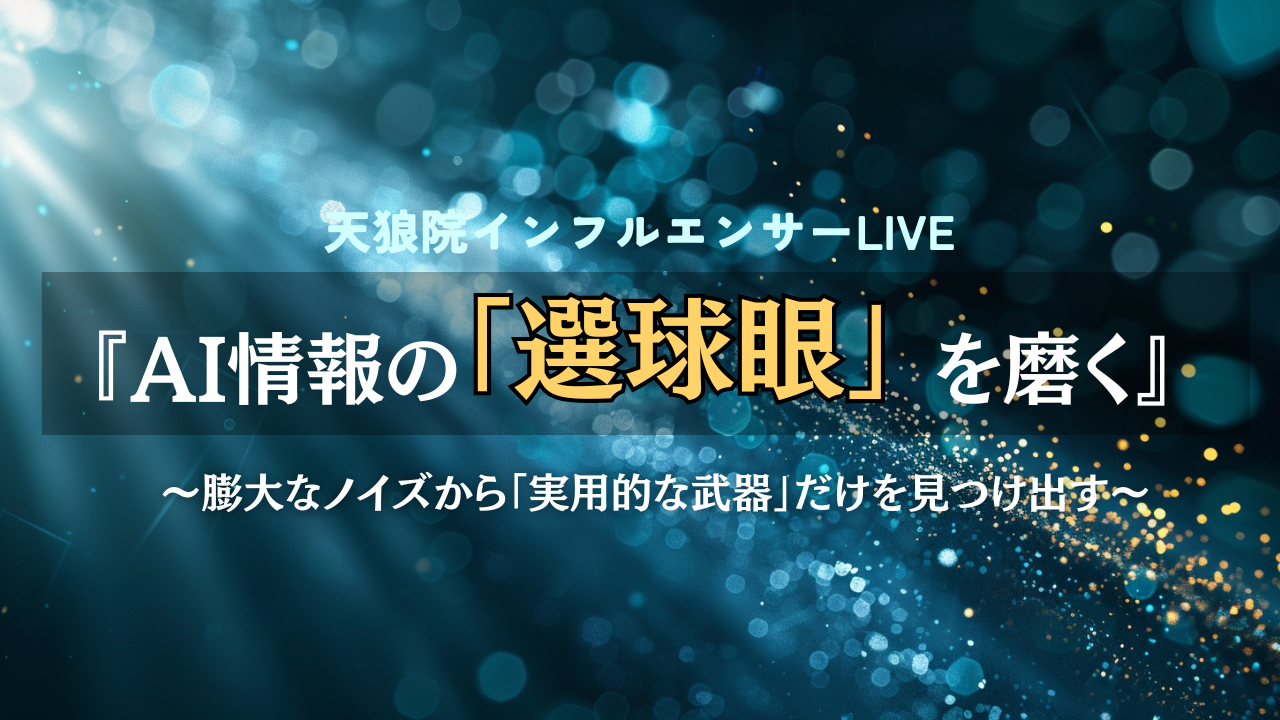日本人なら誰もがお茶を点てたら良いと京都に住む私が思う理由

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
記事:有岡 紘佑(ライティング特講)
突然ですが、皆さんはお茶、好きですか? コーヒー派も紅茶派も、煎茶がお好きな方もいらっしゃるでしょうが、ここでのお茶とは、主に「抹茶」のことです。「なんちゃらフラペチーノ」のことでも、コンビニに並ぶ抹茶フレーバーのお菓子のことでもありません。
お茶室で、ひとつのお椀の中にある緑色の、、そう、あのお茶のことです。日本人なら抹茶と聞いて間違える人はそういないでしょう。ホストが場を設らえて、抹茶をゲストのために点(た)て、お菓子と共に振る舞う。ゲストはそれを味わい、愉しむ。その一連の所作と時間と場を共有する文化、これを「茶道」と呼びます。
東京から京都へ移り住んで3年。京都の通訳ガイドとして外国人のゲストを案内する私は、日本人なら誰もが抹茶を点てる経験を人生のどこかで気軽に出来たら良いのに、そう思うようになりました。何故か。それは、私たち日本人が知らずに忘れ去ろうとしている、世界でもとてもユニークな(私達が当たり前のこととして言語化することなく守ってきた)日本人の美学が、茶道には余すところなく散りばめられている、それも計算されて。そう感じるからです。
お茶が何の役に立つのかって。もし、あなたに外国人の友人や仲間がいて、「お前の国ってどんな国なん」と尋ねられたとします。日本のことを、日本人のことを端的に表すのに、お茶ほどストレートかつダイレクトで訴求力のある文化はありません。お茶を知っているだけで、それは日本人であるあなたをグローバルな世界においてユニークな存在にしてくれます。確実に。これは実際に茶道具屋さんから聞いたことがある話だから間違いないですし、マインドフルネスや瞑想大好きな外国人は、興味を示します。灯台下暗し。当たり前のことほど、その価値に気づくことは難しいものですね。
さて、こんな偉そうにお茶をアピールする私も、僅か数年前まで、茶道の茶の字も学びたいとは思いませんでした。着物を着て正座をして(正確には正座は明治以降、女性が茶道の世界に入るようになってからだと言われています)、型を教わる、堅苦しくて小難しい文化。その程度の印象でした。もちろん、自分が今練習者としてお茶に関わることになってからは、その認識は180度変わりましたけれど。
えっ、そうなの。お茶って良いものなの。百聞は一見に如かず、良いものですとも。1ミクロンでも興味を持ってくれた方に、お茶を学ぶ良いことを3つ挙げますね。1つめ。抹茶の美味しさに気づけます。旬の抹茶と温度管理されたお湯で、抹茶は「本当にお茶なのか」と思うくらいのインパクトを与える飲み物に変わります。インバウンドで押し寄せる外国人は、購入できる小さな40グラムの抹茶缶を見てもっと買えないのかと残念がるらしいですが、抹茶というのは言うなればバターみたいなもの。茶葉を挽いて直接飲むので日持ちがしません。だから、お茶の産地に近いところでしか、美味しい抹茶は飲めないのです。お茶處である宇治を抱え、長いこと都だった京都であるからこそ、美味しい抹茶が飲めるのです。2つめ。四季の移ろいを感じられるようになります。お茶をしていると、季節ごとに和菓子やお花が頻繁に変わります。知らず知らずのうちに、季節を天気や気温以外から感じ取る感性を持てるようになります。四季と来たら和歌、和歌と来れば能楽。どれも互いに関連性があるのです。更にそこに、神道や仏法、禅のエッセンスが絡んできます。特に、禅とお茶の共通点は非常に多くて、外国人がお茶に興味を持つ理由はここにもあると思います。
3つめ。自分をセンタリング(中央に戻す)できるようになります。私達は日々大量のストレスに晒されて暮らしています。自分が何者であったか、本当の自分はどんなだったかを忘れるほどに、何かに自分を切り売りしていませんか。お茶を点てていると、不思議と心が落ち着き、段々とお茶を点てる自分を客観的に見られるようになるのを感じています。自分のコンディションでままならないこともありますがそれは修行が必要ということで。
最後に、お茶の無限の広がりを表す利休のエピソードを紹介します。千利休。言わずもがな、侘び茶から現在の茶道の精神概念を含めた基盤を作りあげた桃山時代の茶人です。利休には戦国時代の武将をはじめ、多くの弟子がいましたが、私が聞いて衝撃を受けた利休と弟子の問答に、こんなものがあります。
ある時、まだ入門して間もないある弟子が利休に尋ねました。
弟子「先生、先生のようにお茶を点てられるようになるには、どうしたら良いのでしょうか」
利休「ただ、お茶を点てることです」
数年後、お茶に小慣れて来た弟子は、更にその先のレベル、侘び茶の深淵に辿り着くためにという意味で、同じ問いを利休にします。
弟子「先生、お茶を学ぶことx年。更なる高みに到達するために、何をしたら良いのでしょうか」
利休「ただ、お茶を点てることです」
このような答えのないやり取りを「禅問答」と呼びます。私はお茶を学び始めて少し経った時にこの話を聞いて鳥肌が立ったことを覚えています。同じ弟子の、同じ質問に対して、同じ言葉での受け答え。しかしそれが奥底で指す意味の大きな違いが分かる気がしたからです。
禅問答では、答えを自分の外ではなく内に発見します。師匠と弟子のやり取りなら、師匠は答えを言いません。代わりに、弟子に気づきを与えるためのキッカケをさりげなく表現します。全ての答えは自分の内にあるという禅の本質が、このエピソードにも表現されていると思うのです。
お茶を上手に点てられるようになりたいのなら「ただお茶を点てることだけだ」、後にも先にもそれしかない。これ以上シンプルで示唆に富む答えは無いのではないかと思うくらいの奥深さです。利休の凄さ、「レベチ」感をこれでもかと言うくらい感じます。
如何でしたか。茶道、そして、お茶の深淵なる世界を少しでも感じていただけたら嬉しいです。そんなあなたにこそ京都へお越しいただきたい、ガイドの私はそう思っています。お茶に関係するツアーもコンテンツも沢山ありますよ。ご縁の町、京都でお待ちしています。
***
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
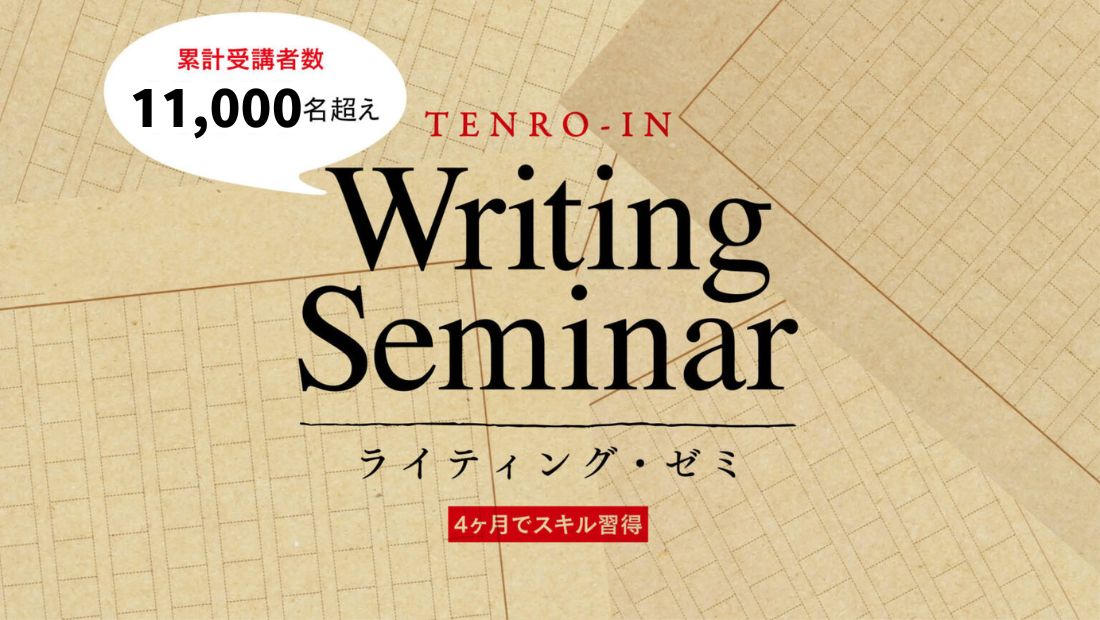
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)
TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792
営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F
TEL:0466-52-7387
営業時間:
平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00