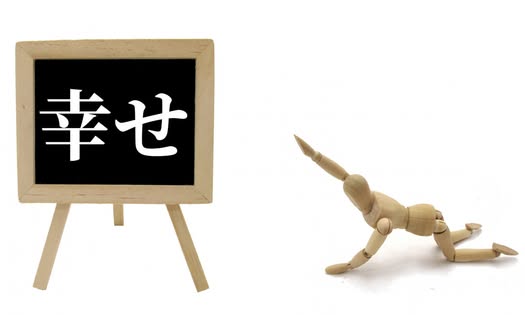海霧

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【6月開講】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ《平日コース》」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
記事:海風 凪(ライティング・ゼミ日曜コース)
※この記事はフィクションです
眠っているような町だといつも思う。人どころか、猫一匹姿が見えない。
通りには、ウナギの寝床のような細長い古い家が並ぶ。
出格子の掃き出し窓。黒い板塀の家からは、三味線の音がかすかに聞こえる。
「糀」と書かれた看板が軒先に吊るされている家は、もう十年以上前に店を閉めた。糀屋の隣の豆腐屋には客の姿は見えない。
明治のころに北前船の交易で財を成した豪商の家が、文化財となって通りの中心にどんと構える。
遠い昔の夢のあと。
春の柔らかい日差しが、包み込むように通りに降り注いでいる。
施錠がされていないガラスの引き戸を開けながら、
「ばあちゃん、こんにちは。来たよ~ 」と声をかける。
ばあちゃんの家は、履物やだった。靴屋じゃなくて「はきものや」。
数年前に店は閉めたが、売れ残りの履物が陳列棚にいくつも置かれたままになっている。
トン、スーツと引きずるような音がして、ばあちゃんが、ゆっくりと店の奥から出てくる。相変わらず髪はきれいに結い上げてある。色が白く、切れ長の黒目勝ちの目。おちょぼ口で、若いころは、さぞかし美人だっただろうと思う。
「ばあちゃん、調子どう? 足いたい?」
ばあちゃんは足が悪い。ヘルパーとして、ばあちゃんのところに通い始めて2年になる。
「ああ、よしちゃん。いつもありがとね。あったかなったら、だいぶようなったんやけど、そんでもやっぱり膝痛いがやちゃ」
「そうなん。なら、そこ座っとって。掃除するからね」そう言って掃除に取り掛かる。
ばあちゃんはきれい好きだ。足が痛いだろうに、部屋はきれいに片付けられている。汚れものがたまっていることもない。ただ小柄なのと足が悪いので、手が届かないことも多く、そんなところをお手伝いしている。
ばあちゃんは足が悪いので、あまり出かけられない。人恋しいのか、私が掃除している間絶え間なく話しかけてくる。話が聞こえなくなるから、掃除機ではなく箒で掃除をする。掃除機の方が早く終わるのだろうけど、ばあちゃんが求めているのは家事の手伝いよりも話し相手なのだ。
ばあちゃんの話は、遠い昔の娘時代のこと、結婚したばかりの旦那さんを戦争で亡くしたこと、生活のために「はきものや」を開いた時のこと。
結婚相手は親が決めた。一度会っただけで、すぐに結婚。そして一年もたたないうちに戦地へ行った。恨むでもなく、後悔でもなく、淡々と過去の日々を話してくれる。
けれどその日は違った。
「よしちゃん、これ捨ててほしいがやけど」
ばあちゃんは、手にブリキの小箱をもっていた。箱ティッシュくらいの大きさの赤い箱。何か文字が上に書いてある。
「これ、もうそろそろ捨てんならんと思って」
「ばあちゃん、これ何? 」
懐かしむように、人気のない通りに目をやり、
「昔の話や」
そう言って、ばあちゃんは遠い昔の恋物語を聞かせてくれた。
この町がもっとにぎやかだったころ。昭和40年代の話。
この町は大型船が入る国際港を抱える港町だ。明治のころは北前船で栄え、昭和に入ってからは、造船、輸出入、漁業で栄えた。
映画館、パチンコ店、麹屋、醸造所、造り酒屋、飲食店、呉服屋などありとあらゆる店が狭い町中に立ち並んでいた。
戦後はロシア船が数多く入港していた。町の中の案内看板は、日本語の下にロシア語が併記してある。
ばあちゃんの恋物語は、そのころに始まる。
高度成長期で、社会全体が高揚していた時代。ばあちゃんの店も、それなりに賑わっていた。お客は地元の人のほかに、近郊の小さな集落から買い物に来る人や、入港した船の船員など。ばあちゃんの恋物語の相手は、ソ連船の船員だった。
「最初にソ連人が店に来たときは、赤鬼かと思ったちゃ。みんなでっかくて、赤い顔して、毛皮着とった」
「お土産に下駄ほしいって言うがやけど、足がでっかいからはける下駄が無かったが。だから下駄屋さんにでっかいサイズ作ってもらって、店に置いといたがやちゃ。そしたら結構売れて儲かった」
そんなある日、一人のソ連人の船員が店にやってきた。
「目がきれいやった。日本語もちょっとできた。最初は下駄買いに来たんやけど、
次の日も、その次の日も、船が港にいる間毎日店に来たが。ほかの人とはちょっと違っとって、小柄で、顔も赤くなくて、いい男やった。」
その船員の船は定期的にソ連からこの町の港に入港していたから、そのあとも何度もばあちゃんの店にやってきたそうだ。
ばあちゃんの赤い箱には、その船員と一緒に写るばあちゃんの笑顔があった。それとおぼつかない日本語で書かれた数通の手紙。
「いい男だったが」
何があったのか、ばあちゃんはそれ以上語ってはくれない。
「子供もおらんし、わしが死んだ後に他の人に見られたら嫌やから、よしちゃん、これ捨ててくれんけ」
「ばあちゃん、これ大事なものなんだよね。だから今まで持っとったんやろ。捨てられんな」
「ほかの人に見られたくないが」
ばあちゃんが言う。大事な思い出なんだろう。誰かも見られたくないのか。
「わかった。私が預かっとく。誰にも見せん」
「よしちゃん、わしが死んだら、棺の中にそれ入れて燃やして」
「わかった。でもばあちゃん、長生きせんとだめや」
ばあちゃんから赤い箱を預かってから半年。ばあちゃんは元気だ。けれど少しずつばあちゃんの時間が戻り始めている。今日のばあちゃんは、50歳だった。先週のばあちゃんは、還暦だった。いつもそういうわけではない。一日の中で、時折時間が逆行する。88歳のばあちゃんでいるときは、「あの箱死んだら棺の中にいれて」と念を押す。
大丈夫だよ、ばあちゃん。私がしっかりばあちゃんの想い出守るから。
ばあちゃんが向こうに逝くときに、必ずこの箱渡すから。
箱がなくなっても、ばあちゃんの思い出はこの町に残るから。
昨日の雨で空気が湿っている。
こんな日は海霧が出やすい。
間もなく霧が海からやってくるだろう。
眠ったようなこの町に、時を止めるように霧が静かに漂っていく。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。 「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/zemi/82065
天狼院書店「東京天狼院」 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F 東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」 〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」2017.1.27 OPEN 〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。