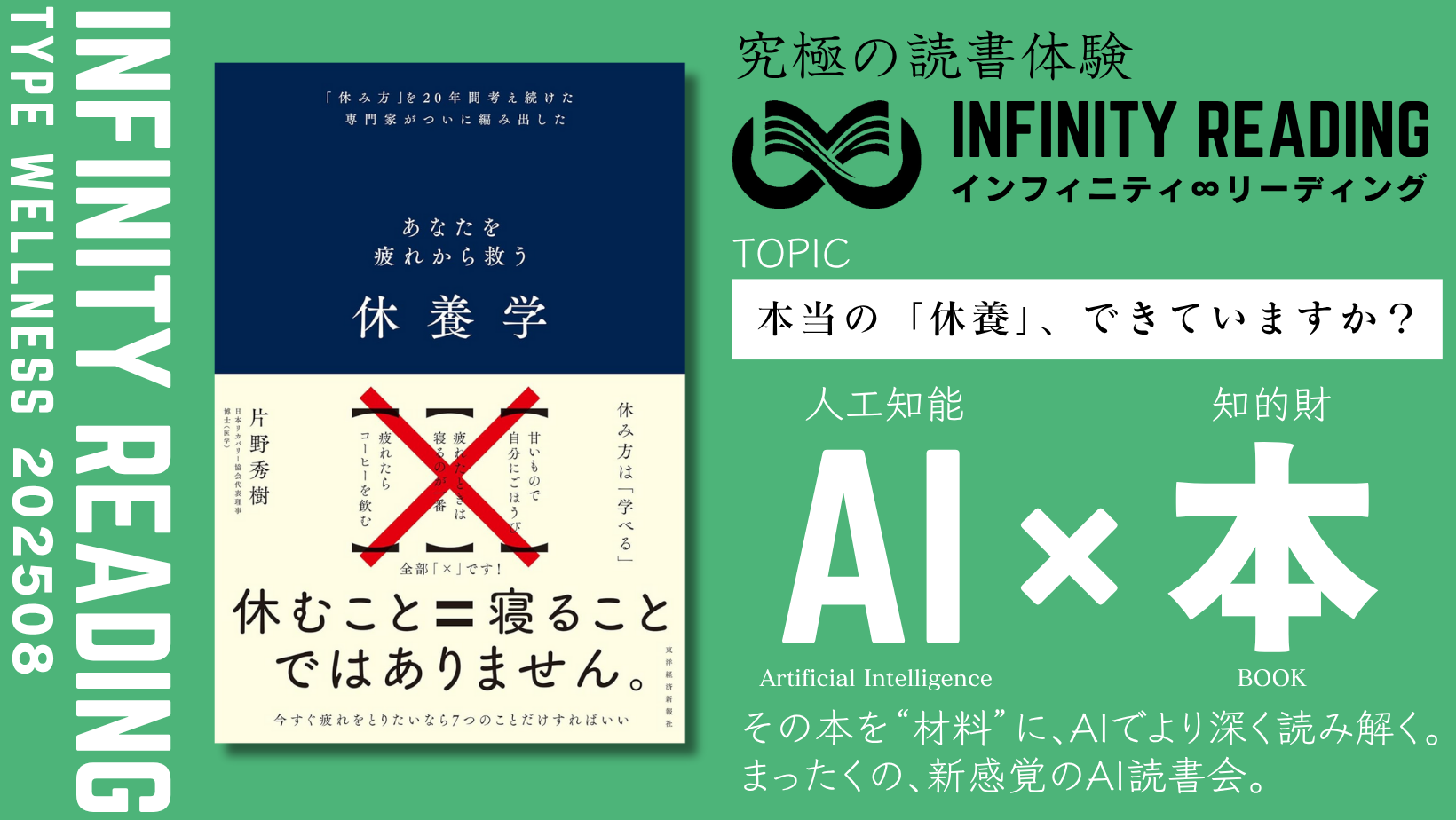ぼくたちの、さぎさわ・めぐむ

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【8月開講】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ《日曜コース》」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
記事:山本周(ライティング・ゼミ平日コース)
「鷺沢萠が好きだったよな?」
ぼくは、当時の主将だった今村に聞いた。
今村というのは、ぼくと同じ京都の出身で、同じ大学、同じ体育会のボート部で出会った男だ。滋賀大学は、滋賀県の彦根市という、人口11万人ぐらいの小さな地方都市にある。この地でぼくらは、30年近く前、4年間の大学生活を送った。
「あ、鷺沢萠ね…そうやね。好きだったというか…。確か『川べりの道』が強烈だったので、そういう話をしたことがあったかもしれない」
どこかで聞いたことのある小説の題名を、彼は口にした。
ボート部は、今年で創部95周年になる。秋に開催される記念行事に参加するかどうか、今村に相談しているついでに、ぼくは彼に聞いてみたのである。
「さぎさわ・めぐむ」なんだか、ちょっと、秘密めいた暗号みたいだ。
彼女が小説、『川べりの道』で文學界新人賞を当時最年少で受賞したのが1987年、その翌年に、ぼくらは滋賀大学に入学した。
そして、ぼくらが大学を卒業した1992年に、『駆ける少年』で泉鏡花賞を受賞している。
当時、彼女は“時の人”、だったのかもしれない。『川べりの道』を書いた時は女子高校生だった。しかし、ぼくは彼女の小説を読んでさえいなかった。
なのに、なぜぼくは、30年近く前に彼が口にした小説家の名前を、記憶しているのだろう。
今もそうなのだが、ぼくらが入学した滋賀大学は、伝統的に体育会系クラブに勢いがあった。強いチームがそうであるように、新入生の勧誘にはとても力を入れる。
怒涛の勧誘アプローチは、新入生の入学の世話をするという手厚いサポートも行っていた
日々接するボート部の先輩たちは、ひたすらボートを漕ぎ、試合に勝利することを誇りにしていた。その反面、生活のやりくりについては、後述するように、ぼくの想像を超えるものだった。でも、ただただ、その心意気と、ストイックな雰囲気、時に崇高に思える精神に惹かれていったのだ。そして、ぼくは、大学4年間をボート部に捧げることになる。
現実の練習はきつかった。
大学の授業の前と、授業の後にも練習、練習。5キロの道を懸命に走り、気候の暖かい時期は琵琶湖にボートを出し、延々と漕ぐ。冬は荒波でボートに乗れない分、気の遠くなるようなウェイトトレーニングやインターバル走、長距離走をこなした。
今村は、自分を信じ、練習にのめり込み、同期の中から頭ひとつ抜け出していた。
次期のボート部主将と目されるのに、それほど時間はかからなかった。
ぼくはといえば、弱音を吐き続けた。ことあるごとに、部を辞める、辞めると言ってまわるようなデキの悪い奴だった。
「おい、山本が辞めるようだぜ」と誰かが聞きつけると、その度に先輩や同期が、慰留のため、ぼくの六畳一間の下宿へ押しかけた。
今村は当時、小説『川べりの道』を「強烈だった」と語った。
30年後の今になり、ぼくは初めて、鷺沢萠の本を手にとってみる。
そこには、家族を捨て、別の女性と所帯を持った父親の別居に、15歳の息子が「川べりの道」を通って、毎月の生活費を受け取りに行く姿があった。
その少年の、世間を達観したような視線は、「世慣れた」とか「擦れた」とかいう言葉は当たらないかもしれない。坂口安吾が『風と光と二十の私と』のなかで、「私は近頃、誰しも人は少年から大人になる一期間、大人よりも老成する時があるのではないかと考えるようになった」と書いている。
ぼくをよなよな引き留めに来てくれた先輩や同期たちは、ひたすら、地方都市の一部学生による、無垢の勝利を説いた。ちょっと気恥ずかしいような熱情を訴えた。大仰に言えば、20歳そこそこでしかない人間が、人生を賭すような意気込みを見せてくれたのだった。
ぼくは、ずるいことに、そうやって、皆の「老成」を見せてもらっていた。
この部に留まる理由を、根拠を、求めていた。
ぼくのほうでも、なにもかも知り尽くしているような心持ちで、いつでも、どこへでも行けるような気がしていた。しかしそれとは裏腹に、自分がいったい何者なのかと、意味や符号を探しまわった。
そうしていつしかもぼくも、熱に浮かされていた。
大学3回生になって、ぼくは全日本大学選手権の出場選手として選ばれることになる。今村と一緒に、ボートの華といわれる、8人で漕ぐ“エイト”に乗ることになった。
その前に、3回生になって少しずつ調子をあげてきたぼくのクルーが、滋賀県石山の瀬田川で行われた瀬田川杯で優勝し、その実績を買われたのだ。
デキの悪かったぼくにとり、そこまでが、でも限界だったのだろう。
埼玉県の戸田のオリンピックコースで行われた、8月の全日本大学選手権では、東京勢のボート部を前に、まったくといっていいほど歯が立たなかった。
試合後、合宿所に戻ると、今村が号泣していた。
1968年生まれで、ぼくらとまったく同年代だった鷺沢萠は、35歳で死を選んだ。
彼女は、早くに達観し、優れた小説を残し、もう何もないとこの世を去ったのだろうか。
ぼくらも、あの精神的に「老成」した自分に戻ることは、もうないのだろう。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。 「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/zemi/86808
天狼院書店「東京天狼院」 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F 東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」 〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」2017.1.27 OPEN 〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。