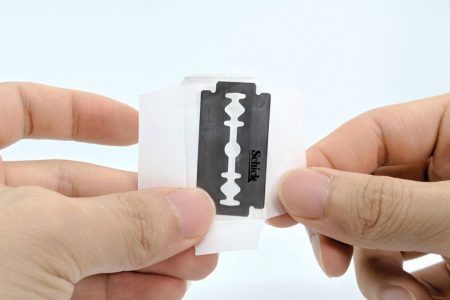私が金曜日に残業できない理由《週刊READING LIFE vol,103 大好きと大嫌いの間》

記事:今村真緒(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
※この話は、フィクションです。
「いやだ。濡れちゃったじゃない」
急に振り出した雨に、近くの店の軒下に急いだものの間に合わなかった。
その日おろしたばかりの青いブラウスに、雨粒が濃い染みをいくつも付けていた。
天気予報では、降らないって言っていたのに。
麻衣は、深いため息をついた。
理由は雨だけじゃない。
麻衣は、仕事中に上司に伝えられたことに動揺していた。
「来月から、利根さんに主任になってもらうことになったから。千葉さん、フォローよろしく頼むよ」
利根さんは、麻衣の3年後輩だ。
麻衣が、今まで何かと相談に乗っていた後輩だった。
密かに、次に主任になるのは自分だと思っていたのに。
もちろん利根さんは、仕事ができる。
テキパキしていて、社内外の人の受けもいい。
そして、麻衣が一番羨ましいのは、堂々とした自信を利根さんが持っていることだった。
企画をプレゼンする時も、おどおどとした態度は一切見せない。
きっぱりとした口調で、この人になら任せても大丈夫というオーラを放つ。
だけど。
その裏で、いろいろとアドバイスをしてきたのは麻衣だ。
本当は企画のアイデアだって、麻衣がヒントを出したものも多い。
利根さんが頼ってきたら、どんなに忙しくても資料だって準備してあげたのに。
それなのに。
どうして、彼女だけが認められる?
どうして、彼女だけが評価される?
どうして、彼女が先に昇進するの?
答えの見つからない問いが、グルグルと頭を駆け巡る。
雨は、降り止まない。
このままでは、本降りになりそうだ。
麻衣は、意を決して雨の中に駆けだした。
びっしょりと濡れた体が冷たかった。
家にたどり着いた麻衣は、急いで温かいシャワーを浴びた。
シャワーに打たれると、その温かさに次第に麻衣の心が解けだした。
同時に、目の奥が熱くなり、じわっと涙が溢れてきた。
分かっている。
悔しいのだ。
認められない自分が。
堂々と毅然とした態度をとることができず、鬱々としている自分が。
そして、そんな自分を変えることができず、僻んでいることが。
嫌い。
嫌いだ。
とてつもなく自分が嫌いだ。
これ以上、自分を卑下したくない。
これ以上、自分を憐れみたくはない。
どうすれば、利根さんのようになれる?
どうすれば、胸を張って堂々と振る舞えるのだろう?
このままでは、利根さんのことを恨んでしまいそうだった。
彼女が悪い訳じゃない。
彼女は、感謝してくれていたじゃないか。
彼女に対して、わだかまりを持つことは避けるべきだ。
だって、これから彼女の部下になるのだから。
麻衣は、グッと苦い何かを飲み込んだ。
「麻衣さん、これのチェックお願いできますか?」
主任になった利根さんは、相変わらずテキパキと仕事をこなしていた。
見ていると、人に仕事を振るのも上手い。
何でも自分で抱え込んでしまう麻衣とは、対照的だった。
「分かりました。主任」
黙々と仕事をこなす。
段取りやチェック、経費の精算など、細々としたことが自分には適している。
適材適所と言うではないか。
自分が置かれている状況で、精一杯のパフォーマンスを心がけよう。
ささくれている心をなだめるように、麻衣は自分に言い聞かせた。
利根さんが主任になって、3ヵ月。
明日は、新たなプレゼンがある。
ギリギリになって資料の追加を頼まれた麻衣は、遅くまで残業していた。
利根さんは、先に帰ってしまった。
仕事を振るのも上手いが、振ったその後は、自分とはまるで関係ないと言わんばかりの態度には、麻衣も違和感を覚えていた。
「明日、主任がしっかり見ておかないと困るんだけどな」
独り言が、思わず漏れる。
次の朝、目が覚めた麻衣は、あまりの頭痛に顔をしかめた。
熱を測ると、38.5度。
フラフラする。
やばい、今日は朝一番でプレゼンがあるのに。
出勤までには、あと1時間半ある。
急いで、頭痛薬を多めの水で流し込む。
ゾクゾクする寒気まで襲ってきた。
家を出る時間になっても、薬は全く効かなかった。
違う薬を飲むべきだったのかもしれない。
どうしよう。
迷った末に、麻衣は、利根さんへ電話をかけた。
「えー、今日来てもらわないと困るじゃないですか。今日に限って具合が悪いなんて。プレゼンの資料できているんですか?」
開口一番、利根さんは大きな声でまくし立てた。
利根さんの甲高い声が、頭に響く。
「すみません。頭がフラフラして出社できそうになくて。指示されていた資料は、まとめて主任のファイルにデータを入れておいたので、不備はないはずです」
「そう。仕方ないですね。資料があれば何とかなると思うので、じゃ」
資料ができあがっていることを確認すると、利根さんはブチッと電話を切った。
最近いつもこうだった。
利根さんは、自分の企画と言いながら、資料を準備するのも構成を考えるのも麻衣の仕事になっていた。
まるで、影武者だ。
光の当たるところには利根さんがいて、自分は陰に隠れていなければならない。
納得できない思いは、利根さんが主任になってからというもの、麻衣にずっとつきまとっていた。
「風邪ですね。最近よく眠れていますか?」
そう言えば、近頃眠りが浅い。
「疲れから体が弱っているのかもしれませんから、温かくしてしっかり栄養も取ってください。点滴打っておきましょうね」
医者のアドバイスに、麻衣は生活を振り返ってみた。
確かに帰りも遅いし、食事をとり忘れることもある。
随分、自分の体をいたわることを疎かにしていた。
ああ、私って頑張っているのにどこか報われない人なんだな。
利根さんとの朝のやり取りを思い出し、またため息をつく。
せめて生活に、何か潤いが必要だよね。
恋愛だって、何年もしていない。
30代も後半に差し掛かり、友人たちは大半が家庭のことで忙しい。
仕事も私生活も、無彩色だ。
モノクロの日常に、一体何を目指して頑張っているのか。
病院からの帰り道、駅に続く商店街の中を、麻衣はフワフワと覚束ない足取りで進んでいた。
「あなたの暮らしに彩りを」
「一輪からでも、お買い求めいただけます」
丸みを帯びた、温かみのある字体で書かれた小さな看板が目に入った。
こっくりとした焦げ茶色の板でできた、手作り風の看板。
こんなところに、花屋があるなんて気づかなかった。
店先に広がる、色とりどりの花々。
鈍く光るブリキのバケツに、季節の花が、彩り豊かに咲き誇っていた。
そういえば最後に花を眺めたのは、いつだろう?
吸い込まれるように、麻衣はその花屋に入ってしまった。
「いらっしゃいませ。あら、ご気分が悪いんじゃありませんか?」
奥から出てきたのは、グレーのショートヘアの女性だった。
白いベレー帽に、シャキッとした黒のシャツ。
おしゃれなストライプ柄のエプロン。
年齢は、多分麻衣の母親と同じくらいか。
瞬時に、麻衣の体調が悪いことを見抜き、椅子を勧めてくれた。
「いえ、大丈夫です。ちょっと通りかかっただけで」
「いいんですよ。お顔の色がちょっと優れない気がして。良かったら、お花のパワーをもらっていってください」
女性は、にっこりと微笑んだ。
花のすがすがしい香りと女性の人懐こい笑顔に、麻衣は居心地の良さを感じた。
「すみません。それでは、ちょっとだけ」
「どうぞ、どうぞ。ごめんなさい。今からアレンジメントを作るんですけど、お気になさらないでくださいね」
女性は、大きなバケツの中から数種類の花と、葉物をピックアップしてきた。
慣れた手つきで、それらを組み合わせていく。
わずかな時間で、配色も見事なフラワーアレンジメントが完成した。
「うわー、素敵ですね」
思わず、心の声が漏れた。
色合いや、花のあしらい方が麻衣の好みだった。
「ありがとうございます。お花って、気持ちを浄化させてくれる気がするんです。だから、毎日見ていて飽きないし、楽しいんですよね」
女性は、再びにっこりと微笑むと、アレンジメントのラッピングを始めた。
花屋に入って、15分くらい経っただろうか。
そろそろ、帰らなきゃ。
女性の手技に見とれ、2つ目のアレンジメントが出来上がる頃、麻衣は立ち上がった。
「すみません。長居してしまって」
「良かったら、これ、もらって頂けません?」
女性が差し出したのは、1つ目のアレンジメントに使っていた花だった。
淡くて、ちょっと渋めのピンクの八重咲の花。
美しいフリルとアンティークっぽい色合いが、麻衣の目を引いていた。
「トルコキキョウです。さっきのアレンジメントで挿そうとしていたんですけど、ちょっと長さが足りなくて」
素早くトルコキキョウを2本、白い紙に包むと、女性は麻衣に差し出した。
「いえ、それじゃ、お代を払わせてください」
「いいんですよ。一輪挿しにでも飾ってやってください、ね?」
柔らかな笑みと一緒に、女性は麻衣に花を手渡した。
「何だかすみません。あの、ありがとうございました。また今度、お店に伺います」
「ええ、また気が向いたら遊びに来てください。まずはお体をお大事に」
麻衣は、ぴょこんと一礼し花屋を出ると、夕暮れの中再び駅へと向かった。
一輪挿しなんて、何年振りに使っただろう。
クロゼットの奥から、ようやく見つけ出し、トルコキキョウを活けてみた。
可愛いな。
優しく繊細な花びらの色と可憐な姿に、思わず顔がほころぶ。
本や資料で山積みになっていたテーブルを片付け、一輪挿しを飾ってみた。
まるで、そこだけ明るい光が灯っているように見える。
それは、薄暗く心細かった麻衣の心を優しく照らしだした。
「律子さん、これ、どうすればバランスよく挿せます?」
初めてあの花屋を訪れてから3ヵ月。
麻衣は、花屋のオーナーである律子さんのフラワーアレンジメント教室に通うようになった。
「麻衣ちゃん、ほらこういう風に挿すと、伸びやかに見えるでしょう」
「さすが、律子さん。いつになったら私にもセンスが身に付くんだろう?」
毎週金曜日の20時からの教室が、麻衣にとって週末の楽しみだ。
フラワーアレンジメント教室は、花屋の2階にある律子さんの自宅で開催されている。
別の曜日にも教室を開いているから、律子さんは忙しい。
金曜日の生徒は、麻衣の他にあと3人。
夫と2人暮らしの瑞江さん、もうすぐ結婚する奈々ちゃん、お孫さんがいる知子さんだ。
瑞江さんは、元々生け花を習っていたけれど、気軽にできて可愛らしいフラワーアレンジメントに魅力を感じて始めたそう。
結婚が決まっている奈々ちゃんは、自分で結婚式のブーケを作りたいと真剣だ。
共働きの息子夫婦のため、お孫さんたちの世話をしている知子さんは、この教室の時間が唯一の息抜きだという。
そして麻衣は、あの日心に灯った明るい光を忘れられずに、律子さんの教室に通うようになった。
4人に共通するのは、律子さんの人柄に惹かれていることだった。
律子さんの持つ温かさが伝染し、教室は、いつも和気藹々とした空気に満ちていた。
1時間の教室が、いつの間にか時間が経ち、律子さんがお茶やお菓子を準備してくれることもあった。
楽しいおしゃべりに夢中になり、居心地のいい仲間と過ごすうち、麻衣の生活にはハリが生まれていた。
仕事で落ち込むことがあっても、律子さんや教室の仲間に話すとスッキリした。
自分だけでは消化しきれなかった想いが、この仲間にかかれば、たちまち魔法のように消えていく。
とりわけ律子さんの温かい眼差しは、いつも麻衣に寄り添ってくれるようで心が和んだ。
私は、決して一人ではない。
そう思えることを、麻衣は心強く思った。
週末は、金曜日に作るアレンジメントで麻衣の部屋が華やかになる。
一人暮らしの寂しさも、金曜日の教室の雰囲気を纏って帰れば、以前ほどではなくなった。
会社では、利根さんの麻衣に対する態度が変化していた。
以前のように、利根さんの影のような仕事をすることが減ってきたのだ。
麻衣が熱を出して会社を休んだ日、利根さんは上司に叱責されたのだという。
「麻衣さんが作った資料、主任ノータッチだったじゃないですか。プレゼンで役員からの質問に、主任答えられなかったんです」
どうやら、利根さんにとっては思わぬ方向の質問だったらしい。せめて利根さんが自分で調べておくなり、人任せにしていなかったなら答えることもできただろう。今までは、麻衣が必ず利根さんに随行して、助け舟を出していたから。
「麻衣さんに丸投げしていたことが発覚しちゃったんですよ。それをチームとしての企画ならともかく、自分が考えた企画として出して、主任、立つ瀬がなくなったみたいで」
後輩が、あの日何があったか、事細かに教えてくれた。
しばらく利根さんは、明らかに落ち込んでいた。
いつも自信に満ちていた彼女が、視線を落として仕事をしていた。
心なしか口調にも、いつもの溌剌としたものが欠けているような気がした。
「麻衣さん、お時間いいですか?」
金曜日の退社前、利根さんが麻衣に話しかけてきた。
今から、律子さんの教室に行くのに。
「ちょっとだけなら」
「すみません。週末ですもんね。最近、金曜日は早く帰りますよね」
何か仕事を頼みたいのだろうか?
自分のやるべき仕事は終えている。
「金曜日は残業いたしません!」
麻衣も、ドクターⅩの外科医・大門未知子ばりにハッキリと言うべきなのかもしれない。
「もし必要なら残業するけれど、あんまり遅くまでは……」
仕方なく譲歩しかけた麻衣を、利根さんが遮る。
「違うんです。一度ちゃんと麻衣さんに謝りたくて。私、ずっと麻衣さんに甘えていたくせに、主任になれたのは自分の実力だと思い上がっていたんです」
人のいない会議室に連れてこられた麻衣は、利根さんの言葉に目を丸くした。
「麻衣さんが協力してくれるのをいいことに、自分のことしか頭になかったんです」
麻衣より背が高いのに、縮こまる利根さん。
その姿に、入社してきたばかりの利根さん、いや、「美奈ちゃん」が重なった。
「美奈ちゃん、あ、ごめんなさい主任」
「いいんです。そう呼んでもらっていた頃が懐かしいです。主任になってからは、何とかして結果を出さなきゃと焦るばかりで、苦しくて」
「私、嫌な思いをさせていましたよね? 麻衣さんがプレゼンに来られなかった日、どれだけ麻衣さんに負担をかけていたかよく分かったんです。本当にすみませんでした」
美奈ちゃんは、泣きそうな顔をしていた。
「自分一人では何もできないくせに、偉そうに指示したりして。麻衣さんが羨ましい。だって自分で何でもできるから」
意外な言葉に耳を疑う。
彼女が、羨ましいという言葉を口にするなんて思いもしなかった。
いつも自信満々だった彼女が、幼い子供のように見える。
「私の方こそ、美奈ちゃんのこと羨ましかった。いつも堂々としていて、怖いものなんてない感じで」
「そんなことないですよ。態度がそう見えるだけで、後は特別な取り柄もありません」
フフッと自嘲気味に笑う彼女。
つられて、麻衣も思わず苦笑する。
「これからは、麻衣さんに頼り過ぎないようにします。もっと勉強して、麻衣さんみたいに実力をつけたいんです」
「美奈ちゃん」に戻った彼女は、いつもの生き生きとした力強い眼差しで麻衣を見つめた。
「ごめんなさい。用事があるんですよね? 間に合いますか?」
「それでは、お先に」
エレベーターに乗り込むと、麻衣は全身から何かを追い出すように、長いため息をついた。
何だ、そうだったんだ。
美奈ちゃんになりたかった自分は、美奈ちゃんに羨ましいと思われていたなんて。
自分の足りない所ばかりを数え上げ、追い込むのはもう止めよう。
私は、私のままでいていいんだ。
もちろん克服していかなければならないこともある。
それでも、必要以上に自分を責めることはないのかもしれない。
ちょっと自分を認めることができた気がして、麻衣の足取りは軽くなる。
律子さんは、今日は何の花を準備してくれているだろう?
3人は、もう教室に来ているかしら?
今日は、皆に良い報告ができる気がする。
麻衣は、弾みをつけて駅の階段を駆け上った。
□ライターズプロフィール
今村真緒(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
福岡県出身。娘とワンコを溺愛する兼業主婦。
自分の想いを表現できるようになりたいと思ったことがきっかけで、2020年5月から天狼院書店のライティング・ゼミ受講。更にライティング力向上を目指すため、2020年9月よりREADING LIFE編集部ライターズ倶楽部参加。
興味のあることは、人間観察、ドキュメンタリー番組やクイズ番組を観ること。
人の心に寄り添えるような文章を書けるようになることが目標。
この記事は、人生を変える天狼院「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」をご受講の方が書きました。 ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
TEL:03-6914-3618/FAX:03-6914-0168
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
*定休日:木曜日(イベント時臨時営業)
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「Esola池袋店 STYLE for Biz」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋2F
営業時間:10:30〜21:30
TEL:03-6914-0167/FAX:03-6914-0168
■天狼院書店「プレイアトレ土浦店」
〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2F
営業時間:9:00~22:00
TEL:029-897-3325
■天狼院書店「シアターカフェ天狼院」
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目8-1 WACCA池袋 4F
営業時間:
平日 11:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
電話:03−6812−1984