【伊勢・二見浦】弾丸女一人旅《川代ノート》

どうしてこの本と出会ってしまったんだろう、と最後のページを閉じた瞬間に、思った。
猛烈に悔しかった。悔しくて、悔しくて、涙が出そうになった。でも涙を流してしまったら、本当に負けを認めなければならない気がして、ぐっと唇を噛んで我慢した。認めるも何も、はじめから私は戦いの土俵にすら立てていないのだけれど、そのときは本当に、悔しくてたまらなかったのだ。
こんなことなら買わなければよかった。本屋に行ったとき、他にも目についた本はたくさんあったのだ。別にこの本を手に取る必要なんて全くなかったし、この作者の本を読んだこともなかった。ただ友達の誰かが「この人の本好き」と言っていたのを思い出したからちょっと手に取ってみたのだ。思えばそれが運の尽きだった。どうして読んでしまったんだろう。槍で刺されたみたいに心が痛かった。しばらく私は放心状態で、ぼーっと旅館の和室の天井の板目を視線でなぞっていた。
だめだ、とりあえず落ち着こう。とりあえずご飯を食べよう。この本にあまりに集中していたから気がつかなかったけれど、ひどくお腹が減っていた。ゆっくりと伊勢海老でも食べて気持ちを落ち着かせよう。そうすればこのモヤモヤもなくなるかもしれない。
不運にも、食事を部屋に運んでくれるサービスはその旅館にはなかった。春休みで浮かれているキラキラした女子大生たちや、おそらくクリケットサークルか何かの友人同士なのだろう、大勢の老人たちが楽しそうにわいわいと話しながら伊勢の海鮮料理や伊勢うどんに舌鼓を打っていた。私みたいに一人で来ている人間なんて見渡す限りは誰もいない。
はあ、気まずい、と思いながらも減った腹は抑えられないので、恥ずかしさをこらえながら黙々と食事をした。伊勢海老がうまい、茶碗蒸しがうまい、カレイの煮付けがうまい。な、なんだこのうまさは。豪勢な懐石料理のあまりのうまさに感動して叫びそうになったが、なんとか我慢する。誰かとこのテンションの高まりを共有できないことをひどく寂しいと思った。
「あらあらあら、まあまあ。一人でねえ、寂しいと思うけどね、はい。美味しく食べてくださいね」
そんなところに空気も読まずに爆弾をぶち込んできたのは私の席の担当の中居さんであった。
「い、いや、あの……」
「はい、これね。もうお鍋にお野菜入れちゃって大丈夫ですからね。うふふ。あたしがやってあげようか?」
おそらく七十近いであろうしわしわのおばあさんがニヤニヤしながら私のことを見ていた。一人で寂しい? 何てことを言うんだ。大丈夫だ、思い出せ。「いや、ちょっと伊勢・志摩のガイド雑誌の取材で来てて。こんなにおいしいご飯一人で食べるのちょっと寂しいけど、でもすごくおいしい。ここに泊まってやっぱり良かったです」この旅館を予約する前に何て言い訳するかちゃんとシミュレーションしていたじゃないか。私は個人的な旅行で来ているわけじゃなくて、あくまでも仕事できているライターなのだ。設定上は。だから別に一人でご飯を食べていても全然寂しくないし私に友達がいないからこの懐石料理を一人で食べるハメになったわけじゃないのだ。大丈夫だ。恥ずかしいことなんか何もない。
でもいくらシミュレーションしてきたとしても、伊勢のちゃきちゃきとしたおばあさんの勢いに勝てるわけもなかった。きっと「失恋でもして一人できてるのかしらね、かわいそうに。あたしが慰めてあげなくっちゃ」とでも思っていたのだろう。あまりの切なさに憤死しそうだった。結局、「い、いや大丈夫です」とすっと目線をそらしてそのおばあさんに言うのが私の限界だった。「あら、そうですか〜はいはい。じゃ、ごゆっくりね」と、おばあさんはニヤニヤしながら去っていく。
ああ、もう、いやだ。一度自分が「寂しいやつ」というレッテルを貼られているのだと気がつくと、途端にすべての動作を監視されているような気がしてくる。変な汗が背中をすっと流れた。心なしかそのおばあさんだけでなく他の中居さんやフロントの受付の従業員もみんなチラチラ私を見ているような気がしてきた。
もうこうなるとご飯どころではない。一食約三千五百円もする伊勢グルメが味わわれる間もなく私の腹の中に収められていく。黙々と急いでご飯を食べ、さっと一瞬の隙をついて写真を撮る。ああ、こんなことなら大型の一眼レフを持って来ればよかった。そうすればきっと「雑誌の撮影か何かかしら」と思ってくれただろうに。
急いで伊勢海老をほじくり、茶碗蒸しを掻き込み、伊勢うどんをすすった。さっと中居さんに気がつかれないうちに食堂を抜けて部屋に戻る。なんだかどっと疲れてしまった。こんなことなら伊勢市駅に着いた時点で何か食べてくればよかったのだ。
部屋はいかにも「旅館」らしい和室だった。一人にしてはかなり広い。部屋に戻るとすでに布団が敷かれていた。
はあ、と一息ついて座り、落ち着こうとお茶を淹れる。見ると、机の上にさっきの本が置かれていた。
青いカバーに書かれた女の子のイラストをじっと見た。なんだか自分と目が合ったような気がして、目をそらしてしまう。やっぱりまだ心のどこかがモヤモヤしているようだった。
薄くて軽い、600円もしない文庫だった。特に期待もせずに読み始めた本に、こんな気持ちにさせられるなんて思わなかった。
もうその本を見たくなくて、半ばやけくそにリュックにつっこんだ。気がつけばもう10時前だ。急いで浴衣を羽織り、私は大浴場へ向かった。
海に面した露天風呂にぷかりと浸かり、ゆるやかに波打つ海をじっと見ながら、私は物思いに耽る。ザザーン、という波の音が心地いい。海面に作られた、月光で輝く金色の道を、ぼんやりと見ているだけで私は……。
……という妄想をしていたからこそ、この二見浦の海岸沿いの宿をとったのだけれど、露天風呂の扉を開けた瞬間に私の願望は打ち砕かれた。残念ながら、現実の海は、「波打つ」どころではなかったのだ。
もはや、台風である。台風の目のど真ん中に風呂を作っているようなものだ。海の近くは風がすごいのだということをすっかり忘れていた。いくら温泉があるとはいえこの風は寒すぎる。ゴオオオオオオオオ、とものすごい音を立てて風が吹いていた。うーん、妄想とだいぶ違う。もっと、なんというか、月とかが海に反射して鏡張りみたいになってて、オリオン座が見えて……とかロマンチックな感じを想像してたのに。全然違うし、そもそも海も別に綺麗じゃない。真っ黒だし月もないし星もよく見えない。だいたい風が強すぎて髪がスーパーサイヤ人みたいになるのだ。海を見ながら温泉を楽しむ余裕なんかない。
けれどせっかく来たのだからと、ぶるぶると震えながらも湯船につかった。あっつ!! 熱い。お湯がとても熱い。でも外に出ている顔は寒い。温まりたいのか涼しくなりたいのかもうわからない。
でも運よく、露天風呂には私しかいなかった。せっかく来たんだし、と自分に言い聞かせ、強烈な風と耳に響く轟音に耐えながらじっと体を温める。
そういえば、最後に一人旅をしたのはちょうど一年前くらいだったなあ、と突然思い出した。あのときもたしか海沿いで、こんな感じのものすごい風が吹いていた。だから思い出したのだ。
あれは……そうだ、湘南だ。12月の湘南。鎌倉の駅すぐ近くに宿をとって、江ノ電の1日乗車券を買って、ずっとぶらぶらしていたのだ。そして朝5時に起きて七里ヶ浜の朝日を見に行った。ものすごい強風だったけれど、朝日は綺麗だった。
そうだ、せっかく伊勢に来たのだから伊勢神宮に行く前に朝日を見に行こう、と私は思いついた。ここは二見浦の旅館だから、歩いて10分程度のところに夫婦岩とやらがあるはずだ。じゃらんで宿を選ぶときに旅館の口コミページに書いてあった気がする。「夫婦岩から昇る朝日は最高!」と。
そうだ、そうしよう。せっかく久しぶりの一人旅なのだ。楽しまないと損じゃないか。
伊勢に来ようと思ったのに、特に大きな理由はなかった。ただなんとなく、そろそろ伊勢神宮に行ってみてもいいかなという気がしたのだ。別に何かがあったわけではないけれど、ちょっと精神的に疲弊しているような、もうすぐ電池が切れそうな感じがした。だから日本一のパワースポットと呼ばれているところに行ってみようと思いついた。
私は別に信仰深い方ではないし、霊感もスピリチュアルなパワーも全くない。今までにオーラとか幽霊とかを見たこともない。だから伊勢神宮に行ったところで別に何もわからないかもしれない。
けれど、なんとなく、本当になんとなくだけれど、自分ともう少しちゃんと話してみてもいいかなと思った。ゆっくり、一人で歩いて、なるべく難しいことはあまり考えないようにして、感情にきちんと耳を傾ける。忙しくて、そういう時間を最近持てていなかった。たまにはいいじゃないか、そういうロマンチックなのも。うん。
でも、と私は思った。
伊勢に着く前にあの本を読み終えてしまったのは失敗だったなあ。ちょっとショックがデカすぎる。まだ胸のところに、何かがつっかえたみたいに衝撃の余韻が残っている。
まあ、いっか、と私は呟いた。もしかすると、明日1日ゆっくりかけて一人旅をすれば、このモヤモヤとも決着がつくかもしれない。どうしてこんなにモヤモヤしているのかわかるかもしれない。
明日だ、と思った。風呂から上がり、浴衣を着直して布団に入る。ゴオオ、と風と海がうねる音を聞きながら、私はそのまま眠りについた。
次の日の早朝、私は夫婦岩の朝日を見ていた。早起きできてよかった。夫婦岩の間から覗くまん丸の朝日は元気いっぱいという感じがした。なるほど、やっぱり伊勢にはスピリチュアルな何かがいるのかもしれないな。だから東京よりも朝日が元気に見えるのかもしれない。
ここで本当に一人旅が好きな女性なら、きっとコートのポケットに手をつっこんでじっと朝日を見るか、もしくは海沿いでタバコを一服して、「……きれい」なんて呟いたりするのかもしれないけれど、私はただ黙って朝日を見続けるのが耐えられなくて、結局何枚か写真を撮ってすぐに旅館に戻ってしまった。「……きれい」なんてアンニュイな感じじゃなかった。「うん、はい、綺麗。うん、OK! 見た見た!」という感じだった。あれ? おかしいな、と思った。前に一人旅をしたときにはもっと感傷に浸っていたはずだし、もっとこう、じっと朝日を見れていたはずだ。
でもそういえば、あの頃はまだ大学を卒業する前だった。社会人になってせかせかすることが増えて、心の余裕がなくなったのかもしれない。
なるほど、これが伊勢神宮か、なるほど。
伊勢神宮は私が今までに見てきたどんな神社とも雰囲気が違っていた。予想していたよりも随分とシンプルだったので驚いた。
おみくじもない。派手な飾りもない。鳥居も赤じゃなく白い木の色だった。お土産売り場もほんの少し。
なるほど、これが日本一のスピリチュアルスポットか、と私は思った。
神々がいる雰囲気も感じなければ、撮った写真にオーブとやらも映らなかったけれど、この神社に人が集まる理由はなんとなくわかる気がした。余裕があるのだ。どっしりと構え、ぶれない意思のようなものを感じた。この神社はきっと自分に自信があるのだ。もしかすると、その強い自信や意思を感じた人が、「神様がいた」と言っているのかもしれない。
伊勢神宮でお参りをしたあと、おかげ横丁を回り、醤油のお団子を食べ、松坂牛串を食べ、コーヒーショップに立ち寄って濃厚なブラックコーヒーを飲んだ。ただ目的もなく、ガイドも持たず、ぷらぷらと気の向くままに色んな店を回る。
たしかに、こんな風にゆっくりと散歩したり、知らない土地で観光するのは久しぶりのことだった。
大学生の頃は、特に三年生の頃なんかは、一人旅が大好きだった。夏に10日間くらいかけて九州と中国地方を回ったこともあった。ドミトリーに泊まって色々な旅人と話すのがとても好きだった。
でも……でも。
やっぱり何かが、前と違う。
自分の中で、たしかに、何かが変化しているのがわかった。
夕暮れになり、伊勢市駅に預けていた荷物をピックアップし、近鉄特急に乗り込む。就職して、今は名古屋に住んでいる友人に会いに行く予定になっていた。
ぼんやりといかにもローカル線らしい電車の車窓から、暗くなった伊勢の街が遠くなっていくのを見ていた。
あの子は今、元気にやっているだろうか。
ふいに、高校生の頃のことを思い出した。なぜだろう。脈絡なんかない。でも急に頭の中にあの子の顔が浮かんできたのだ。
いくつだったろう。16歳くらいだろうか。思春期で多感だった私は、一人の女の子に、強く影響を受けていた。
自由奔放で、かわいくて、頭がよかった。とても魅力的な子だった。
その子といるのはとても楽しかった。色々なことを教えてくれて、刺激を与えてくれた。でもだからこそ、私はいつも彼女に振り回されていた。まるで小悪魔に魅了されるヘタレ男みたいに、「痴人の愛」のナオミに振り回される譲治みたいに、私はいつも「いやだ、いやだ」と愚痴っておきながらも彼女の周りから離れられなかった。
そして彼女にひどく傷つけられたと思った。どうしてだろう。今思えば、彼女にいじめられたわけでも彼女に特別ひどいことを言われたわけでもない。今ならたいして気にも止めないような些細なからかいの言葉ばかりだった。でもあの頃の私はひどく傷ついていた。
そうか、と赤から深い青へ、青から黒へと変わっていく空を見ながら思った。
私は、私の個性がなくなっていくのが嫌だったんだ。
彼女の強烈な個性と一緒にいると、自分がどんどん消えていくような気がした。彼女はどこにいても目立った。どこにいてもみんなに声をかけられた。どこにいても私より価値があるように思えた。
彼女と一緒にいると、どんどん自分の周りの空気が薄くなっていくような気がした。自分が立っていられる場所が狭くなっていくのだ。彼女が私の分の酸素まで吸い込んでしまうから、息がつまる。苦しい。
彼女といればいるほど、彼女の色が濃くなればなるほど、私の色は薄くなっていく。透明になっていく。
私は誰? 私は何? 私に存在する意味なんて、あるの?
そして私はいよいよ息ができなくなると思って、彼女と離れた。絶交したとかそういうことではないけれど、自然に、離れていった。
彼女のことが好きだった。大好きだった。でもだからこそ、憎らしくて憎らしくてたまらなかった。彼女を好きだと思う自分の気持ちを認めたくなかった。羨ましかった。彼女が立っている場所にいるのが自分ならどんなにいいだろうと思った。
はあ、とため息をつく。
もう空は真っ暗になっていた。次はー、四日市、四日市、というアナウンスが聞こえた。名古屋まではまだ時間がありそうだった。
私はリュックから本を取り出した。ずっと私をモヤモヤさせていたものが何なのか、やっとわかったような気がした。もう私はそのページをめくっても動揺したりはしなかった。
柚木麻子の「終点のあの子」。
その青いつるつるとした文庫カバーの表面を、手の平でゆっくりとなでる。
簡単に言えば、中高一貫の女子校で暮らす主人公が、高校から入学してきた女の子を、いじめてしまう話だ。
そうか、私はあまりにも強く、感情移入しすぎたのかもしれない。だからずっとモヤモヤしていたのかもしれない。
私は大学に入っても、彼女への嫉妬心を抱き続けた。大学の友人たちと飲み明かし、「今までにあった衝撃的な出来事ってある?」と聞かれると、「実は、友達に裏切られたのがトラウマなんだよねー」と偉そうに語った。
別に裏切られたりなんかしてない。ただ自分の思うように彼女が動かなかったのが嫌だっただけだ。自由に振舞う彼女に振り回されて傷つけられた自分を作り上げて、「かわいそうだったね」という言葉を言ってもらえるように仕向けた。
そして自分の嫉妬心や承認欲求は、思春期の頃に彼女に張り合われたから出来上がったものなのだと思い込もうとした。「親しい友人に裏切られた」というかわいそうなエピソードがあれば、今の自分の性格の悪さやプライドの高さも許されるような気がした。
最終的に、彼女への「トラウマ」という名の幻想を捨て切れなかった私は、素晴らしい解決策を思いついた。
書けばいい。
書いて、吐き出せばいい。
そうすれば、この思いも昇華する。歪んだ自分はいなくなる。新しい自分になれる。
ちょうど都合よく、天狼院の雑誌「READING LIFE」が創刊することになった。
編集長の三浦さんから、「小説を書かないか」、と私は言われた。
チャンスだ、と思った。はっきりと。これであの子への思いから決別できると思った。
こうして、生まれて初めて書き上げた短編小説は、雑誌「READING LIFE」に掲載され、販売されることになった。
実家の本棚を思い浮かべた。ああ、あんなに一生懸命書いた小説を掲載した「READING LIFE」は今、私の本棚の奥でほこりをかぶっているかもしれない。他の記事も面白かったし、読み応えがある雑誌だった。でも私の小説が載っているというだけで、もう一度読み返す気にならなかったのだ。
私はその小説に自分のその子への憎しみを全部吐き出したつもりだった。今までにされて嫌だったこと、苦しかったこと。いい加減、解放されたいということ。もう見逃してくれ、と思った。どれだけ私はお前に傷つけられてきたと思っているんだ。そんなドロドロした憎しみを全部吐き出した。
でも、違うのだ。
何かが、確実に違う。
私が書きたかったのはこんなんじゃない。
自分の欲求や感情を紙面に思いっきりぶつけたのはたしかだった。でもどこか、本当に大事なことを、一番抜かしてはいけないことを書けていないような、そんな気がした。
だから、「終点のあの子」を読んだとき、後ろから思い切り、鋭い何かで刺されたような気がしたのだ。
悔しかった。悔しくて悔しくて涙が出そうだった。
どうしてこんなにうまく、人間の本性をひん剥かせられるんだろう。
どうしてこんなに的確に、私の感情を言い当ててくれるんだろう。
どうして。
どうして、これを書いたのが、私じゃないんだろう。
この小説を書いたのが、自分以外の誰かだという事実が、悔しくて仕方なかった。
私が書きたかったのは、まさに、これだったのだ。この「終点のあの子」に間違いなかった。私がずっと胸の奥に燻らせていて、モヤモヤさせていたあの子への思いは、全部この本の中にあった。
あまりにも忠実に、私の感情や汚いところをつまびらかにしていた。淡々としているのに、ある種の熱がこもった文章は、すべてを見透かすように私に真実を突きつけた。
私はどんなにあがいても、書けなかったのに。
空からはもう、赤も青も消えていた。真っ黒な空に、光がぽつりぽつりと増えて行く。
ずっと田舎の家々や畑が続いていた車窓から見える風景が、徐々に変わりつつあった。
田んぼが消える。古びた日本家屋が消える。道路が増え、ビルが増え、電子看板が増えて行く。
もうすぐ名古屋なのだ。
私は隣の人にも聞こえないくらいの小さな声で、悔しい、と口に出して言ってみた。
ここまでこの小説に感情移入してしまう自分が、悔しかった。
どうしてこんなにも自分の物語みたいに思えたんだろう。
簡単だ。
主人公を振り回す、ひどく自由奔放で、けれど魅力的な、奥沢朱里という女の子が、あまりにも高校の頃のあの子に、似ていたから。
そして、自分はまともだと信じ込み、正当化しながらも、嫉妬に駆られて朱里をいじめてしまう没個性的な主人公が、憎しみを文章に吐き出して鬱憤を晴らそうとした自分自身に、そっくりだったから。
どんな人が書いたんだろう、と作者名をネットで検索する。
皮肉にも、「終点のあの子」の作者である柚木麻子は、私と同じ高校の先輩だった。
「次はー、名古屋、名古屋です。お降りの際は、忘れ物に……」
ざわざわと周りの客が、吊棚に乗せたお土産やキャリーケースを取り出したり、コートを着たりしていた。
私ももう降りなくちゃ、と私は思った。二泊三日にしてはかなり少ない荷物と、会社の人に配るために買った赤福の袋を持った。コートのボタンを閉め、マフラーをぐるぐる巻きにする。
もし今、あの子に会ったとしたら、私はまだ嫉妬を抱くだろうか。
きっと抱くだろうな、と私は思った。あの子は5年経ってもまだ魅力的で、ますます多くの引き出しを増やしていることだろう。
そしてそれを見て、私はやっぱりああこの子には敵わないと痛感するだろう。
心の中のモヤモヤはまだ燻っていて、徐々に心の下の方に沈殿していくのがわかった。私があの子に対して抱いた強烈な嫉妬や、焦りや、執着心は多かれ少なかれ私の心の中のどこかにこびりついて、ずっと残り続けるだろう。
でもなんとなく、本当になんとなくだけれど、この子が憎い、とはもう思わないだろうと思った。
恨みを抱くことも、おそらくもう二度とないだろうと思った。あの子に裏切られたことがトラウマだと、被害者ぶって言いふらすこともないだろう。
そう思えるようになったのが、この本との衝撃的な出会いのせいなのか、自分が社会人になって、ちょっとずつ成長しているせいなのかはわからない。
でも一つだけ確信を持って言えることがあった。
人は変わる。
それが望んだものにせよ、そうじゃないにせよ、人は変わるのだ。確実に。毎日毎日、少しずつ。不思議なもので、変わろうと思っても簡単には変われないけれど、意識していないところで、がむしゃらに毎日を生きているうちに、なりたかった自分になっていたりするのだ。
そしてふとしたときに、それを実感する瞬間が来る。
自分の感情に耳を傾けていれば、必ずそんな瞬間が来る。
ああ、やっぱり一人旅をしてよかったな、と私は呟いた。
別にはっきりとしたメリットがあったわけでも、発見があったわけでも、思い出ができたわけでもないし、特別楽しかったわけでもないけれど、きっと今日伊勢に一人で来ていなければ、そんな自分の些細な変化になんて、気が付けなかったはずだ。
よかった。
さあ、電車を降りて、おいしいごはんを食べよう。そして、大学の頃の友人と再会して、楽しい話をたくさんしよう。
プシュー、と蒸気の音が聞こえる。
「終点、名古屋、名古屋です。お出口は左側です。お足元に、お気をつけて……」
リュックの持ち手の部分を、ぎゅっと握りしめて、電車を降りる。
もう終点だ。
【出て来た書籍】
・「痴人の愛」谷崎潤一郎 新潮文庫 670円+税
・「終点のあの子」柚木麻子 文春文庫 540円+税
・「READING LIFE創刊号」天狼院書店 2000円+税
▼上記書籍のお取り置き・ご注文はこちらから(お名前、お電話番号をご入力ください)▼
TEL:03-6914-3618
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】
【有料メルマガのご登録はこちらから】
関連記事
-
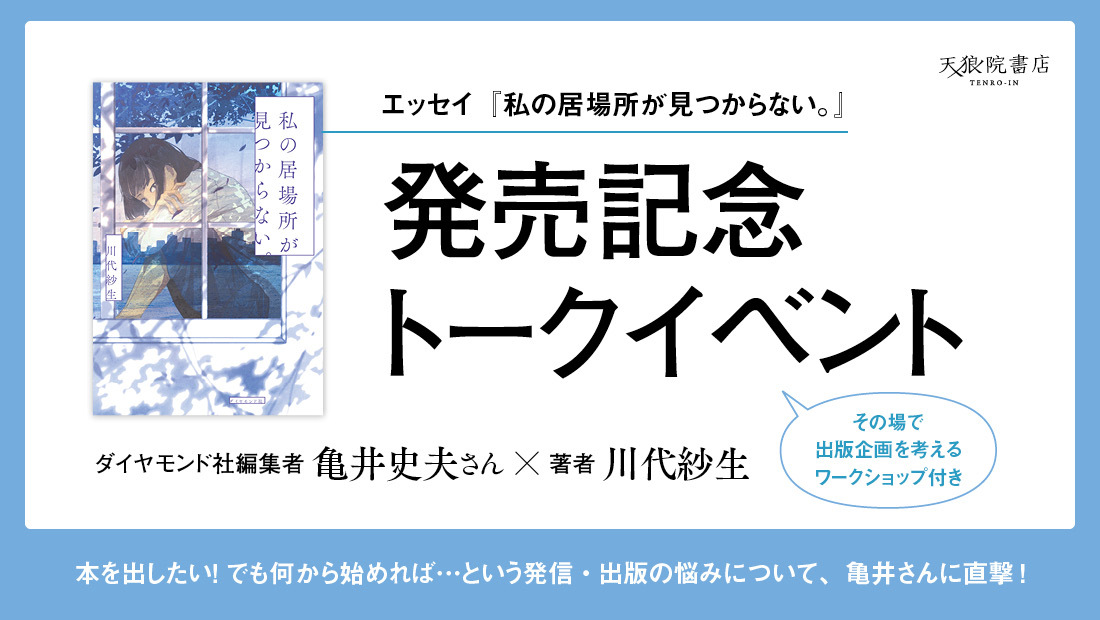
【2月11日(金祝)10:00】エッセイ『私の居場所が見つからない。』発売記念!ダイヤモンド社編集者・亀井史夫さん×著者・川代紗生トークイベント《テーマ:本を出したい!でも何から始めれば…という発信・出版の悩みについて、亀井さんに直撃!その場で出版企画を考えるワークショップ付き》
-

5万投資して執筆効率がめちゃくちゃ上がった意外なツール《ライティングTIPS》
-

【似合う髪型の見つけ方】美容師さんがカット前にめちゃくちゃ話を聞いてくれる人で最高だった《川代ノート》
-

★800冊突破★雑誌『READING LIFE』vol.3 『自分史上最高の文章を書くための「文章術会議」』各店&通販にて好評発売中!《2021年11月14日発売!》
-
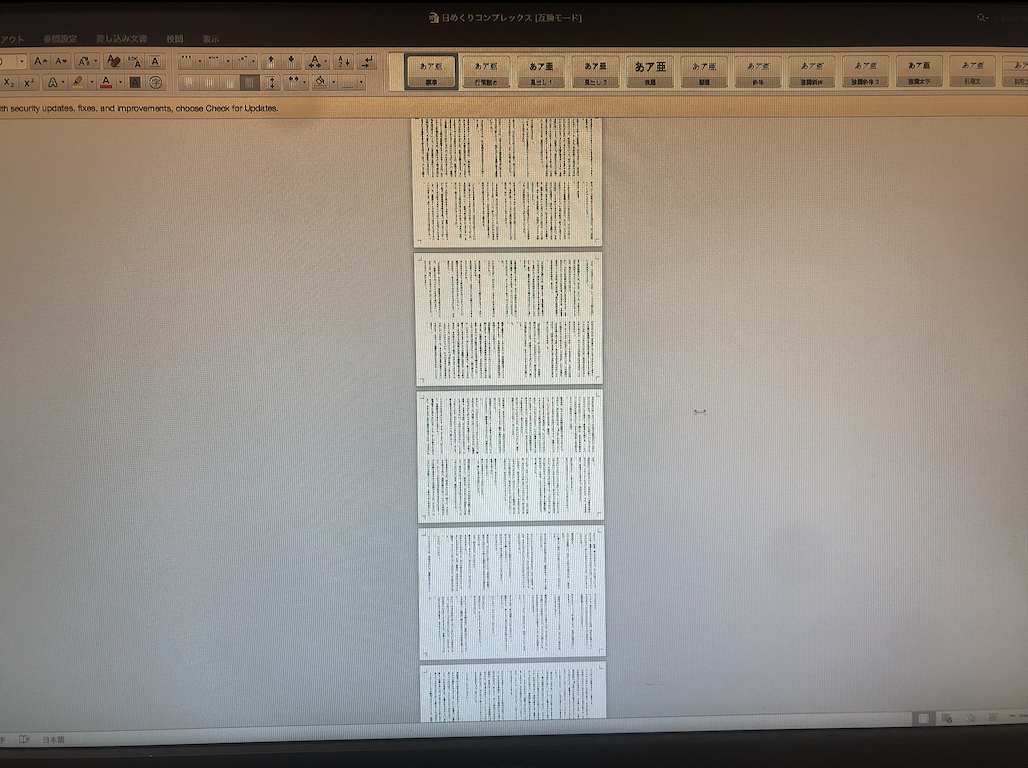
ダメ就活生だった7年前の自分が書いた文章が古いUSBから出てきて爆泣きしてしまった《川代ノート》


























































































