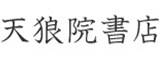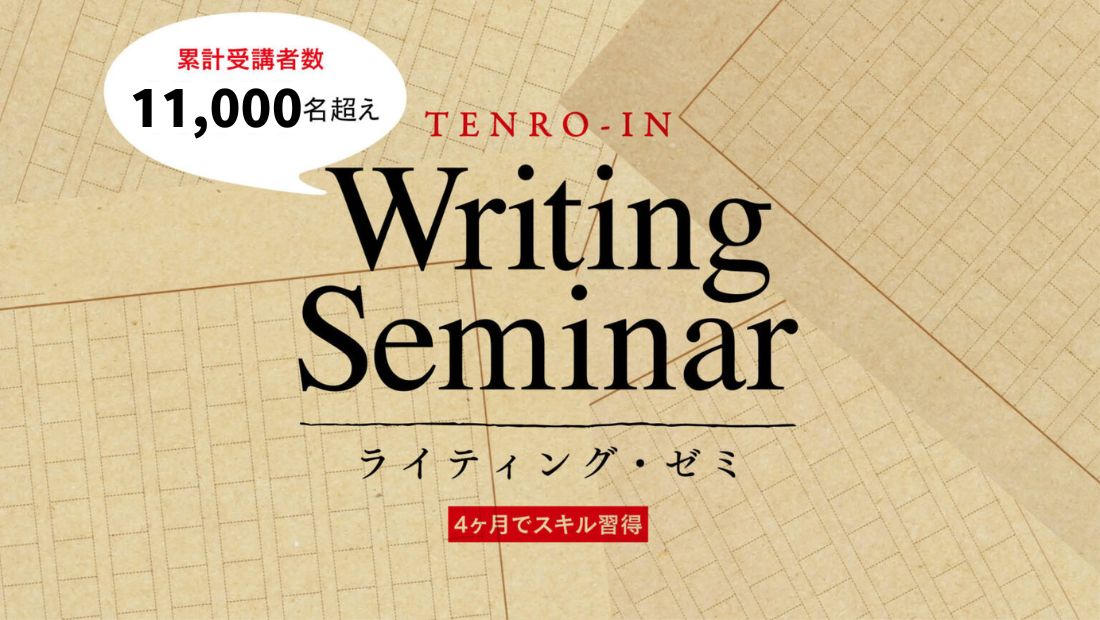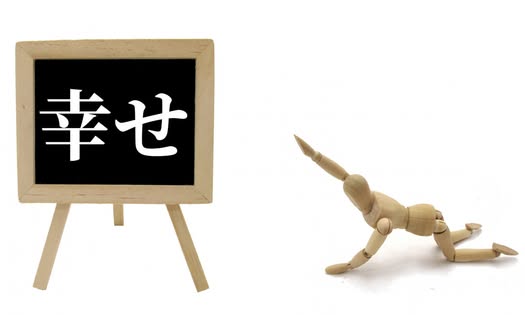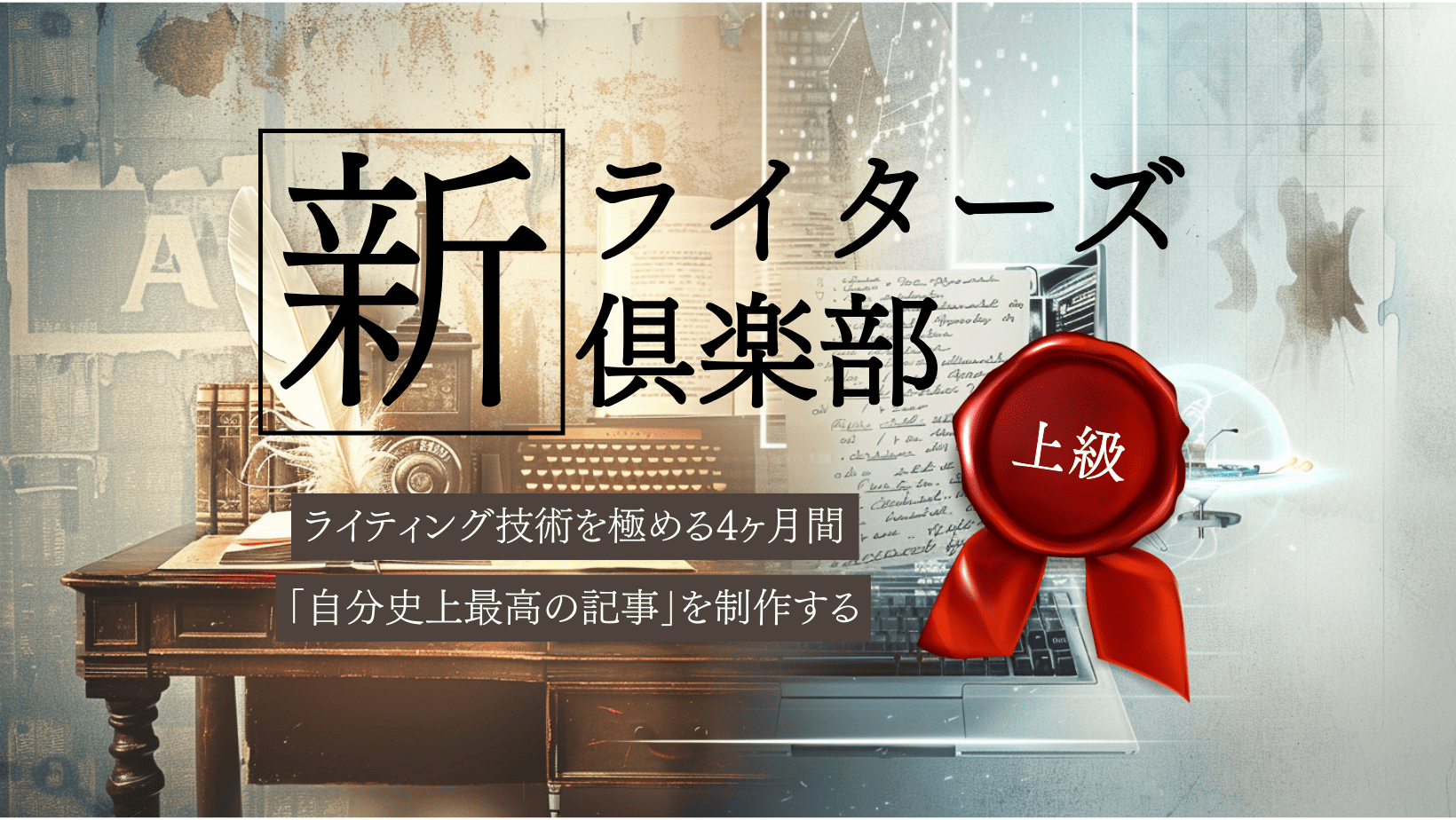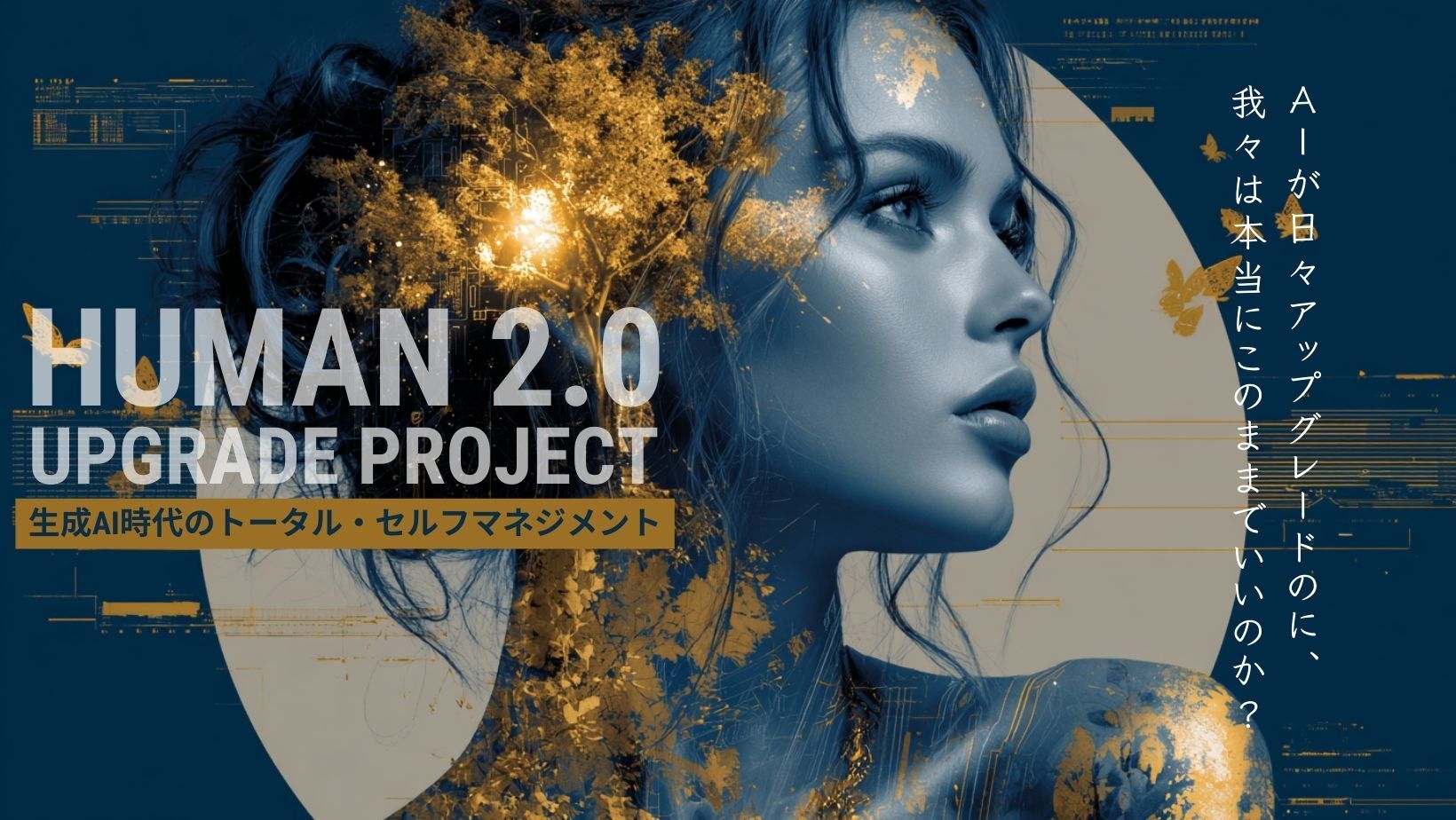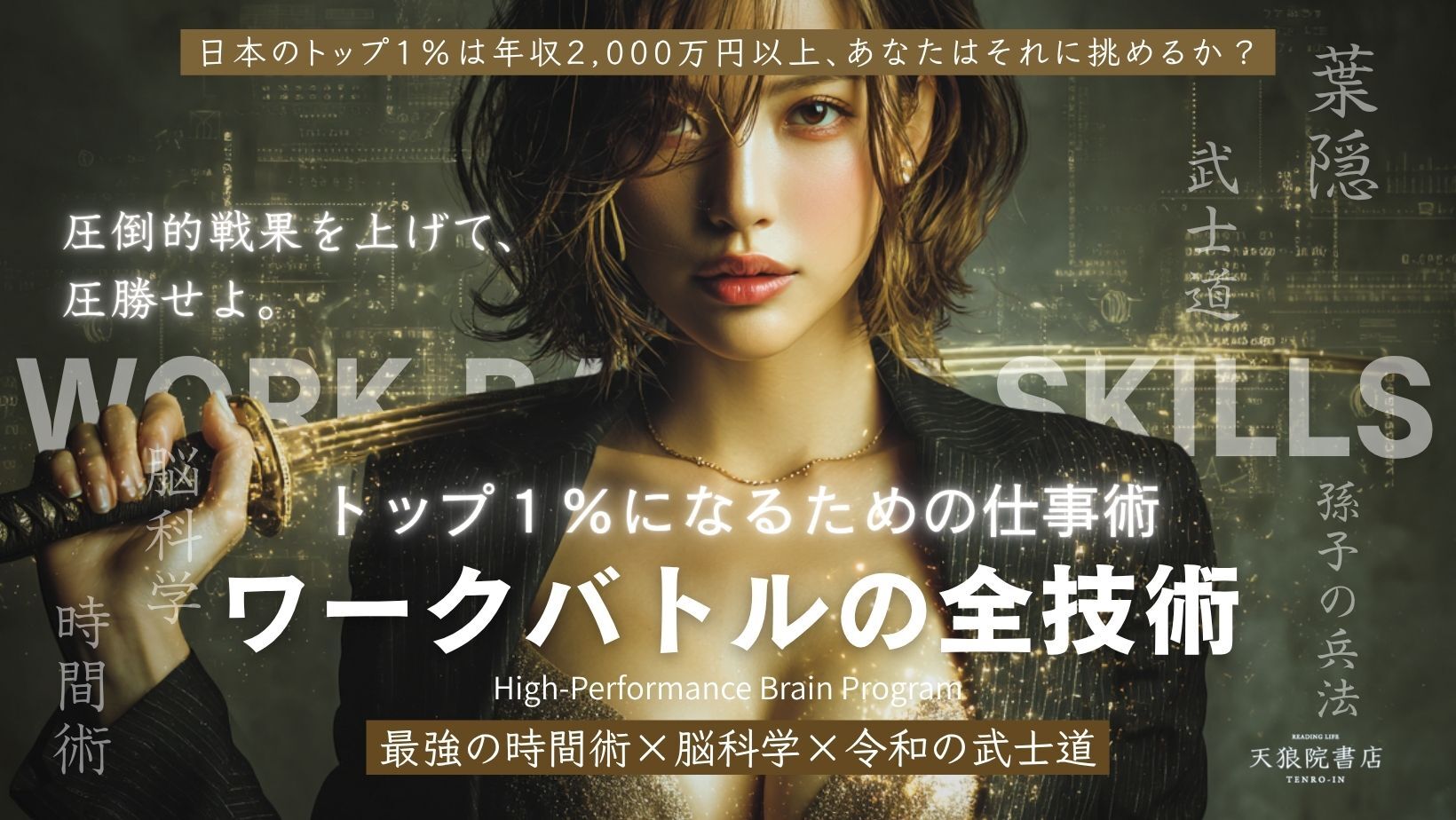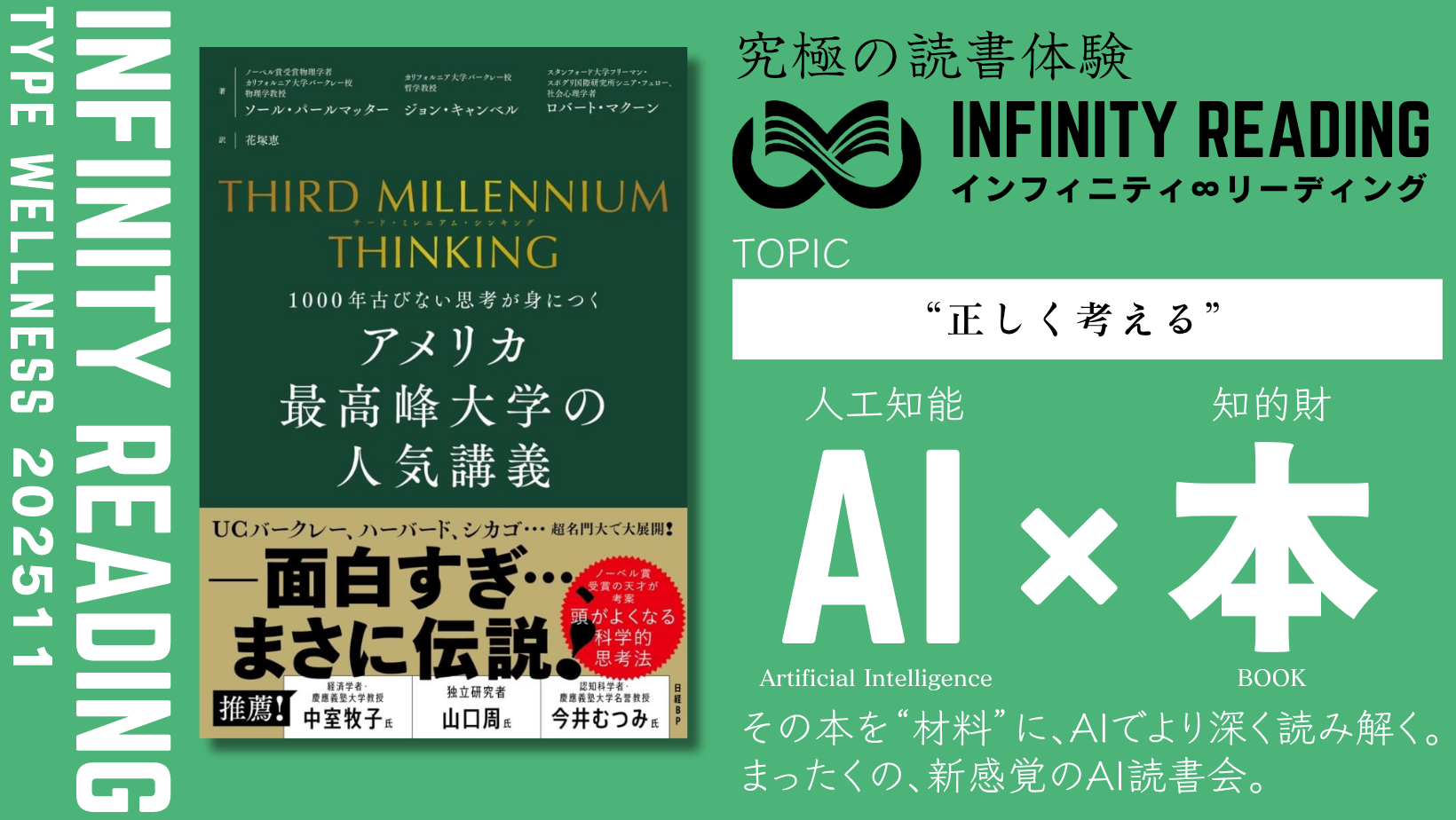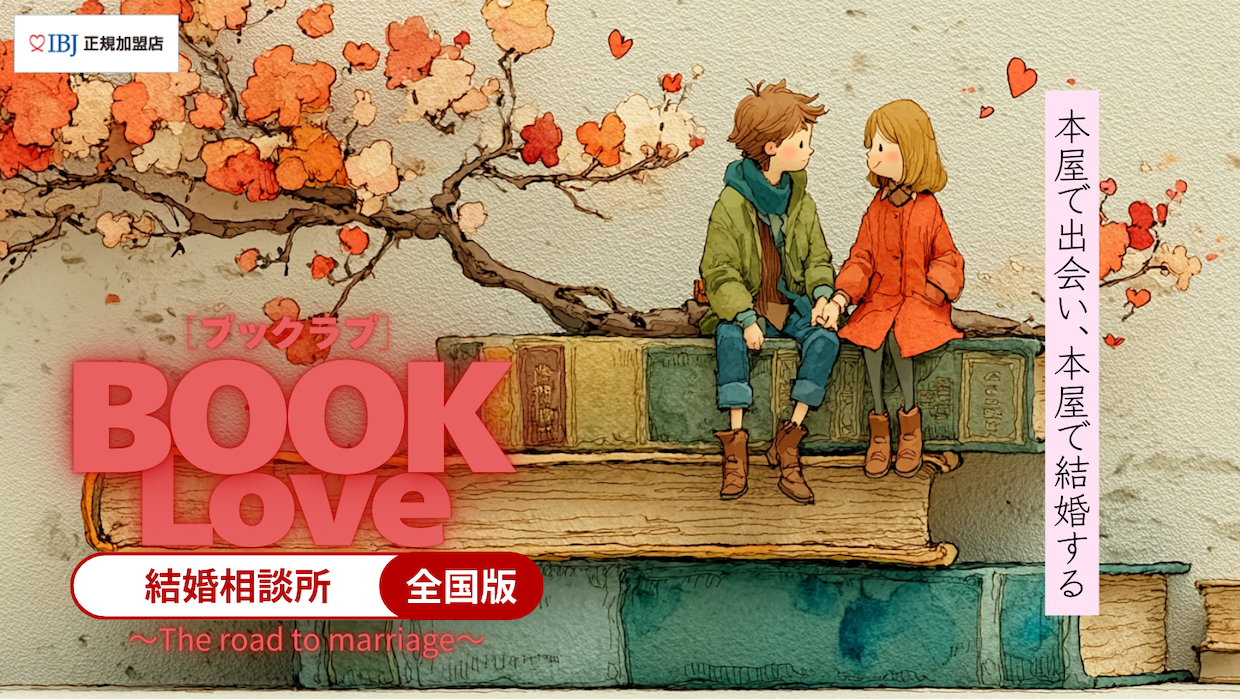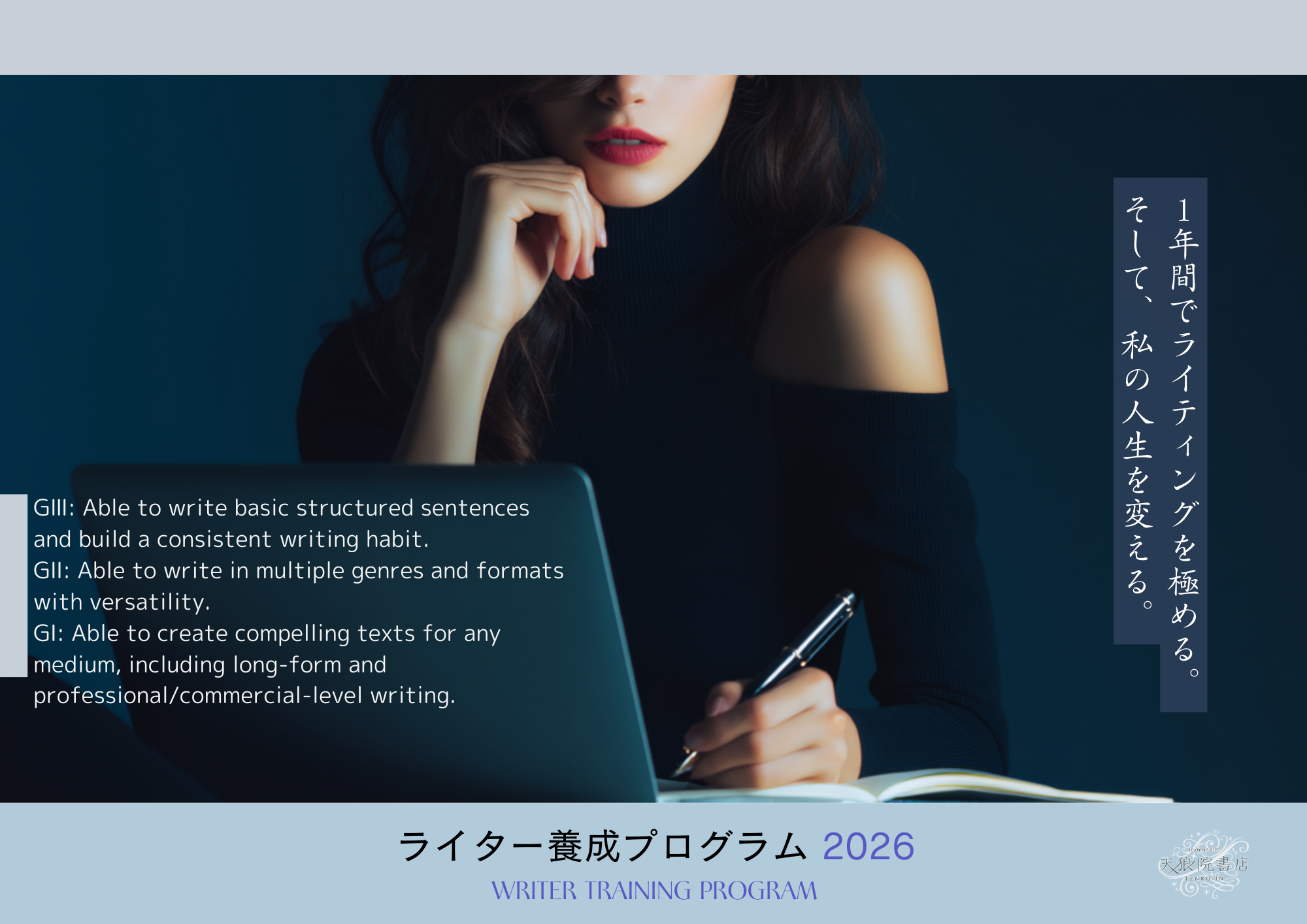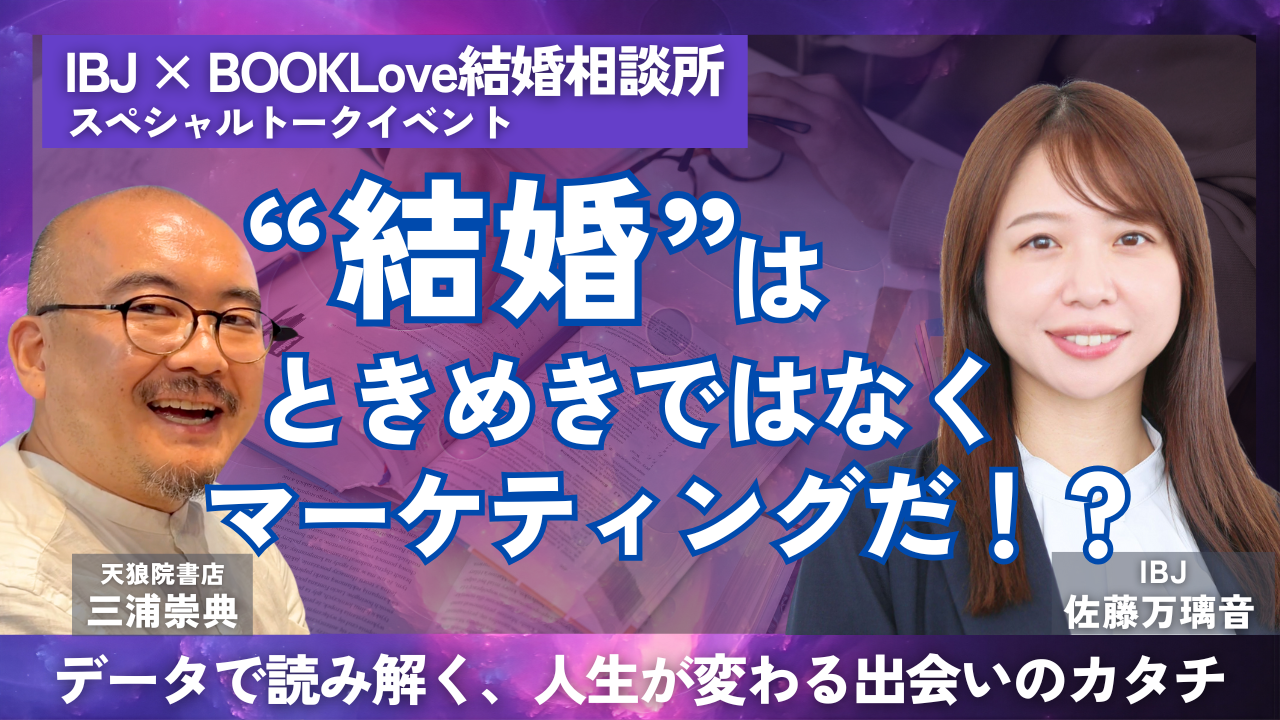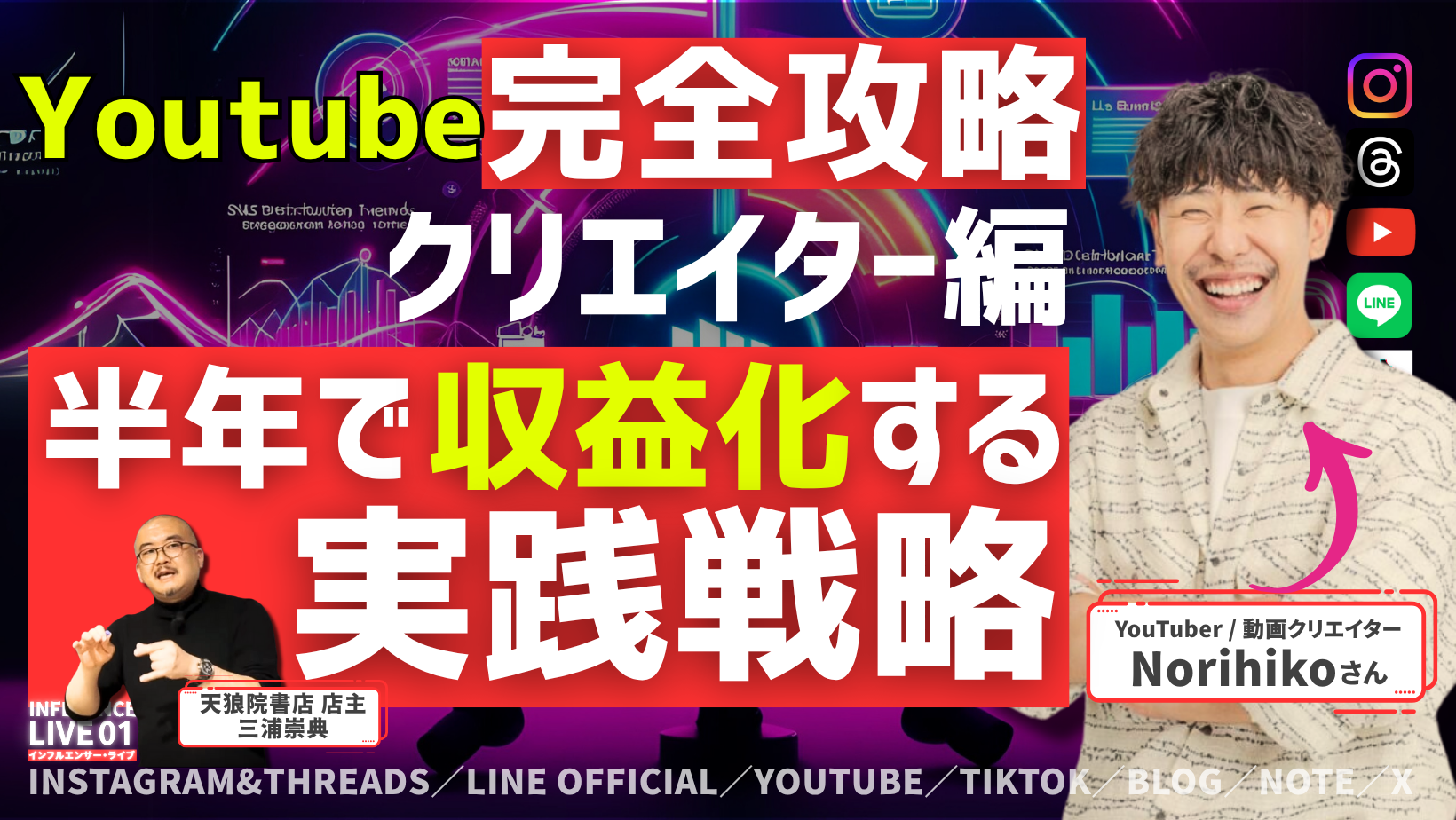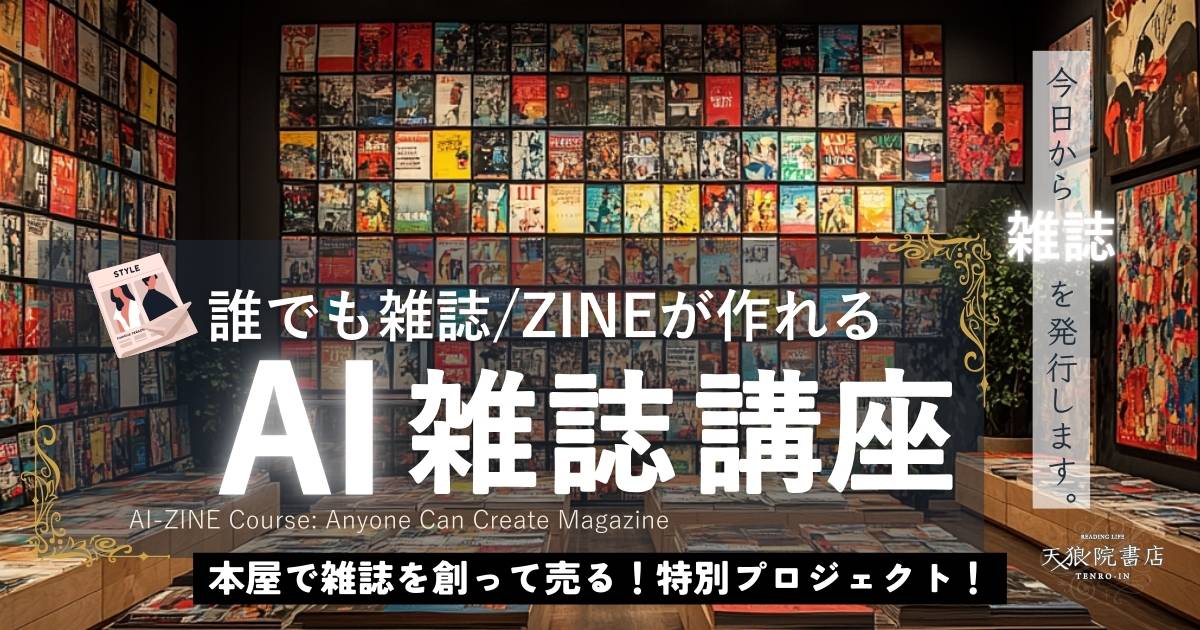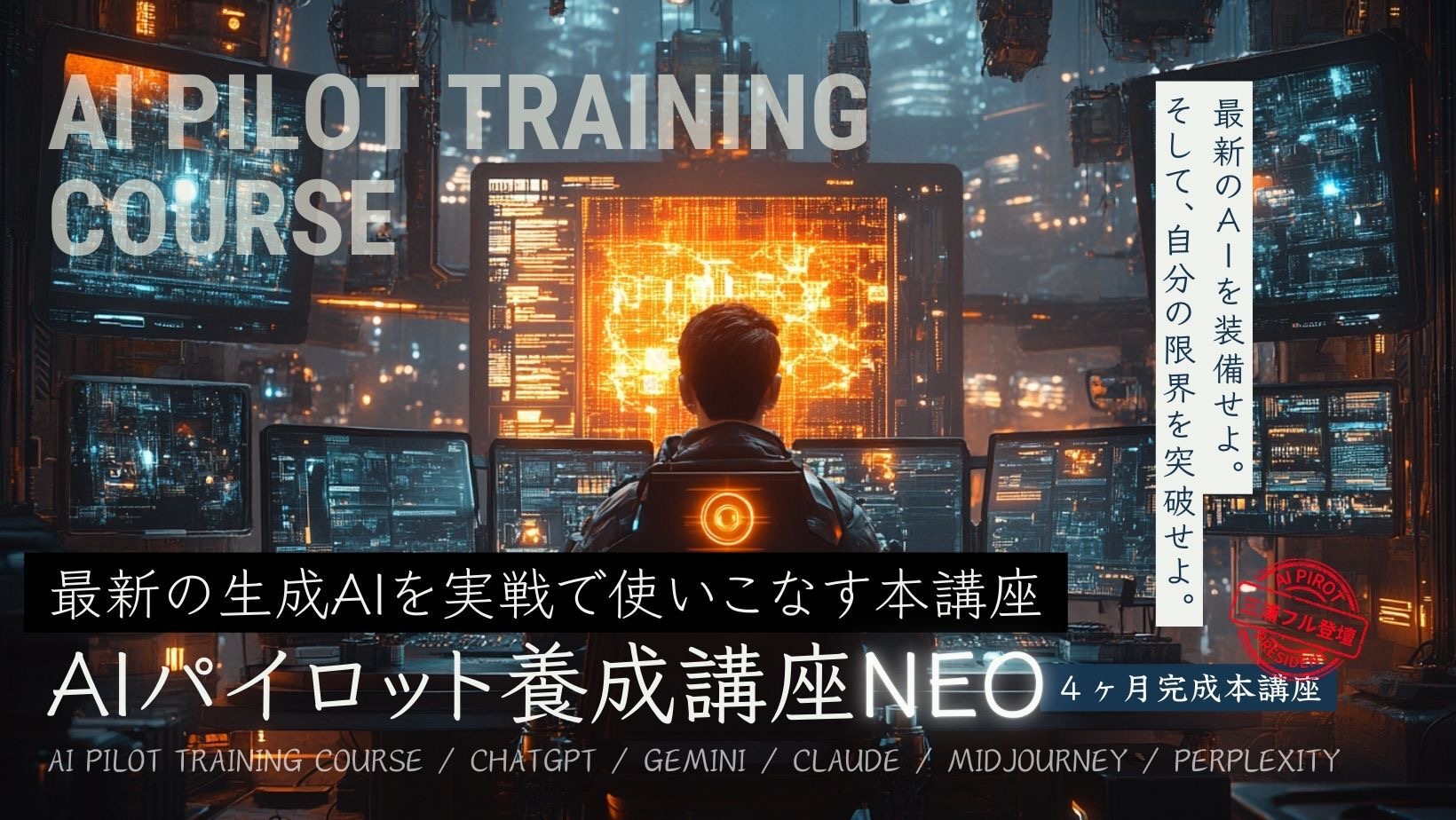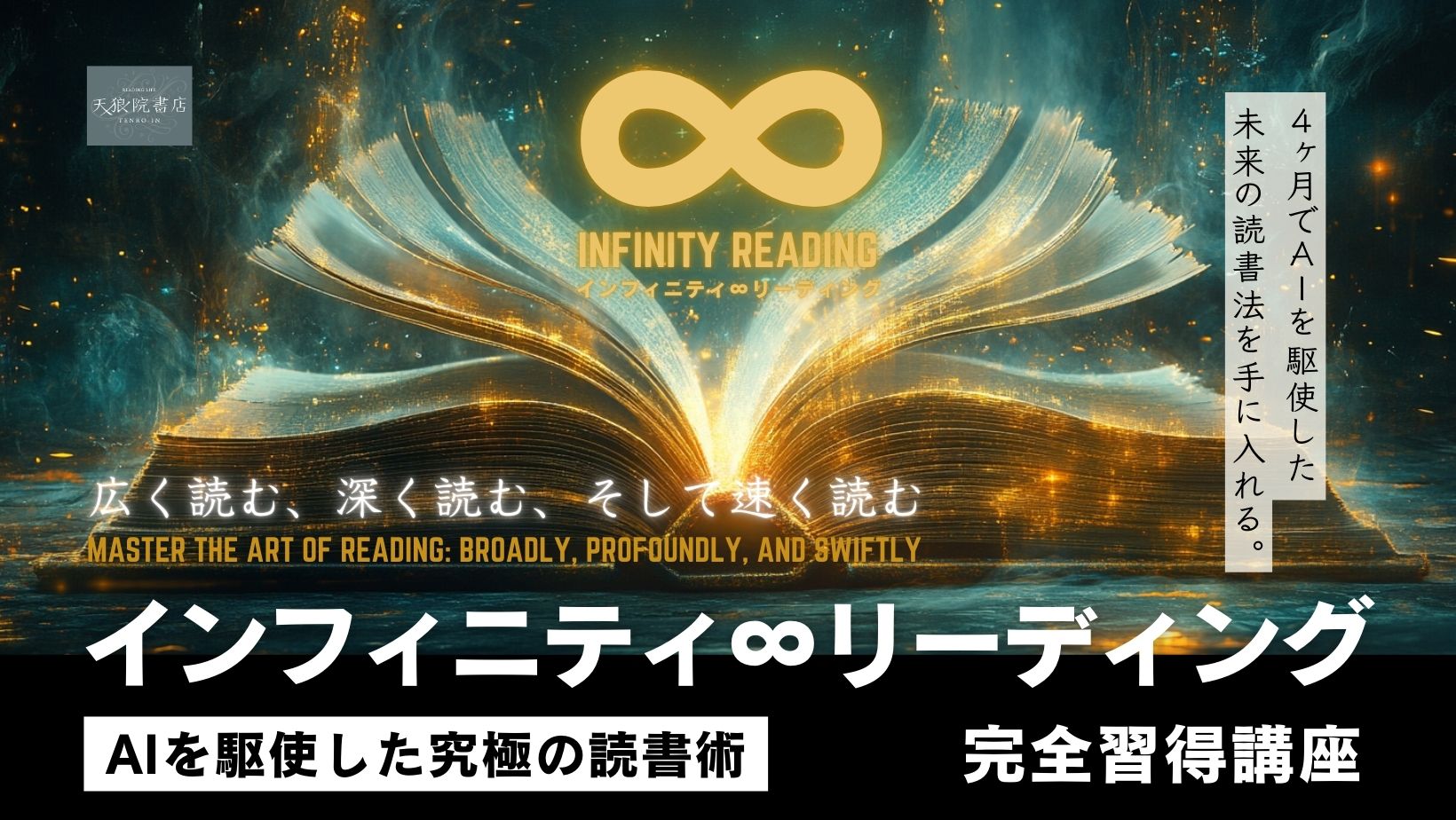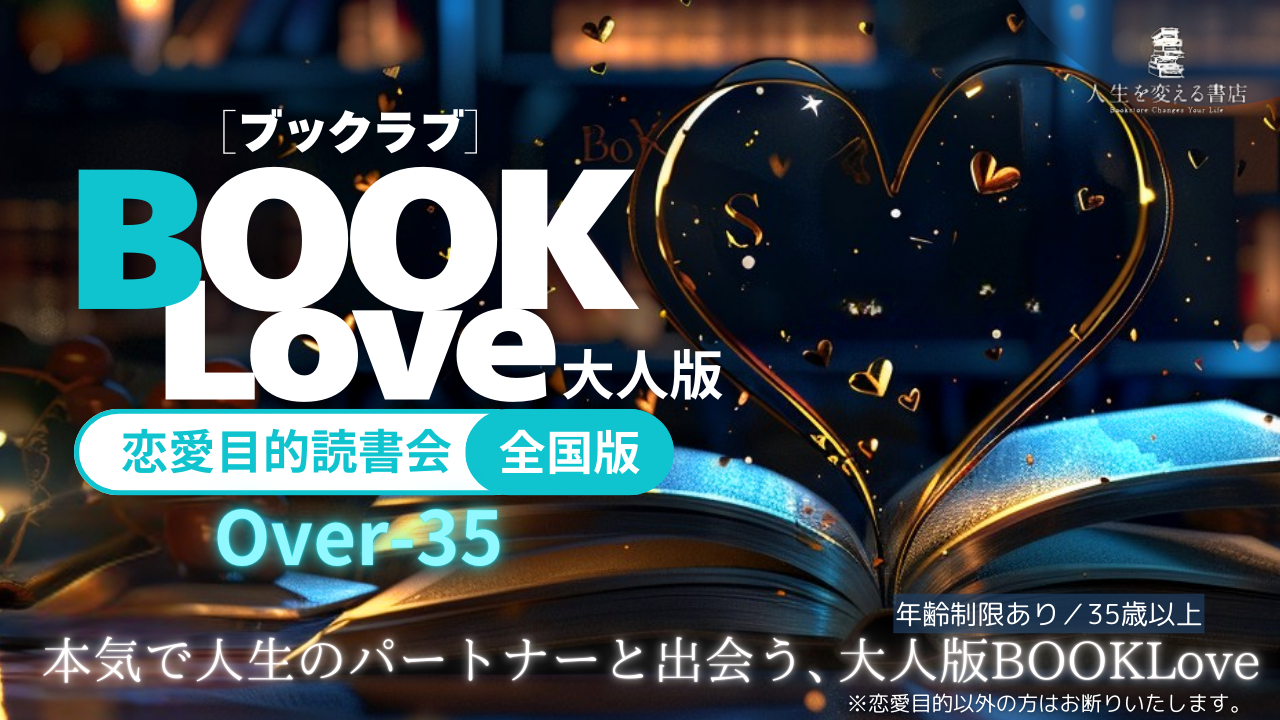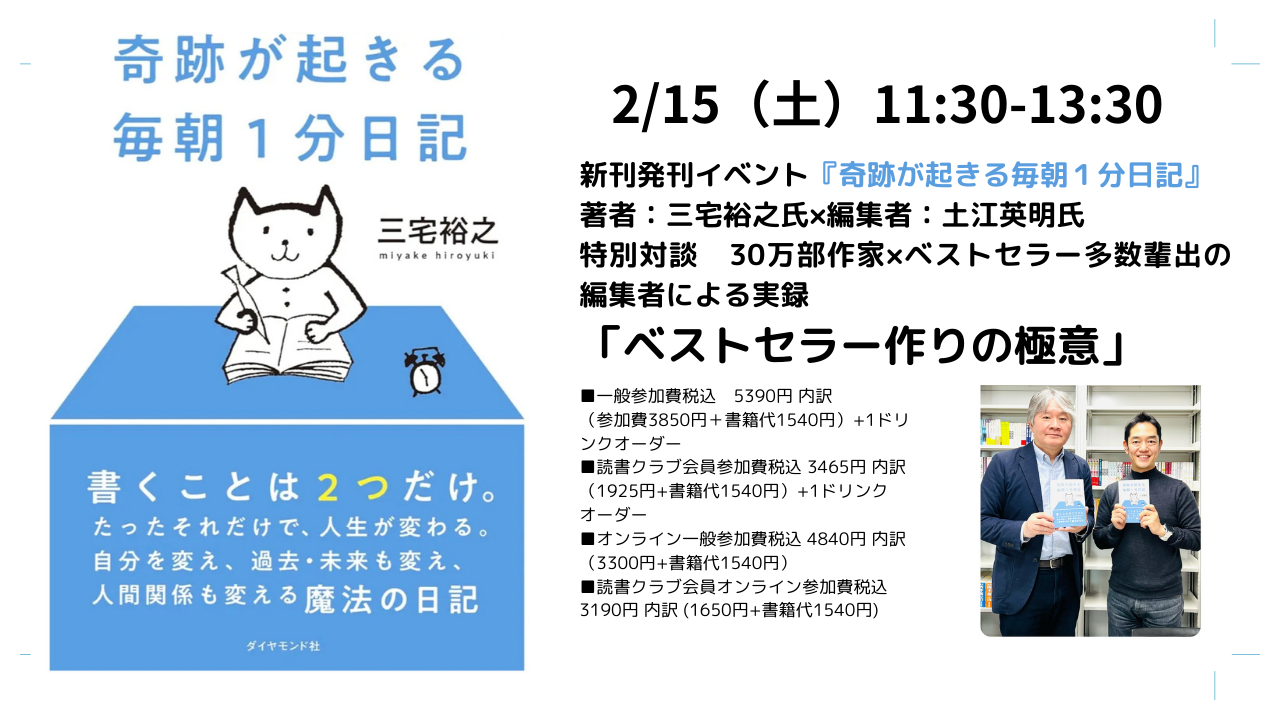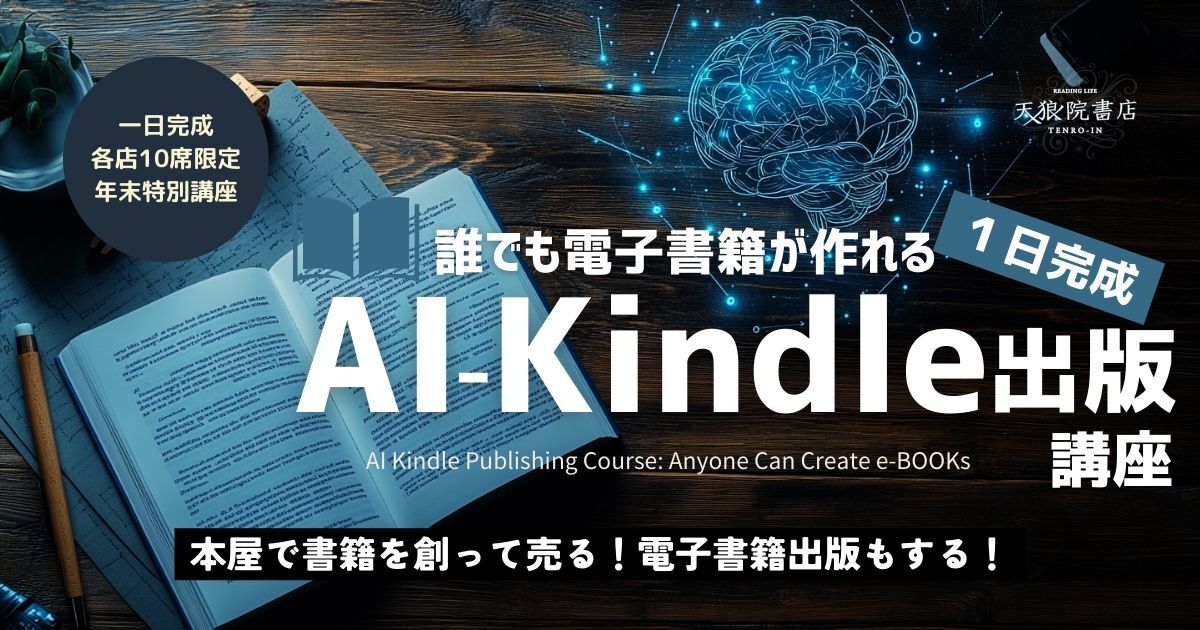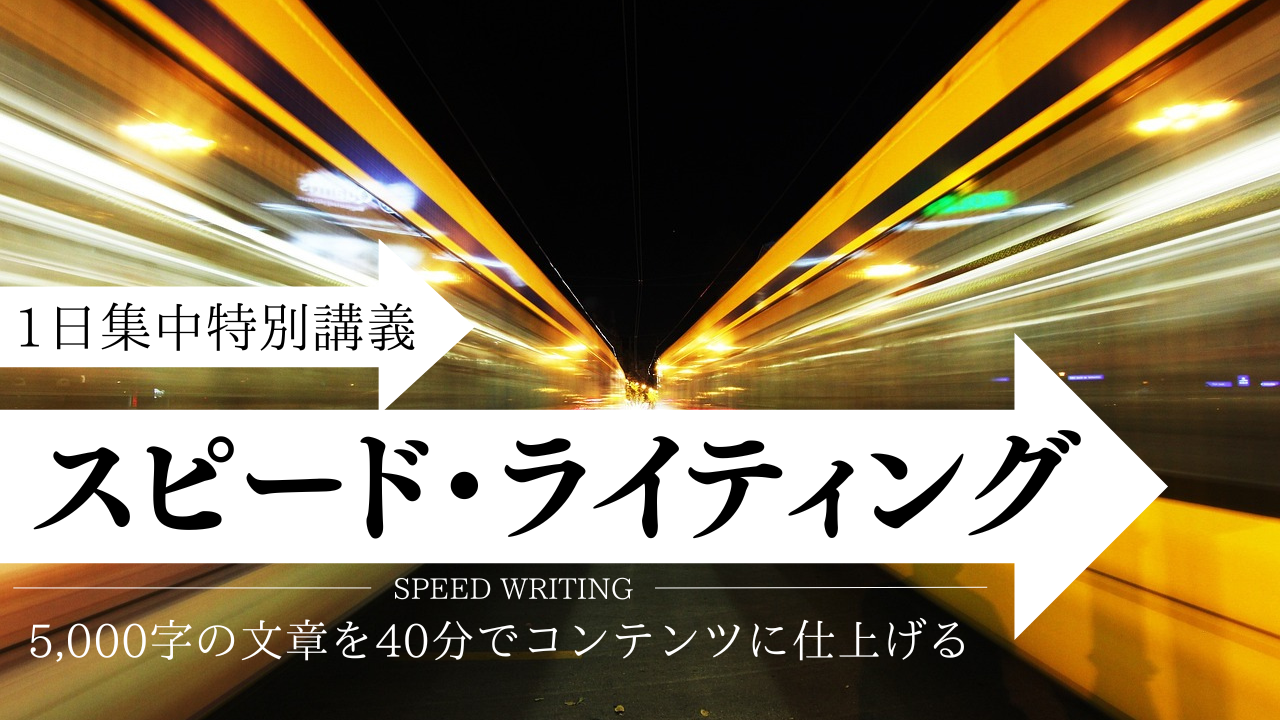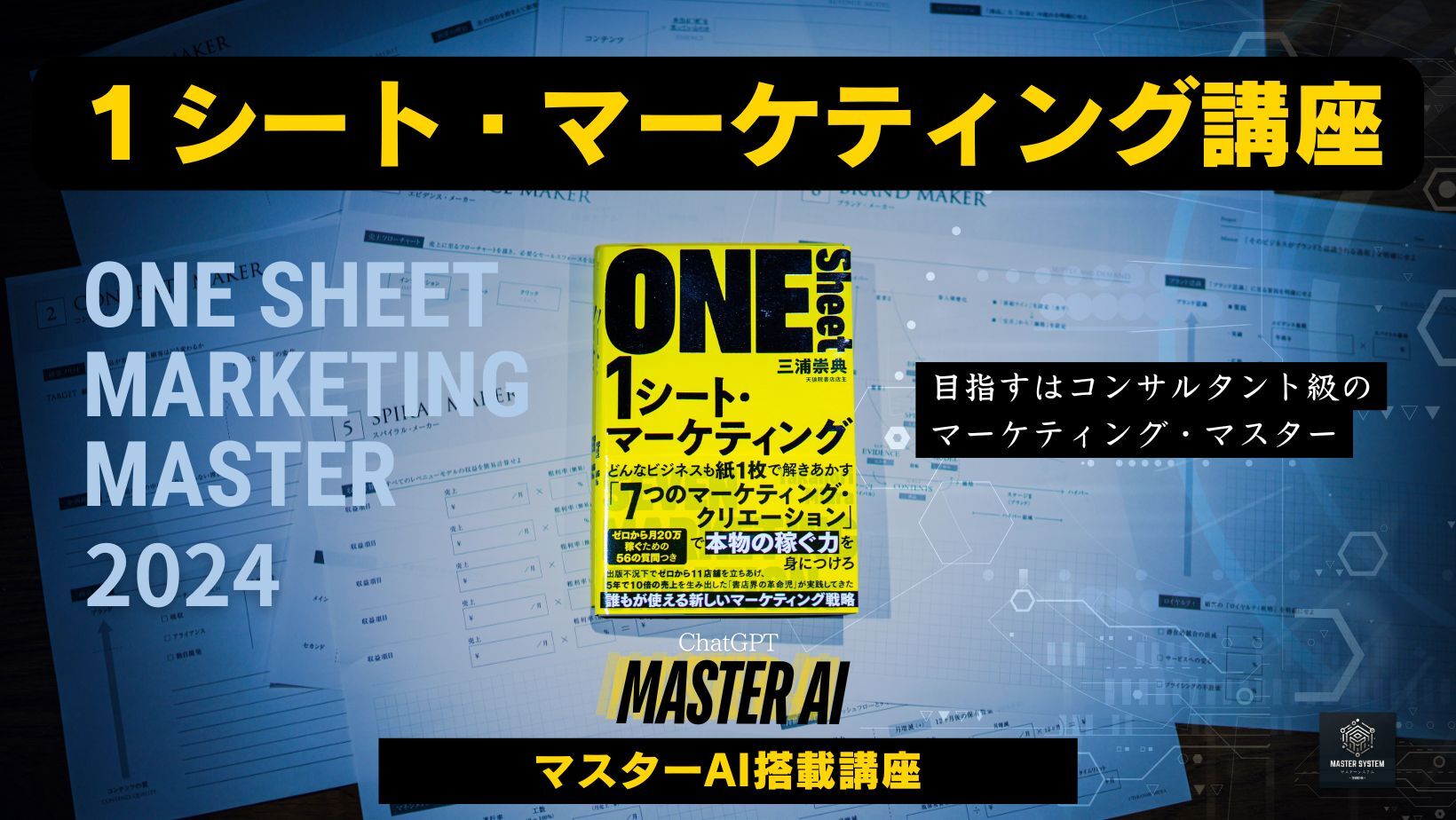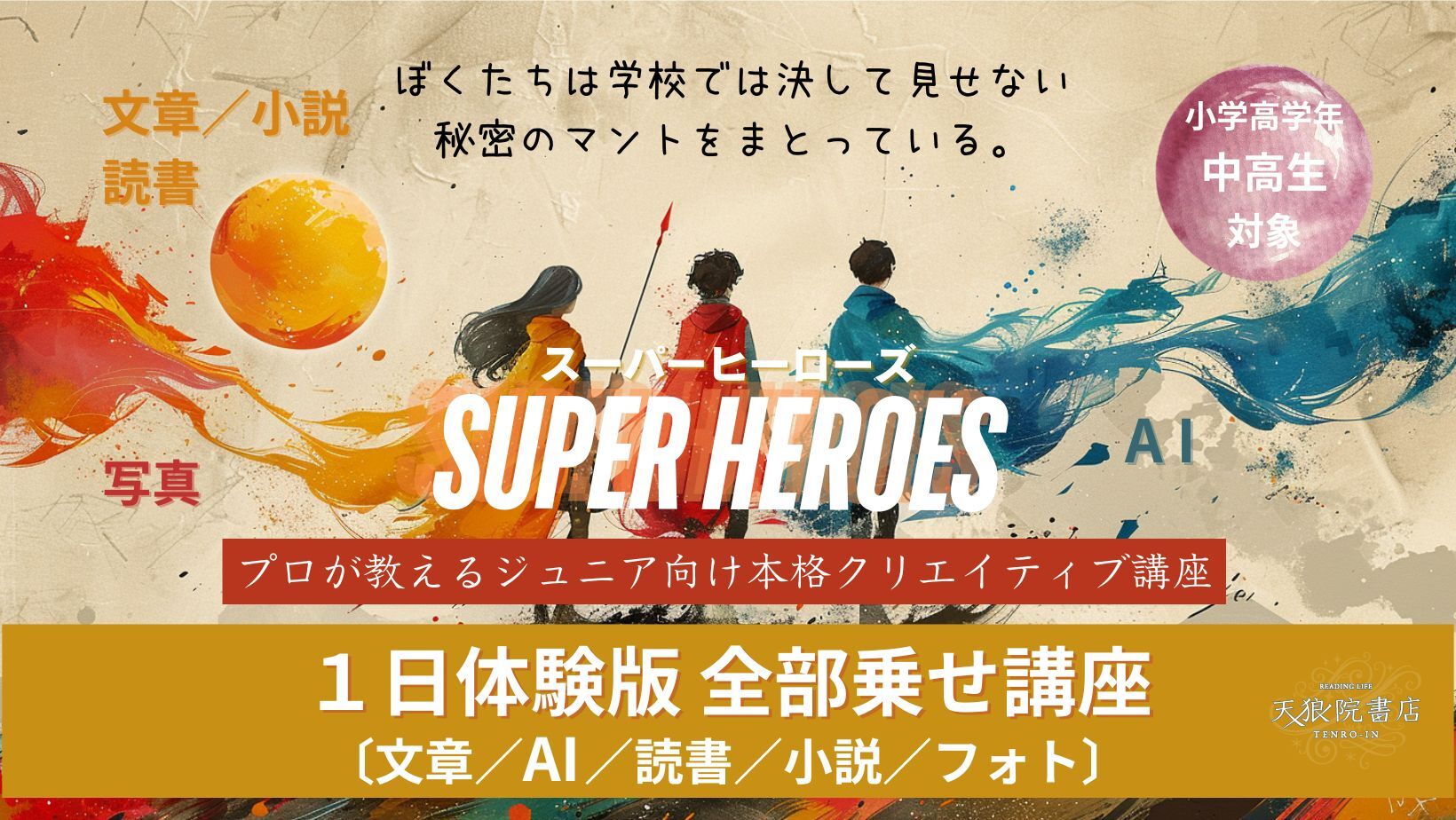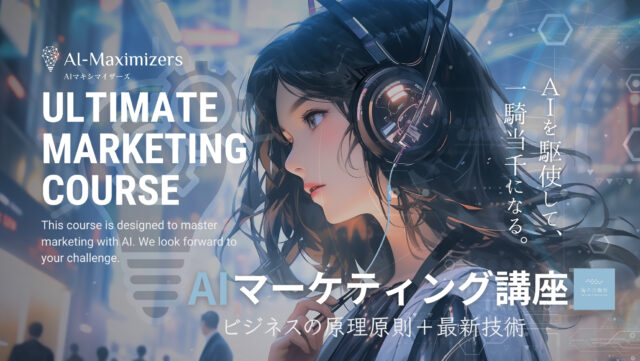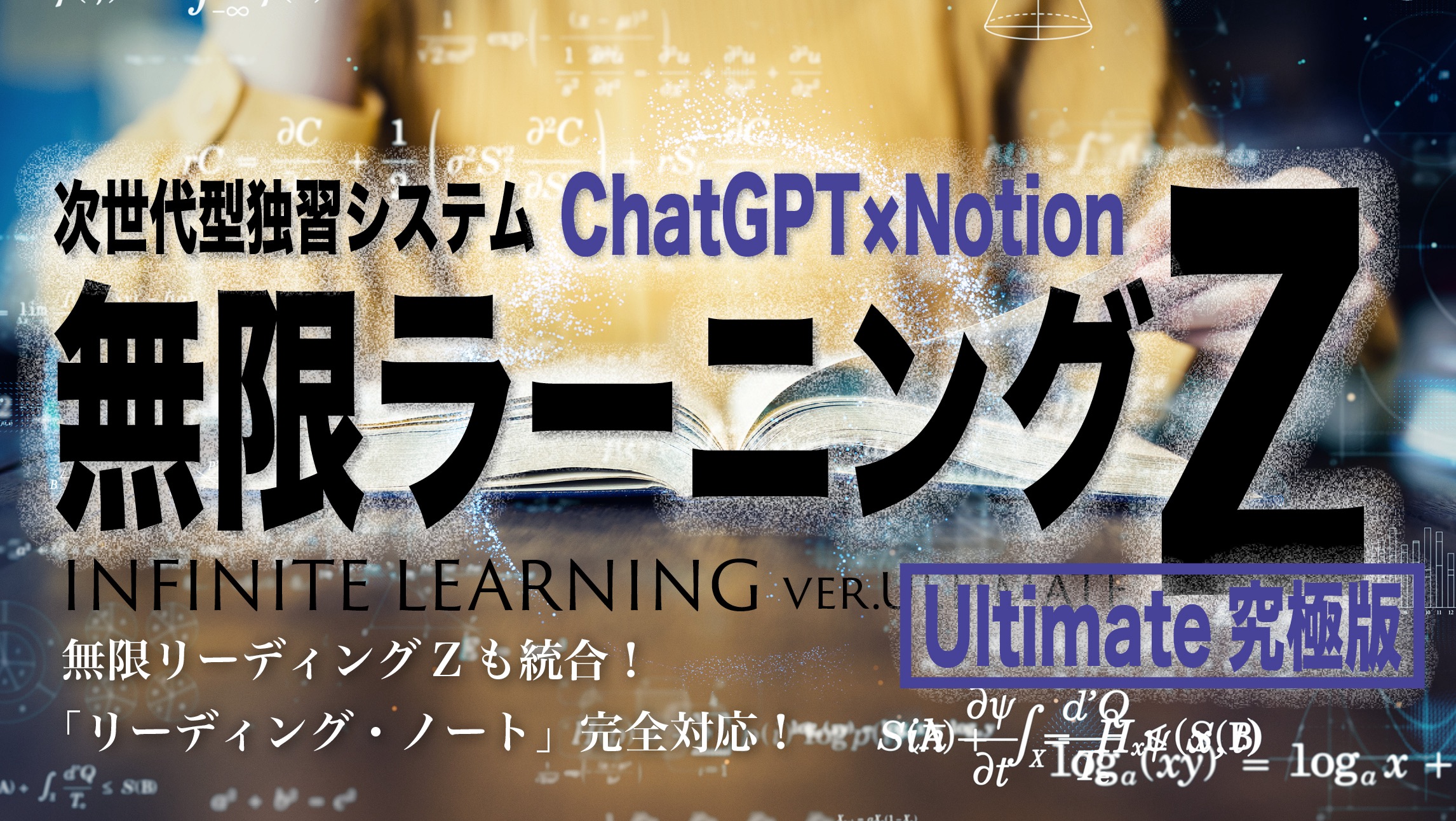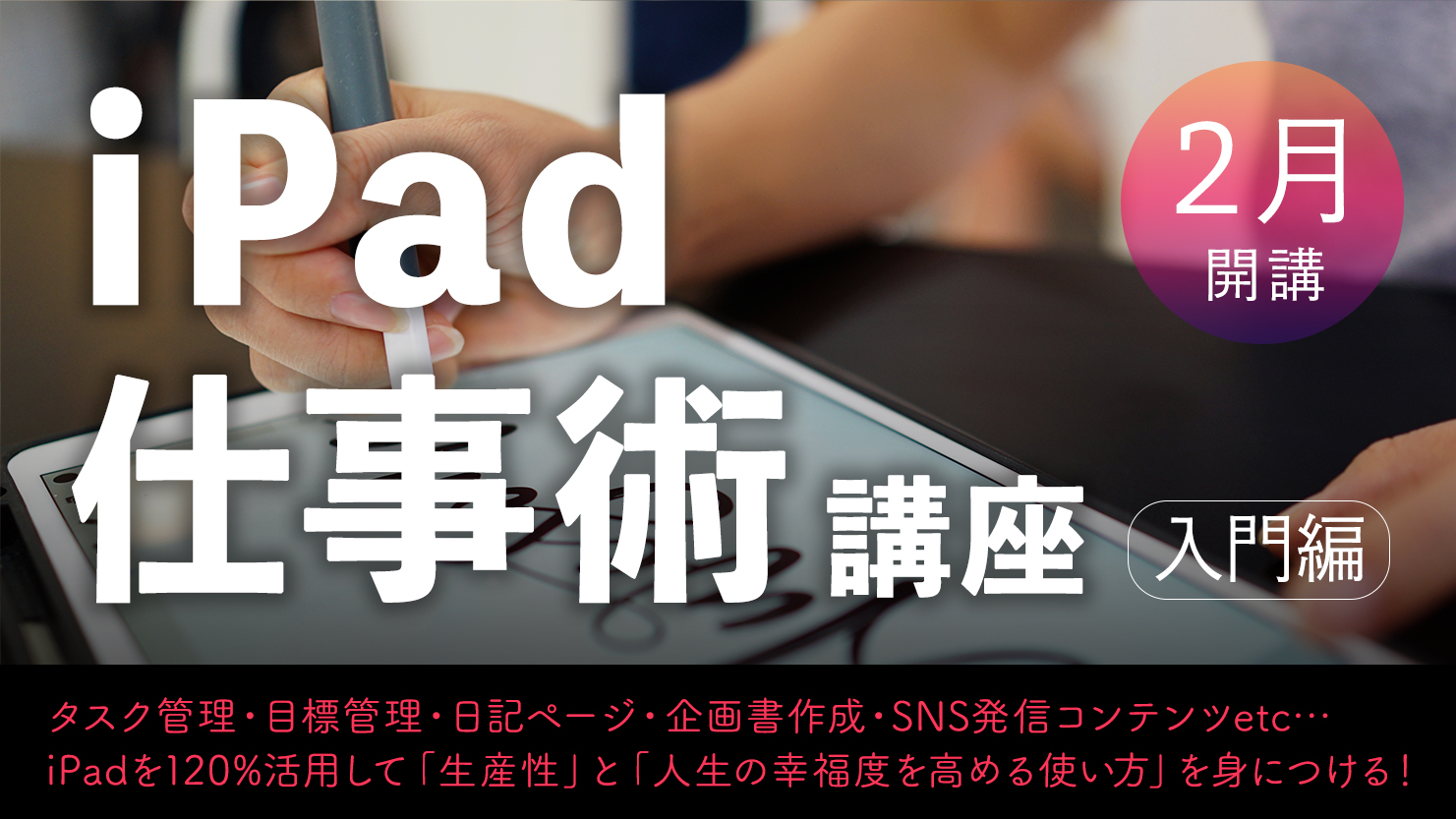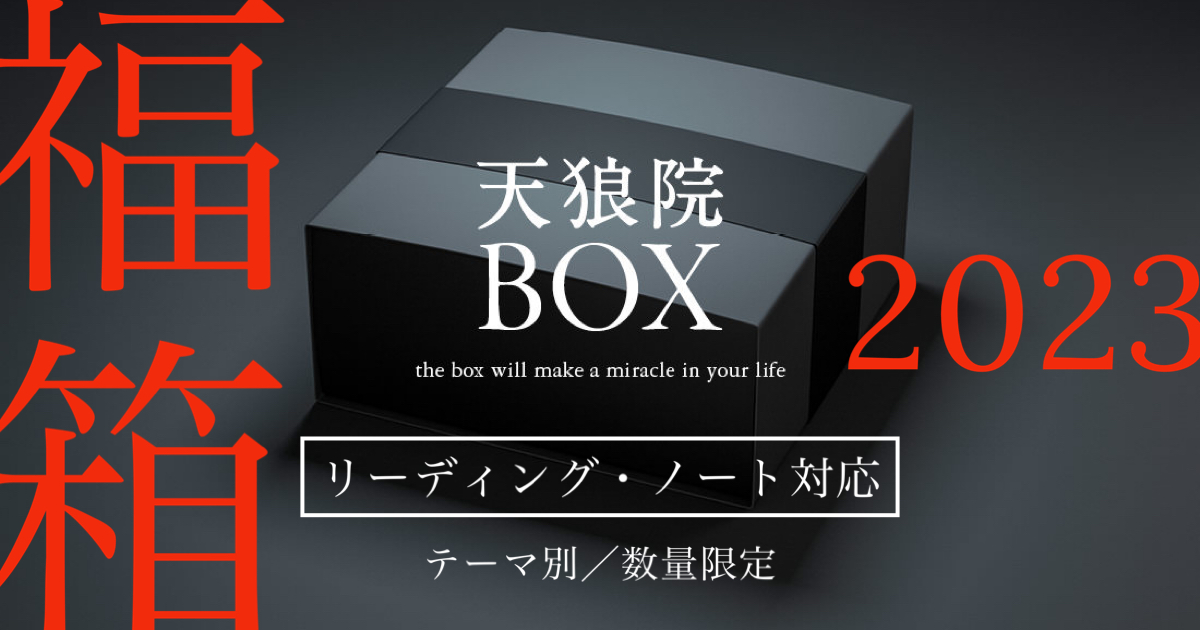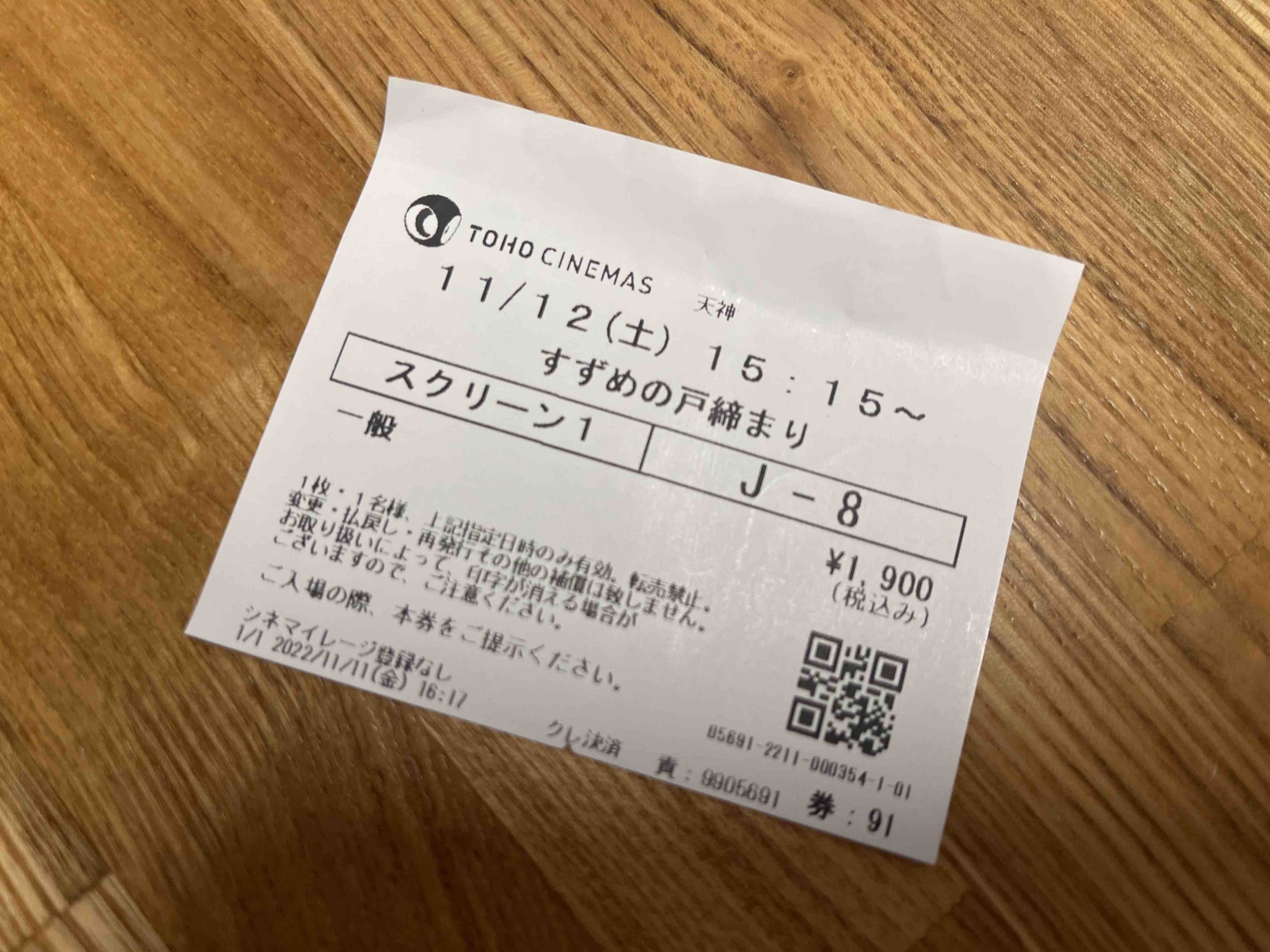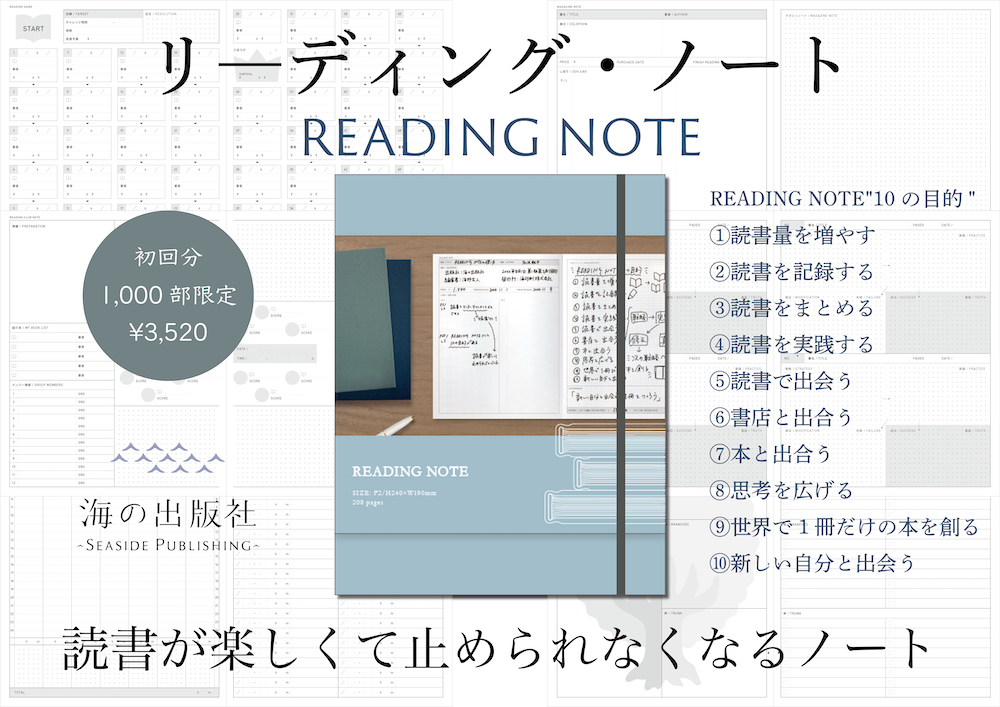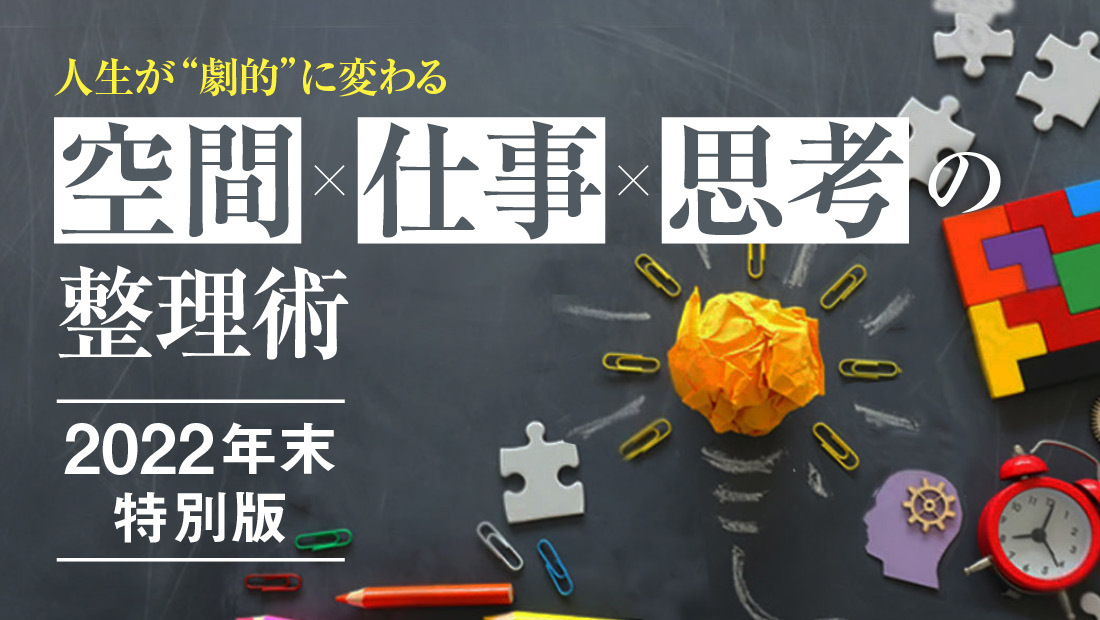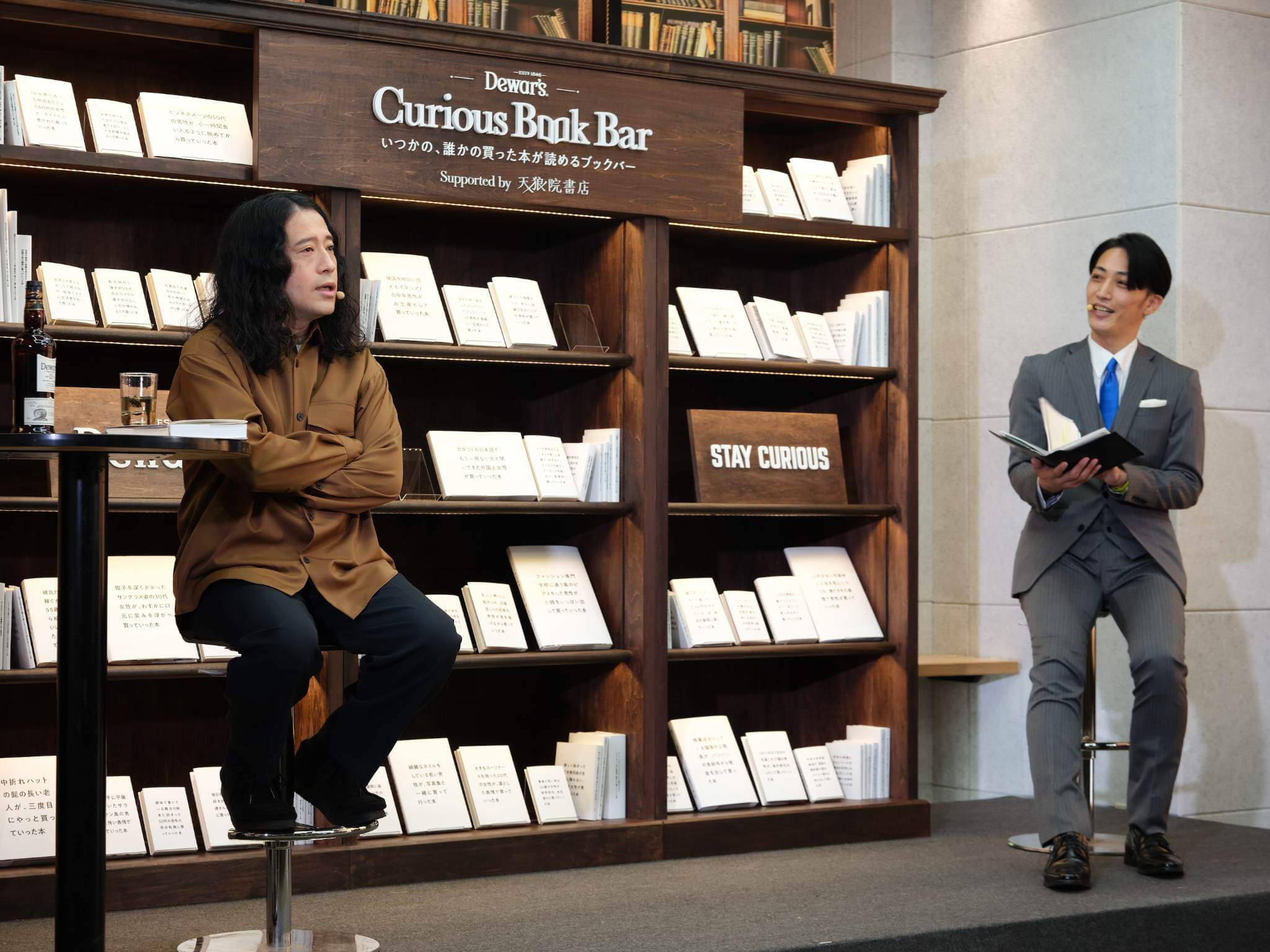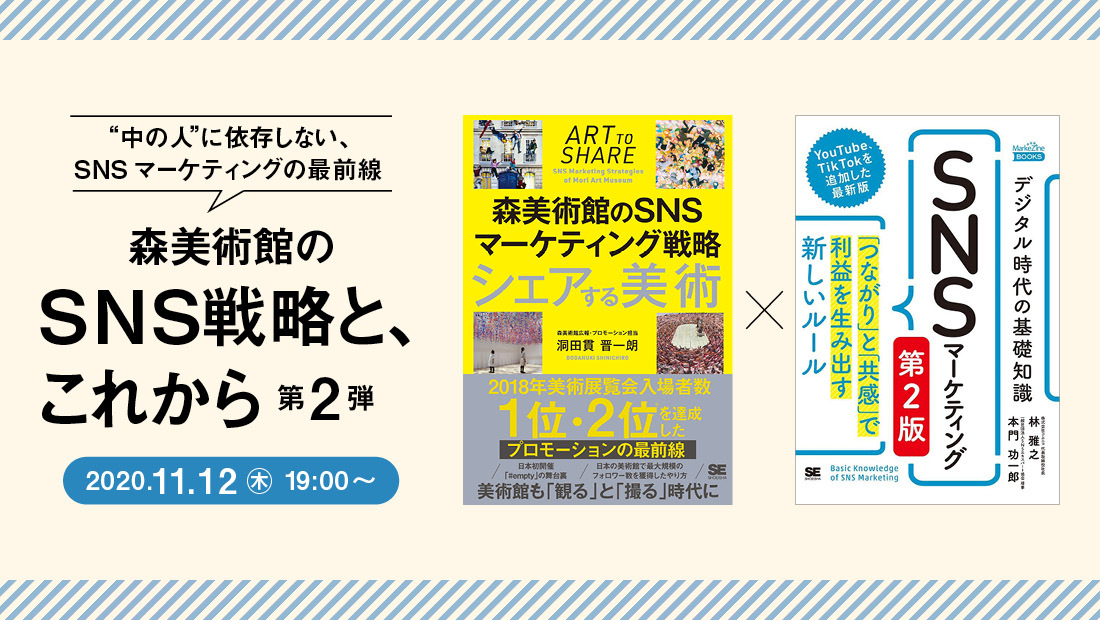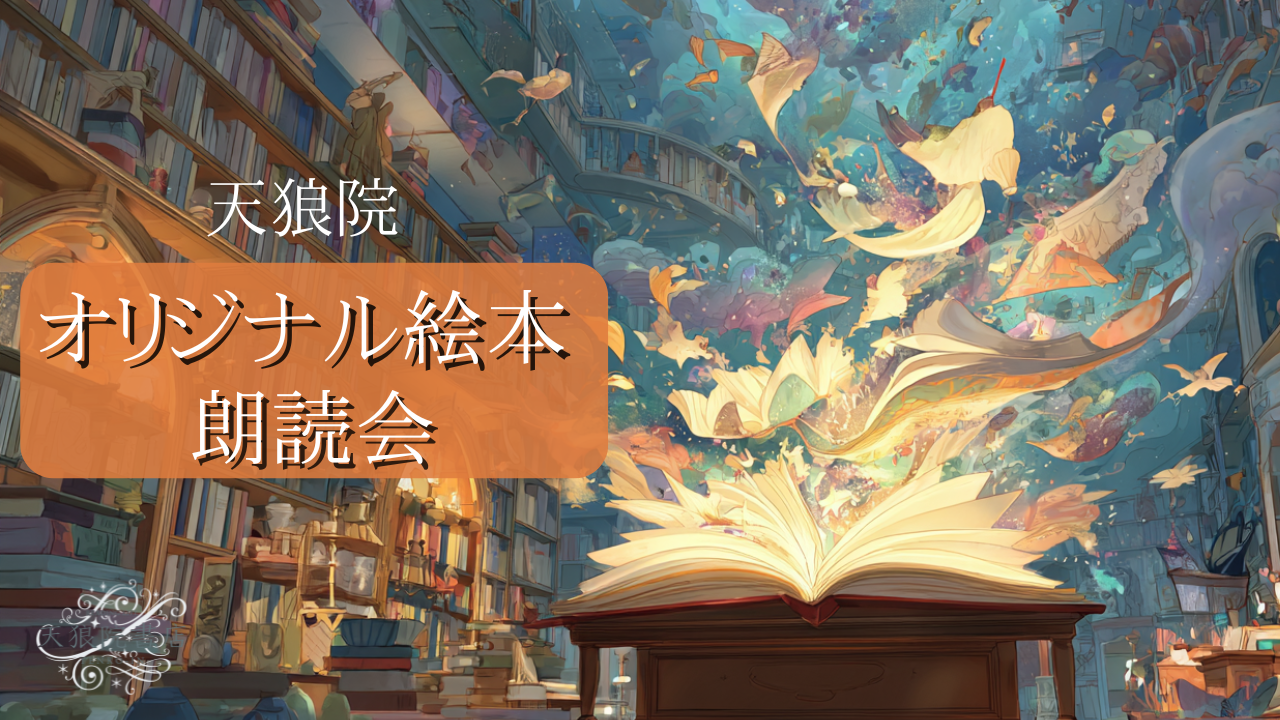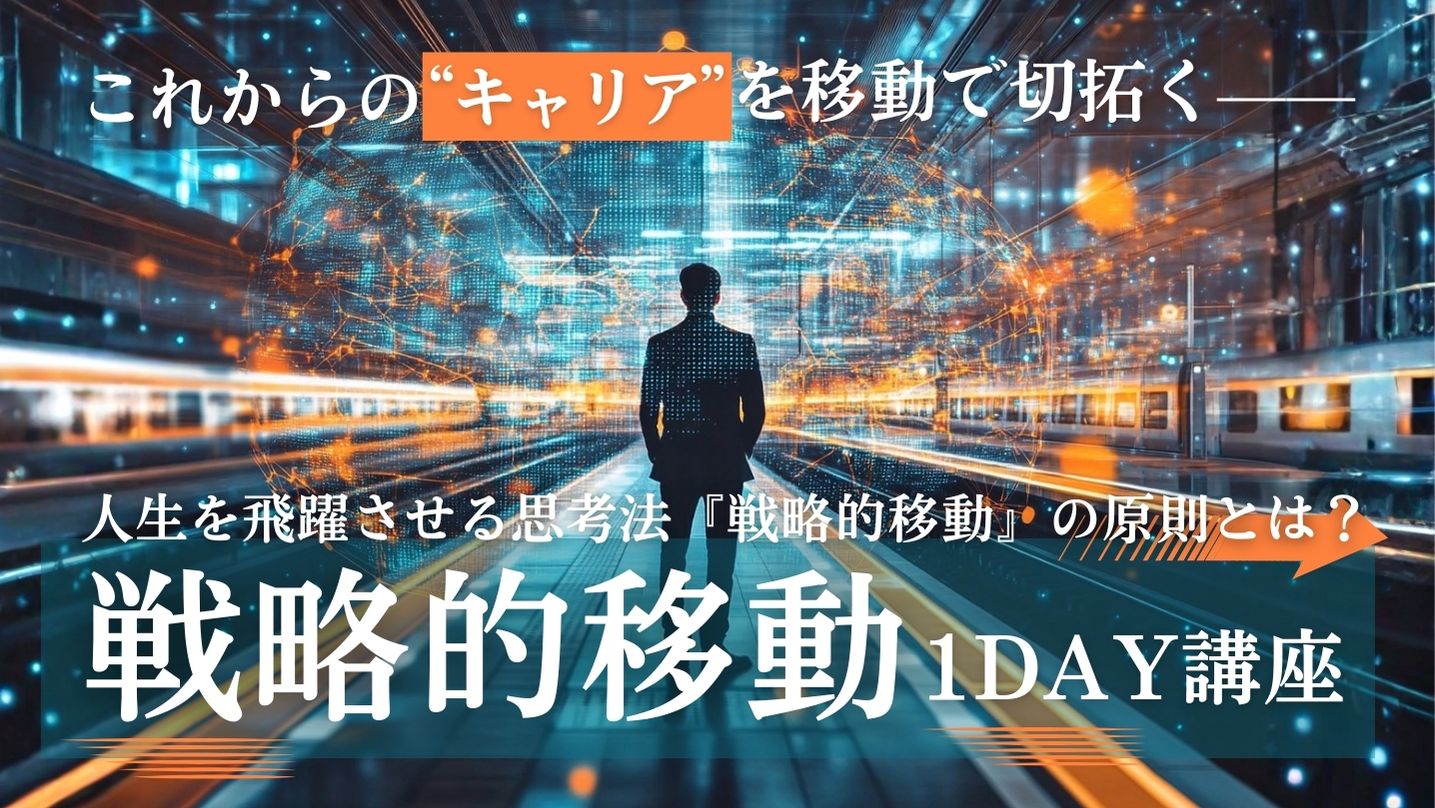徳の一文字で天下を掴む戦略~~~徳川家康に学ぶ「志に基づく長期戦略をブランドシンボル(花押)に託す」~~~
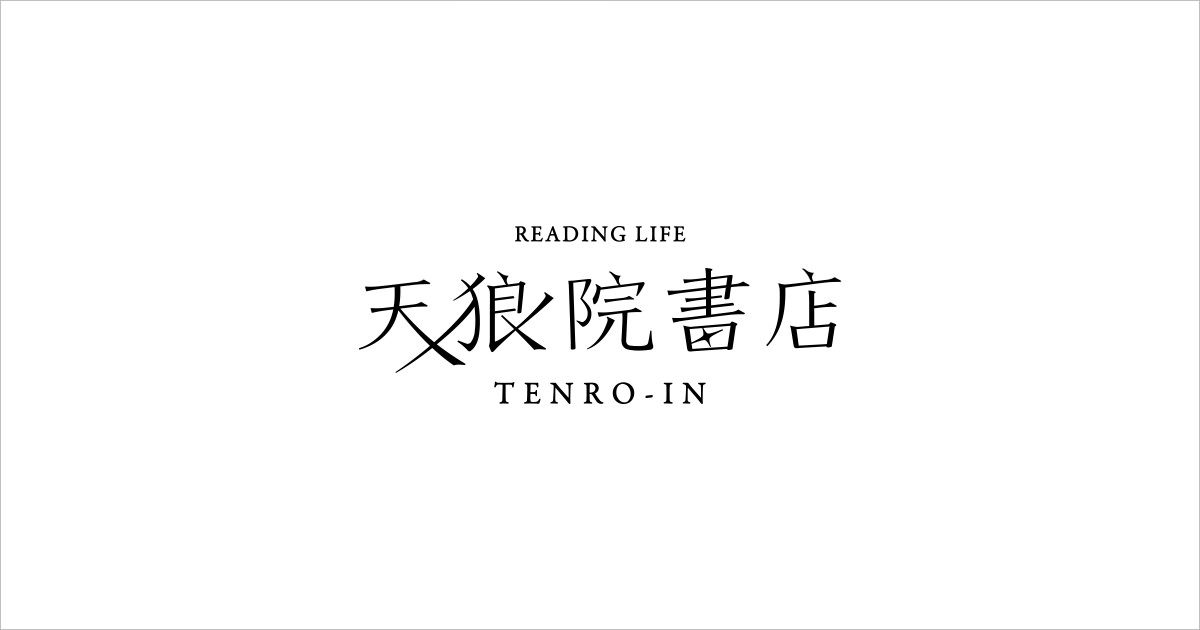
*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
記事:有川翆雲(ライティング・ゼミ3月コース)
徳川家康という名は、日本史上において最も知られた名前のひとつである。戦国乱世を終わらせ、江戸幕府を開き、約260年にわたる泰平の時代を築いた人物として、彼の名は歴史の中に燦然と輝く。しかし、家康がこの「徳川家康」という名前を名乗るようになったのは、彼が25歳となる永禄9年(1566年)のこと。それまでは「松平元康」と称していた。
14歳で元服した家康は「松平次郎三郎元信(まつだいら じろさぶろう もとのぶ)」と名乗った。それは今川義元から「元」の字をもらった名前であった。この時、家康は今川義元もとに預けられていた「人質」であった。
その後、「松平元康、松平家康」を経て、25歳のときに「徳川家康」へと改める。
名前を変えることは戦国武将としては一般的なことかもしれない。だがそこには、極めて緻密で、戦略的な意図が隠されていた。単なる改名ではない。家康は自らの人生哲学、政治理念、野望=志、未来構想のすべてを、「徳」の一文字に込めていたのだ。
時は永禄9年(1566年)、家康は三河国を平定し事実上の支配者となっていた。だが、ただ力で領地を支配しただけでは、人々の心はついてこない。支配には「正統性」が必要だった。そこで家康は、朝廷から「三河守(みかわのかみ)」という官職を授かり、公的にその地位を認めてもらおうと動き出す。
しかし、その道は平坦ではなかった。松平家は地方の豪族に過ぎず、その系譜も不明瞭で、貴族社会からの信用には乏しかった。この当時官職を朝廷に申請する場合、室町幕府を通じて行うものだったが、この時期の室町幕府は将軍不在のという異例の事態となっていた。やむなく家康は関白・近衛前久を通じて直接朝廷に任官を求めるという「異例のルート」をとらざるを得なかった。
当初、家康は清和源氏の新田家の流れをくむ「得川氏」が先祖であるとして改姓を申し出たが不調に終わった。紆余曲折があり、藤原氏の分流「得川(とくがわ)氏」であると主張し、「松平」から「得川」へ改姓することを申し出て、「藤原得川家康」として「三河守」に任官を許されることとなった。
だが、ここで注目すべきは、朝廷の記録には「得川」という字が用いられているのに対し、家康本人はあえて「徳川」と記している点である。なぜ「得」ではなく「徳」だったのか、ここに家康の大いなる「野望=志」が隠されている。
第一に、「徳」は儒教において為政者の理想を体現する文字であるという点が挙げられる。『論語』にある「為政以徳、譬如北辰、居其所而衆星共之」という一節は、徳による統治がもっとも安定的で正しい支配であることを説いている。家康は、後に江戸幕府の儒学顧問となる林羅山らの影響を受け、この思想を政治理念として採用していた。すなわち、武力による覇道ではなく、徳をもって国を治める王道こそが、自らの理想とする統治の在り方であった。
<参考>
読み下し文
政(まつりごと)を為すに徳を以(もっ)てす。譬(たと)えば北辰(ほくしん)のその所に居(お)りて、衆星(しゅうせい)これに共(むか)うがごとし。
現代語訳(意味)
政治を行うには徳によって行うのがよい。たとえるなら、北極星が定まった場所に輝いていて、他のすべての星がそのまわりをめぐるようなものである。
第二に、「徳」は宗教的な意味も持っていた。家康は浄土宗の信仰が深く、「厭離穢土 欣求浄土(おんりえど ごんぐじょうど)」を旗印として戦場にも掲げていた。「徳」の字には浄土宗における「功徳」の意味も含まれており、彼の戒名「東照大権現 徳蓮社」や日光東照宮の神号にも通じている。宗教的正統性の演出もまた、家康の戦略の一環であったのだ。
第三に、「得」は「利益を得る」という意味が強く、戦国の世においては世俗的な響きを帯びていた。これに対し「徳」は、より高潔で道徳的な響きを持ち、支配者としての品格を高める意図があったと考えられる。家康は、松平一族との差別化を図るとともに、新たな支配体制の象徴として、「徳」の字を選び取ったのである。
こうして改姓された「徳川家康」という名は、やがて江戸幕府の正統な姓として全国に広まり、以後の将軍家にも受け継がれることとなる。そして、家康はこの「徳」の字をモチーフに花押を創り「志の花押」として大切にした。
これはまさに、「徳」の精神を秩序と安定の象徴として表現したものと見ることができる。
花押とは公的な文書に用いられる「本人認証」としてのサインであり、いわば家康の「ブランドシンボル=権威の象徴」である。家康はこの「志の花押を」、公文書や命令書、外交文書などあらゆる重要書類に用いた。それはまさに、「この国は徳によって治められている」というメッセージを、家康自らが「志の花押」によって国中に発信していたことになる。
家康の生涯を振り返れば、戦いに明け暮れた時代を駆け抜け、信長・秀吉という強烈なカリスマと時に争い、時に協調しながら、最後に天下を手中にした稀代の戦略家である。その彼が、最終的に「徳」の一字に全てを託し、天下泰平の礎を築こうとした事実は、我々に多くの示唆を与えてくれる。
徳川家康の「徳」は、単なる文字ではない。それは彼の「野望=志」そのものであり、戦略であり、未来への祈りでもあった。そして家康は「徳による政治」を「志の花押」というブランドシンボルに永遠に刻み込んだのである。
この花押に託された「野望=志」の深淵さ、それこそが、徳川家康という人物を読み解いてくれる、最も雄弁な手がかりなのかもしれない。
***
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)
TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792
営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F
TEL:0466-52-7387
営業時間:
平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00