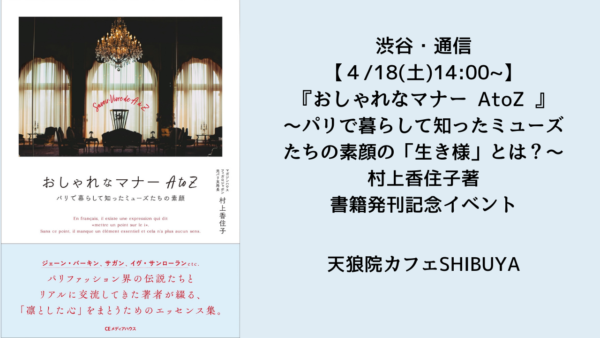【京都天狼院物語〜あなたの心に効く一冊〜】第六話 トラウマを消し去りたいあなたへ 前編≪もえりの心スケッチ手帳≫

文:鈴木萌里(京都天狼院スタッフ)
「もえりさんは、4月からどうするんですか?」
香り立つボロネーゼをくるくるとフォークに巻きながら私にそう訊いてきたのは、失恋の悩みを打ち明けられて以降、なんだかんだで仲の良い友人となった仲野香穂だった。
今日は、一年の終わりが迫った12月末の土曜日。私たちは時々こうしてお昼や夜に一緒にご飯を食べるのだが、この日も例に漏れず、最近京都にできたばかりだというイタリア料理店を嗅ぎつけて来ていた。
京都には全く異常なほどに飲食店がたくさんある。単なる思い込みかもしれないけれど、街を歩けば、「ここも、ここも!」と一本の通りに気になるお店がずらりと並んでいるのだから、収拾がつかない。とりわけ京都天狼院のように、町家の造りを残した和テイストなカフェは、私の好みのど真ん中を貫きすぎて、訪れても訪れても、「行きたい店リスト」はなくならない。あの京都天狼院で一番カフェに詳しいユキさんでさえ、「行きたい店があと80軒ある!」と語ってくれたほどだ。
そんなこんなで、「行きたい店リスト」に名を連ねていた新しいイタリアンの店の門を、私は香穂と、ようやくくぐることができたのだ。
そこで散々メニューとにらめっこした挙句、香穂はボロネーゼを、私はジェノベーゼリゾットを頼んだ。
「4月から?」
「はい。もうすぐ卒業ですよね」
そう、私は大学4回生で、香穂は大学3回生。彼女よりも一年早く卒業する(予定の)身だった。
「あれ、言ってなかったっけ?」
まだ会って間もないのに、香穂とは好きな作家の話をしたり頻繁にLINEしたりしていたため、すっかり何でも話していると思い込んでいた。なんてったって、出会って最初に話したのが、失恋話だったから。しかも、香穂はかなり落ち込んでいて重たい空気だったし。今となっては良い思い出だけれど、冷静に考えると初対面で恋愛なんていう一番プライベートで繊細なところの話をしてしまったのは、なかなかクレイジーなのではないかだろうか。
「聞いてません!」
むうっと頰を膨らませている香穂。その頰の奥にはきっとボロネーゼがいっぱい詰まっているんだろう。何にしろその顔が素晴らしく可愛いから、全くもって文句はない。
「そっか、ごめんごめん。えっと、4月からだっけ。普通に働くよ」
「その、“普通の”の部分を詳しく知りたいんですが」
彼女の言うことは最もだ。
私は大事な部分をすっ飛ばして、ものすご〜い概略を話したという自覚があったから。もはや確信犯だ。何でかって? そりゃあ、自分の進路を人に話すことほど面白くないことはないと思うからに決まってるじゃない。
「えーっと、とりあえず普通の会社に、就職します」
さっきよりは幾分かマシな説明じゃないか、と思いながらそう言ったが、香穂は私のことをジト目で見てくる。あっ、怒らせてる? でもそんな表情もまた可愛い。
「教えてくれないんですね?」
はあ、残念。
とばかりにため息をつく香穂。
「自分の就活の参考にしたかったんですけど……」
ああ、そうか。
そうこうしているうちに、香穂の学年も本格的に企業の採用試験が始まる時期になるのだ。だから私に進路を聞いたのか。察しの悪い先輩で申し訳ない。
と反省し、私は彼女に、就職してからの仕事を説明した。とはいえ、私もまだ働いたことがないため、これまでに情報収集した内容しか語れなかったけれど。就職にヒントを求める後輩への誠意は見せられただろう。
「なるほどです」
ふんふんと相槌を打ちながら私の話を聞いてくれた香穂が、納得した様子で頷いた。良かった、上手く伝わったかは分からないけれど、彼女が求める答えには辿り着けたようだ。
「でももえりさんは、作家になりたいんじゃないんですか?」
香穂の質問に、私は思わず「え?」と、ジェノベーゼリゾットをスプーンですくおうとしていた手を止めてしまった。
「なんで……?」
なんで、そのことを知ってるの?
スプーンを握っていた右手を下ろして、私は彼女に問いかけた。
だって、あまりに唐突だったから。
私は香穂に、自分の将来の夢なんて話したことはなかった。彼女と話すことはいつもおすすめの本の話、新作で「これはっ!」と目をつけている本の話、それから女の子が大好きな恋愛トークだけだ。
「すみません。この間、聞いたんです」
「聞いたって、誰から?」
全てが疑問だった。香穂の口から「作家」なんて言葉が出てきたその時から。私の夢の話を聞いたとすれば、それはたぶん。
「京都天狼院の店長さん——、確か、ナツさんでしたっけ」
やっぱり。
香穂が私のことを聞いたとすれば、そこしかないよなあ……と、情報の出所がナツさんならひどく納得がいった。
「はい。ついこの間、お店に行ってみたんです。その時はもえりさんはシフトに入ってなかったんですよね。『もえりさんはいますか?』って聞いたら、今日は休みだって、その店長さんが教えてくださいました」
うーん、やっぱりそうなんだ。
私がバイトに入っていない日に香穂が店を訪れていたって、全く不思議ではない。
「そっか。それで、ナツさんと私の話をしたってことかな?」
「そうですそうです! もえりさんに悩みを聞いてもらうまでの経緯とか、その後も仲良くやってるんですよ〜って話をしたんです。あんまり他のお客さんもいなかったから、ついつい話し込んじゃって。ナツさんってすごく親身に話を聞いてくださいますよね。話をしてるうちに、ふともえりさんはこの先どうするのかなって思って、聞いてみたんです」
そしたら、もえりさんには小説家になるって夢があるとナツさんが教えてくれました。
香穂は、ナツさんとの会話を思い出しては本当に楽しそうにその内容を語ってくれた。
もちろん京都天狼院書店のこともたくさん話を聞いたみたいだが、彼女が楽しそうなのは、今まで知らなかった私の夢を、第三者つてにでも知れたからだろう。
「で、どうなんですか? 働きながら小説を書くんですか?」
香穂のまあるくて大きな瞳が、私の心の目にそう問いかける。
私は今日香穂に会うまで、まさか彼女からこの手の核心的な質問をされると思っておらず、対応に戸惑う。できることなら話を上手く逸らしたいのに、私を見つめる彼女の瞳はもう、私の心の一番深い根っこのところまで掴んで離さない。どうしよう、これはもう万事休すか。
「まあ、それでもわたしは全然素敵だと思うんですけどね」
「え?」
何て返事をしよう……と困っていた私より先に、香穂は自分なりの意見を私にぶつけてきた。いや、”ぶつける“なんて乱暴なものではなく、間違いなく、私の未来を肯定してくれる言葉だった。
「もえりさんが本当に小説家になりたくて、それでも普通に働く選択をしたのなら、わたしはそれが一番だと思います!」
なんだこの子は。
まるで、私が欲しい言葉をテレパシーか何かでキャッチしてそのまま口にしてくれているかのような。
世間はこういう他人を、“自分のことを一番に分かってくれる唯一無二の友達”と表現するんだろう。
「あ〜、わたしも頑張らなきゃなぁ。年明けたら本格的に、就活開始です!」
語尾を盛り上げて気合を入れている彼女の右手に握られたフォークが、少しだけ震えている。言葉でははりきって頑張ろうとしているが、就活期はやはり気持ちが不安定になる。きっと怖いんだろう。分かるよ、私なんて、就職先が決まった今でも怖いもん。少し前に、「本当は就活なんてやめて歌手になりたい」と私に相談を持ちかけてきた香穂の友達の増田くんだって、めちゃくちゃ不安そうだった。みんな不安なんだ。将来とか夢とか、そんな聞こえばかりが格好良い言葉に翻弄されて、悩んで立ち止まって、気づいたら同じ道を行ったり来たりしている。私も、同じだった。
「うーん、美味しかった!」
彼女が、不安に押しつぶされそうな心を抑え込んで、最後の一口だったボロネーゼを呑み込んだ。え、ちょっと待って、私まだあと5口ぐらいある!
彼女に遅れをとりながら、私も空っぽのお腹を満たしてくれるジェノベーゼリゾットを完食した。それにしてもすごく美味しかった。わざわざ新しくオープンした店を狙ってやって来た甲斐があったと思う。
それから私たちはまた少し女子トークに花を咲かせて店を後にした。いつもいつもLINEでやりとりしていても、実際に会って話すとまた新しい話題がどんどん出てくるのが楽しい。彼女とは店員と客という全く違う立場で出会ったのに、すっかり仲良しこよしだ。それだけ最初に出会ったときにシンパシーを感じたからかもしれない。
「それじゃあ、わたしはここで」
二人で最寄り駅まで歩いたところで、香穂が私にぺこりと頭を下げた。
「うん、じゃあまたね」
就活頑張って、という月並みな応援の言葉は心の中でそっと呟いておく。たぶん、わざわざ言葉にしなくても普段のやりとりで十分伝わっているから。「頑張れ」なんてプレッシャーのかかる言葉は、たくさん言わなくていい。
「はい! もえりさん、また小説書いたら、わたしに見せてくださいね」
香穂が最後に、そう私に言ってくれる。
私が作家になりたいなんて夢を持っている話をナツさんとしたことが、よっぽど楽しかったんだろうか。
「分かったよ、絶対教える」
絶対、なんて言葉を使うのはいつぶりだろう。
私の高校時代の恩師が言っていた。高校三年生、受験勉強で情緒不安定になって、一度の試験で落ち込んだり喜んだりしていた未熟な私たちに向かって。
——“絶対”を使っていいのは一度だけ。人はいつか“絶対”死ぬ。それは本当に必ず起こる。だから、それ以外のときに“絶対”なんて言葉を使っちゃだめ。絶対落ちるとか、絶対受かるとか、そんなふうに言うのはだめよ。
賛否両論はあったと思う。
確かに先生の言う通りで、人がいつか死んでしまうという事実以外に、“絶対”なんてないのかもしれない。限りなく100%に近いことであったとしても、それは99.999……%であって、100%にはならない。
私は笑顔で手を振る彼女に、どれだけの確率を見積もって”絶対“と言ってしまったのだろう。
分からない、自分でも全くもって分からなかった。
2019年1月。
実家でダラダラと年末年始を過ごし、帰京したら年明けの京都の人の多さに愕然とする、というのは京都に来て4年経った今でも変わらない。
年末年始の京都は国内でも屈指の有名な寺や神社に訪れる人たちで溢れかえっているので、祇園の只中にある京都天狼院は、一年で一番のかき入れどき。「これでもかっ!」というぐらい店がオープンしている。なんてったって、大晦日から1月初めまでずっと開いているのだ。朝から晩まで一向に客足は途絶えない(と聞いている)。
私が年明けに初めてシフトに入ったのは、そんな超忙しいお正月が過ぎ去った頃だった。時間帯は夕方から夜にかけて。とはいえ、一月はやはりまだ寺や神社を見物に来る観光客が多く、気を抜くことは許されまい。
新年一発目の仕事に精を出しつつ、そろそろ立ち疲れたなーなんて思っていたとき、“その人”は現れた。
「こんにちは」
店内の様子を伺いつつ、開けっ放しの扉からスッと入ってきた男性に、私は見覚えがあった。
見覚え、というか、不覚にも思い出してしまった。
その人は——その男は、店頭で本を並べながら「いらっしゃいませ」と腰を上げた私に目を向けると、「ああ、見つけた」とでも言うように訳知り顔になった。
「お久しぶりですね、鈴木さん」
京都天狼院書店の中で、私のことを名字で呼ぶ人間はいない。それこそわざわざ私に会うために来てくれる知人以外はどこにも。
彼が、その“知人”でなければ一体何だと言うのだろう。
「杉崎さん……」
狭い店内ではもはや逃れようがなかった。私は記憶の底に眠っていたその人の顔と名前を一致させて、そう呟く。
入り口付近に立っている推定50代のその男性は、私が自分の名を呼ぶのを聞いて、嬉しそうに目を細めた。
「覚えてくれていたとは、光栄です」
“覚えてくれていた”だなんて、この間岡本を介して私に手紙を寄越したのは当の本人だ。それで彼の名前を思い浮かべないほど、私は薄情な人間じゃない———と、思いたい。
なんて、他愛ない社交辞令をいちいち噛み砕いてる余裕は、今の私にはなかったのだけれど。それでも、ぎこちない笑顔だけでも彼に向けられたことは、誰か褒めて欲しい。これでもいっぱいいっぱいなのだ。
「いえ。この間、お手紙くれましたよね。それで思い出したんです」
側から聞くととっても白々しい言葉だが、事実だから仕方がない。あの手紙がなければきっと、顔を見ただけで私はこの人の名前を瞬時に思い浮かべられなかったはずだ。
「お読みいただけたんですね。ありがとうございます」
杉崎はそう言うと、恭しく頭を下げた。
「岡本さんとお知り合いだったなんて、すごく偶然ですね。私も岡本さんとは、最近知り合ったものでびっくりしました」
「そうそう、そうだった。英介さんに頼んだんだ。彼が君と知り合いだと聞いて、私の方こそ驚いたよ。だってずっと君に、直接伝えたいことがあったから」
伝えたいことがある。
彼は確かに今、そう口にした。
以前もらった手紙から、彼の“伝えたいこと”が何なのか、なんとなく察していた私は、ギクッと身を固めて身構えた。
それと同時に、次の瞬間彼の口から紡がれるであろうその言葉を、反射的に聞きたくないとも思った。
私の予想が、どうか外れて欲しい。
この一瞬の間に、そんな願いを、心の中で5回は反芻した。
でも。
「私はね、あなたにもう一度小説を書いて欲しいんですよ」
杉崎がにこやかな表情でそう言った。
まさに予想通りの言葉が耳に入ってきて、私は言いようもないほどの虚しさと、苛立ちを感じた。
「……その件に関しては、岡本さんからも少し伝えていただいたかと思いますが、答えは”NO“です」
私は、未だ入り口の側で優しい表情を浮かべた——ともすれば幼い頃に近所に暮らして自分のことを可愛がってくれたおじいさんみたいな、その穏やかで人の良さそうな男性に、はっきりと断りの意を示す。
最初から決めていたことだ。もし彼の手紙に返事を寄越すならば、私はもう、小説を書かないという旨を血の気のない文字に乗せて送っただろう。
その前に、ご本人が登場したわけなのだが。
「ねー、ここ、本屋さん?」
「えー本屋なの? カフェもあるっぽいけど」
私の返事を聞いてもなお、食い下がろうとしていた杉崎の後ろから、二人の女性客がお店を外から覗いているのが見えた。
京都天狼院書店の店の前には一応「本」という看板があるが、おいしそうな天狼院名物、和三盆ソフトの写真が載ったのぼりが出ているせいで、パッと見ただけでは本屋と分からない人が多い。極め付けはその風貌だ。もともと町家を改装して造られたこの書店は、外から見ると「え、家?」という感想が思わず溢れそうな外観をしている。見た目は家だし、看板やのぼりには本だのカフェだの書いてあるしで、「何の店なんだろう」と中を覗いていく人はたくさんいた。
だから、この時も普段京都天狼院を外から覗いてくる客と変わらなかったのだけれど。
20代ぐらいの綺麗なお姉さん、といった二人の女性客は入り口付近で私と杉崎が何とも気まずい空気感の中対峙しているのを見て、「ここは入ったらマズイ」とでも思ったのか、ちょっと中を覗いてから「や、やめとこか」と、すうっと立ち去ってしまった。
ああ、せっかくお客さんが来たのに惜しいことをしたな……と残念な気持ちになりながら、しかし杉崎にこれ以上どう言えば引き下がってくれるのか考えるのに必死だった。
「そういうことなので……、申し訳ありませんが、今日のところは……」
お引き取り願えませんか、と言いたかった。
書店員かつカフェ店員としては、たとえ自分にとって都合の悪いお客さんだとて、商品の一つや二つぐらい売りたかったけれど、この時の私にまだそれほどの余裕は持ち合わせてなかった。
だからこそ、今日はもうやめにしてほしい、と伝えたかったのだが。私がそれを言うよりも先に、彼が私の腕をガシッと掴んだ。
「お願いです。短編でもいいんです。書いてくださったら、私の方で必ず目を通して本にします」
どうしてそこまで……とか、そんな都合の良い話があるの? とか、つっこみたい部分はたくさんあった。
けれど、先ほどまでの優しい笑みとは裏腹に、私の腕を掴む右手にだんだんと力を込めて鬼気迫る様子になった彼が、それらの疑問を全部呑み込ませた。
「書けないです」
「はい?」
「書けないんです、私はもう……書かないし、書けない。だから、許してくださいっ」
最後は泣きそうになりながら、私は今まで自分の心の奥底に眠っていた鬱々とした感情をぶちまけた。
「……もう今日は、帰ってくださいませんかっ」
「で、でも——」
「帰ってください!!」
自分でもなぜこんなに声を張り上げて来客に失礼な言葉を浴びせているのか、説明ができない。きっとこれは自分の言葉じゃない。杉崎への“拒絶”の感情が理性を追い越して、私の脳を借り、目を借り、口を操って暴走しているとしか思えなかった。
二階でゆっくりとくつろいでいるお客さんや、外から立ち止まって店内を覗いていたお客さんたちの姿が、一瞬頭をよぎる。それでも、荒くなってしまった呼吸や肩の震えは止まらない。
そのうち視界がぼんやりとし出して、私は自分が泣きそうになっていることに気づく。困惑の表情を浮かべた杉崎が、滲んでゆく視界の中で何か口を開きかけてやっぱり閉じるのを見た。
「……」
彼は、目の前でみっともない姿を晒している私を見てどう思っただろうか。
こんな弱っちい私なんかが、もう一度小説を書けるなんて考えられなくなっただろうな。
杉崎はこれ以上、私に何を言えば良いか分からなくなったに違いない。
押し黙ったまま、ゆっくりと後ろを振り返って、そのまま京都天狼院をあとにした。
店を出る前、
「また、来ますね」
と聞こえたのが幻聴だったか、それとも彼の社交辞令だったのか、彼が立ち去った途端に溢れ出した涙の前に、私は判断できなかった。
≪第六話 前編 終≫