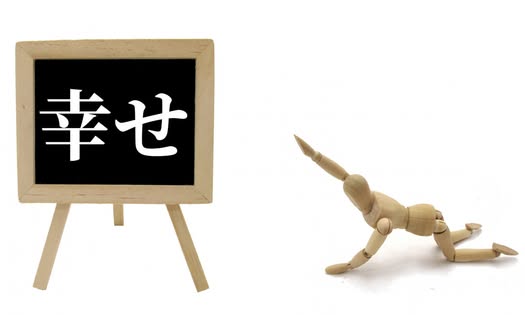「おせちの壁」を乗り越えたら、至福のひと時を味わえた話

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【6月開講】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ《平日コース》」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
記事:樋水聖治(ライティング・ゼミGW特講)
「“おせち”って聞いて何を思い浮かべる?」
「それはもう絶対出し巻き卵」
「私は栗金団」
「重箱」
大学4年生になった年の年末、僕が兄妹に投げかけた質問と回答一覧である。なるほど、兄は好きな食べ物を、妹は自分が担当する料理を当てはめる傾向にあるらしい。末っ子はよくわからない。でも、さすがにおせちのイメージを「巨大な壁」と捉えている人間は僕だけだった。
「おせちは壁である」というイメージを持つようになったのは、大学生になり某宅配会社で働き始めたのがきっかけだった。配達員として働き始めてから迎える初の大晦日。その日は朝から晩までのシフトの日だった。
出勤してみると、冷蔵物と冷凍物を運搬する高さ2メートルにもなる機材がいつもより多いことに気づいた。でも気づかないふりをする。が、そうも言っていられないので、着替えて、装備を整え、恐る恐る、観音開きの機材群のその中の一つを開けてみる。目の前に現れたのは、綺麗に整頓され積まれた「おせちの壁」。本当にそのままの意味で壁だった。この壁を乗り越えることができるかどうかが、大晦日に課せられた僕への試練らしい。
配達中の僕の相棒は、リヤカー付きの電動自転車、自転車の名前は通称「大五郎」。僕がつけた名前ではなく、なぜかそう呼ばれていたので僕もそう呼んでいた。
「絶対に“サイコロ”をするなよ」
作業に取り掛かろうとする僕の背中から、そう先輩がドヤしてきた。「サイコロ」とは、「サイコロのように荷物を転がしてしまう」という過ちを端的に言い表した言葉だ。おせちの場合に「サイコロ」をしてしまうとどうなるのか。聞いた話だけれど、「サイコロを転がすと職人が動く」らしい。つまり、事故発生の一報が入ると、そのおせちを作った職人さんたちが急ピッチで作り直すのだ。僕はいたって真剣なトーンで「はい」と答えた。
「どうか今日1日を無事に乗り越えられるように、あのおせちの壁を乗り越えることができるように力を貸してください」
祈りにも似た叫びを、大五郎にかけて師走最終日を迎える町にくりだした。
交差点を曲がる時、遠心力を考慮して曲がらなければならないこと。急ブレーキによって、荷物が前にどっと倒れ込んでしまう危険だけは犯してはならないこと。荷物を抱えて絶対に転んではいけないこと。配達が完了したことを職人さんに伝えるために、配達完了のデータはすぐに入力すること。
いつも当たり前に気をつけていることを、いつも以上に繰り返し、繰り返し頭の中で唱えた。凍てつく北風にさらされているにも関わらず、背中は常に温かく湿っていた。大晦日、町はいつも以上に賑やかだった。鏡餅を抱えて帰る、いつもはスーツ姿で見かけるお父さん。転倒しまいかと心配になる程の食品を自転車の前後のカゴに乗せたおばさん。公園で遊ぶ、大掃除に際して戦力外通告を受けた子供達。そんな人々の姿を観察できるほどには余裕もできてきたのだろう。
気づけば、夕方になる頃にはおせちの壁は目の前から消えていた。残すは、夜に指定された数十個の荷物たち。「これで今年も締めだ」と気合を入れ直して、日も落ちきった町へと漕ぎ出した。
「大晦日ももう終わりか。なんかあっという間だったな」というごく何気無い感想を抱きながら1件目の配達先に向かう途中、ある一つの変化に気づいた。
「誰もいない?」
日中、慌ただしく行き交っていた人や車の喧騒で賑わっていた町から、それら全ての気配が消えていたのである。少なくとも僕には全く感じられなかった。自転車を止めてみる。
「シーーーン」
「静寂が町を支配していた」というのは文学作品でよく見る表現だけど、本当にその表現がぴったりと言った様子だった。機械的に変わる信号の色だけが動的なものとして目に映り、それが異質な町の雰囲気をさらに盛り上げていた。
ただ、そんな「異世界」のような中で感じていたものは決して居心地の悪いものではなかった。むしろ、どこか暖かく包み込んでくれるような、ホッとできる何かを感じていた。「この感覚の正体は一体……」と考えているうちに、1件目の配達先に到着する。インターホンを押す。
「はい?」
社名ときた理由を告げてしばし待機する。玄関の灯りがつき、柔らかい光の中に人影が見えたが早いか、ドアから見知ったおばちゃんが顔を出した。僕はいつもの言葉を発する。
「こんばんは、ご主人様宛に◯◯さんからのお荷物をお届けにあがりました」
「あらー、こんな時間まで大変ね。ちょっと待っててね、すぐにハンコ取ってくるから」
そう言い残して家の奥へと戻っていくおばちゃん。僕の意識が家の中に向けられ、その中から聞こえてくる音に耳を立てる。
「お、紅白歌合戦」
今年流行った、とあるアイドルグループの曲のラストのサビの部分が聞こえてきた。曲が終わるタイミングでリブングから歓声と、遅れて笑い声が聞こえてきた。いつもは聞こえないたくさんの声。僕は少し考え、「なるほど」と頷く。そうやって勝手に納得顔をしていると、ドタドタと足音が近づいてきた。
「ごめんなさいね、大掃除のせいでハンコの行方が分からなくなっちゃって」
笑いながら、荷物を手渡し、その場を後にする。次のお客さんは、毎週のように配達に伺う大学生の男の子だった。アパートのインターホンを押す。しかし、いつもなら絶対にいるはずの彼は一向に出てこない。そもそもドアの向こうに人間の生気を感じられない。「やられたー」と思う頭の一方で、「そういえば彼の出身は」という考えが浮かぶ。僕は「なるほど」という納得顔をし、不在票をポストに投函してその場を後にする。
3件目に向かう途中で、また新たな変化に気づく。いつもはその時間に点いてないはずの灯りが点いている家が多いということに。反対に、学生や社会人になって間もない人たちが住むマンションやアパートはいつもより静まり返っているように見えた。
全ての配達を終え営業所に戻る途中、僕には、配達を始めた時に感じた「暖かな感覚の正体」がわかった気がしていた。静まり返った異世界のような町で感じた「暖かな感覚」は、きっと家々から漏れ出した「幸福感」だったのだ。
帰るべき場所に帰って、愛する人達に再会できた喜び。色々あったけれどなんとか新しい年を迎えられそうという安堵感。不在だった大学生の子が、久しぶりに家族と再会している場面を思うと笑みが溢れた。
大晦日の夜の配達の途中からは、そんな幸福感をお裾分けしてもらっているような気持ちだった。「いや、誰も分けているという感覚はないから、泥棒か? いや、それはちょっと。よし、おせちをつまみ食いしているような気分。これくらいにしておこう」と、訳のわからないことを考えながら僕も帰るべき場所を目ざす。
白組の優勝を見届けた後、除夜の鐘の様子を伝える画面を見ながらもう一度考える。あの満ち足りた雰囲気は意識していればいつも感じられるのだろうか。それとも大晦日という日が特別なのか。それはわからなかったけれど、一つの予感が胸の中にあった。
「来年もきっといい年になる」
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。 「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/zemi/82065
天狼院書店「東京天狼院」 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F 東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」 〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」2017.1.27 OPEN 〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。