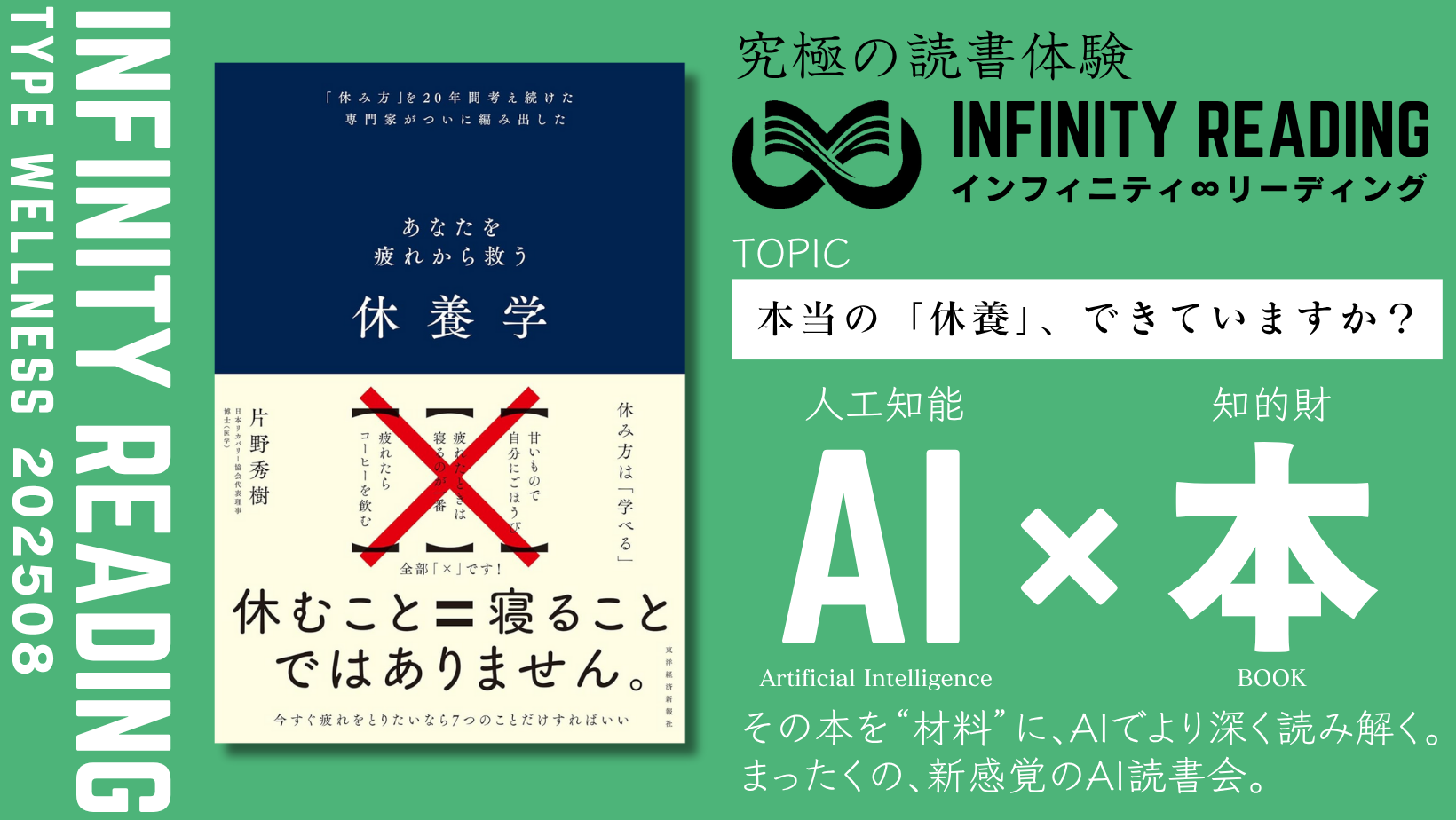ショート小説『おいしい気持ち』

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
記事:鳥井春菜(ライティング・ゼミNEO)
※この記事は、フィクションです。
やってしまった、と思ったときには大体いつも遅い。休み時間でガヤガヤと話し声が飛び交っていた教室が今はシンと静まり返っている。
「昔、バレンタインチョコくれたよね?」
少し離れたところでザワめいていた女子たちの中に、川口沙織を見つけて、思わずそう言っていた。丸顔でおかっぱ風の髪型は昔と変わらない。彼女の赤い頬をみた瞬間に、チョコレートの甘さがふんわり蘇ったような気がして………そんなことあるはずないのに。
教室の全員が黙り込み、沙織は一拍あとにパッと顔を伏せて、何も言わずにパタパタと教室を出ていく。
「ちょっと、なに今の」「ありえないでしょ……」と周りの女子たちが後を追うのをみながら、しまったと思ったけれどもう遅かった。あぁ、転校初日からどうしてこんなことになったのか。
記憶がまだ少し残っていて、景色はなんとなく懐かしい気がした。転校が決まったのは小学四年生の終わりだったと思う。父親の転勤で、急なことだった。けれど、まさか両親の離婚が原因でまたこの田舎の中学校に戻ってくることになるとは。
——大体、あんな理由で離婚するなら、最初から結婚しなけりゃよかったのに。
両親のせいで、毎日、食卓の時間は地獄だった。濃い味派の父親と薄味派の母親。結婚前からそんな違いはわかっていたはずなのに。
確かに、それぞれに工夫していたと思う。味付けを分けて料理していたこともあったし、割り切ってそれぞれに好きなものを買ってくることもあった。けれど、「そんな濃い味、ミキオの体に悪いよ」とか「薄味ばっかじゃ、物足りないだろ」とか、俺を挟んで食卓の雰囲気はだんだん淀んでくるようになった。
『ごはんが、おいしくない』
気づいたときには、味覚がなくなっていた。味が全くわからないのだ。父さんがケッチャプを絞る音は母さんを非難しているように聞こえるし、母さんの箸でカツカツと米粒を茶碗によせる音は神経質になっているように思えた。子供のためにと時間を合わせてたのかもしれないけれど、いつも食卓は居心地が悪くて……
だから、味覚がなくなったとき、正直ほっとした。これで何を食べたって、どっちにも気を遣わなくていいんだと思ったからだ。結局二人はそのまま離婚することになったけれど、それでも味覚は戻らなかった。
——だから、びっくりしたんだ。
沙織の顔を見た瞬間に、昔もらったチョコレートの“甘さ”がふんわり脳裏をかすめていったような気がした。雪がふりそうなほど寒くて、赤いマフラーを巻いて下駄箱の前で待ってくれていたんだろう、頬を真っ赤にさせた沙織は、小さな紙袋を差し出してきて……あのときのチョコレートは、口の中に入れるとひんやり冷たくて、舌の上でゆっくりと溶けていった。
放課後に担任教師から校舎を案内してもらったら、もう日も暮れかけていた。登校初日のすべり出しは最悪だけど、ひとまずようやく帰れる。新校舎の前を通り過ぎようとしたときに、ガラッと教室の窓が開いた。
「わぁ!!」
勢いよく開いたガラス窓の向こうには、沙織が立っていた。
「ごめんなさい。人がいると思わなくて………」
今朝のことで気まずくて、こちらも「あぁ……」としか反応できない。彼女は三角巾とエプロンをしている。
「何、してるの?」
「あぁ、これ……料理部なの。お菓子とかご飯とか作ったりしてて。今日はシュークリーム作ってたんだけど………」
思わずつなげてしまった会話に、彼女は三角巾をとりながら、少し俯く。
「シュークリーム!? 中学生でも作れるんだ!」
すごいな、と純粋に驚くと沙織はますます下を向いた。色白なせいか、頬が赤くなるとすぐにわかる。
「ねぇ、それ食べてもいい?」
また思わず、その頬を見ていると聞いてしまった。
「えっ!?」
パッと顔を上げ、誰もいないのに助けを求めるように左右を見る彼女。彼女の赤く染まる頬を見ているうちに、やっぱりあのチョコレートのことが思い出されたのだ。別に味覚がないことを、今ではどうとも思っていない。嫌いなものはないし、食べ過ぎることもないし、何よりあの異様な気まずさから解放してくれた。けれど、昔もらったチョコレートの記憶が、なんだろう、少し好奇心をくすぐったのかもしれない。
「い、いいけど……」
意を決したように、彼振り返って後ろの流し台から白いお皿を持ってきてくれる。ふんわりと膨らんだシュークリームが二つ乗っていた。
「すごいな、本当にシュークリームだ」
食べても味はないのはわかっているから、まずは見た目を褒めておく。沙織は、何も言わずに、そっと皿を差し出した。一つ掴んでかぶりつくと、ふんわり空気を噛んだあとに、中からクリームが溢れてくる。やっぱり味は、ない。
——まぁ、そうだよな。
心の中で独りごちながらふと目を上げると、沙織がじっとこちらを見つめている。この子は黒目が大きいのだ。だから、瞳が少し潤んで見えるのかもしれない。ぽってりとしたくちびるが、何かを注意深く待っているときのように少し緩んでいて、その表情に、思わず黙ってしまう。
「あの……おいしい?」
あぁ、そうか、食べたら普通は感想を言うんだった。味はわからなかったが「おいしいよ、すごいな」と答えた。
「わぁ、そっかぁ!よかった!!」
その瞬間、まるで止めていた息を吐き出すみたいに、一気に彼女の顔がほころんでいく。「おいしい」と言っただけでこんなに喜ぶのか……そんなに、心配してたんだ。
「自分で味見してるとだんだん分からなくなって。もうちょっと甘い方がいいかぁと思ってたとこだったんだ」
バニラエッセンスがいい香りでしょ、と嬉しそうに話す彼女を見ていると、本当に甘い香りが急に鼻先をかすめたような気がした。
「今度、レシピのコンテストがあるから、部活の後に残って考えてたの。おいしいなら、安心した!」
なんだ、やけに喜ぶと思ったらコンテストのためのお菓子だったからか。当たり前なのに自分のための反応じゃなかったのかと思うと、少し気落ちする。
「あのさ、また食べに来ていい? ほら、自分じゃ味がわからなくなるって、さっき言ってたから」
なんで俺はこんなこと言ってるんだ? 味がわからないのは、俺の方なのに。だけど、また食べてみたい、と思ったのは本当なのだ。だって本当に、ふんわり甘いお菓子の味が、わずかにしたような気がしたから。
焼き菓子は、ショートケーキ、タルトタタン、マドレーヌ。生菓子なら羊羹、大福、水饅頭。沙織は、菓子部門に挑戦するようで、おかげでこちらもだんだんとお菓子の名前に詳しくなった。そのどれもが綺麗に仕上げられていて、美しかったけれど、やっぱり味はしなかった。それでも毎回、試食タイムにじっと息を呑んでこちらを見つめる彼女の顔や、「おいしいよ」と答えると「よかったぁ!」と表情を緩めるところを見るとまた通いたくなった。「これはね……」と嬉しそうにお菓子のことを話し始めると、甘い香りや味までしてくるような気がする。おいしいような気が、するのだ。
「今日は、トリュフチョコを作ったよ」
そう言って差し出した皿には、丸いチョコレートが乗っていて、指でつまむとふにゅっと柔らかい。小学生の頃にもらったチョコレートは、硬いチョコレートだったけれど進化しているなぁ。
——このチョコレートも、あのときみたいに甘いのかな……
柔らかなトリュフチョコは、あっという間に舌の熱で溶けて口の中に広がっていく。
「うん、やっぱりおいしいよ」
そう答えると、彼女がまた笑ってくれる………はずなのに、顔をあげると、目の前で沙織が泣いていた。なんで? え? おいしいって言ったのに?
「……嘘」
沙織はしゃくり上げながら一生懸命に言葉を続ける。
「信じてたのに、ミキオくんは嘘つくような人じゃないって。でも噂で『味覚がないから、なんでも食べれて楽だ』って言ってたって……」
涙は溢れて、彼女の手の甲を伝って、腕まで濡らしている。
「嘘なんか……」
ヒリヒリと乾いた喉で、言葉を絞り出すけれど、
「このチョコレート、本当は甘くないの。辛いんだよ」
あぁ、そうだ、こうなることは予想できたはずなのに。なんで試食役をするなんて言いだしたんだろう。いつかは、バレてしまうとわかっていたのに。彼女のそばにいれば「おいしい」の感覚になれるような気がして………
「なんで? からかってたの? なんで騙したの………」
うまく答えられないまま、走っていく彼女を引き止めることもできなかった。
その日から、沙織は目もあわさないようになった。レシピコンテストに向けて真剣にお菓子を作っていたのだ。あんなに綺麗に、あんなにいろんな種類を試して。それを味もわからない俺が毎回「おいしいよ」なんて答えたなんて、きっと許せないだろう。
——でも、嘘じゃなかったんだけどな……
「おいしいよ」と答えたあとに彼女が笑うたびに、うれしかった。そんなに喜んでくれることに驚いたし、こういう食卓ならずっと座っていたのにと思った。お菓子の解説をしだすと止まらなくて、そんなお菓子をまた食べたいと思った。それって、おいしいってことじゃないのか……
——やっぱり、そんなんじゃダメか。
味覚なんてなくなって、せいせいしたと思っていた。嫌いなものを嫌な顔をして食べる必要もないし、食べ過ぎて気分が悪くなることもない。別に生きていけるし、なくたって困らない。そう思っていたけれど、今は味覚がほしい。沙織にちゃんと「おいしい」って言えたらいいのに……
結局、コンテストの結果も聞けないまま年が明けた。赤いマフラーを巻いた沙織を何度か見かけて、声をかけようと思ったけれど、いざとなるとなんて言えばいいのかわからないままいつも通り過ぎてしまった。激甘から激辛まで、色々な調味料を買い込んで舌の上に乗せてみたけれど、やっぱり味覚も全くないままだった。でも、誤解だけでも解きたい。からかったり、騙してたわけじゃないって……
——やってみるか。
思い立ったら、もうやってみるしかなかった。準備は入念に、できる限り丁寧に。それでも、上手くいくか検討もつかないけれど……
赤いマフラーがよく似合っていて、すぐに見つけられる。校門で呼び止めた沙織は、寒さでまた頬が赤くなっていた。
「何……?」
つぶやきが白い息に変わる。立ち止まってはくれたけれど、目は合わせてくれない。
「あの、これ、もらってほしくて!」
本当は「あのときはごめん」とか「嘘をつくつもりじゃなかった」「からかってなんかいない」とかそういうことから話そうと思っていたのに、全てが頭の中を走り去って、とりあえず持っていた手提げを突き出す。沙織は、なんだろう? という顔で受け取ってくれない。
「……バレンタイン、っていうか。これまで散々、お菓子もらってたから」
自分でも何を言っているのか、話の順番がバラバラになってしまう。けれど、そうだ、今日はバレンタインだからってどうにかこじつけてでも話がしたくて……
沙織は数秒、じっとこちらを見つめたあとに、袋を受け取った。中から箱を持ち上げると、するりとラッピングのリボンを解く。
「これ……もしかして作ったの?」
うん、と答える間にも彼女はリボンを袋に入れて、箱のフタをあけて……
「チョコマフィン?」
難しいものは無理だし、マフィンなら形が多少崩れても大丈夫そうだったから、これを選んだのだ。
——うわぁ、ちょっと待て。まさかここで食べるのか?
沙織はヒョイっとマフィンを箱から持ち上げると、迷いなく一口かぶりつく。
——大丈夫か、これ? 多少パサついてた気もするけど、マフィンってそういうものでいいのかな? 味はわかんないし……
まさか目の前で食べられるとは思わなくて、思わず、モグモグと動く口元をじっと見つめてしまう。モグモグ、モグモグ。しゃべらない彼女。
「あの……おいしい?」
たまらず尋ねると、彼女は顔をあげてじっとこちらを見つめて
「おいしい、気がする」
——気がする?
「でも、ちょっとしょっぱい……これもしかして、砂糖と塩を間違えたんじゃ……」
その瞬間、一気に血の気が引いた。砂糖と塩。確かにそうかもしれない、よく確認せずに白いさらさらした粉を入れたけれど……
「ご、ごめん!!!」
チョコマフィンを回収しようとすると、彼女はさっと後ろに身を引いた。
「でも、おいしい、かも」
「嘘だよ!! 美味しいわけないだろ!」
あんなにたくさん綺麗なお菓子を作っておいて。
「こういうのは、気持ちだから!」
そう言うと、彼女はチョコマフィンを死守しようと素早く箱に入れて、胸の前に抱く。お互いにじっと、見つめ合うと沙織が先に笑った。
「ねぇ、緊張した? 自分が作ったお菓子を食べてもらうって緊張するでしょ」
確かにすごく心臓に悪かった。彼女はいつもあの美しく仕上げられたお菓子を出しながらもドキドキしていたのかもしれない。
「本当はコンテストに出すお菓子は、一種類だけでよかったの。でも、色々食べてほしくて」
沙織の頬は、今日もマフラーと同じくらい赤い。
「初恋だったんだよ、ミキオくんに小学生の頃にチョコレート渡したの。だから転校してきたときはびっくりしたけど、なんでも思ったこと素直に言っちゃうところとか変わってなくて……だから、『おいしいよ』って言ってくれるのも、すごくうれしかったの……」
違うんだ、それは嘘じゃなくて——
そう弁解する前に沙織が、いつもと同じようににっこりと笑いかけてきた。
「でも、『おいしい気がする』っていうのもあるんだね。これ、嬉しかった」
手提げを、ヒョイっと持ち上げて見せると、彼女はマフラーをグイッとあげて、赤い頬を隠してしまう。
「今度、教えてくれない? おいしいお菓子の作り方」
また、思いつきでこんなことを言ってしまう。けれど沙織は、マフラーの中、こくりとうなずいて笑っていた。
***
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
TEL:03-6914-3618/FAX:03-6914-0168
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
*定休日:木曜日(イベント時臨時営業)
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「Esola池袋店 STYLE for Biz」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋2F
営業時間:10:30〜21:30
TEL:03-6914-0167/FAX:03-6914-0168
■天狼院書店「プレイアトレ土浦店」
〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2F
営業時間:9:00~22:00
TEL:029-897-3325