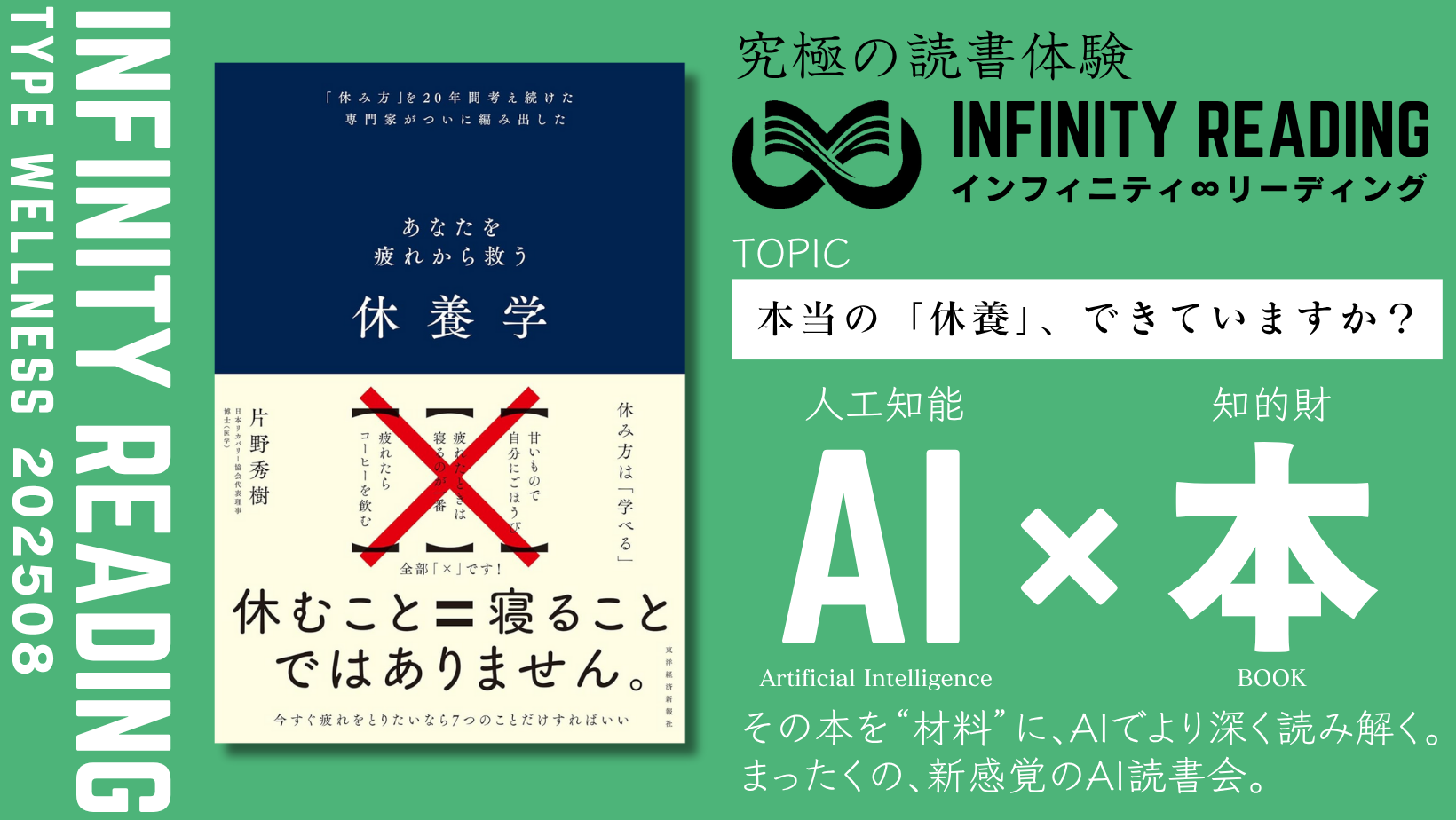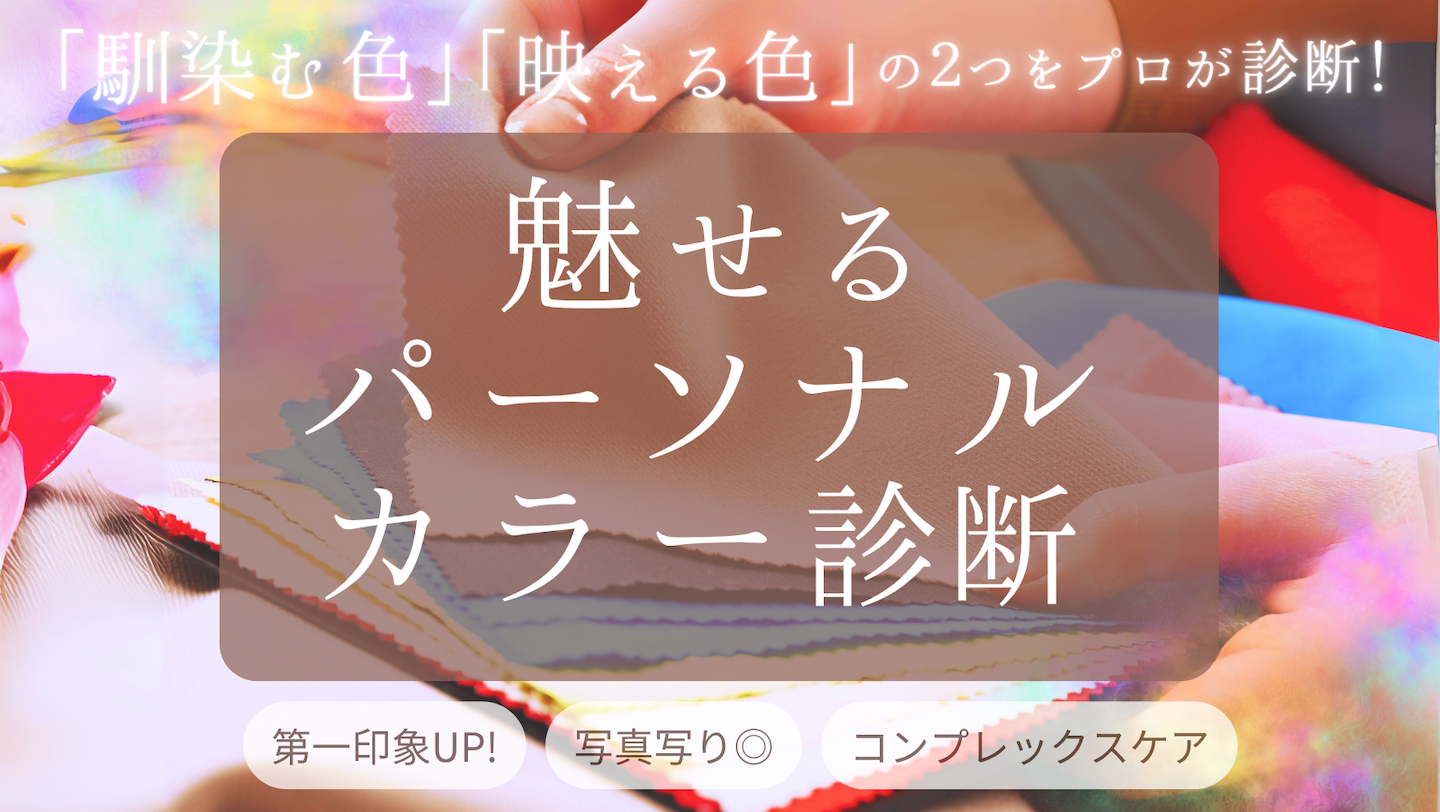秘密の部屋

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【6月開講】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ《平日コース》」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
記事:武田紗季(ライティング・ゼミ特講)
言葉にしなくてもわかる、なんて絶対嘘だ。以心伝心、テレパシーでもない限り、どんなに親しい人間関係であっても言葉なくして通じ合うことはできない。そう思っていた、あの夜までは。
ずっと田舎でひとり暮らしていた祖父が、亡くなった。数年前に心臓を悪くして手術をし、退院したあとは老人ホームへの入居も視野に入れていた。でも祖父はひたすら田舎の家へ帰ることを望み、週に一回、ヘルパーさんの助けを借りることを条件に家へ戻った。わたしたちは車で二時間ほどのところに住んでいて、頻繁に様子を見に行くわけには行かなかったけど、週に一度は交代で顔をだすようにしていた。それでも死は突然訪れ、発見されたときは手遅れだった。苦しんだ形跡はなく、むしろやっと休める、というようなほっとした顔をしていたのが印象的だった。
慌ただしくお通夜をし、葬式を出し、一旦戻って火葬が済むのを待った。一人娘である母は、慣れない着物姿で畳の上に足を投げ出している。
「ああ疲れた。やっぱりひとが一人死ぬって大変ね」
母を労ってお茶を手渡すと、ありがと、と目で言われた。
「あの家、どうしようかな」
「おじいちゃんの家?」
「そうよ。私達も戻るつもりはないし、でもあんな立派な日本家屋は今建てようと思っても木がもう見つからないらしいから。どうしようかと思って」
「バラバラにして材木を売るとか」
「結構現実的ね、あなたは」
「それよりもあの部屋が気になる。家よりも気になる」
「……それも避けては通れない問題ね」
祖父の家には絶対に開けてはいけない扉があって、赤の他人であるヘルパーさんはもちろんのこと、娘であるわたしの母や、孫のわたしですら、その扉に触れることは許されなかった。古い日本家屋の縁側の突き当りにある扉は、ずいぶんと濃いこげ茶色をしていて、普通の部屋の扉となんの違いもないような見た目をしている。どんな部屋なのか、祖父以外誰も知らない。母が言うには物心ついたときからあったそうだし、わたしは縁側で遊んでいてちょっと扉のほうへ転がったビー玉を取りに行くだけで、祖父に睨まれた思い出がある。
でも、祖父が亡くなったことで、もうあの扉の番人はいないのだ。肝試しのようなゾクゾクと、秘密の国を覗くようなワクワクが混ざり合う。
「ねえお母さん、骨を拾って帰ってきたら、あの部屋開けてみようよ」
「ええー、もうちょっとあとにしない? 四十九日終わってからとかさ」
「だめ。こういうのは時間が経てば経つほどタイミングを逃すんだよ」
「確かにそうかもね」
しぶしぶだったけれど、母はその提案を飲んだ。
人間の骨は、わたしにとっては初めて見るものだった。祖母は生まれるずっと前に亡くなっている。
「こちらが仏様です」
喉仏の骨を渡され、不思議な気持ちになる。人間の中にある、合掌したひとのかたち。当たり前だけれど全部の骨は骨壷には入らず、選ばれたものだけを抱える。一緒に帰ろうね、心の中で呟く。あの部屋開けるね、とも。まぶたの裏のおじいちゃんは、泣いているような、怒ったような複雑な顔をして、何も喋らない。
決行は夜十時に決めた。早すぎると折角の怖さが薄れるし、遅いと怖さが増して無理だと思った。母と縁側を進み、月明かりに浮かぶ扉の前に立つ。ギギギ……と軋んだ音を立てて、あっさりと扉は開いた。手探りで電気のスイッチを探すが、わからない。閉まったカーテン越しの月明かりに、何かの輪郭がうつる。なんとなく人の形のようだけど、怖すぎて言葉にできない。
「暗くてわからないわね」
「ちょっと、お母さん!」
待って何かいる、と言う間もなく母が思いっきりカーテンを開ける。
現れたのは、ひとの形をした、背の高さもそれくらいあるハリボテだった。よく文化祭とかで作る、新聞紙と竹で作ったような、手作り感溢れるもの。でもそれは何かのキャラクターではなく、明らかに誰かに似せようとして作ってあった。
「おかあさん……」母が涙声で呟く。おかあさん、おかあさん!! ハリボテに泣き縋り、撫で回す母を黙って見つめるしかできない。
「お母さん、これって……」
たっぷり十分ほどは待っただろうか。落ち着きを取り戻した母に確認する。
「あなたのおばあちゃんよ」
やっぱり。母が三歳のときに病気で亡くなった、わたしのおばあちゃん。おじいちゃんはずっと再婚しなかった。男一人で弱音も吐かず、母を育てた。頑固なおじいちゃんは、昔気質だし再婚するにも相手がいなかったのだろう、くらいにしか考えたことがなかった。でも、この部屋は。
月明かりでやっと見えた壁のスイッチをつけると、明かりの下に広がった部屋は想像を越えたものだった。
壁一面に貼られた、どこか母に似た女の人の似顔絵。部屋に散乱するのはおばあちゃんが使っていたのだろう、櫛や爪切り、まな板に包丁、洋服や靴。おじいちゃんが寝ていたと思われる布団には、黄ばんでボロボロになった白無垢。そして、骨壷。誰のものかなんて確認しなくてもわかる、絶対これはおばあちゃんの。
正直、めちゃくちゃ不気味だった。あの頑固でニコリともしないおじいちゃんの部屋が、こんな様子だとは思わなかった。でも、不気味さと同じくらい愛おしかった。おじいちゃんは何も言わなかったけど、おばあちゃんを愛しすぎたのだとわかったから。死んでも一緒にいたかった、大好きだった、その気持ちが溢れた部屋だった。最初から鍵なんてなかった。もしかしたらおじいちゃんは聞いてほしかったのかもしれない。「おばあちゃんのどこが好きだった?」と。答えは聞くまでもない、「全部」だ。
言葉にしなくても、黙って態度で示す、わかったよおじいちゃん。
「おばあちゃんの骨壷も、一緒にお墓に入れるからね」
そう言って、わたしはおじいちゃんとおばあちゃんを並べてから部屋の扉を閉めた。この家をどう残そうか、あとで母と話をしようと思いながら。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。 「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/zemi/82065
天狼院書店「東京天狼院」 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F 東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」 〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」2017.1.27 OPEN 〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。