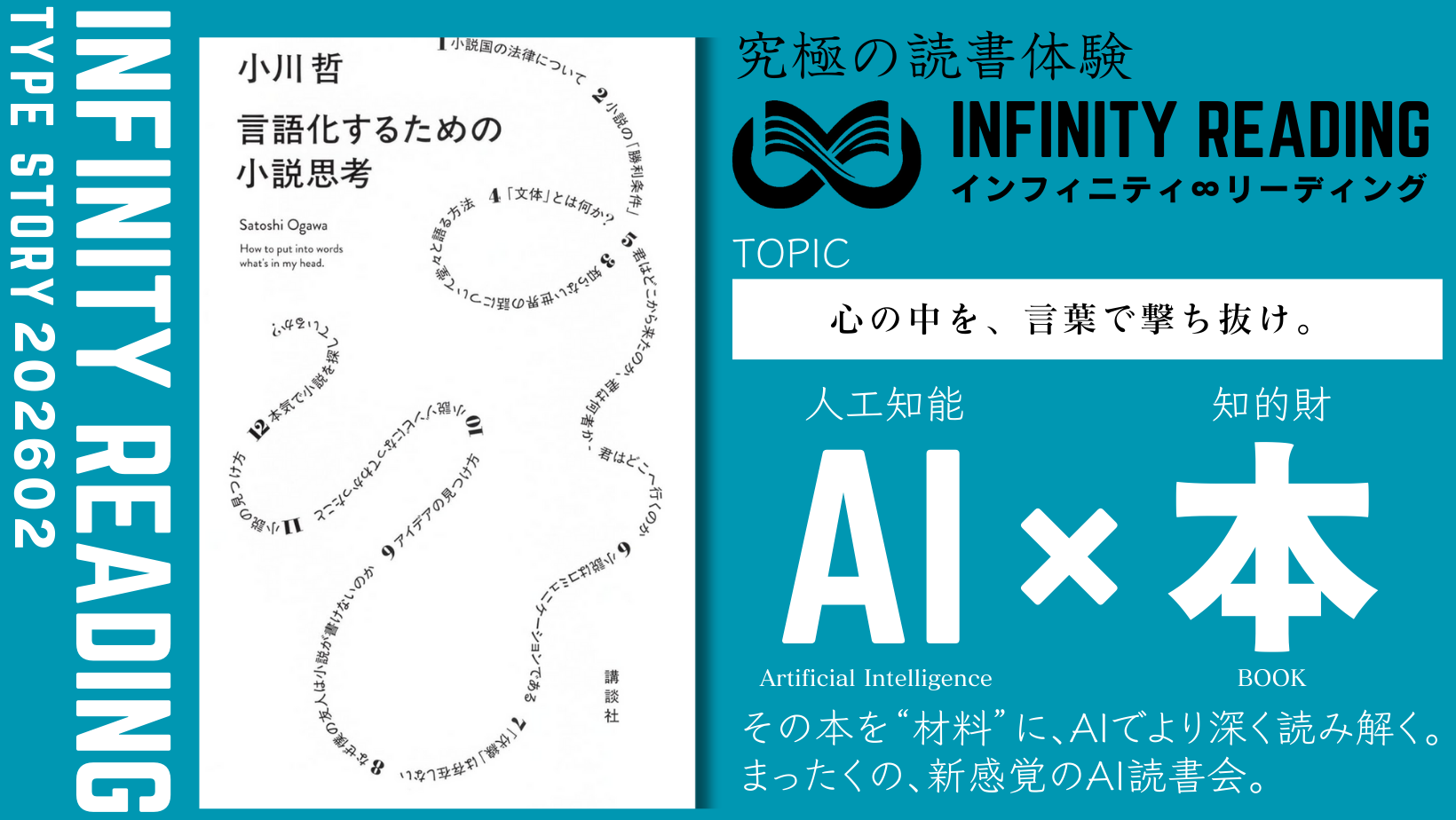書店人失格 〜ある残念な書店員の話〜《天狼院通信》

結論から言うと、大した話ではございません。
大した話ではありませんが、どうしても、いつか書きたいと思っていたので、書くことにいたしました。
その婦人が駅の中にある小さな書店にご来店されたのは、お昼も間際という時間帯だった。
その小さな書店の店長は、品出しもほとんど終えて、それほど切羽詰まっていたわけでもない。レジには昼のパートさんが来ていたし、お客さんも平常通りで、夕方の忙しなさと比べれば、店の中はむしろ落ち着いていた。
ただ、その小さな書店の店長は、焦っていた。
毎日、昼前には前日の売上を計算して、明日の釣り銭を準備して、階上の売店のおばさんに売上金を預けなければならず、あと10分で時間だというのに、まだひとつも手をつけていなかった。今日、売上金を送らないわけにはいかなかった。なぜなら、昨日もアルバイトが休んだために、精算が間に合わず、送っていなかったからだ。
10分。もうかれこれ3年も店長を務めている彼としては、全力でやれば、何とか間に合うかもしれないというギリギリの時間帯だった。
誰にも声をかけられないように、電話がかかってこないようにと祈りつつ、その小さな書店の店長は、急ぎ足で裏の狭い事務所へと向かった。
事務所のドアに手をかけたそのとき、近くの地図売り場で地図を見ていた婦人が、彼に声をかけたのだった。
「ちょっと、いいかしら」
彼は内心、良くはない、と思った。が、もちろん、そのまま言うわけにはいかない。
チラリと時計に目をやり、舌打ちしたい衝動を何とか抑えてこう言った。
「ええ、何でしょうか?」
「あの、この地図なんですけどね、ちょっといろんな種類があってわからないので、どれがいいのか、一緒に選んでもらおうと思って」
彼が婦人の手元を見てみると、首都圏の地図で、ちょうどこの街が載っているページを開いているようだった。
正直、どれがいいのか、彼にもわからなかった。地図は、毎週、版元の担当者が来ていたので、自動的に補充もされ、比較的整理もされるので、放おっておいていることが多かったからだ。
そんなことより、彼は時計が気になった。こうしている間にも、受付〆切の時間が近づいてくる。
それで、彼は背に腹は代えられない思いで、婦人にこう言ったのだった。
「どれでも、大差はありませんよ。お客様自身で、お好みに合わせてじっくり選んでください」
本当は、こんな忙しい時にそんな要件で話しかけないでくれ、と彼は言いたかったのだ。自分でも、大人の対応をしたと思った。
事務所に急いで駆け込み、金庫を開けて、大急ぎで札の計測器を回したが、無常にも時計の針はお昼を回った。
「ああ、まったく」
彼は大きくため息を吐いた。
精算作業を終えて、少し、胸に引っかかっていたので、彼はレジのパートさんの方へ行って聞いた。
「あのさ、さっき、地図を見ていた年配の女性、いたよね。あの人、買っていった?」
「ええ、1冊買って行きましたよ」
それを聞いて、彼はほっと胸をなでおろした。どうやら、事なきを得たようだった。
夕方の混む時間の前に、今度は返品作業をしなければならなかった。
店長と言っても、実態はアルバイトと何ら変わらないのだ。小さな店舗だと、何でもやらなくてはなくなる。それだからと言って、給料が高いわけでもない。
今日は、コミックの返品と女性誌の返品が台車に山となっていた。少しバランスを崩すと雪崩が起きそうだった。
それをみて、また、彼はため息をついた。
コミックは、アルバイトの人に丁寧に一個一個にシュリンク(ビニール)をかけてもらっているので、これをまずは破らないとならなかった。
雑誌は、みんな紐か輪ゴムで付録づけをされているので、これを解かなくてはならなかった。
シュリンクを破り、紐と輪ゴムをとっているだけで、あっという間に時間が過ぎた。まもなく、パートさんを上げて、レジに入らなければならない時間だ。けれども、どうも終わりそうにない。
イライラが募ってきた、その時、レジでチーンとベルが鳴らされる。
さすがに、舌打ちをしてしまう。レジが混んできたか、パートさんでは対応できないことが起きているということだった。
こんな時に限って、まったく・・・。
彼は、そう思いながらも、レジに走った。
レジの前に立っていたのは、見覚えのある後ろ姿だった。
そう、さきほど地図を買っていった婦人だった。さきほど、と言っても、あれはお昼前だったから、もう5時間は経過しているだろう。
どうした?と目で聞くとパートさんがこう言う。
「あの、この地図、返品したいんだそうです」
もちろん、乱丁や落丁での返品、または交換なら事情によっては受けるが、全て受けるわけにはいかなかった。
店長としての責任があるので、手順通りに彼は婦人にこう言った。
「本に何か、問題がございましたか? または交換ご希望でしょうか?」
なるべく、穏やかに言った。
けれども、その婦人は、彼の方を振り返りもせずに、パートさんに向かって業を煮やしたように、こう言ったのだった。
「いいから、早く返金してちょうだい! 理由は言いたくありません!」
もちろん、そんな理由で返金を受けることは通常はない。けれども、とんでもない剣幕であり、また、彼にもちょっとばかり後ろめたさがあったので、パートさんに小さく返金して、と言った。
そして、逃げるようにして、裏の事務所に戻った。返品作業に没頭し、レジで忙しく働いているうちに、その婦人のことは頭から消えてなくなっていた。
しかし、何日しても、ふとした瞬間に、彼はあの婦人のことを思い出した。
そのたびにこう思うのだった。
あれは仕方のなかったことだ。
そして、そのときにレジに入っていたパートさんに、あとで事情を話したりもした。
「僕は悪くない。仕方のなかったことだ。対応も、それほど悪くはなかったはずだ。本当は返金しなくてもよかったのに、してやったのだ。まあ、運が悪かっただけだ」
パートさんも、彼の話を聞くと、確かに運が悪かったですね、と合わせるだけだった。
運が悪かっただけだ――。
そうでないということは、彼自身が一番知っていた。
もしかして、あの婦人は、最近、この辺りに引っ越してきたのではないだろうか。だから、この辺りのページを探していた。
どの地図がいいか教えて欲しかったのではなく、これから住む街にある、きっといつも寄ることになる本屋さんに、この街のことを少し教えてもらおうと思っていたのではないだろうか。
家に帰り、また書店に戻ってくるまで、5時間という長い時間があった。その時間を、あの婦人はどんな思いをして過ごしたのだろうか。
最初は寂しい思いをしたのかもしれない。そのうちに、怒りがふつふつとこみ上げてきたのだろう。そう、5時間かけて、ふつふつと。こみ上げた怒りは、彼女を再び、書店に向かわせた。
文句を言おうか。本部に電話をかけようか。
逡巡したに違いない。
5時間もかけて、ようやく怒りがこみ上げてくるような方だ。本来は、いたって穏やかな方なのだろう。
そんな婦人が示した最大の怒りの表現が、「理由は言いたくありません」だった。
僕は、7年間、書店にいましたが、あれ以上の怒りに触れたことはありませんでした。
そして、あの時以上に後悔したこともありませんでした。
そう、その書店人失格な彼、残念な書店員は、実は5年ほど前の僕だったのです。
あの時のことは、今でも鮮明に覚えていて、ため息をつきながら、時折、思い出すことがあります。
たしかに、見ようによっては、大した話ではないのかもしれません。
けれども、僕にとっては、それ以上に、あのご婦人にとっては、どうでもいい話ではなかったのです。
今から僕が創ろうとしている天狼院書店は、この時の反省が、出発点となっています。