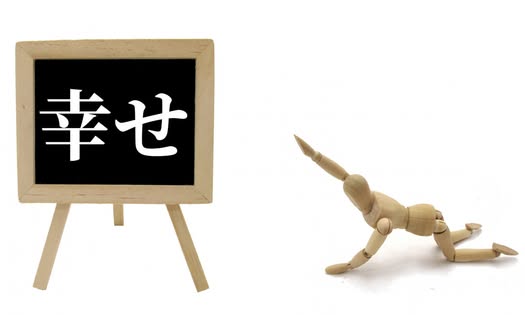ALL YOU NEED IS LOVE 目がさめると、私はオノ・ヨーコの家にいた。《川代の夢日記》


目がさめると、私はオノ・ヨーコの家にいた。
木製の古びた建物。青や緑のガラスの空き瓶や、ところどころ凹んだお菓子の缶が部屋の隅に積み上げられ、そこらじゅうに見たこともない植物が飾られていた。観葉植物なんてぬるいもんじゃない、下手したらこちらを襲ってきそうなくらいの生命力を感じさせる大きな葉っぱが部屋の大半を埋め尽くしている。ほとんど植物に浸食されているようなものだった。まるで物語の中の魔女の家みたいだ、と私は思った。
オノ・ヨーコは私が目を覚ましたことに気が付くと、カップにあついコーヒーを持ってきてくれた。
「お砂糖、ミルクはいる?」
彼女は静かにそうきいてくる。私はいらない、と答えてマグカップを受け取る。ビートルズのアビイ・ロードのジャケット写真がプリントされたカップだ。でも長年使っているからか、ジョンの顔の部分がかすれて白くなってしまっていた。
私は不思議とこの家にいることに疑問を抱いていなかった。私はオノ・ヨーコに出会うべくしてここにいるのだということが感覚として理解できていた。私の目的は間違いなく彼女だった。でも私は誰で、どこから来て、何のためにオノ・ヨーコに会いに来たのかがどうしても思い出せなかった。
ヨーコはとても優しかった。彼女は私が起き上がると、あたたかいうどんを作ってくれた。一人用の土鍋に、ネギと豚肉と大根とたまごをのせた具だくさんのうどんだった。私とヨーコは小さな二人掛けのダイニングテーブルにかけて、ふたりでゆっくりと黙って食べた。
彼女は私になんの質問もしなかった。どこからきたの、とかなんて名前なの、とか一切きいてこなかった。私がヨーコの家にいるという事実を当たり前のように受け止めていた。彼女にとっては他人が自分の家で目を覚ます事なんて日常茶飯事なのかもしれない。彼女はそれくらい落ち着いていて、あなたがいたいだけここにいていい、戸締まりはしなくていいから出かけたくなったら好きに出かけなさい、と言った。
「ここには面白い自然がたくさんある。生命のエネルギーに満ちているの。森もあるし川もある。私の畑の野菜や果物も自由にとって食べていいわよ。きっとあなたも気に入ってくれると思う。でもあまり森の奥に進みすぎないようにね。あんまり行くと戻ってこれなくなるから」
彼女はそう言うと、つばの広い帽子をかぶって外に出て行った。畑の手入れをしにいくのだろう。
彼女の家に一人ぽつんと残された私は、何をしていいかわからなくなった。記憶をなくしているにも関わらず、自分がどうしてここまで落ち着いているのかもわからなかったが、ひとまず散歩でもしようと思った。なにかヒントが見つかるかもしれない。
けれど私はまだ部屋着だったことに気が付いた。大きめの薄手のガウンにショートパンツ。これでは外に出られない。
私が着てきたものを見ればなにか思い出すかもしれないし、と室内を探すことにした。ヨーコは自由に動いていいと言った、ある程度部屋の中を探っても気にしないだろう。ヨーコの家はそれほど広くなかったが、土地の変形に合わせて建てられているためか、部屋の構造は入り組んでいた。小さな階段がいくつもあり、私が寝かされていた大きなソファのあるリビングの奥のドアを開けるとバスルームがあり、その横のはしごを登るとそこに狭いキッチンがあった。あまりにたくさん階段があるので、私は自分が今何階にいるのかもちゃんと把握できなかった。
リビング、ダイニング、キッチン、バスルームのほかに部屋が三つあった。一番長いはしごを登ると、同じかたちをした三つの扉があった。それぞれに1、2、3と番号がふってある。私は順にのぞくことにした。
1の部屋は物置で、壁一面大小かたちの違う抽斗が並んでいて、それぞれに「マザーリーフ」「リュウケツジュ」とか植物の名前が書いてあるもの、「サメ」「ホウライエソ」「ウナギ」とか魚の名前が書いてあるものもあった。その抽斗の中に何が入っているのかとても気になったけれど、なんだか怖くなって空けられなかった。その倉庫は不思議なにおいがした。なつかしいような、さびしいような、せつないような。ずっとその部屋にいると息がつまりそうになった。子供の頃部屋でひとり母の帰りを待っていたときのことを思い出した。そうだ、ひょっとして私は母を助けようとしてここに来たんじゃないか?直感的にそう思った。どういう経緯でここに辿り着いたのかはまだ不明だけれど、母が絡んでいることは間違いなかった。
冷や汗が落ちる。とたんに不安になった。母は大丈夫なんだろうか?
でも大丈夫ってどういうことだろう。なにが大丈夫じゃないの?私はなにが不安なの?
よくわからない。でも急いだ方がいいような気がした。私は急いで1の部屋を出て、2の扉をあけた。
その部屋には大量のタイプライターがぎっしりと部屋につまっていた。ざっと見ても30はあるだろうか。
それ程広くない部屋はほとんどタイプライターだけで埋め尽くされ、そのタイプライターの山の真ん中にぽつんと小さな机と椅子があるだけだった。異様な光景だった。すべてのタイプライターがその机の法をじっと見つめている。古いのも新しいのも、さびついたのもぴかぴかに磨かれたのも、全部同じ表情をして真ん中を見つめていた。まるでそこに誰かが座っているかのように。私にはタイプライター達のささやきがきこえた。はやく文字をうってよ、言葉をうみだして、はやく私を使ってちょうだい、と真ん中にいる「誰か」に、30のタイプライターが一斉にささやいていた。
そしてそれは幻聴などではなかった。
ぱち、ぱち、という音が静かにきこえたかと思うと、とたんに信じられないくらいすさまじい音が鳴り出した。タイプライターのキーがひとりでに言葉を打ち始めたのだ。それは嵐が窓ガラスをたたきつけるような猛烈な音がした。その音の振動だけでこのもろい木造の壁は壊れてしまいそうだった。私は思わずドアを閉めた。それでもタイプライター達の音は鳴り止まなかった。ドアが振動でカタカタと震えているのがわかる。私は気味が悪くなって、いそいで3番目の部屋に入った。
その部屋はどうやらヨーコの寝室のようだった。ベッドと机、それから本棚とワードローブ。家具はそれくらいのシンプルな部屋だった。けれど私は部屋に入った瞬間、思わず息をのんだ。
壁一面も天井もすべて、ビートルズのポスターに、レコードに、雑誌の切り抜きに。寸分の隙間もなくビートルズで埋め尽くされていた。もはやもとの壁の色が何色なのかもわからない。レット・イット・ビーのポスターの上にヘルプ!のレコードがあり、その隣りに黄ばんだリボルバーのインタビュー記事が貼ってあった。どこを見てもビートルズだった。本棚をのぞくと、なかにはいくつもスクラップブックがあり、なかにはビートルズ関連の記事が保存してあった。本棚はそれでうめつくされていた。奥にもクローゼットらしき扉があったが、そこにも同じようにビートルズのグッズがぎっしりとつまっているのだろうことがわかった。またあの物置と同じ、せつない匂いがしたからだ。
異様なのは、そのビートルズのグッズの中で、ジョン・レノンの写真の部分だけがくりぬかれていたことだった。どのポスターも、ポストカードも、レコードも、どの写真にもジョンだけがいなかった。何処をさがしても、ジョンの気配という気配は意図的に遮られているようだった。
気が付くと、私はヨーコの部屋で大泣きしていた。どうしてかはわからない。悲しくて悲しくて仕方なかった。なんて自分は無力なんだろうと思った。私に出来る事なんてなにもない。誰を救うことも出来ない。私は誰の役にも立てない存在だ。誰にも必要とされていない。必要とされたい。寂しい。辛い。何も考えられない。
私はそのまま床にへたりこんでいた。気が付くと、となりの部屋のタイプライターの嵐のような音はとまっていた。
2番のドアをもう一度開けると、小さな机に古くさくてさびで黒くなったタイプライターをぱたぱたと打っている男性の後ろ姿があった。大きな背中を丸めて熱心に何かを書き連ねている。
ギシ、床を踏む音が静かな廊下に響いた。
男性はふとタイプライターを打つ手を止め、ゆっくりとこちらをふり返った。まん丸の眼鏡をかけた男性が、にっこりと私に微笑んだ。
ジョン・レノン。
私は静かに息をのんだ。
***
「ヨーコはね、僕を蘇らそうとしているんだ」
ジョンは静かにそう言った。
「僕らは実体なんてなくても一緒にいられる。僕がいなくなっても僕の歌は残る。そうだろう?だからヨーコが怖がる必要はないんだよ。僕の魂はいつも彼女とともにある」
私は静かうなずき、彼の話をきいていた。
「きみは、どうしてここにきたの?」
母を救うためだ、と私は言った。
「ヨーコが何かすれば、きみのお母さんは救われるのかい?」
わからない。直感的にそんな気がするだけだ。
「きみは、素敵だね。綺麗な目だ。どことなくヨーコに似ているよ」
ふふ、とジョンは笑った。
「僕に任せて」
***
その夜、日が暮れてずいぶんたってからようやく、ヨーコは家に戻ってきた。それは朝に見たヨーコとはずいぶん違っていた。髪を振り乱し、目の下にはくまができていた。昼間の間にあの不思議な植物たちに養分をすいとられてしまったのだろうか。
「大変なの。ジョンがいないの」
ヨーコは悲痛な声をあげ、私を見つけるなりそう言った。
「ジョンを見なかった?どこをさがしてもいないの。あの森にもいないの。絶対にどこかにいるはずなのに」
ヨーコは明らかに取り乱していた。黙っている私をじっと見て、それから私の肩に勢いよくつかまってきた。
「あなた、ジョンに会ったんでしょう?そうでしょう?わかるの。私にはわかるのよ。だってジョンのにおいがちゃんとするもの」
私はゆっくりとうなずいた。
ヨーコはますます取り乱し、「お願い、あの人がどこにいるのか教えて。私、ずっとさがしてるのよ。どこにもいないの。どこかであのぱち、ぱちっていうタイプライターの音は聞こえるのに、どうしても姿が見えないの。はやくあの人に会いに行かなくちゃならないのに」
私は胸元のポケットから、すっと小さな紙を取り出した。
「・・・これは、なに?あなた、何か知ってるの?」とヨーコは言った。
あけてみて、と私は言った。
ヨーコはその四つ折りの紙をゆっくりと開き、タイプライターで書かれたたった五単語の一文を、しばらくじっと見つめていた。
うつむいて動かない、ヨーコ。
しばらくして、気が重くなるような沈黙がすっと晴れるのがわかった。
「・・・ああ、本当にかえってきてくれたのね」
彼女はしばらくの間目を閉じてその場に佇んでいた。息を殺して涙を流しているのがわかった。
私のうしろをすっと風が通り抜ける。ジョンはしー、と私に合図をすると、目をつぶったままのヨーコの前に佇み、優しく微笑んだ。
「・・・どうして教えてくれなかったの」
ジョンは黙って、ヨーコの額に唇をそっとつけた。
ヨーコはふ、と少し微笑むと、私が渡した紙にキスをした。
ジョンは消えていた。
彼女はゆっくりと目をあけ、こちらを振り向き、じっと私を見つめ、それからかたく抱きしめた。
私は手を彼女の背中に回し、しばらく抱き合って、声も出さずに泣いた。ずっとずっと泣いていた。
私は彼女を救うことができたのだろうか。私は彼女に必要とされているのだろうか。今、この瞬間だけでも。それだけでいい。どうか私と必要としてくれないか。
「ねえ、ありがとう」
耳元で優しい声がする。
ああ、私はこのためにここに来たのだと、そのときはっきりと悟った。
という夢を見ました。
自分でも本当にびっくりしました。ビートルズは好きだったけど、ジョン・レノンとオノ・ヨーコの話とかちっとも知らないし、関心を持ったこともなかったんですが。夢って不思議ですね。どうしてこんなに突拍子もないストーリーになるのか。でも、久しぶりにものすごくワクワクする、目がさめたくないと思った夢でしたので、忘れないうちに、書き綴っておきます。お付き合いいただきありがとうございました。
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
【天狼院公式Facebookページ】
天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をして頂くだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。イベントの参加申し込みもこちらが便利です。