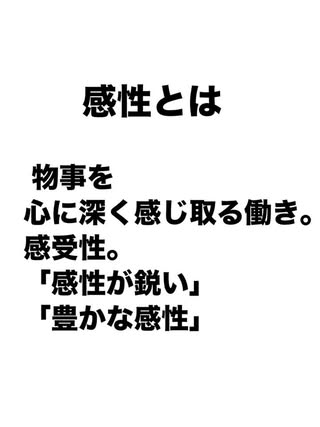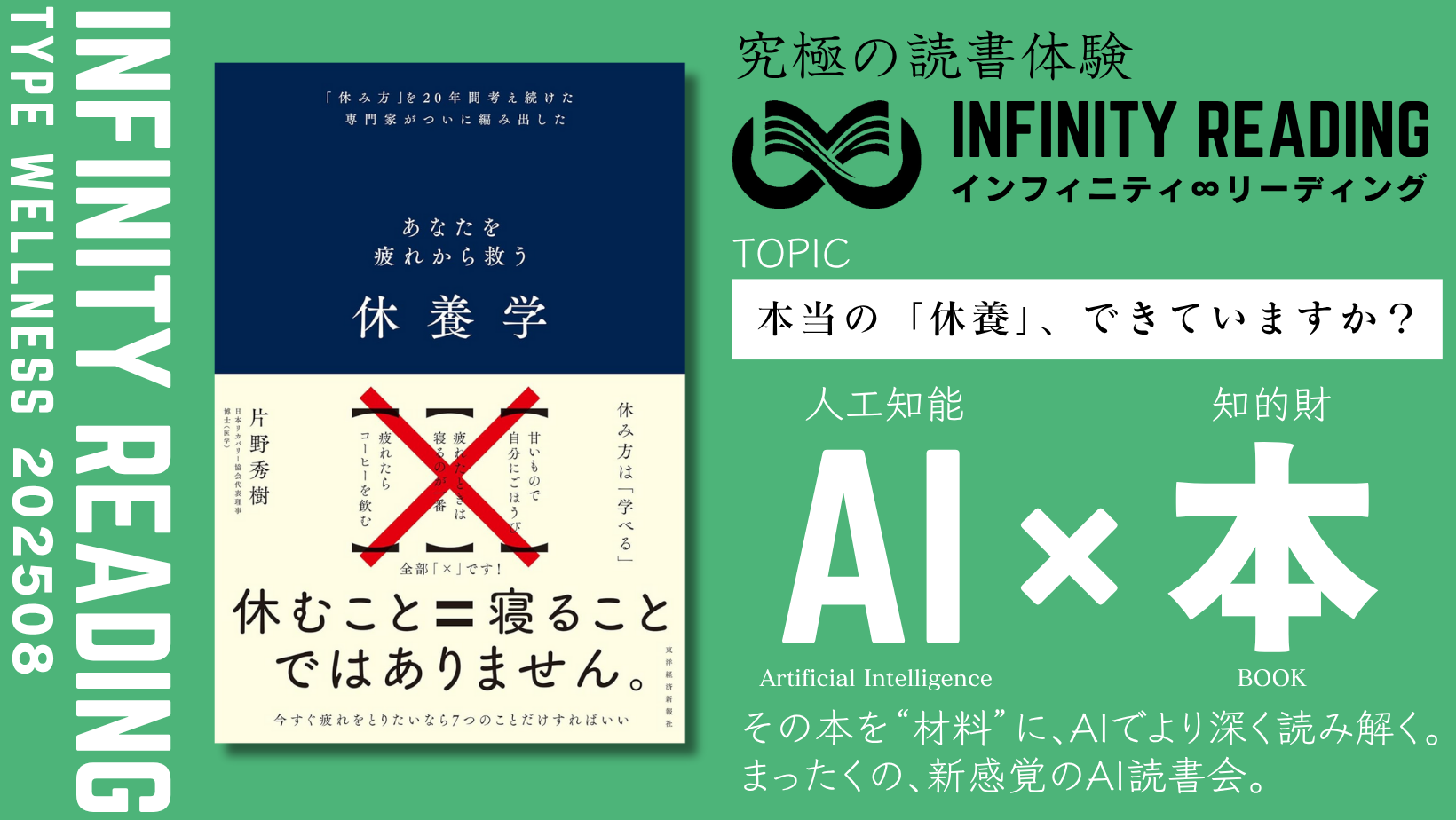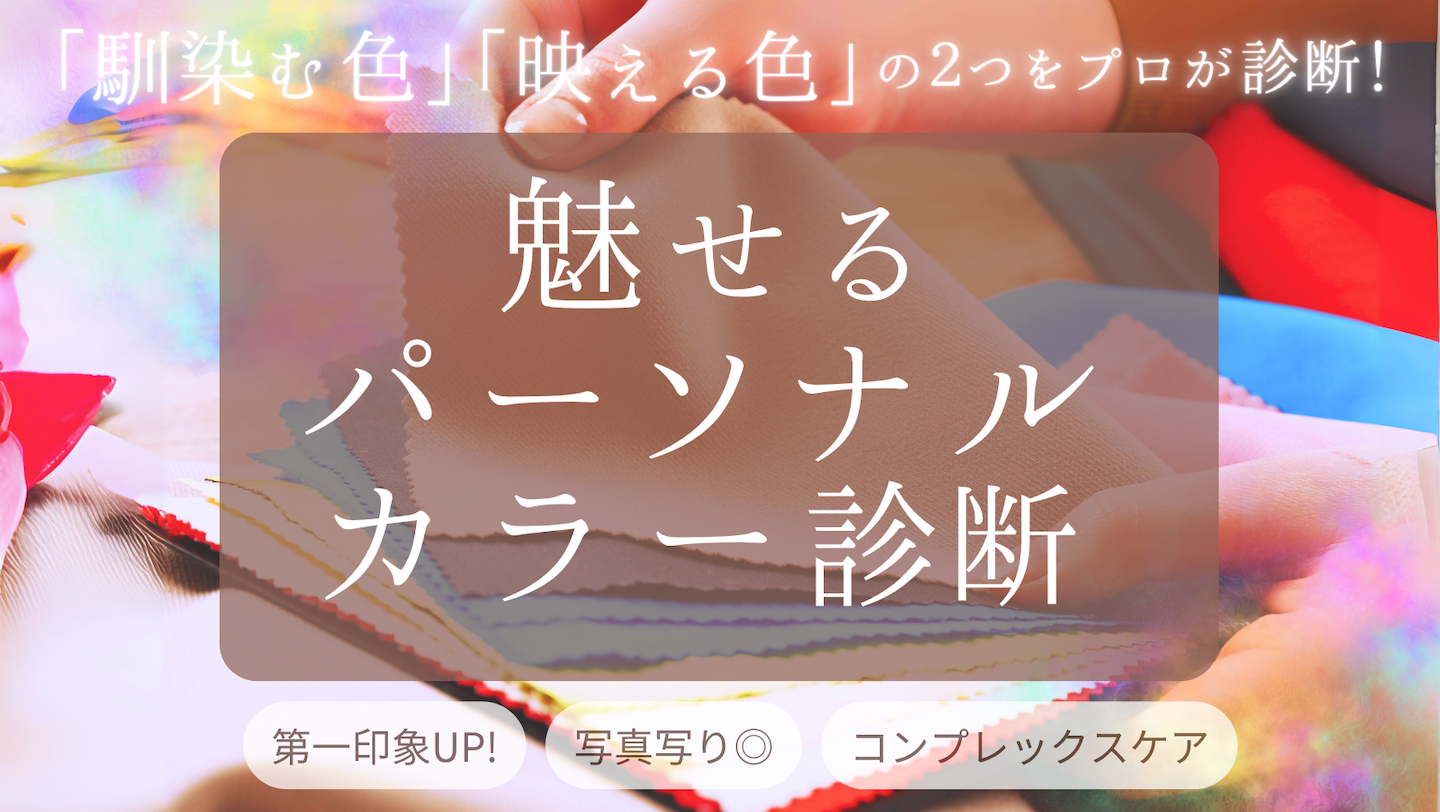二重作家

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
記事:赤羽かなえ(ライティング・ゼミ超通信コース)
※この話はフィクションです
「本気ですか? 名前変えるなんて」
「お願いします、どうしてもペンネームにしたいんです。今後の小説は、平下絹依にしてもらえないでしょうか」
白いメモ用紙に漢字で平下絹依と書き、渡す。編集を担当してくれている木村が紙を受け取り苦々しい顔でメモに目を落とした。
「まいったなあ、数々の賞を取りまくってきた女流作家、坂上麻衣というネームバリューがあるというのも大きいんです。坂上先生が改名したと言わなければ、平下……きぬえ? でしたっけ、そんな名前なら、ただの新人作家だ。何十万部も売り上げが変わるような問題なんですよ」
「木村さん、私は、この話で、直木賞を取ります」
木村が息を飲むのがわかった。目をつぶってぶるっと震えるのがわかる。彼は、今まで何人か直木賞候補の編集をやっているが、まだ悲願が果たせてない、と聞いていた。
大きな賭けだ。下手したら、失敗して路頭に迷うだけかもしれない。でも、もう決めたのだ。
「もしも受け入れてもらえなければ、他の出版社をあたります。なんなら、新人賞の応募からやり直してもいいの」
原稿を入れたUSBメモリーは、私の手の上でコロコロと転がっていた。木村が私の手のひらをじっと見つめる。
「わかりました、まずは原稿を読ませてください。内容次第で、社内に通すか坂上麻衣としてなら引き受けるか、返事します」
大丈夫だ、木村は作品を見る目はちゃんとしている。きっと彼なら、上手く話を通してくれる。これまでも、絶妙な編集でベストセラーを作ってきた人だ。だからこの作品なら大丈夫だ。
さよなら、坂上麻衣。
作家としての坂上麻衣の人生はもう終わり、今日から平下絹依として書く。たとえ、新人賞からもう一度やり直せと言われても絶対にやる。
私は、あの人に、勝負を挑むんだ。
「あなたの書いた話って、人に訴えかけるものがないわよね」
あの人は私に言った。その言葉の矢は、ひどくギザギザしていて抜こうともがくほどに食い込んでくる。
彼女は言ったことすらもう忘れているかもしれないけど、私は食事を作っているときとか、洗濯をしているときとか、ふとした時に思い出してその傷を何度も味わうのだ、悔しさと共に。
作家の収入でなんとか生計が立てられるようになっても、あの人は、私の作品にケチをつける。これが渾身の作と思って出して、それが賞を取ったとしても、だ。
あの人は、プロの作家ではない。誰もが知っている文豪が言うなら素直に受け入れることもできたかもしれない。しかし、あの人は、書くことを生業にしていない。ただ、私のことを生んだ母親だというだけで、もっともらしく口を出すのだ。彼女の口癖は、あなたは、いつまで経っても私の娘なのよ、だった。
結婚をしたときに、母への感謝の気持ちを伝えたくて手紙を書いたことがある。
それを結婚式で読み上げた時、彼女はきっと泣いて喜んでくれるだろうと思った。
それなのに、母は式が終わってから、私に激怒した。
「あんなに大勢の人の前で恥をかかせるなんて、今までの恩をあだでかえされたみたいだわ」
どうやら、最初の方で観客にわらってもらおうと思って入れたエピソードがプライドを傷つけたらしい。でも、ひどくがっかりしたのだ。母が感激して泣いてくれるところを想像しながら書いた手紙は渡した花束の下敷きになってひどくしょんぼりしていた。
文筆業をしている私が、一番身近にいる母すら喜ばせられないなんてなんて出来損ないなんだ……。ずっとずっとそう思ってきた。でも、なんかおかしい。賞を取り、それなりに売れている作品でも、あの人は一度たりとも私の書く文章をほめてくれることはなかった。
私だから、批判するのか。だったら、名前を変えて私が「坂上麻衣」ではなくなったら、あの人はどのように評価するのだろうか。その思い付きのおかげで少し愉快な気持ちになった。
とにかく母の純粋な評価を聞きたかった。
不意に携帯電話がガタガタと机の上で震えた。木村は、持ち帰った原稿をどう思ったのか、うまく上司たちを説得できただろうか。
「坂上先生……」
その声があまりにも興奮していたので、心の中でガッツポーズをした。木村のこの反応なら多分行ける。
「素晴らしい、素晴らしかったです。これなら、直木賞いけるかもしれない。ただ、ペンネームを使う件です。飲まなければこの話を出版してくれないという心意気はわかりました。ただ、こちらもそのままの条件は飲めません」
追加で条件があります。と続けた声は少し冷静さを取り戻していた。その静かさに背中がヒヤリとした。
「条件、ですか」
「はい、この話は、平下絹依名義で、来月のうちの新人賞に出します」
確かに、新人賞からもう一度やってもいいと言った。言ったが、新人賞に出すと言われたら、途端にもったいないような気がしてくる。
「そして、坂上麻衣としては、あくまでも小説を出し続けて下さい。あなたは、だいたい3か月に1回小説を出版している、そのサイクルはなるべく崩さないこと」
思ってもない提案に目が泳いだ。自分の中では作家としての坂上麻衣は終わっていたから、残骸から自分の形を探し出さなければいけないようで途方に暮れる。
「坂上麻衣が急に創作をやめたというのは、あまりにも唐突過ぎる。文体やジャンルがガラっと変わらなければ、いずれ正体もバレるかもしれない。だから、これまで通り、坂上麻衣としての活動もする。そして、新人作家、平下絹依として直木賞ではなく、芥川賞を狙ってもいい」
「そんなことしてもいいんですかね」
「え、何を今更? そんなのいいかどうか、って言ったら、新人賞は、基本デビューした作家は無理なことは知っていますよね。もしバレて後ろ指さされたって甘んじて受けてもいいと思うような強い理由があるんでしょ?」
木村が強い口調で詰め寄ってくる。私は、コクコクと頷いた。
「そうしたら、一切表には正体を明かさない、会社ぐるみで平下絹依を守ります。その代わりに、平下先生は、ずっと、わが社だけの独占出版だ。」
さっきから、自分が唾を飲み込む音が妙にうるさい。自分が軽々しく口に出したことがとんでもない悪事に繋がってしまったような居心地の悪さだ。
「新人賞からもう一度上がるなんて可能なんですかね?」
自分ではないようなしょぼくれた声が出た。そこに木村がたたみかける。
「コレで芥川賞を狙うと言っているんです。新人賞ごときで躊躇しないでいただきたい」
はい、と、うなだれるしかなかった。
坂上麻衣と平下絹依という二つの人格でそれぞれの作品を創り上げていくこと自体は、思った以上に面白かった。
絹依で書くことは自由だった。絹依で作品を書き始めたことで、麻衣として小説を書くときに、思った以上に書く内容に縛られていることに気づいた。
絹依で書くときには、母の目から、いや、あの人の目だけではない、父や友人や、沢山の私を知る人たちの目を気にしなくて良くなる。
キャラクターたちの陰湿な行動も、親への憎悪も、恋人への執着も、絹依ならブレーキがかかることなく思う存分書き込むことができた。
一方、麻衣の時には、そういう制約の中でどんなことが求められていくのか、という表現を追究することができた。
2つの名前で同時期に創作をしていても全くテイストの違う作品が出来上がることを、木村が何よりも喜んでいた。
しかし、自分の身体に作家を二人宿すのは、かなり過酷な作業だ。坂上麻衣一人だった時でもごく普通の生活を送る自分と作品に集中している自分のギャップに戸惑うことはしばしばなのだ。特に、話が佳境に入って、毎日長時間机に向かうようになると、キャラクターに自分を乗っ取られたようになって、書き進めながら涙を流し、怒り、笑うような創作の世界に自分の魂を持っていかれたような感覚になるのだ。それが、さらに絹依の世界にまで首をつっこむことで、まるで多重人格になったかのように、ころころと意識が変わって色々なキャラクターの思考が混ざり合っていく。
一日が終わると、自分がどこの誰で、どこに住んでいるのかということすら一瞬思い出せなくなることもある。
これ、果たして長続きするのだろうか。あの人にまっさらな状態で評価をもらいたい、たったそれだけの理由で、毎日こんな過酷な二重生活を送らなければいけなくなってしまった。けれど、木村から、絹依として出した二冊目が芥川賞候補に残りそうだ、ということを聞いていた。
「最初の作品は、今から思うと、完全に平下先生ではなかったところがありましたからね、今回の作品は、もう、平下作品が確立している。今までになかった独特の言い回しも、このしつこさと熱心さの紙一重なところの表現も坂上先生にはみられないですし」
木村は興奮気味に、私の手を握りしめた。
「平下先生、一緒に芥川賞を取りに行きましょう」
私は、ゆっくりと頷いた。私には、私のやりたいことを応援してくれる人がいるんだ。例え、身内にそっぽ向かれようとも。
「麻衣の話は、結局、もう一押しが足りないのよ。直木賞候補と言ったって、候補じゃ意味がないじゃないの。芥川賞を見てごらんなさいよ、平木だっけ、あの子の小説を読んだことある?」
私は、あの人の様子をじっくりと伺いながら目線を下に落とした。
「平下さん?」
「そう、芥川賞取った子。全く謎の人物だって言うじゃない。すごく話題になっていて読んでみたけど、すごい面白いじゃないの。自分の人生そのものを暴露していて、あんたはあそこまで自分をさらけ出せるの?」
勝った……! そう思った。母に、初めて、書いた著作を褒められたのだ。喜ばしい、はずだった。
自分の中でもっともっと愉悦が沸いてくるはずだった。結局あの人は、私のことをこき下ろしたかっただけで、平下絹依として書いた私の作品をベタ褒めしたじゃないか……!
そのはずなのに、ちっとも気分は盛り上がらなかった。むしろ、妙な敗北感がやってきた。坂上麻衣は、平下絹依にはかなわないのかもしれない。絹依は何も制約がない。好きな題材を好きなように書くことができた。麻衣は……私は、その境地まで達していない。
両方とも自分の作品のはずなのに、今、はっきりと麻衣として絹依に嫉妬していた。
悔しい、悔しい、悔しい……!
私はどうして、自分が書いたものに嫉妬しなければいけないんだ。
というか、なんで、もう一つペンネームを使ってまで、この人に評価されたいと思っているんだ、そもそも、私は、何のために小説を書き続けているんだ。
私、まるで、母に認められたくて書いているみたいじゃないか。いや、まさにそうだ。
愕然とした。私は、ただただ、母に褒めてほしくて、上手にかけたねって言われたくて、結婚式の時にうれし泣きしてほしくて、小説で賞を取った時には、よくやったわねって言われたくて、喜んでほしくて、笑ってほしくて、たったそれだけのためにやってきたんだ。
「はは、ははは……」
目の前に座っていた母が、あまりにも乾いた私の笑い声にぎょっとして、私の顔をまじまじと見た。
今回、母は、確かに平下絹依としての私の作品を褒めてくれた。でも、私が書いたということに気づいていないから、喜んでもくれなかったし、褒めてももらえなかった。
なんて、浅はかな行動だったんだろうか。
祭りのあとで、すっかり抜け殻のようになってしまった。
「私、帰ります。次の作品書きたいので」
私の異変に母は気づいただろうか。びっくりして、追いかけるような気配は感じられたけど、止まる気もなかった。
『お母さんに正当に評価されたい? たったそれだけのために、平下絹依先生になったということなんですか?』先日、ようやく、木村に打ち明けた時に、彼は飲んでたコーヒーをむせてこぼした。おしぼりでテーブルを拭き取り、喉のつまりを咳払いをする。
『たしかに最初はかなり驚きましたけどね、坂上先生があまりにも真剣だから、やってみようと思ったんです。そうしたら、出来上がった作品は、本当に別人が書いたようだった。そこまで書ききれたことはすごいことですよ』
その時には、ピンと来なかった言葉が急に私の耳元に流れ込んで、そのまま、目から流れ落ちていった。涙におぼれて見えずらいまま、スマホを操作して、木村に連絡する。彼には、今日、母に会うと伝えていた。
「木村さん」
『ああ、坂上先生ですか? どうでした? お母さんの鼻はあかしてやりましたか?』
珍しく飲んでいたのだろうか、後ろの声がにぎやかでがやがやしていた。いつも冷静な木村と違い、今日は陽気だ。
「無理でした」
え? と向こう側で聞き返す声が聞こえた。
「無理でした。確かに絶賛はしてくれました。でも私が書いたって知らないから褒めてもらえなかったし、喜んでももらえなかった。私、こんなに頑張ったのに、褒めてもらえませんでした」
そこから先は、嗚咽も涙も止まらなくなった。
『坂上先生……麻衣さん? どこにいますか? 行くんで、どこかで少し待っててもらえますか?』
家の近くの公園のベンチに座っていたら、タクシーから木村が降りてきた。慌てて来たのだろう、眼鏡が白く曇って息も、乱れている。
「もう、坂上先生、今日、僕は初めて芥川賞をサポートできたお祝いをしてもらっていたんですから、こんな日に仕事をさせないで下さいよ」
私はうなだれて彼の顔を見ることもできなかった。
「僕に喜びを与えてくれたのは、あなたなんですよ。すごい才能です。でも、その才能は、全部努力からきている。それは、お母さんに認めてもらわなければいけないんだろうか? お母さんがどうこうじゃなくて、それをできる自分を、自分で褒めてあげることが大切なんじゃないんですか?」
「それでも、褒めてほしかったんです、私の原動力は、ただそれだけだった、ということに気づいてしまって情けなくて悔しくて」
「お母さんはスゴイ人ですね」
木村は、曇った眼鏡をハンカチで拭いてかけ直した。その動作を見ながら彼の言葉が唐突過ぎて戸惑った。
「考えてみたら、剛腕の編集者ですよ、坂上麻衣を焚きつけるだけでなく、平下絹依まで芥川賞を取らせるようなモチベーションを引き出すんだ。僕には到底真似できません」
私は、納得がいかなかった。
「これからもお母さんがあなたを認めるまで書き続けるのか、その呪縛から外れて新しい道を行くのか、それはあなた次第です。別にどちらも間違いじゃない。これから長い時間かけて見つけていけばいい。結局あなたは書き続けるのだから」
ひんやりとした夜の風が涙で濡れた顔をひどく冷やした。
それでも、このことをネタにいつか何か形にしてやる。頭の片隅では、もう次の作品の構想が走り始めたのだった。
***
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
TEL:03-6914-3618/FAX:03-6914-0168
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
*定休日:木曜日(イベント時臨時営業)
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「Esola池袋店 STYLE for Biz」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋2F
営業時間:10:30〜21:30
TEL:03-6914-0167/FAX:03-6914-0168
■天狼院書店「プレイアトレ土浦店」
〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2F
営業時間:9:00~22:00
TEL:029-897-3325