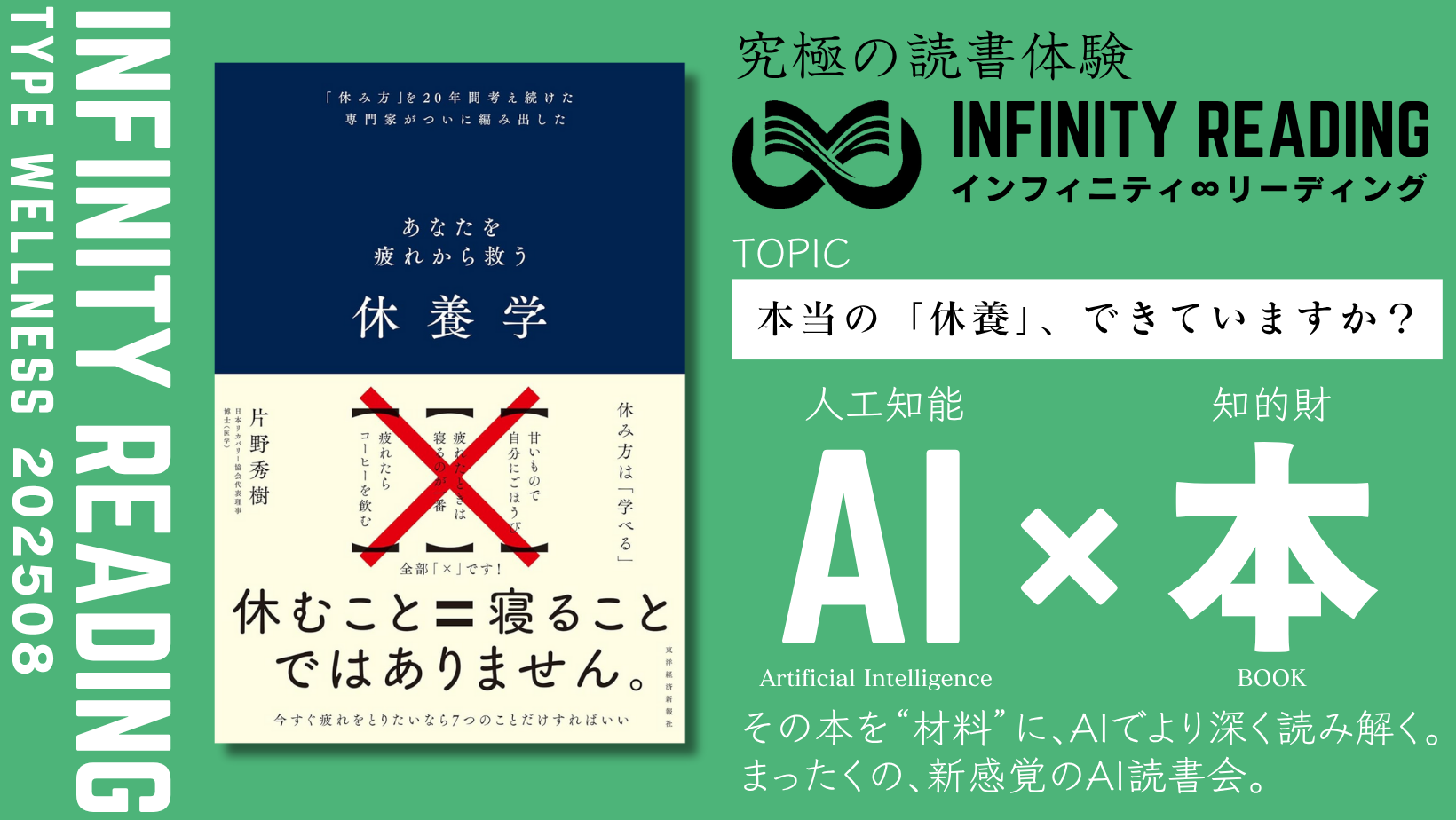家族に会いたいと思わなくなるのは、幸せなことだと気がついた話。《川代ノート》

人生で初めて見る生まれたての赤ちゃんは、真っ赤な顔をして泣いていた。
ああ、赤ちゃんだ、と思った。赤ちゃんって本当にいるんだ。この世に存在するんだ。こんなに小さいのに、それでも動いているなんて、すごい。なんか、おもちゃみたい。
自分の目の前にいるもののように思えなくて、はじめのうちは手が伸びなかった。かわいい、とは思ったものの、それ以上体が動かないのだ。脳がフリーズを起こしていた。赤ちゃんという生き物は自分の世界の中には存在することはなくて、どこかファンタジーの世界に生きるもののように思えていたのかもしれない。
ただ、泣いて、笑って、ミルクをのんで、げっぷをして、おならをして、ひたすら、生きるという行為だけに集中しているその動物が、どこか、なんだか羨ましいと思えた。
今、私が抱いている悩みなんて、ひどく面倒な感情なんて、きっと微塵も感じることなく生きていられるんだろう。
何もしなくても愛してもらえるだなんて、すごいな、すごいことだなと、純粋に思った。
六つ上のいとこの赤ちゃんが生まれたと聞いたのは、12月のなかばだった。
うわ、ついに生まれたんだ、と思った。いとこが本当に母親になったのか。なんだか実感がわかなかった。子供のころから何度も遊んでいるいとこのお姉ちゃん。一人っ子な上、人見知りなので、小学校にも友達がそれほどいなかった私にとっては、いとこたちが遊びに来る長期休みが何よりも楽しみだった。いつも祖母の家に集まってみんなで遊んだ。私には年の近いいとこが4人いたが、その中でも、一番仲がよかったのが、先月出産したそのお姉ちゃんだった。
だいたい想像がつくと思うけれど「六つ上のお姉ちゃん」というのは程よい憧れの存在になりやすかった。私が小学校に入学する時、彼女は中学一年生だった。私が中学校を卒業しようという頃、彼女は大学生活を謳歌していた。「自分がああなるかもしれない未来」を生きている彼女は、とてもきらきらして見えた。彼女はいつだって、私が目指したい憧れの存在で、そして、私にないものをたくさん持っている人だった。明るくて、社交的で、面倒見がいい。のんびり屋でどんくさく、何をするにも不器用な私とは全然違うタイプだった。あんな風になりたい。でもなれない。なれないからこそ、ますます憧れの対象になっていくのだった。
私が大学生になり、彼女が社会人になって、それぞれがそれぞれの道を歩むようになってからはそれほど会う機会はなくなったものの、それでも正月休みやお盆休みには親戚で集まって話をした。彼女の話を聞くのはいつも面白かった。自分の知らない世界を教えてくれるような気がした。
ちょうどよい距離にいる、人生の先輩。
だから、きっと彼女が出産して本物の赤ちゃんを見たときには、私も影響さえて母性が目覚めたりするのかなあ、なんて、彼女が妊娠したと報告を受けたときにはぼんやりそう思っていた。
私が天狼院で働くようになると、彼女と話す機会は格段に減った。お盆休みは掻き入れ時で毎日のようにイベントが入っていたし、年末年始には毎年恒例の年越し天狼院がある。仕事なので仕方がないとはいえ、会うたびに夜遅く、眠くなるまでおしゃべりをする時間がなくなってきてしまったのは、単純に寂しいなあと思っていた。
昔は、みんなはいつ来るの、って待ちきれなくて、毎日毎日母に聞いてたくらいなのに、今は私の方が行けるかどうかわからない、なんて。
人生、どう転ぶかわかんないもんだなと、1月3日の夜、仕事終わり、祖母宅に向かうバスに乗りながら、そんなことを考えていた。
久しぶりに降り立った地元の駅は、来るたびに様相が変わる。再開発のためか駅ビル内は工事が行われ、祖母宅方面に向かうバス停の位置が変わっていた。思いの外、老人がとても増えたようにも思えた。
混雑するバスの中も老人がほとんどで、吊革をつかんでいると、香ばしい匂いがした。なんだろう、と思って匂いのする方を見やると、おばあちゃんがぽりぽりとせんべいを食べていた。バスの中にのほほんとした空気が漂っていた。そうだ、そういう街なのだ、ここは。穏やかに暮らしたい人が、心を乱されることなく穏やかに暮らすための街。今私が住んでいる、池袋じゃないんだ。
妙なところで感傷に浸っていると、目的地に着いた。真っ暗だった。住宅街がひたすら続く。お正月ということもあって、車も少なく、少し怖くなった。道路沿いのバーミヤンの看板の光だけがぽつりと見えた。
勝手知ったる祖母の家にピンポンも押さず入ると、何も変わらないいとこと、その旦那さんがいて、目の前には小さな布団があった。どうしてかはわからないけれど、布団の上に風呂場の椅子が置いてあった。なんだあれ、と思った瞬間に、その下にいるのが赤ちゃんだと気づいた。まぶしいから光を遮るため、便宜的に風呂場の椅子を頭の上に被せて置いていたのだ。
あ、赤ちゃん、本当にいるんだ。その場に突っ立ってぼおっとしていると、以前会ったときよりも一回りくらい小さくなった祖母が私を出迎えて、寒かったでしょう、はやく手洗ってきなさいと言うなり、バタバタとキッチンに消えていった。コートを脱ぎ、手洗いうがいをした。そういえば、手洗いうがいなどきちんとしたのは、いつぶりだろう。
こわごわ近づくと、私の握りこぶしくらい小さな頭が、風呂場の椅子の影で寝ていた。うわ、赤ちゃんだ、と思わず声が出た。どうしてか、第一印象は、「かわいい~」でも「小さい~」でもなく、「赤ちゃんだ」と、それだけだった。なんだか驚いてしまったのだ。こんなに小さなものが、生命体として存在しているという事実が信じられなかった。
スヤスヤと気持ちよさそうに寝ている赤ちゃんを起こすわけにもいかないので、先にご飯を食べた。誰かの作ってくれたご飯を食べたのは久しぶりだった。平日土日関係なく仕事していて、ほとんど家には寝に帰るだけの生活をしている私の食生活はひどいもので、毎日コンビニか外食だった。食べきれないほどの量をどんどん出してくるいかにも「おばあちゃんち」的な雰囲気も久しぶりで、少し気恥ずかしくなった。
あー、あー、と小さな声がした。見ると、小さな、本当に小さな手がひょこりと布団から飛び出ていた。あ、ぐずった、と言っていとこが慣れた手つきで抱き上げる。黒目がとても大きかった。あー、とかうー、とか言葉にならない声をあげ、口をぱくぱくさせていた。顔を覗き込んでじっと見つめてみる。目が合わないな、と思っていたら、新生児だからまだ視力が弱いのだという。
さきちゃんも抱いてみる? と言うので、恐る恐る手を伸ばした。小さな頭を自分の腕に乗せて抱き上げる。軽かった。とても軽かった。これでも重くなったんだよ、といとこが言ったけれど、信じられないくらい軽かった。こんなに軽いのに、こんなに小さいのに、生きていられるんだ、と思った。人間ってすごいな。私もこんな風に、小さい体で生きていた時代があったのか。
あるいは、リアルな赤ちゃんを抱き上げたら、母性が芽生えたりするのだろうかと思っていたけれど、そんなことは全くなかった。私にとって、「赤ちゃん」というものは未知の生物として認識された。同じ人間というジャンルのくくりに入れていいのかどうかすら疑問だった。いずれ自分の体の中からも同じような赤ちゃんが出てくるのだろうかと思うと信じられない気持ちだった。
妙に現実味がなかった。一晩だけ祖母宅に泊まって、翌日の朝に池袋に戻った。ふわふわとした浮遊感が続いていた。なんだろう、何なんだろう。すごいな、と思った。単純に、そう思った。こんな人生があるんだ。私と六つしか変わらないいとこが、母親になった。6年後の自分は、一体何をしているんだろうか。まだ、書き続けているだろうか。まだ、天狼院にいるだろうか。まだ、夢を追いかけ続けているのだろうか。まだ、今みたいにがむしゃらに働き続けているのだろうか。もしくは、すでに結婚して子供を産んで、育てて、彼女のように母親になっているのだろうか。
母親になる、だなんて、全くもって想像できなかった。この自分に母性だなんてものが存在するのだろうか。自分すらも十分に育てられていないというのに、他人の命を、人生を背負うことなんて、できるのだろうか。自分とは全く別の人間の人生を、私なんかが左右してしまっても良いのだろうか。
そんなことを考えていると、プアー、と音を立てて電車のドアが開いて、人の流れが大きくなった。はっと気がつくと池袋駅だった。慌てて席を立つ。現実に戻ってきたような気がした。どこかの異世界にでも飛び込んでしまっていたのだろうか。
ぼんやりと池袋駅のコンコースを歩いて、ワッカに向かった。人が多い。ものすごい人ごみだった。みんなそれぞれ、何を思い、何を考えて生きているのだろう。どうして、なんで、何が楽しくて。
祖母宅に行くまでは、今年は何をしよう、なんて考えていた。何を目標にしよう。どうやって生きていこう、と。
Facebookに何を書こうかな、と考えた。いつも書いているみたいに、「今年は何々をやります!」と宣言しようか。今年こそは作家デビューします、小説を出しますとでも書こうか。何か大きな賞をとりますとか、宣言してみようか。宣言したほうがやる気も出るだろう。そうだ。大きな目標を掲げて、それに向かって頑張れるように気持ちを新たにしてみよう、と。
思っていたはずなのに、やる気が自分の中ですっかりしぼんでしまっているのがわかった。心の真ん中に空洞が開いてしまったような感覚だった。いや、それでも試しにと、キーボードに手を乗せてはみた。みたものの、言葉が浮かんでこない。自分が何をしたいのかがまるでわからないのだ。ぶつぶつと途切れて、文章と文章の繋がりがまるでない。なんだろう、赤ちゃんに会ったことがそれほど衝撃だったのだろうか。祖父母が自分の記憶よりも老けたことが悲しくなったのだろうか。ずっと憧れていたいとこが母親になったというのに、自分は未だに何も成し遂げられていないという事実にショックを受けたのだろうか。
色々な仮説を打ち立ててみたが、どれも違うような気がした。どれも当てはまらない。何が。一体何が、私の心の中を埋めつくしているのだろう。
モヤモヤとした感情を抱えたまま、それでも普通に仕事をした。年明けの池袋はそれなりに混んでいた。初売りにはしゃぐ大学生くらいの女の子たちがサンシャイン通りを楽しそうに歩いていた。おそらく新年最初に会ったのだろう、カップルが腕を組み、顔を近づけて話をしていた。そんな人たちを横目に、いつもの業務をこなした。メールを返し、データを確認し、次にやるべきことを洗い出していった。
お正月の浮かれた空気から日常に戻っていく自分を、どこか俯瞰で見ていた。私、普通に働いているな。とくに正月ボケというものも感じなかった。いつも通り、特に変わらない日常。池袋に自分の体が馴染んでいくのがわかる。落ち着く。そうだ。ここが私の場所なんだ。
じわじわと、ゆっくりだけれども確実に、自分の体が、心が、存在が、この池袋という街にーー天狼院という場所に、溶け込んでいく。
あ、そうか。
そういうことだったんだ。
赤ちゃん。一人の人間としてではなく、母親として生きることになったいとこ。以前よりも小さくなった祖母。東京の、人気のない田舎町。池袋から電車で一時間半もかかる場所。大学生まで、私が暮らしていた場所。
私の、私だけの、居場所。
居場所だった、場所。
ぶわりと、今までに味わったことのない寂しさが、胸の奥の方からこみ上げてくるのがわかった。
私は、自分の居場所が、祖父母や、両親や、いとこたちがいる暖かいあの場所から、この池袋の、「天狼院」という場所に移りつつあることに、気がついてしまったのだった。
お正月が楽しみで仕方なかった。夏休みが楽しみで仕方なかった。何よりも、家族に会えること、いとこたち、親戚たちが集まる場所に戻ること。そこで自分が今何をしているのかを報告し、がんばってねとか、体に気をつけてねとか、そう言ってもらえることで安心をしていた。あそこに帰ると、ホッとした。自分を受け入れてくれる場所が、ここにある。やっぱり私の人生において、軸となる部分は、ここにあるのだと思っていた。帰るたびに、そう実感した。
けれども、いとこが赤ちゃんを産んで、思ったのは。
私は、私たちは、自分だけの居場所を作れるようになったんだ。
子供じゃなく、大人に。
私は、もう守られる存在ではなく、誰かを守っていく存在に、シフトしていかなければならない。
もう私は、いざとなれば、あの場所に頼らずとも生きていけるような力を、徐々にではあるけれど、身につけつつある。
もちろんまだまだ親に頼っている部分はある。きつくなって母親に電話することもある。子供で、周りに迷惑をかけることがどれだけあるか、数え切れない。
けれども、そうだとしても、私の、「今」の私の居場所はもう、あそこじゃない。「おばあちゃんち」でも、両親のいる実家でもない。
池袋なのだ。天狼院なのだ。
私は気がつかないうちに大人になっていて、毎日毎日がむしゃらに働いているうちに、次第に、あれほど恋しかった家族のことを思い出す回数が減ってきていた。
天狼院で働きはじめてから、もうすぐ2年になる。
あっという間の2年だった。本当に一瞬だった。毎日毎日、ただひたすらに働いた。目の前の業務をなんとか終わらせることで精一杯。自分が失敗していないことを、他人に迷惑をかけていないことを、誰かに嫌われていないことを祈りながら、日々を過ごした。この2年、気が完全に休まった日なんて1日もない。たったの1日もだ。何をしていても、食事をしていても、久しぶりに友人と飲みに行っていても、仕事のことが頭にあった。あれは大丈夫かな。これは。ああ、あれってもう終わったんだっけ。いや、戻ったらあれをやらなくちゃ。
朝が来るのが怖くて、夜が恋しかった。次の日にならなければいいのにと思った。正確に時を刻み続ける地球を呪いたくなった。生きれば生きるほど、働けば働くほど、自分のことがわからなくなり、そして、嫌いになった。
自分との戦いだった。日々、自問自答した。答えを探していた。家族に答えを求めるわけにはいかなかった。なぜならもうこの戦いは、家族の戦いではないからだ。社会に出た以上、私の問題は私の問題なのだ。私の戦いは、私個人の戦いなのだ。「川代家」の戦いは、もう終わってしまったのだ。私は今まで所属していた「川代家」というチームから、一人で飛び出していって戦わなければならない。苦しいけれど、出ていかなければならない。
でもそうこうしているうちに、私は「天狼院」という仲間を見つけ、今はこのチームで戦っている。みんなで力を合わせて、難局を乗り越えようと試行錯誤している。
自分が成長しているのか不安だった。何をしてもダメな気がした。毎日毎日、仕事をしていても、何をしていても成長していないように思えた。何も変わっていないように思えた。私の悪いところは何一つ治っていなくて、私のコンプレックスは何一つ解消されていなくて、それなのに、いいところは一つも増えていかないような気がした。苦しかった。自分は、変われているのだろうか。ちょっとでもよくなったところがあるだろうか。誰かの役に立てる自分に、なれているのか、はたして。
正直言って、私は未だに、2年前の自分から、成長している気がしない。何も変わっていないような気がするし、自分の嫌な部分も何も治っていない。自信がない。常に……常に、私ははたして、天狼院の役に、人の役に立てているんだろうかと、私がいてよかったと言ってくれる誰かはいるのだろうかと、不安で、仕方がない。
でも、それでも。
私は、祖母宅に行った時に感じたあの違和感を、あの寂しさを、「成長」だと呼びたい。
家族を必要だと思う回数が減ること。
家族に会いたいと思わなくなること。
自分を育ててくれた場所よりも、今生きている場所の方により、安心感を覚えること。
それはとても、とてつもなく寂しいことかもしれない。嘆かわしいことかもしれない。
あるいは誰かには、そんな親不孝なと、言われるかもしれない。
けれども、誰かにそう非難されようとも、私は今抱いているこの感情が、私にとって一つの「成長」であると、そう認めてあげたい。
人は、親元を離れ、社会に出て、自分の居場所を作る。
苦しくなって、もがいて、辛くなったらときどきもといた場所に戻って泣いて、元気を取り戻して、また戦場に出て行く。
そんな往復を繰り返しているうちに、じわじわと、見えないけれど確実に、自分の居場所が出来上がっていく。
いや、居場所を作るしか、ないのだ。
それがきっと、この社会で、大人として生きていくということなのだ、たぶん。
何もしなくても愛してくれる、無償の愛情を注いでくれる家族の元から離れ、無条件で愛してくれる人が誰もいない場所で、仕事をし、人の役に立つことで徐々に、本当に少しずつ、自分の居場所を作っていく。
それしかない。そうやっていくことでしか、生きていけないのだ。
いとこも、自分の居場所を作り、そして今度は新しい、生まれたばかりのあの子の居場所を作っていかなければならない。
そうだ。
私たちはもう、自分で自分の人生を決めていい。
自分の人生の責任をとるのは、自分だけなのだ。
誰の目を気にすることもなく、親がこう言うからという言い訳をすることもなく、ただ、「自分がこうしたいから」という理由で人生を選んでいいのだ。
ああ、自分の人生を生きることができるとは、どんなに素晴らしいことだろう。
誰の許可もいらず、自分の力で何処へでもいける。誰とでも生きていける。どんな仕事にも挑戦できる。辛くなったらやめてもいいし、やめなくてもいい。
自由だ。
私は、自由なのだ。
25歳になってやっと、私は今、最高に自由なのだと気がついた。
何にも縛られることのない、25歳なのだ。
何をやりたいと言っても、どんなことを思っていると言っても、何を選んでもいい、これからどうにでもなれる未来が待っている。
こうしてここで、自分の居場所があって、しかもその居場所は誰かに作ってもらった場所ではなくて、自分がもがきながら少しずつ作り上げてきた場所で。
家族のいる暖かい場所を離れ、自分で次の居場所を作ることができているのは、なんと幸せなことだろう。
何を宣言したっていい。
どうなりたいと、どんな目標があると言ってもいい。
芸能人になりたいと、ユーチューバーになりたいと、政治家になりたいと、科学者になりたいと、医者になりたいと、作家になりたい、と。
何を成し遂げたいと、どう生きたいと言っても、自由なのだ。
だって、私の未来を決めるのは、周りではなく、私だからだ。
2018年をどうしようと、楽しくしようと、暗くしようと、どう方向転換するのか決められるのは、私しかいない。
自分で責任を取れるようになってきたことは、家族に会いたいと思わなくなってくることは、もしかしたら、思っていたよりもとても素敵なことなのかもしれない。
たとえば、私がどこかの大富豪の娘だったなら、こんな風に苦しむことはなかったのだろうか。
たとえば、私にもっと才能があったら、もうとっくにデビューできていたんだろうか。
たとえば、私がもっと愛情溢れる人間だったら、私を助けてくれる人がもっともっとたくさん、いたんだろうか。
毎日、自分への期待と後悔。他人への嫉妬と執着。
落ち込んで、また復活して、そしてまた落ち込んで、の繰り返し。
泣いて、笑って、怒って、泣いて、また笑って。
めまぐるしく感情を動かして、それでも大人として生きていく。生きていかねばならない。
誰かの役に立てる存在になるために、自分の居場所を作ったのだ。
そうして、生きる。
日々、生きる。
たとえばこうだったらと、別の未来を恋い焦がれることもある。
でも、きっと私は、このままでいい。
今の私の居場所は、もうここなのだ。
ならばもう、できるところまで、ここでやっていくしかない。
さあ、条件は満たした。
「川代紗生」としての戦いをそろそろ、はじめようか?
*この記事は、人生を変える「ライティング・ゼミ《ライトコース》」のフィードバック担当でもあるライターの川代が書いたものです。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになると、一般の方でも記事を寄稿していただき、編集部のOKが出ればWEB天狼院書店の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/event/44700
❏ライタープロフィール
川代紗生(Kawashiro Saki)
東京都生まれ。早稲田大学卒。
天狼院書店 池袋駅前店店長。ライター。雑誌『READING LIFE』副編集長。WEB記事「国際教養学部という階級社会で生きるということ」をはじめ、大学時代からWEB天狼院書店で連載中のブログ「川代ノート」が人気を得る。天狼院書店スタッフとして働く傍ら、ブックライター・WEBライターとしても活動中。
メディア出演:雑誌『Hanako』/雑誌『日経おとなのOFF』/2017年1月、福岡天狼院店長時代にNHK Eテレ『人生デザインU-29』に、「書店店長・ライター」の主人公として出演。
【天狼院書店へのお問い合わせ】
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」2017.1.27 OPEN
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。