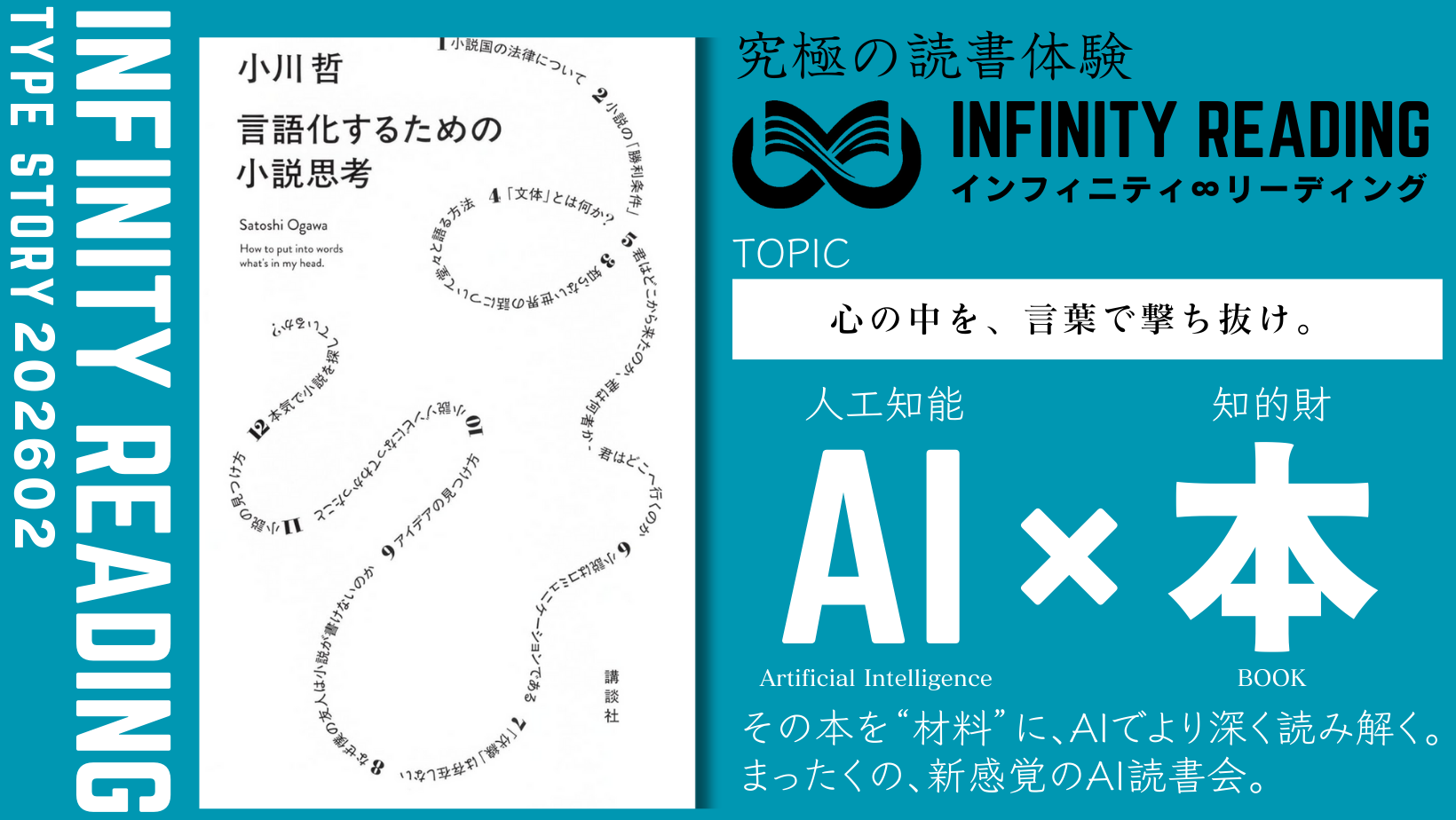『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』村上春樹著《READING LIFE》
思えば、小説を読むのは、ほとんど一年ぶりだった。
『海賊とよばれた男』百田尚樹著(講談社)のプルーフを読んで以来のことだ。
その『海賊とよばれた男』が本屋大賞を取り、その数日後に、こうして村上春樹さんの新刊を読むというのは、なんだか皮肉なことだ。まさか、直木賞の元締めである文藝春秋さんが、本屋大賞に逆襲するために、あえて村上春樹さんの新刊をピンポイントでこの時期にぶつけてきたのではあるまいかと、穿った見方ができないでもないが、おそらくそれは邪推というものだ。
ともあれ、村上春樹さんの新刊である。
そもそも、僕は村上春樹さんの本は『ノルウェイの森』と『羊をめぐる冒険』くらいしか読んでおらず、『海辺のカフカ』も『1Q84』も読んでいない。読む前に、あれよあれよという間にベストセラーとなってしまい、売れるにつれて読む意欲が反比例的に減少してしまい、結局読み損なっていた。
今回の新刊も、そうなっても少しもおかしくはなかった。
今日が発売日でなく、打ち合わせと原稿整理を終えて、息抜きのためにジュンク堂書店池袋本店にふらりと行き、そこでこの新刊用の1F特設の台に、新刊を補充しているのが、「あるいは」文芸担当の美人の店員さんでなければ、もしかして僕はこの本を永久に読まなかったかも知れない。
財布に十分なお金がないことに気づき、銀行でおろし、再びジュンク堂に来て、この本を買って以来、僕は今まで、原稿整理を追いやって、ともかく、この新刊を発売日当日に読みきってやろうと決意した。その決意の裏には、別に合理的理由も打算もなく、直感的なものだったが、その読書によって、「意識のあるものにとっての究極の辺境」であり、「しかし同時にそれは豊潤な場所」であるところの、ある種の読書体験の狭間へと、トリップできるのではないかと思った。
そもそも、僕が小説を読まなくなった理由は、他でもない、「まわりの重力の質が変化」するのではないかと恐れたからだ。小説を読むという行為は、現在のフル・ビジネスシフトにおける重力環境に、煩わしい変化を与える恐れも考えられた。それは、「浪漫飛行」を久しぶりに聞いて、ビジネスシフトの重力環境に、ある種の歪みが生じたのにも、「あるいは」関係しているかもしれない。
特に村上春樹さんの小説を読むことは、ここ数年で組み上げてきた、強靭なはずのビジネスシフトの重力環境を、足場からひとつひとつ丁寧に崩していく作業へと変換させるかもしれなかった。言い換えれば、それは、せっかく様々な合理性や理論で鎧っていたのに、そのひとつひとつを剥いでいって、ヴェールをめくっていくように、あたかも、感受性が豊かな「シロ」が持つ感性のコアの部分を、もろみとして世間の風に晒してしまうことに似ていた。
ところが、およそ7時間かけて読み終えた今、結局はビジネスシフトの重力環境が、少しも崩れなかった。そのことに、安心しつつ、また20歳の「多崎つくる」がはじめて感じた強烈な「嫉妬」のような、人間の原始的な欲求に基づく感情が、そのまま発露されなくなったことに、多少の淋しさも感じるものだった。
そう、僕も、まもなく、主人公と同じ、36歳になろうとしている。
時の変遷の中で、人生は彩りを失い、「あるいは」彩りを濃くし、その一方で「シロ」的な立ち位置にいた子が、色味を失っていくのも実際に親しい中で見もした。また、逆に「沙羅」のように、「話したくない」高校時代を送りつつも、38歳になって、彩り豊かになる人をやはり、見たりもした。
なるほど、それを彩りによって、表現するのか、と思い、これからはこの見方は人生において大いに使えるのではないかと思った。
僕は、それを個人的には「威力」という言葉で今まで認識していたのだが、確かに、特に女性を表す場合は「彩り」としたほうがはるかに認識しやすいことに気づく。
さて、天狼院らしく言えば、「あるいは」、この作品を「限定された目的は人生を簡潔にする」という一文をもって、ビジネス書だと言い切ることもできるかもしれないし、「アカ」や「つくる」の父の生きざまに、それ相応のビジネス的要素を見出すこともできるだろうが、それは本質でないので、柔道の「かけ逃げ」みたいになるやもしれないが、この際、触れなくてもいいかと思う。
また、小説を「これは前作の何々の要素を引き継いで、これこれの時代の要請を上手く汲み取り、かくかくしかじか」なぞと大上段から評することくらいつまらないことはないと思ったので、ともかく、このREADING LIFEにおいては、あえて取り留めもなく、本文中に出てくる要素とこの本における僕の読書体験をつないでみた。
そうする中で、「あるいは」と思ったことがあった。
村上春樹さんの小説に対する姿勢やクリエーターの才能に関する捉え方というのは、もしかして、本文中にあった、次の一文に現れているのかもしれないと。
しかし才能というのは、灰田くん、肉体と意識の強靭な集中に支えられて、初めて機能を発揮するものだ。
そういった、危うい均衡の元で、この作品が紡がれたと思えば、なるほどと納得できるのだ。
また、僕は、この本に触発されてこう思った。
天狼院書店は僕が創り出すある種の「作品」として生み出そう。
この感覚があれば、間違いないような気がする。
最後に、本文中に、強烈に共感できる一文を見つけたので、それを引用して皆さんにも問題提起したいと思う。
「『コックはウェイターを憎み、どちらも客を憎む』」と灰田は言った。「アーノルド・ウェスカーの『調理場』という戯曲に出てくる言葉です。自由を奪われた人間は必ず誰かを憎むようになります。そう思いませんか? 僕はそういう生き方をしたくない」(本文P66より)
村上春樹さんの熱狂的なファンも、そうでない人も、本の前においては、僕は平等だと思う。
そして、それぞれがそれぞれの感じ方をすればいいのだと思う。
ぜひ、臆することなく、手にとって頂きたい。たとえ、その売場にちょうど新刊を補充する美人の店員さんがいなかったとしても笑。