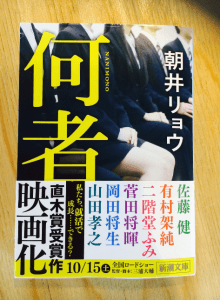朝井リョウ先生、天狼院書店に来ていただけませんか。《勝手に熱烈ファンレター》
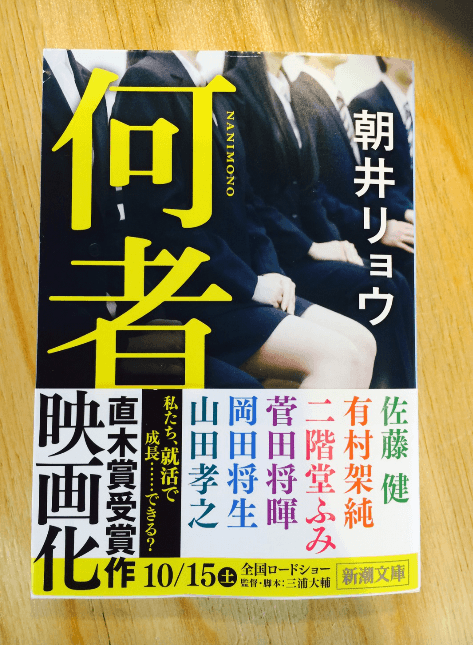
拝啓 朝井リョウ先生
はじめまして。
池袋にある天狼院書店のスタッフをしております、川代と申します。
単刀直入に申し上げます。
天狼院書店に、来ていただけませんか。
お願いします。
無理なお願いとはわかっています。
けれども、私はあなたを天狼院にお呼びしてイベントをやる前には死ねないと思っているくらい、どうしても、あなたに、天狼院に来て欲しい。
天狼院書店では小説家養成ゼミというイベントを定期的に開催しており、ぜひ、そこで朝井リョウ先生に、特別講師として登壇していただきたく思っております。
きっと小説家養成ゼミに参加されているお客様も、若くして直木賞作家であるあなたのお話を聞ければ、モチベーションが上がると思います。
私も、書くことが好きな一書店員として、ぜひとも朝井先生のお話を聞きたいと思っています。あなたをお呼びすることによって、私はありとあらゆる小説家志望の方に貢献したいと考えております。
いかがでしょうか?
天狼院書店に、来ていただけませんか。
あ、やっぱり、だめですね。
本気で、熱烈に、思っていることを正直に、飾ることなく書かないと、嘘っぽくなってしまう。
ごめんなさい。
今まで書いてたの、全部嘘とまでは言いませんが、詭弁です。
ぶっちゃけてしまえば、私は、あなたが天狼院に来ようが来なかろうが、どちらでもいい。
これを聞いたら、店主の三浦や、別のスタッフや、お客様に、なんてわがままな、と言われるかもしれませんが。
私は、私個人があなたに会えれば、どうでもいいんです。
別に小説家養成ゼミに貢献したいとか、書店員としての使命とか、どうでもいいです。私があなたに会いたいんです。死ぬほど。ただそれだけで、このお願いをしています。
この際なので、もっとぶっちゃけてしまいますが、あなたに会える手段として最も実現可能性が高いのが、この、今私が働いている天狼院書店にあなたをお呼びするという方法なので、だからこうしてイベント登壇のお願いをしているわけです。もしも私がものすごい力を持っている権力者で、「今すぐに朝井リョウという作家を私の元に連れてこい」と命令できる立場ならば、わざわざこんなことはしなくても済んだのですが、残念ながら、私は平凡な家で生まれ、平凡に育った質素に暮らしている平凡な人間にすぎませんので、こういった、ある意味卑怯な手段を使うほかありません。
私はどうしても、あなたに会いたい。
そしてどうしても、あなたに伝えたいことがあります。
確認しておきたいことがあります。
あの、あなた、私自身じゃ、ないんですよね?
あなたは、本当に、川代紗生という23歳の女性ではなくて、朝井リョウという、26歳の男性で、間違いはないんですよね? と。
本気で会いたいと思っている相手に対して取り繕うのもなんだか嫌なので、もう、全部暴露してしまいますが、私はもともとは、「朝井リョウ」という作家のことが、好きではありませんでした。
思えば、「朝井リョウ」というとんでもなく若い作家が新人賞をとって華々しくデビューした、というニュースを見たときから、私はあなたのことを気に食わないなと感じていたのかもしれません。
もともと、本に関して偏食気味な私です。好きな作家は村上春樹と星新一。人生のバイブル的な本は「赤毛のアン」。私が本を選ぶ基準は、いかに人の苦しみや葛藤が描かれているかどうかでした。「全然苦労してなさそうな人間が書いた小説なんてなあ」と、食わず嫌いをしていました。
だから、大学2年生の頃、「朝井リョウの本面白いよ」、と仲の良い友人から「何者」をすすめられても、素直に受け入れられなかった。
彼女は私の「親友」と言ってもいいくらいに気の合う子で、彼女に今まで勧められた本はどれもとても面白かったので、もしかしたら自分も気にいるかもしれない、と一瞬、思いました。
でも彼女に、「じゃあ貸して」とは言えなかった。「今度読んでみるね」と社交辞令的に言っただけ。内心では読むつもりなんか毛頭なかった。
どうしても、読みたくなかったんです。読んでみたら面白いかもしれない。自分は食わず嫌いをしているだけかもしれない。何度もそう思いました。でもやっぱり手に取る気にはなれませんでした。
どうしてだろう。
自分でも不思議になるくらい、あなたのことを、毛嫌いしていました。
「朝井リョウ・作家ーーーー早稲田大学出身。若者ならではの視点で、現代の社会問題に鋭く切り込んでいく小説が魅力である」
雑誌やテレビやネットニュースで、そういった紹介文を見るだけでうんざりしました。
なんだこいつ、と思いました。
まず、「早稲田出身」というところが気に食わない。
どうして私の先輩なんだ、と思いました。どうせなら慶應ボーイでいてくれよ、と。
早稲田大学の先輩で、学生時代はダンスサークルに入っていて、在学中にうっかり新人賞をもらっちゃったりして?
しかも、作家として才能もあるのに、新卒でちゃんとした会社に就職するって?
なんだそれ、と思いました。ふざけんな、とも。
いかにも「大学生活をエンジョイしてますよ」という感じが、気に食いませんでした。いわゆる、「リア充」の空気を感じました。なんとなく。
この作家は、私が持っていないものを全部ひょいひょいと手に入れてしまっている。そう思ったのかもしれません。わからないけれど、まあとにかく、悔しかったのです。あなたは私とは生まれつき違う人間なんだと思いました。
頭もいい。
文章の才能もある。
彼女も普通にいそう。
いい会社に就職も決まったらしい。
私が必死になってがんばってがんばってようやく、手が届くか届かないかくらいのものを、こういう人間がさっとかっさらっていくんだろうな、と私は思いました。
私みたいに、真面目で、何やっても損してばかりの人間が、底辺で息も絶え絶えになっているところに颯爽と現れて、一瞬で軽々と私を飛び越していくような、そんな人間なんだろうと思いました。そんなやつの小説なんか読んでも面白いわけがない。
本を読むって、苦しんでる人間の感情とかどろどろしたものに共感するから面白いのであって、自分と全然違う、なんの苦労もしてなさそうな薄っぺらいやつの書いたものに共感できるわけないでしょ。時間の無駄。
きっと、無意識的にそう思っていたのでしょう。だから、あなたの本を手に取る気にはなれませんでした。一生読むもんか、くらいに思ってたんです、本気で。
けれど、運命と言うべきか、偶然と言うべきか。
「何者」がもう一度私の手元に巡ってきたのは、就活を終えた直後のことでした。
私は大学四年生で、必死になって就活をして、ようやく内定をもらえた会社に就職を決めていました。受ける授業もあんまり残っていなくて、週に三回学校に行き、あとはほとんどアルバイトをしていました。
もうサークルも引退しているし、仲の良い友人も限られてきているから、飲み会もあんまりない。
新しい出会いもないから、毎日好きな本を見たり、今のうちにと映画をたくさん見たり、資格試験の勉強をしたり。
そんな、穏やかな、けれどある種退屈な毎日でした。
「これ、すごい好きだと思う。きっと気にいると思うよ。よかったら貸すけど。どう?」
思わぬところで、ぐい、と大型書店のベージュのカバーがかけられた本を渡してきたのは、知り合って一週間も経たない、同級生の男の子でした。
たまたま取った授業で友達になった彼は、私とは違って、フレンドリーで、友達が多くて、勉強もできる明るい人。
明らかに、私が一番苦手とする種類の人間でした。顔見知りになってそれほど時間が経っていないのに、「君、きっとこれ好きでしょ」と屈託なく言える。それでいて、決めつけるような嫌味もない。いかにも就活で引っ張りだこになっていそうな感じ。
こういうみんなの人気者タイプの、下品な言葉で言えば「一軍」の人は、いったいどんな本を読むんだろう。
普段の私なら、「一軍」タイプの人は大の苦手で、なるべく関わらないようにするのが普通なのですが、今回ばかりは、彼が持っていた本の内容が気になりました。彼は、学年で目立つタイプの人間全員を束ねるくらいの力を持っていて、ツイッターの個人アカウントも1500人くらいフォロワーがいる人でした。あなたの作品で例えるなら「桐島」的な人です。そんな人は何を読むんだろう? それがやたらと気になったので、本を開きました。「朝井リョウ」という文字が目に入りました。
もちろん声には出しませんでしたが、うわ、と思いました。
同時に、やっぱり、とも思いました。そして「桐島」的な彼の姿をもう一度見直しました。
男の子にしてはなかなかカラフルな服のチョイス。今時のパーマがかった髪型。そして人懐っこい笑顔。何の苦労も知らなさそうな、選ばれた人間的な、雰囲気。
やっぱりな。
心の中で、こっそり、ため息をつきました。
そうだよ、朝井リョウの本を読むやつっていうのは、こういう人間なんだよ。
こういう、派手で、明るくて、頭も良くて、みんなの頂点に立つような、優秀な人間なんだよ。朝井リョウの本を面白いと思えるのは。
どうせこいつも大して本なんか読まないんだろう、と私は思いました。読書の体験が乏しいからこういう作家の書くものを面白いって思えるのだろう。
けれど臆病な私は、人気者の彼に差し出された本を、拒むことができませんでした。たとえそれが一生読まないと決めていた「朝井リョウ」の本でも。
今だから、言えることです。
下心があったんだと思います。
「人気者の彼が貸してくれた本を読んで感想を言ってもり上がれば、自分も一軍に入れるかも」
そんな意地汚い欲望がありました。だから、拒めなかった。
彼に「何者」を借りたはいいものの、やっぱりページをめくる気にはなりませんでした。
一応鞄の中に「何者」を毎日入れていくのですが、どうしても、開く気にならない。
そして結局は、「今は気分じゃ無いや」と読み慣れている星新一のショートショートに手を出しました。
週に一回あるそのクラスで彼に会うまでには読もう、と毎週毎週決意するのですが、結局だめで、「読んだ?」と彼に聞かれるんじゃ無いかといらぬ心配をしていました。
借りてから、どれくらい経った頃のことかは、よく覚えていません。けれど、いい加減に最初のページだけでも見ようと思って、ぱらりと本を開いたのです。
でもそのときから、私はもう、ページをめくる手を止められなくなりました。
読んでいる途中、息が止まりそうになりました。
頭が真っ白になって、少し指先が、震えてさえいました。そんな感覚は初めてでした。ただ本のページをめくる指先にだけ神経を集中していました。完全に物語の中に入り込んでいました。どっぷりと。あまりに衝撃的すぎて、途中、不安にすらなりました。私はこの世界から抜け出せないんじゃないか? と思いました。
どうして、そこまでハマってしまったのか。
簡単です。
そこに、私がいたからです。
私か、これは?
本気で、そんな錯覚に陥りました。
これは、私じゃないのか。他でもない、私じゃないか。
主人公がまるっきり、自分自身かと思いました。
主人公の名前が自分じゃ無いことが不思議なくらいでした。
で、このキャラクターはあいつ。これは、あの子だな。こっちは……あー、たしかいたな、こういうやつ。あの会社のグループディスカッションのときに。
就活生の、葛藤が描かれていました。
そう言葉で言ってしまうと、あまりに単純なのですが、事実、その本の中の世界は、私が数ヶ月前に身を置いていた、逃げ出したかった世界、そのものでした。
リアルだ。
あまりに、リアルすぎる。
感情移入をしすぎて、呼吸ができなくなるかと思いました。喉の奥に、脱脂綿をぎゅうぎゅうに詰められているような、そんな感覚でした。
読み始めたらもう、止められなくて、そのまま一気に最後まで読みました。
そして、最後の最後で、裏切られました。
まっすぐに一心不乱に、前だけを見て全力疾走していたのに、突然隙だらけの背中にズドン、と思いっきり太い鉄の釘か何かが刺さったような気がしました。
なんで。
え?
こんな、どんでん返しって、あるの?
最後のページをぱたり、と閉じた私は、放心状態で、何をする気も起きませんでした。
「朝井リョウすげえ」
読み終わった瞬間、一人なのに、思わずそう口にしていました。
「朝井リョウ、すげえ」
何度も、自分に言い聞かせるように。あまりに、感動しすぎて、動けない。
何かを吐き出したくなりました。気持ちが悪いわけでも吐き気がするわけでもないのに、何かを思いっきり吐き出したくなりました。この喉の奥につまっている脱脂綿を全部吐き出したい。解放されたい。そんな気分でした。
本来の私なら、そこできっと、「朝井リョウの本なんかどうせつまんないだろうとか思って食わず嫌いしてたなんて、バカだったな」とか、「やっぱり偏らずにいろんな本読むと発見があるな」とか反省できたはずなのですが、もはや、そのときの私には、そういった冷静に思考する気力すら、残されていませんでした。
それくらい。
それくらい、衝撃を受けたんです。あなたの文章に。
あの、朝井先生。
朝井リョウ先生。
私、どうしても聞かなきゃ気が済まないことがあります。
あなたは本当に、私じゃないんですか?
私と同一人物じゃなくて、本当に、全く別の人間なんですか?
いや、冷静に考えれば、もちろん別の人間に決まっているのですが、私はあなたの作品があまりに、自分とリンクしすぎているので、どうしても、あなたが自分じゃないという事実に、納得がいかないんです。
俺はお前だ、って言ってほしい。
別の人間じゃなく、同じ人間だよ、って言って欲しい。
あなたは、私が生み出した別の人格なんだと思いたい。
あなたと同一人物じゃ無いという事実が、悲しくて、辛くて、そして、悔しいです。
だって、本当に違う人間だって言うなら、どうしてここまで私の考えていることを、事細かに言葉にしてくれるんですか。
どうして、こんなに私のことがわかるんですか。
どうして、こんなに刺さる文章が、書けるんですか。
悔しい。
悔しい。
死ぬほど、悔しい。
なんで、この文章を書いているのが、私じゃ無いんですか。
私が書きたかった。私が言葉にしたかった。
でもこれほど完璧なものを出されたら、もう、どうしようもない。何を書く気も起きません。だって、このことに関して、あなた以上に、多くの人に響くように書ける人はいないだろうから。
この前、「小説BOC」のトークイベントで登壇していた朝井さんは、こう言っていました。
「書くなら自分にしか書けないものを書かないといけないって思っています」
「他の人に書けることなら、別に自分が書かなくてもいい」
その言葉を聞いた時、私が「何者」を読んだ直後、「何を書く気も起きない」と感じた時の気持ちを、思い出しました。
たとえどんなに自分の感情を代弁してくれる作品があったとしても、自分も同じことを考えていたとしても、自分も同じ題材について書きたいと思っていたとしても。
その作品があまりに見事だと、もう、何を書く気も起きなくなる。
もう、「何者」は、私そのものでした。
よく「この本を読んで人生が変わった」とか言いますが、私にとって「何者」は、それどころのものじゃありませんでした。
何も考えられない。
人はあまりに感動したとき、これからの生活に生かそうとか、プラスにしていこうとかすら思わないのだと、そのとき初めて知りました。
「何者」を貸してくれた彼に、「めっちゃくちゃ面白かった」と言って返すと、例の「桐島」的な彼は、また屈託の無い笑顔を見せて、こう言いました。
「でっしょー!? 絶対君なら気に入ってくれると思ったんだよね」
苦労してなさそうで、明るくて、生まれた時から「勝ち組」に確定していそうに見える彼は、正しかったんだな、と思いました。
どうして「何者」を気にいると思ったんだろう、と私は思いました。
万人ウケする話ではないと思います。私のように思いっきり刺さる人と、全く刺さらない人、はっきりと分かれる作品だと思います。
でも彼は、これを私に合うだろうと言った。
自意識との葛藤に苦しんでそうに見えた?
プライドが高そうに見えた?
承認欲求をなくしたいともがいているように見えた?
わかりません。
ただ「なんとなく」かもしれないし、ただの勘かもしれない。
一軍の人の考えることなんか、わかりません。
でも私は、彼に「プライドが高いやつ」と見られていたかもしれない可能性なんか、もうどうでもよくなっていました。
そして、思ったんです。
「苦労した人間が書いた文章の方が面白い」なんて、ただの幻想だったんだと。
というよりも、ただの、願望だったんだと思います。私の。
「この人は自分よりも苦労した割合が大きいから、自分より人に響く文章が書ける」と思いたかったんです。
だから、朝井さん自身のことは何も知らないくせに、「勝ち組」っぽいやつにいい文章が書けるわけないと決めつけて、手に取ろうとしなかった。
本だけじゃありません。人間関係だってそうです。
私はどんなときでも、そうやって自分よりも苦労してなさそうな人間を避けてきました。
何の苦しみも味わっていないやつに自分の気持ちなんかわかるわけない。仲良くなれるわけない。
「一軍」とか「意識高い系」とか「スイーツ」とか「リア充」とか。
そういう言葉でくくって、それっぽく見える人とは関わらないようにした。
自分は人とは違う。年の割に苦労してきたし、人生経験もあるほうだから、何も知らなそうなヘラヘラしたやつらより面白い人間。
まさに、「何者」かになりたくて、出来うる限りの言い訳をしてきたんだと、気がつかせてくれたのは、あなたでした。
長々と、書いてしまい、すみません。
熱い思いが溢れすぎて、支離滅裂になってしまった気がします。
末筆になりますが。
朝井先生、改めて、お願いです。
私は、どうしても、あなたに会いたい。そして、あなたがどうしてあそこまで人に刺さる文章が書けるのかを、教えて欲しい。
電話で「小説BOC」の担当の方にお願いしようとも思いました。
編集の方に企画書を提出しようとも思いました。
でも、「書くなら自分にしか書けないものを書きたい」。そう言った朝井さんの言葉が何度も頭の中で反芻したので、今、こうして記事にしてファンレターを送るという、ちょっとずるい方法を取っています。
朝井さんに会って、たしかめたい。
「あなたは、私じゃないんですよね?」と。
いや、もしかしたら単純に、会ってあなたに伝えたいだけかもしれません。
純粋なこの思いを、直接言いたいだけかもしれない。
「書いてくれてありがとう」
「作家になってくれて、ありがとう」と。
朝井リョウ先生。
お願いします。
本当の本気で、お願いしています。
天狼院書店に、来ていただけませんか。
ご検討、よろしくお願いします。敬具
2016年5月8日
天狼院書店
川代紗生
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
朝井リョウさんの「何者」は天狼院書店でもお買い求めいただけます!
お取り置きは下記お問い合わせフォーム、もしくはお電話(03−6914−3618)で承ります!
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】
【有料メルマガのご登録はこちらから】