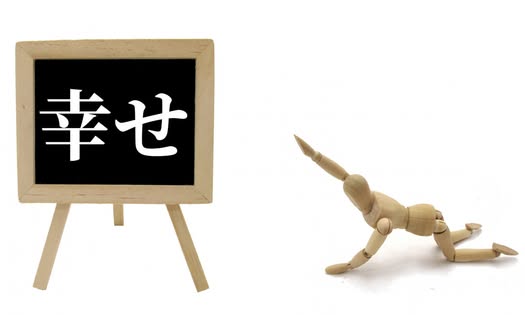「家族にだって言えないこと」なんていくらでもある《川代ノート》


スタッフ川代です。
お盆に、親戚の集まりがありました。
私の家ではお盆の過ごし方というのはパターンが決まっていて、親戚が10人くらい、一堂に祖父母宅に集まって、みんなのお土産をだらだら食べながら、クーラーの効いた部屋であれやこれやとおしゃべりをするのですが、親戚みんながキャラが濃すぎて、話がとっても面白いんです。
警察のお偉いさんだった祖父の濃い九州男児の血を受け継いだためか、私の母含め、伯母も叔父も、従姉も、みんなキャラがたっているというか、一言で言ってしまえば、強烈です。
そのなかでも、一番強烈なのが、お化けが見える伯母。
母の姉である伯母は霊感が強くて、しょっちゅう家にお化けが出てきて金縛りにあって襲われたり、お風呂で宇宙人に意識をうばわれて宇宙船に連れていかれたり、パラレルワールドに飛ばされたり、会うたびに不思議な体験を話してくれます。でもその不思議なカンの鋭さと、強烈なスピリチュアルなパワーで、松岡修三的に、いつも周りの人のお尻をたたいて持ち上げています。私も受験のときに、謎の光を放ってもらって(?)、第一志望の入試前日にパワーをもらったこともあります。
いつも自信満々で、自分のやっていることに誇りをもっていて、プライベートもエンジョイしていて、郷ひろみの大ファンで、毎度毎度、ツーショット写真を自慢してくる面白すぎる伯母ですが。
今回のお盆では、意外な話が出ました。
「私ね、今でこそコンサートとか行きまくってるけど、子供の頃さ、あまりに真面目すぎて、郷ひろみのファンだってこと、言えなかったの」
姉妹で昔話をしているときに、突然こんなことを言い出した伯母。
「え?姉さん、昔からファンだったの?」と驚く私の母。
「そうだよ。はじめて郷ひろみが出てきたとき、『わあ、この世にはこんなに素敵な人がいるんだあ』って、本当に感動したんだもの」
「ウソ!だって姉さん、私が郷ひろみのポスター壁に貼ったり、レコード集めてたとき、『あんた郷ひろみなんか好きなの?変なの』って、馬鹿にしてたじゃん!」
「違うの。あまりに真面目すぎて、誰かのファンだなんてこと、言えなかったの。私は長女で、母さんから頼られてて、勉強もできたし、運動もできたし、完璧じゃなきゃいけない、いい子でいなきゃいけない、っていう想いがずっとあった。『こうじゃなきゃいけない自分像』が強すぎて、本当に真面目だったから、『誰かのファンだ』っていうことすら、言えなかった。だから、平気で郷ひろみのポスターを貼ったり、レコードを買ったりしてるあんたが羨ましかったんだよ」
ええ!そんなこと初めて知った!母は本気でびっくりしていました。でも、真面目すぎてファンだって言えないって、意味わかんない!と、一堂は一通り爆笑。
心に抱えていた、誰にも言えなかった本音を、半世紀弱のときを経て、ようやく解禁した伯母に、笑っていた母でしたが。
でも実は、母の方はむしろ、なんでもできる完璧な姉といつも比べられてしまうというコンプレックスがあって、「自分は駄目な子だ」という自意識があったことを、つい最近まで言えずにいたのです。
姉ばっかり頼られて、自分は母からは手がかかる子扱いされる。私だって、個性がある!お母さんに認めてほしい!私だって出来ることがあるのに!と、そうずっと思ってきたので、母はむしろ両親に振り向いてほしいという隠れた願望のもと、伯母よりも体裁は悪くても、やりたいことは好き勝手にやってきました。
母はよくこう言っていました。
「私は『いい子』だった経験がない。いつもいつも、私は姉とくらべて『駄目な子』だった。だから、自信がないの。そのぶん、プライドも見栄もないから、好きなことをやってこれたけど」。
だから母には、真面目すぎて郷ひろみのファンだ、と公言することが出来ない、ということの意味がわからない、想像が出来ないのです。ファンって言えないってなによ、と、ずっと不思議がっていました。母だけでなく、伯父も、伯母の娘である私の従姉も、祖母も、それどういう心理なの?と言っていました。
けれど、私には、伯母の言う意味が、本当によくわかりました。
私は、所謂「いい子」でした。子供の頃はとくに。
真面目すぎて、悪いことができない。親を困らせるようないたずらなんてもってのほか。なにか悪いことをしてしまうと、罪悪感がつのりすぎて、すぐに母に懺悔してしまうような子供でした。
小学生なのにニックネームはなくて、呼ばれるのはいつも「川代さん」。成績優秀で、テストは満点ばっかり、足はクラスの女子で一番速く、リレーの選手に。学級委員を選ぶときは、「やっぱり川代さんでしょー!」とか言われて、他薦で決まっちゃうようなタイプ。
でも、本当に仲のいい友達はいなかったんです。授業のあと、近所で遊ぶ友達も、自転車で一緒に出掛けに行く友達も、土日に遊園地に行く友達もいなかった。「川代さんは優等生だからね」という、お約束のせりふと一緒に、誘ってもらえない。それがものすごく寂しかったんです。成績は悪くても、いたずらばかりして先生を困らせていても、クラスの中心的人物で、友達がたくさんいる子のことが、羨ましくて仕方なかった。私もみんなの仲間に入れてほしかったし、思いっきりふざけたこともしたかった。でも、「優等生」というイメージを崩しちゃいけないという使命感のもと、どんどん真面目に拍車がかかって。
それこそ、アイドルが好き、なんて全然言えなかった。家族にさえも。一番信頼していた母にさえも。というよりも、家族だからこそ、なおさら言えなかった。
私はもともと、はまりだすととことんはまる質で、中学生の頃なんて、好きな漫画も、ドラマも、俳優もたくさんいたけれど、何故だか、家族にそれを知られるのが、恥ずかしかった。
「好きなものがある自分」が許せないんじゃないんです。なんだか、「真面目で優等生な自分」のイメージに、「誰かを猛烈に好きである」という特徴が、うまく一致しないような気がして、堂々と公言できなかったんです(私の場合は隠しきれずに駄々漏れでしたが)。
だから、叔母の言うことは、本当によく分かりました。みんな、なんで恥ずかしいの?と不思議がっていましたが、ある意味、私と叔母はよく似ていて、その子供ながらのプライドの高さが痛いほどよくわかったのです。
こういう告白も、きっと、この記事を通してはじめて知るであろう母は、ものすごく驚くと思いますし、母とは昔から仲の良い私がある意味での隠し事をしていたことを、悲しむだろうとも思います。私は反抗期もほとんど来たことが無いし、母とはいつも考えを共有してきました。母は間違いなく私の一番の理解者ですし、大切な存在です。
でも、それくらい仲のいい親子でも、家族でも、それでも言えないことなんて、いくらでもあるのです。
「家族なら話して当然」
「親子なのに言ってくれなかった」
「母親なのに知らなかった」・・・。
母というものは、なんでも知っているものだ、なんてよく聞くけれど。たしかに母親というものは、こちらが知らず知らずのうちに察してくれていて、陰ながら支えてくれるものです。けれど、それでも言えないことだって、あります。
ひとりひとり、それぞれが、社会のなかでなにかしらの役割をもって生きています。どんな立場も背負わない、「ただの個人」として生きるのは、結構骨が折れるものです。学生、会社員、自営業、主婦・・・そんなレッテルをはられていた方が、不満はあっても楽に生きられる。人間ひとりひとり、違う人間なのだから、そんな立場だのなんだのに、振り回されないべきだ、とは思っていても、「自分だけのなにか」「どんな立場も持たない自分」というのは、他の人が持たない自分の強い個性だけで勝負しなくてはならないということですから、社会に頼ることが出来なくなるし、苦労します。多くの人は、「立場」や「レッテル」の存在にうんざりしつつも、結局はそういう言葉に守られて生きている。
そして真面目で、プライドが高く、コンプレックスを持っていたり、「こうしなきゃ」という使命感を持っている人ほど、その「立場」やイメージに合わせてしまう。「みんなが抱いている自分像」から逸脱しちゃだめだ、と思って自分を追い込んでしまう。本当の自分よりも、みんなが求める自分になることを優先してしまう。本当の自分でいたいけど、みんなに嫌われたくないという、矛盾した感情。
そういう相反する気持ちは、社会だけで生まれるものではありません。家族の中ならば、なおさらそう。つながりが深い家族だからこそ、「家族の求めているであろう自分像」を演じてしまうのです。
たとえそれが、本当に家族が求めているものでなくても、母は、自分の本当の姿も、どんなにみっともない欠点も受け入れてくれるとしても、どうしても、自分で勝手に作り上げてしまう、「家族はこういう自分でいてほしいんだろう」というイメージからは、ぬけだすことが出来ません。
もしかしたら、人は家族のなかで、社会に出る前の練習をしているのかもしれない。
人が対面する最初の、一番小さなコミュニティとして、家族というものがあって、みんな、素の自分を出しているようでいて、本当は無意識のうちに、コミュニティのバランスをとろうとして、立場を身に着けてしまうんじゃないかと思うのです。
だから、「家族にだって言えないこと」、なんて言いますが、「家族だからこそ言えないこと」が、いくらでもあって。
ひとつのチームとしての家族をうまく保とうとして、そのために自分が動こうとするならば、「本当の自分」のなかでも、言えることもあるけれど、言えないこともある。
ですから、母と叔母の姉妹は、お互いがお互いに強烈に憧れていたという本音を、齢50をようやく越え、それぞれが別の家族を持ち、子供たちが自立するまで、ずっとずっと、言えなかったのです。
母と叔母が家族だった頃には、ある意味、祖父母に与えられた「姉」と「妹」の立場を、図らずも、そのまま守ろうとしてしまっていたのかもしれません。
私も同じで、一人っ子で、大切に育ててもらって、親からの愛をたっぷり注いでもらって。
なんとなく、「それだけのものをいただいてるのだから、同じくらい返さないと申し訳ない」という自意識が働いてしまったのかもしれない。
母や父からすれば、私が好きなことを好きなだけできるのが、彼らにとっての幸せだったのでしょうが、私は幼いながらに、自分も家族の中で、なにかしら役に立たなきゃいけないという使命感のもと、バランスをとろうとしてしまっていました。
子供だからこそ抱いてしまう、「自分」と「家族」を守るための、小さなプライド。
本当の本当は、家族なのだから、自然体な自分でぶつかっても何も間違いはないし、それが一番家族というチームをうまく経営できる方法なのに、やっぱりどこかで、なんとか役に立とうと、努力してしまう。家族を守りたいからこそ、愛しているからこそ、「言えないこと」が、どんどん増えてゆく。
家族に隠し事をしたくないのは、こちらも同じです。私も尊敬する両親に、嘘も吐きたくないし、自分のすべてをさらけ出せればいいのにと思う。
でも、「家族」とはいっても、所詮は他人なんです。私と母も、私と父も、母と伯母も、いくら同じ家族に所属していたって、血がつながっていたって、長年一緒に住んでいたって、まったく別々の他人。結局は「個」と「個」のぶつかり合いです。
「家族」みんなが同じ価値観になればいいというのを無意識に願ってしまう人は、結構多いのでしょう。私も、母と仲がいいだけに、高校生頃までは、絶対に同じ価値観を常に共有していたいと思っていました。大好きだったからこそ、母と同じ人間になりたいとすら思っていました。
でもやっぱりどうしても、お互いが共有できる時間が減っていくほど、私と母が別の経験をすればするほど、価値観の違いはどんどん積み重なっていく。
とてつもなく寂しいし、ずっと母と一緒でいられればいいのに、とも思うけれど、それはやっぱり年を取っていく限り、避けられないことなのです。
むしろ、本当なら、親と違う価値観が増えていくことを、お互いに喜ぶべきで。
親の分身であった子供が、親とはどんどん違う人間になっていくというのは、それだけ子供が多くの経験をして、成長していっているということで、つまり、一人の「個」として、立派に自立していっている証なのですから、祝福すべきことなのです。
だから、「家族にも言えないこと」がたくさんあっても、別に構わない。
もちろん殺人とか犯罪とか、限度はありますし、人として間違ったことをしているとか、恥ずかしいことをしている、という意味では、ちっともよくありませんが、ぞういう場合を除いて、むやみに「家族なのに知らなかった」と、悲観するのはちょっと違うなあ、と思うわけです。
家族だからって同じ人間というわけじゃないということを、十分に理解しないと、それぞれがお互いの成長を妨げてしまうことになる。
家族を守ろうとして、逆にチームとしての家族全体が、うまくいかなくなってしまうかもしれない。
母も伯母も、これだけ長いときが流れて、お互い別々に多くの経験をしてきてようやく、認め合えたこと、告白しあえたこと、いろいろありましたが、きっとこれでよかったんだろうなあ、と思いました。
その、自分がどうしても「言えなかったこと」を、ようやく「言えること」にできるまでの紆余曲折が、とっても面白くて、人間らしくて、濃度の高い、価値のある時間だったんだろう、と。
私も、家族に言えないこと、意外と結構ありますし、ばれたくないことも、それなりにあるけれど。
きっと20年後、30年後には、「実はあのときさー」、と、笑い話にしてしまっている自分が、容易に想像できて、その時が来るのが、とても楽しみなのです。
今は、家族には、「すいません、気長に待ってください」としか言えませんが。
「家族にも言えないこと」を、いつかちゃんと言える日を迎えるために、家族のなかの自分ではなく、家族とは違う価値観の、「個」としての自分を確立させるべく、いろんな場所に飛び出していきたいと思う。
親とは違う人間になるってことを考えると寂しくて、涙が出そうになるけれど。
でももしかすると、この不思議な切なさが、大人になる、ってことなのかもしれない、と、ちょっとだけ思いました。
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
【天狼院公式Facebookページ】
天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をして頂くだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。イベントの参加申し込みもこちらが便利です。