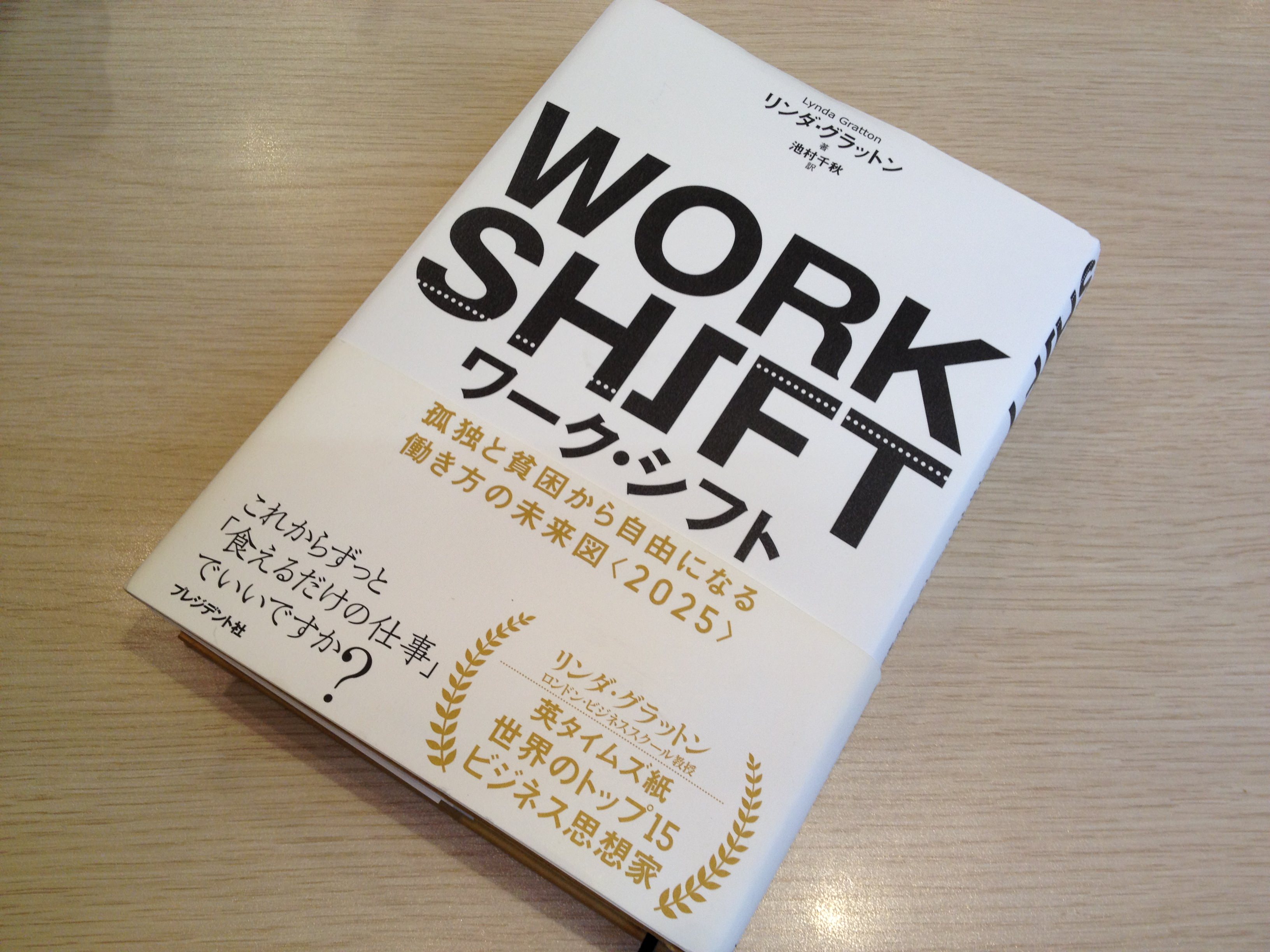『ワーク・シフト』リンダ・グラットン著《READING LIFE》
正直言うと、難航していた。
今制作を進めている『READING LIFE』の「働き方」テーマにどの作品を選ぶか、この数週間、思った以上に悩んでいた。
オープニング作品ははじめから『僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?』木暮太一著(星海社新書)に決まっていた。そして、「LESS IS MORE」、つまりは「足るを知る」の論点を取り入れながら、「ワークライフ・バランス」で幸せのかたちを模索し、その一方で、「仕事=人生」という生き方も悪くない、と提示する。また、パーソナル・ブランディングが重要視される「フリーエージェント」的な働き方も紹介しながら、けっして安易なノマドは推奨しないというラインも決まっていた。
そう、大筋はもう早い段階から決まっていたのだ。
ところが、このテーマを「締める」ための重要な作品が見い出せないでいた。
それはたとえば、体操でいえば、着地のようなものだ。『READING LIFE』の「働き方」テーマは、内村選手のようにビシッと着地を決めたいと思っていた。
そんなときに、この本と出会った。そして、すべての悩みは解消された。
間違いなく、本書は、「働き方」テーマに、あるひとつの着地点を見出す作品である。すべてを総括していると言ってもいい。
これは、ここ1年間はベストセラーとして書店のメインの棚を占めるべき作品であり、数年後は揺るぎなく平積みされるべき作品である。
とにかく、読んでもらいたい。
最初はもしかして、「あれ、第一のシフトってなんだっけ?第二のシフト?Y世代って何年生まれ?Z世代?」と混乱し、何度も戻りながら読むことになるかもしれない。けれども、そういう些事はあまり気にせずに、とにかく読み進めてほしい。読み終える頃には、ここにある聞きなれない言葉たちが「すとん」と体内に消化されるだろうと思う。
この本のすごいところは、たとえば、映画でいうところのカメラワークにあると思う。
すなわち、未来を生きるあるひとりの人物に「寄った」かと思えば、次の項目では高いところまで「引いて」歴史的な観点から俯瞰的に描いてみせる。「寄った」ときも「引いた」ときも、その精密な彩りが失われないということは、相当に作りこまれているという証拠である。逆をいえば、相当に作り込んでいるという自負がなければ、こんな自在のカメラワークは不可能である。なぜなら、すぐに粗が見えてしまうからである。
本文を見ていこう。
グローバル化が進んで、様々な国とリアルタイムで仕事をこなすようになる未来、今よりも、人は時間に追われることになるだろうと、ある一人の男性の生活にクローズアップしてから、こう問題提起する。
では、時間に追われる生活を避けるためには、どうすればいいのか。一つのものごとに集中して取り組む時間と、専門分野に深く習熟する機会を増やし、気まぐれと遊びの要素を生活に織り込むためには、なにが必要なのか。自分をすり減らさず、活力と才能を失わずにすむ働き方を実践するためには、どうするべきなのか。
そもそも、こういった疑問があるからこそ、今多くの人が「働き方」テーマの本を手に取るのではないだろうか。
この本は、この問題に対して、豊富な考察と論証を元に、丁寧に答えを紡いでいく。
たとえば、ミステリーなどで風呂敷を広げすぎて、興味だけを煽り、最後に収斂できない作品など多く見受けられるが、この本は違う。
前半部分は、エネルギー問題や新興国の台頭など、もしかして未来は暗いのではないかと危機感を覚えながら読むことになるのだが、この本の後半部分には、多くの「希望」が提示されている。どうすれば、「ワーク・シフト」できるかという明確なモデルが示されている。
つまり、大きく大きく風呂敷を広げたのに、恐ろしいほどにきちんと収斂もしているのである。
ただ単に未来を提示するばかりではなく、それを手にするために我々は何をしなければならないのか、我々はどういうスタンスでいるべきなのか、という覚悟を求める。
世界は、目まぐるしいペースで変化している。「仕事とはこうあるべし」「仕事はこのようにおこなうべし」という固定観念の多くが過去のものになり、新たな選択肢とチャンスが拡大する。お仕着せのキャリアの道筋ではなく、充足感とやりがいをいだけるキャリアを切り開けるようになる。
ただし、自分に会ったオーダーメイドのキャリアを実践するためには、主体的に選択を重ね、その選択の結果を受け入れる覚悟が必要だ。
結局はこれを読んだ我々の決断と行動にかかっているということだ。
第8章以降は、具体的にどのように「ワーク・シフト」して行くべきかがわかりやすく書いてある。
実は、多くの働き方テーマの本で、最大の弱点となっているのが、「では、具体的にどうすればいいか」という点が欠如しているか、もしくは曖昧になっているということだ。しかし、この本は、本当に丁寧に、そして明確にその疑問に答えている。
働き方をシフトして行かなければならない。しかも、それは三段階に渡るものである、と。
第一のシフトはこういうようなものだ。
未来の仕事の世界で成功できるかどうかを左右する要因の一つは、その時代に価値を生み出せる知的資本を築けるかどうかだ。とりわけ、広く浅い知識や技能を蓄えるゼネラリストを脱却し、専門技能の連続的習得者への抜本的な〈シフト〉を遂げる必要がある。多くの分野について少しずつ知っているのではなく、いくつかの分野について深い知識と高い能力を蓄えなくてはならないのだ。
ゼネラリストから「連続スペシャリスト」へとシフトしなければ太刀打ちできなくなるという。
その上で、高度な専門技能を身につける方法についても書いてある。ここに出てくる「ギルド」の考え方と「遊び」の論点は特に重要である。また、セルフマーケティングのために、「シグネチャー(署名)」を残すべきだという考え方も実に印象的だ。
また、この章をこう締める。
働き方の未来を考えるとき、はっきり認識すべきなのは、これまでのキャリアの常識が通用しなくなるということだ。本書で論じてきた五つの要因により、仕事の世界が大きく様変わりすることを考えると、私たちは働き方を〈シフト〉させなくてはならない。これまでの固定観念を〈シフト〉させ、身につける能力を〈シフト〉させ、行動パターンを〈シフト〉させる必要がある。
第二のシフトは、コ・クリエーションという考え方だ。つまり、人的ネットワークを駆使して、協力してイノベーションを起こす時代になると示唆する。
ここで出てくる「ビックアイデア・クラウド」は、今本格的に広がりつつある、ソーシャル・ネットワークの進化系のような知的集合体のことである。マーク・ザッカーバーグ的に言えば、「ソーシャル・グラフ」を使った集合知とでもいうべきだろうか。
この章のキケロについての記述がまた興味深い。
キケロはこう述べている。「世界で最も強い満足感をもたらす経験とは、地球上のあらゆる題材について、自分自身に向かって語るのと同じくらい自由に話せる相手を持つことである」。そういう人間関係は、まさに再生をもたらす関係と言える。それは、一つの目的に限定されたメリットをもたらす関係ではなく、人生のあらゆる面で好ましい作用を生み出す関係であり、「未来に向けて希望の明るい光を投げかける」ものだからだ。
第三のシフトは、まさに「LESS IS MORE」つまりは「足るを知る」の論点であり、「ワークライフ・バランス」および「ワークライフ・シナジー」の論点である。
〈第三のシフト〉は、未来に向けて求められる三つの〈シフト〉のなかで最も難しい。やりがいと情熱を感じられ、前向きで充実した経験を味わえる職業生活への転換を成し遂げ、所得と消費を中核に据える職業人生から脱却しなくてはならない。具体的には、自分の前にある選択肢の一つひとつを深く理解し、それぞれの道を選んだ場合に待っている結果を知的に分析したうえで、行動に踏み切る勇気をもつ必要がある。簡単なことではないが、それを実践しない限り、自分が望む働き方、自分にふさわしい働き方の未来は切り開けない。
また、なぜ「足るを知る」必要があるのか、ということについて、こんな論拠を提示している。
宝くじの当選者の頭の中で起きていることは、経済学の分野では「限界効用の逓減」という言葉で説明される。簡単に言えば、あるものを得る数や量が増えれば増えるほど、それに価値を感じなくなるという法則である。
その上で、ここで注目すべきことがある、とさらに重要な論点をあげる。
お金と消費には限界効用逓減の法則が当てはまるが、それ以外の経験にはこの法則が当てはまらないという点である。たとえば、高度な専門技能を磨けば磨くほど、あるいは友達の輪を広げれば広げるほど、私たちが新たに得る効用が減る、などということはない。むしろ、私たちが手にする効用は増える。
だから、「ワーク・シフト」が必要なのだ。
これを読めば、「年収3000万円が目標です!フェラーリに乗りたいです!」と未だに言っている人が、じつに古臭いということを実感できるだろうと思う。「あの頃の価値感」は永遠ではない。
そう、我々は価値観を「シフト」させながら、進化していかなければならないのだ。
その先に、本当の意味での幸せがあるのだと思う。
働き方を考えることは、幸せのかたちを考えることでもある。
我々は、この本を読み、働き方を考えることを通し、もう一度、自分の幸せのかたちについて考えてみるべきなのではないだろうか。
そういった意味において、この本を買わない理由が見当たらないのである。
訳者があとがきで書いてあるように、「キルト」のような色鮮やかなこの本の世界観をご堪能いただきたいと思う。
*ぜひ、お近くの書店でお買い求めください。