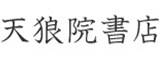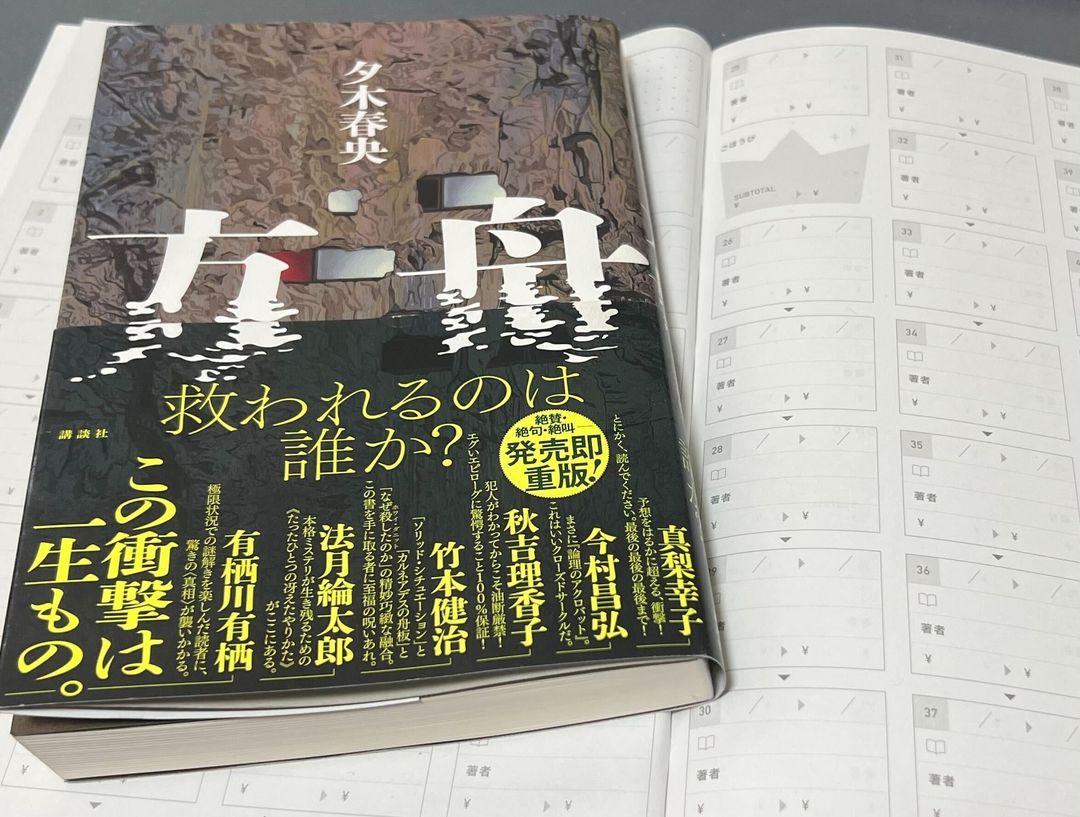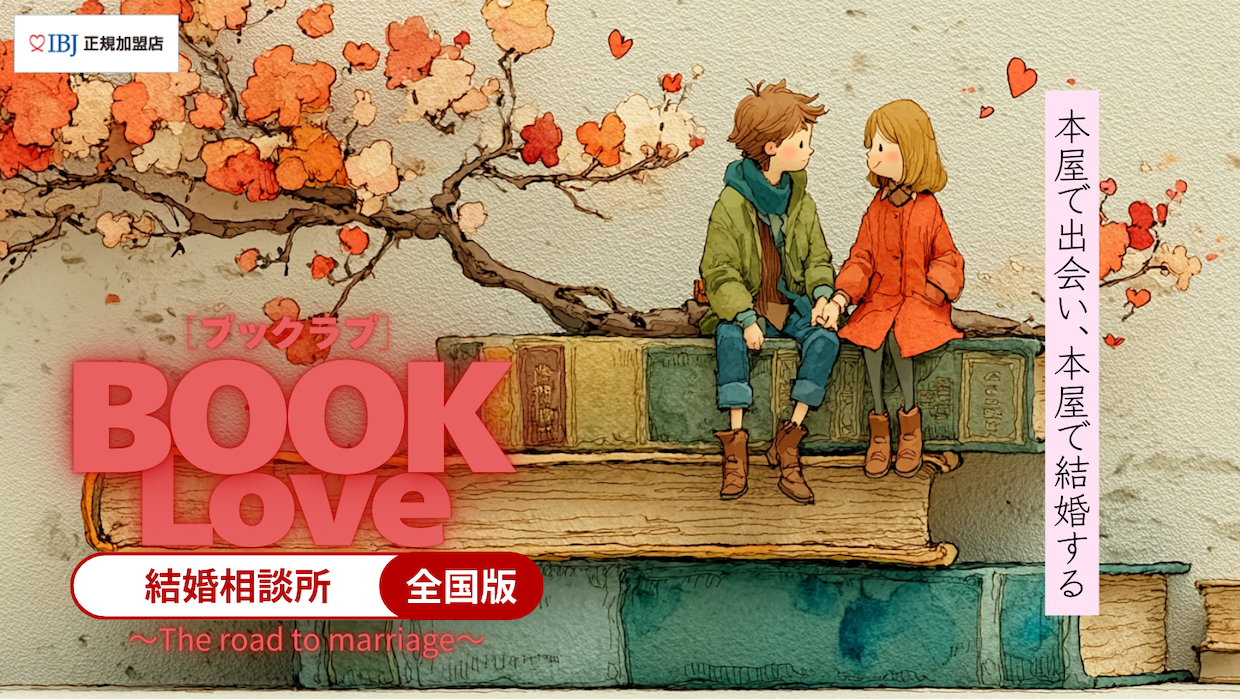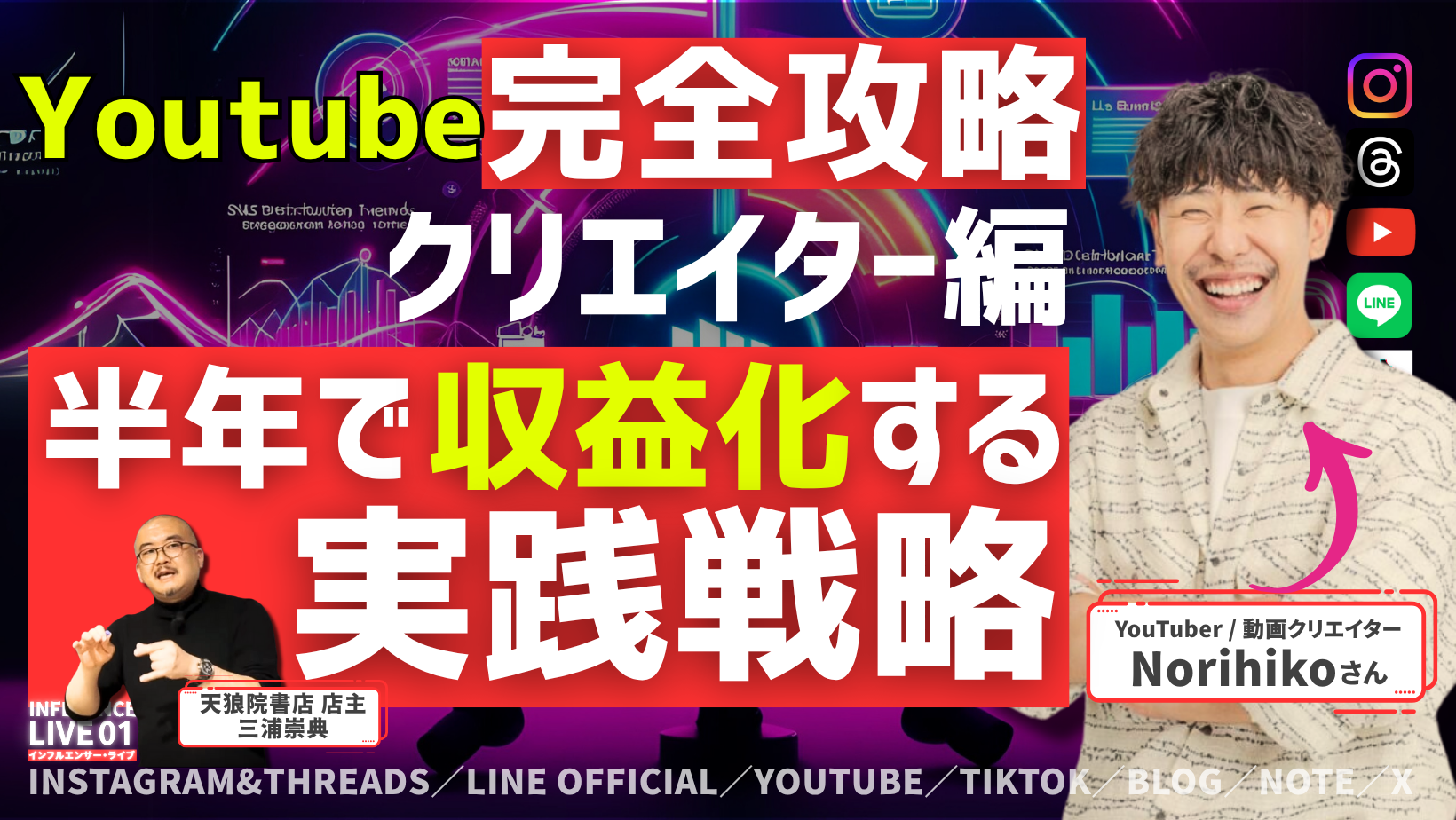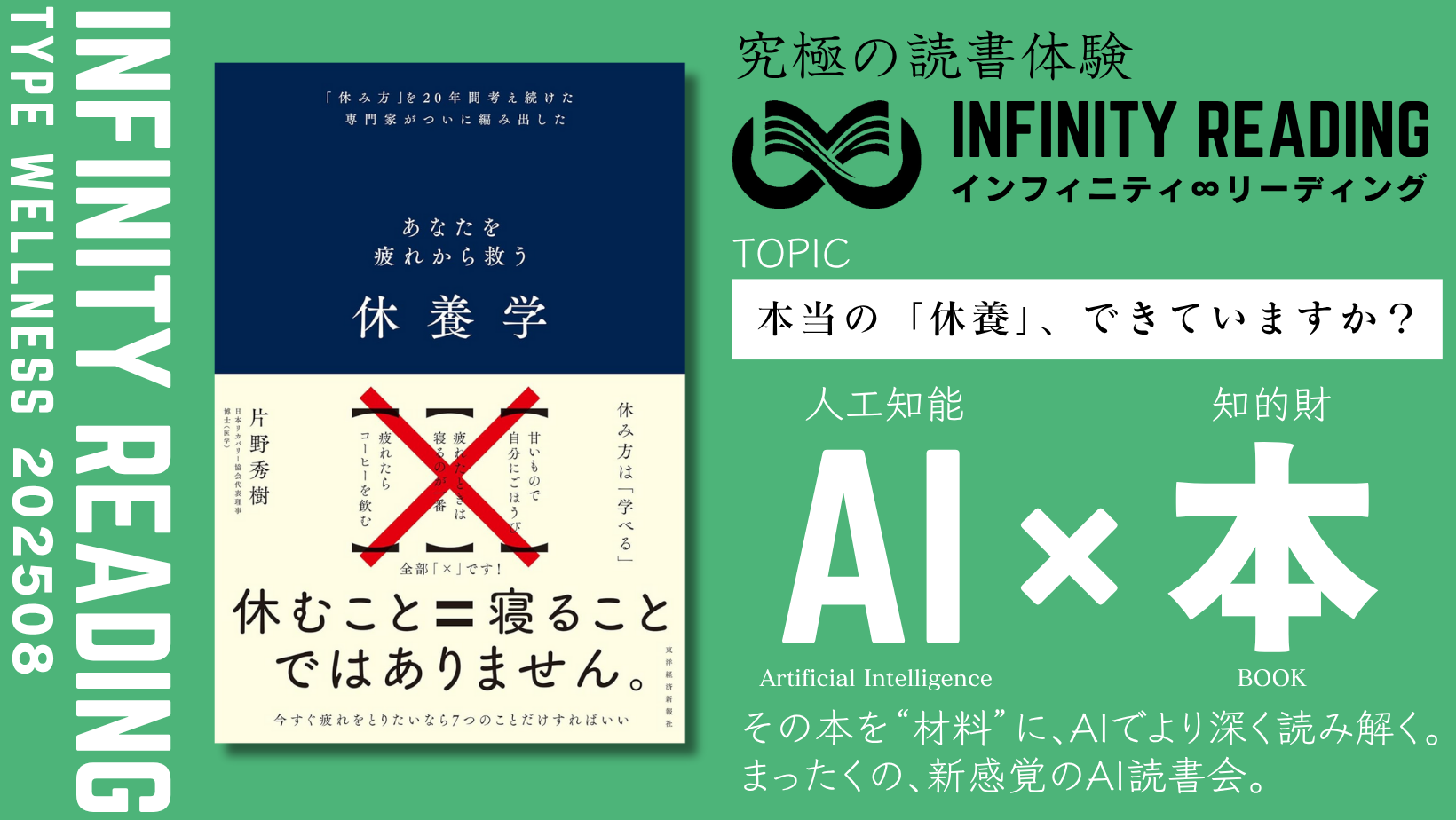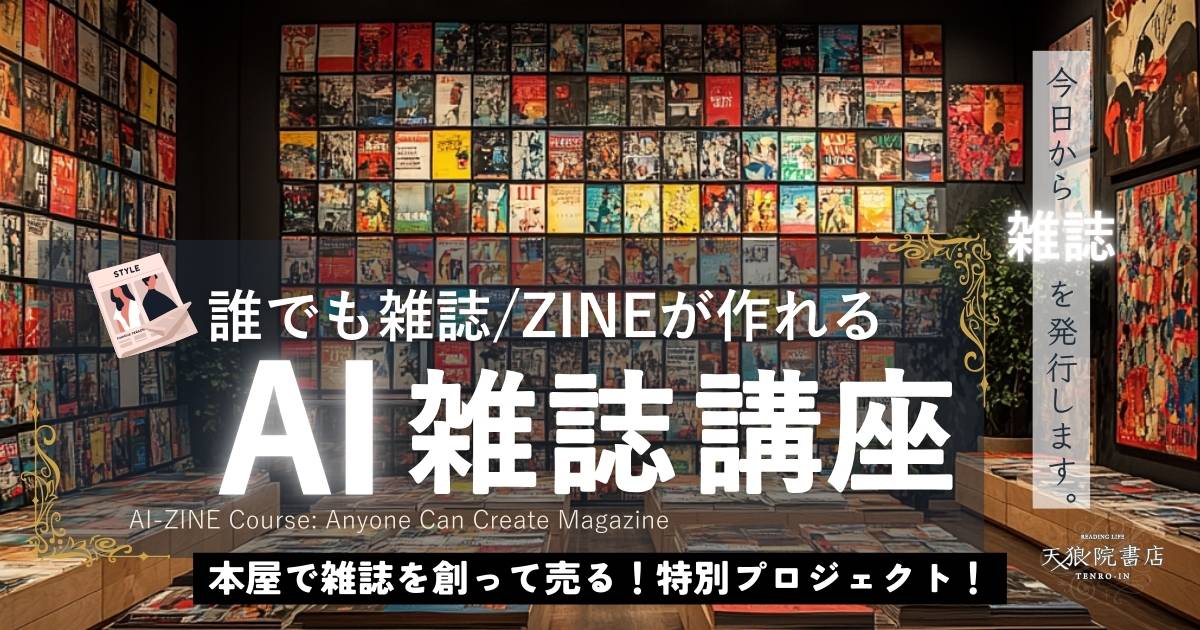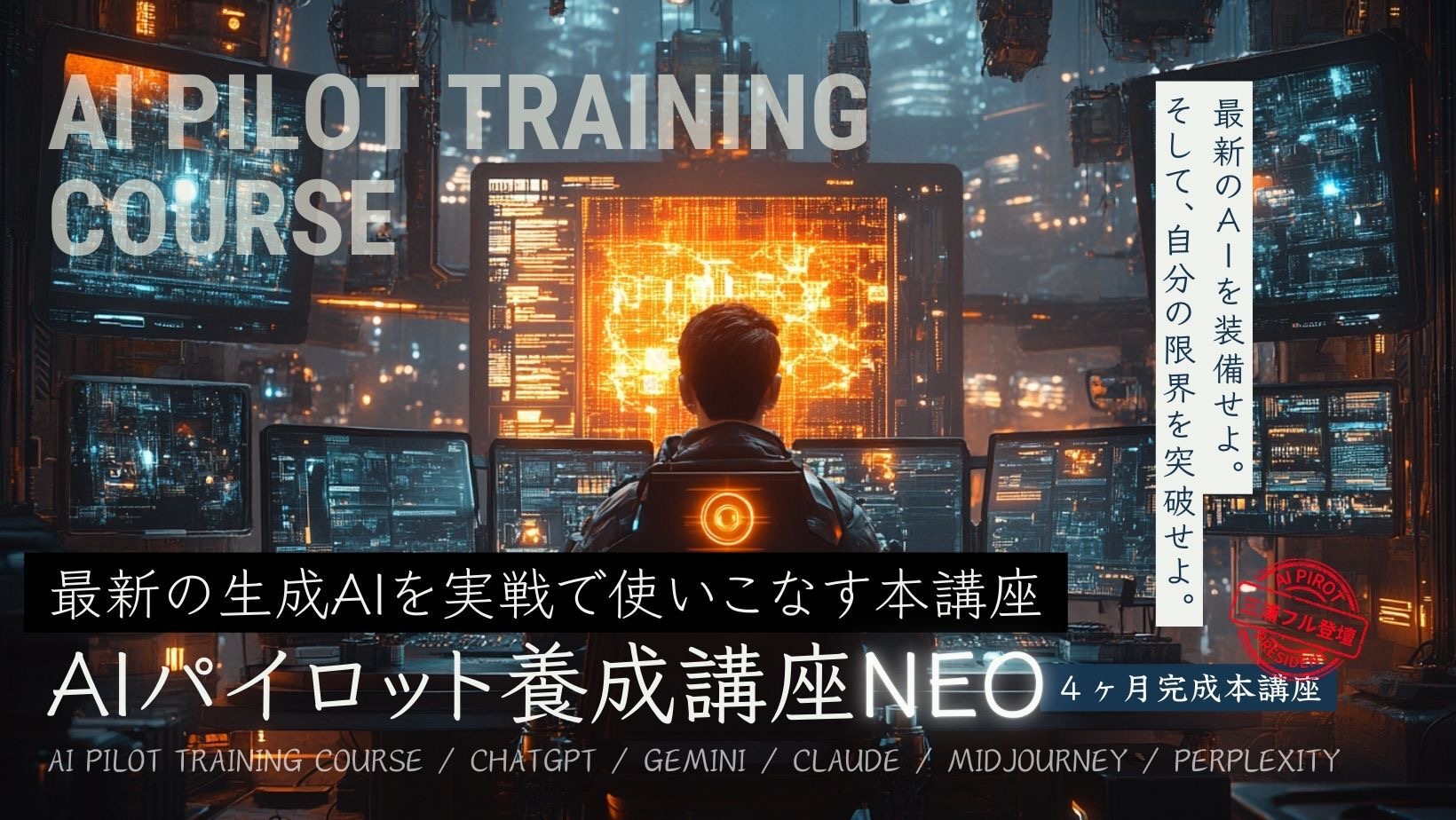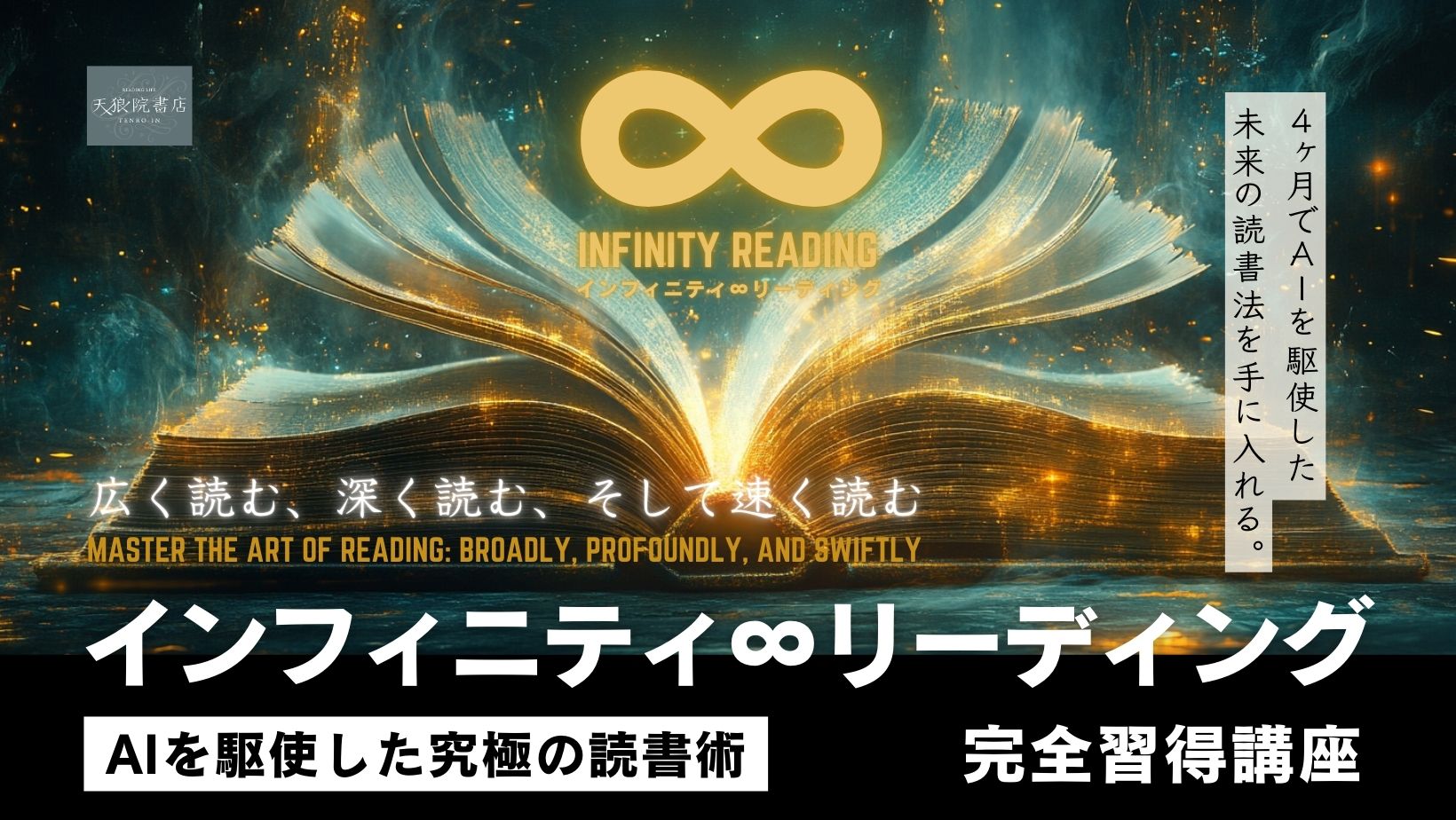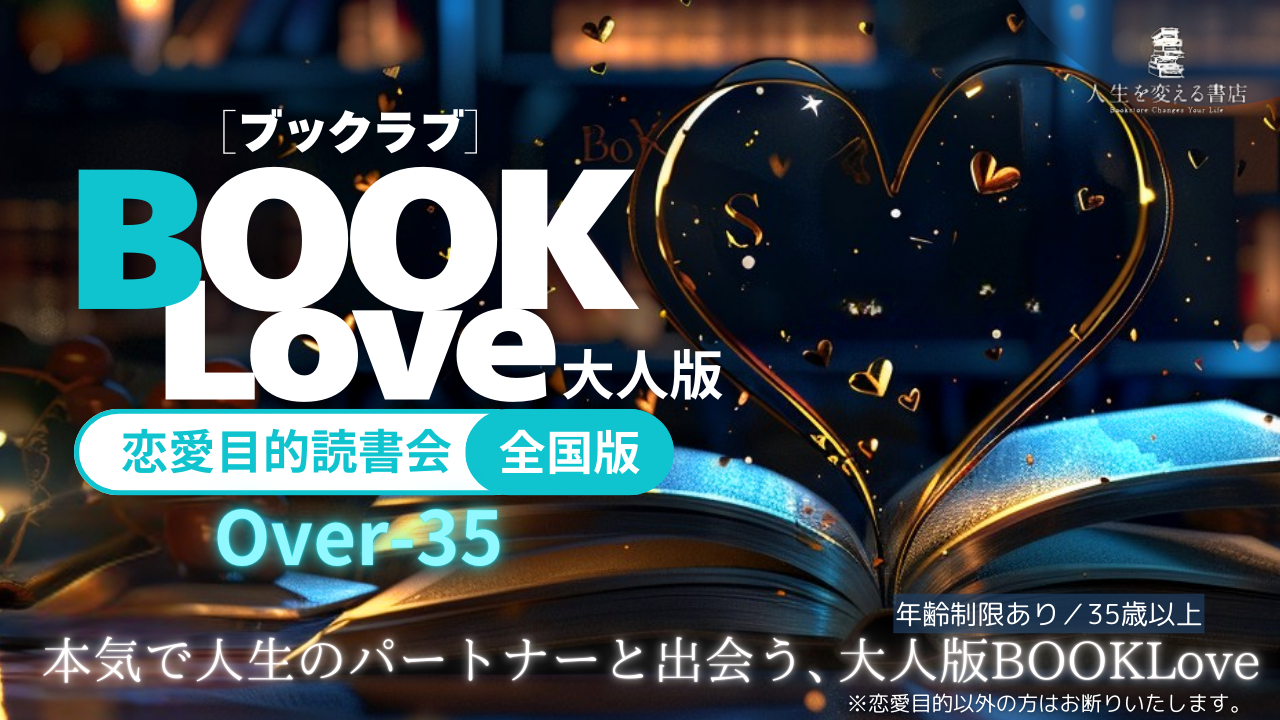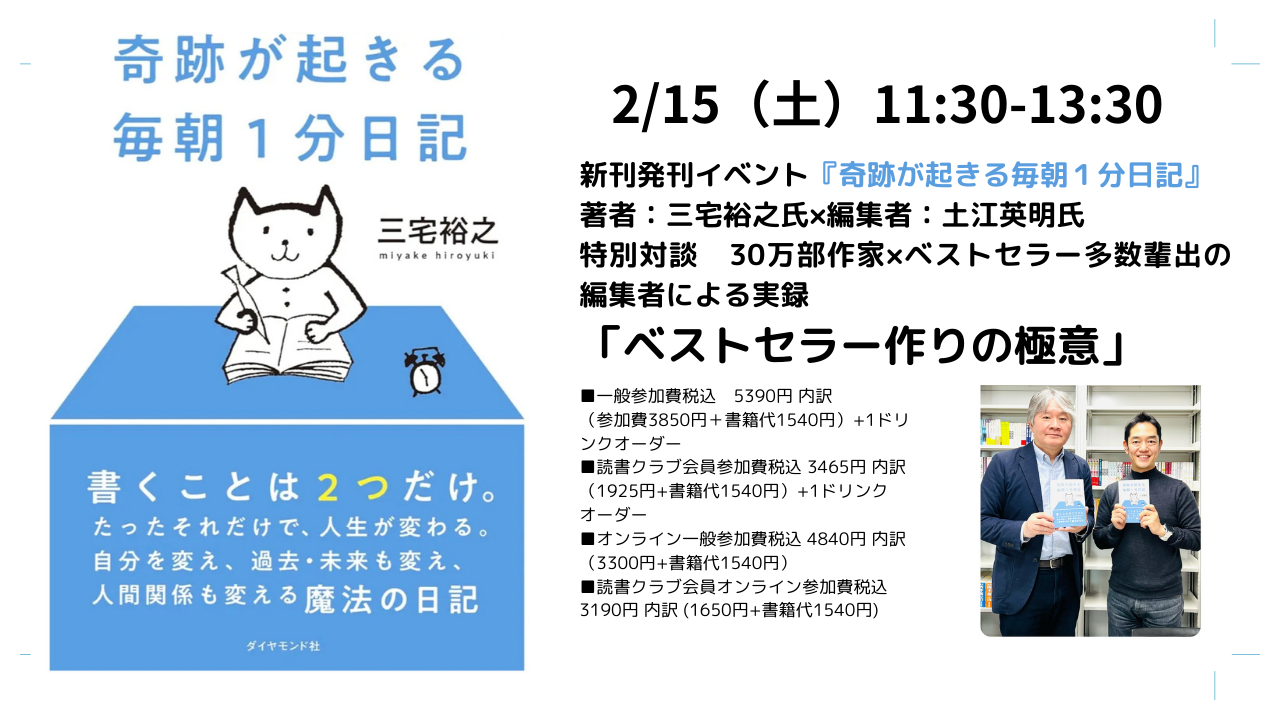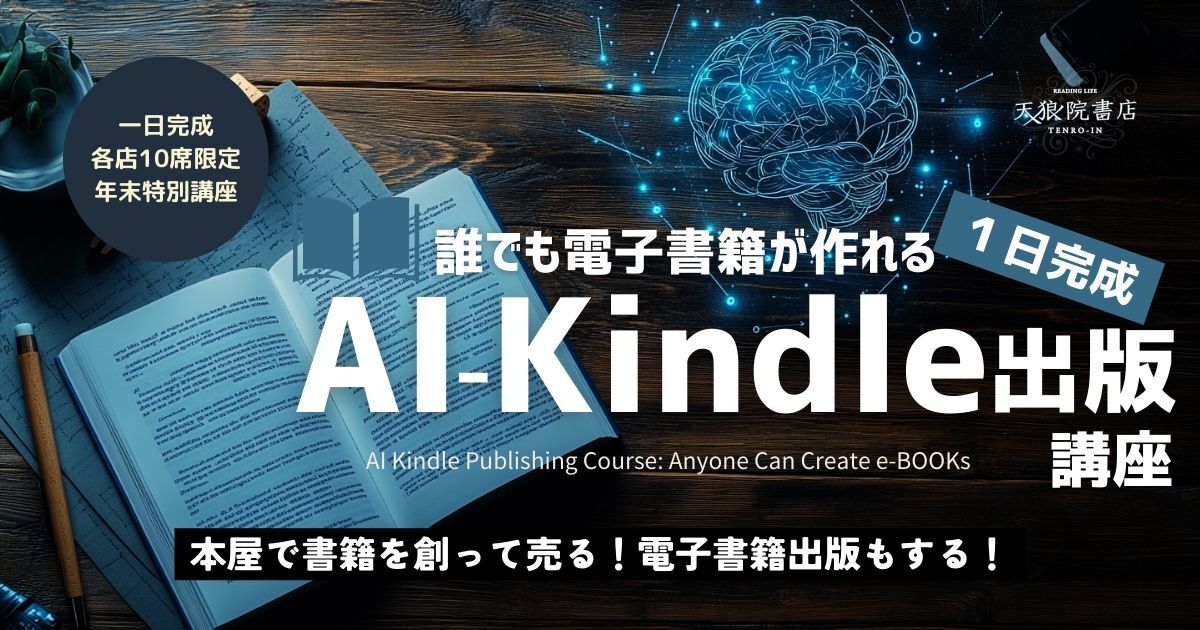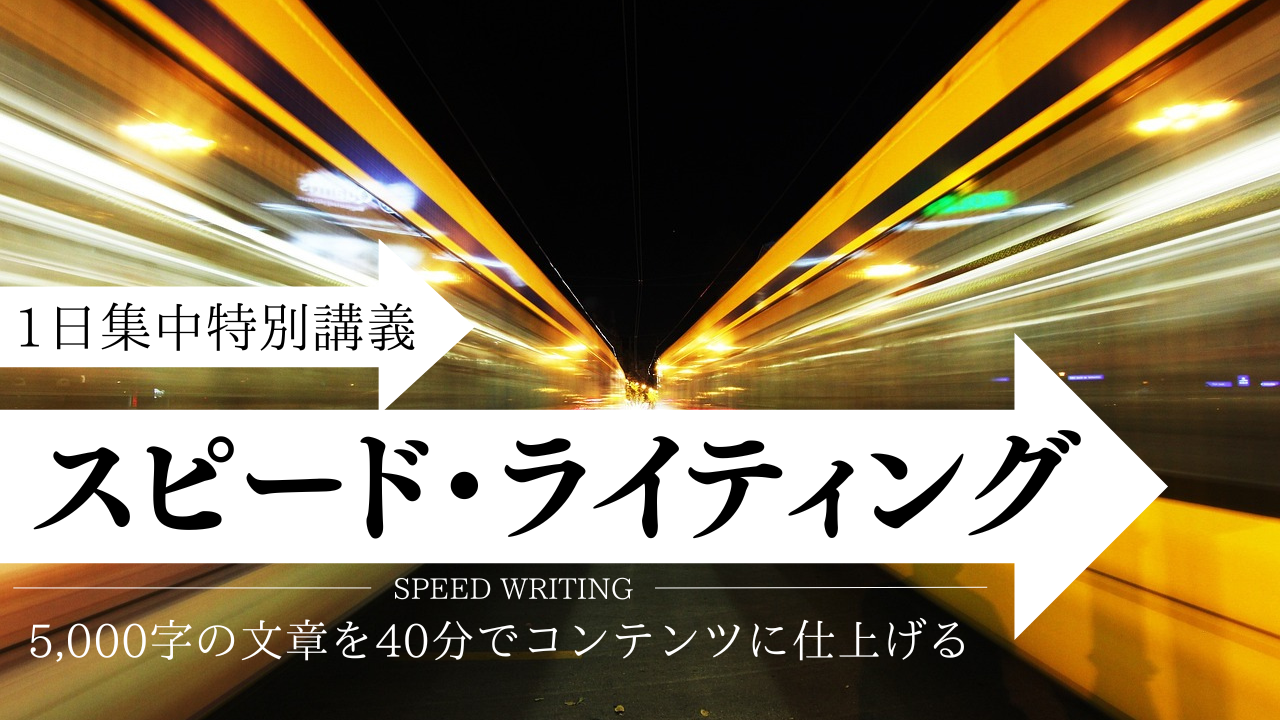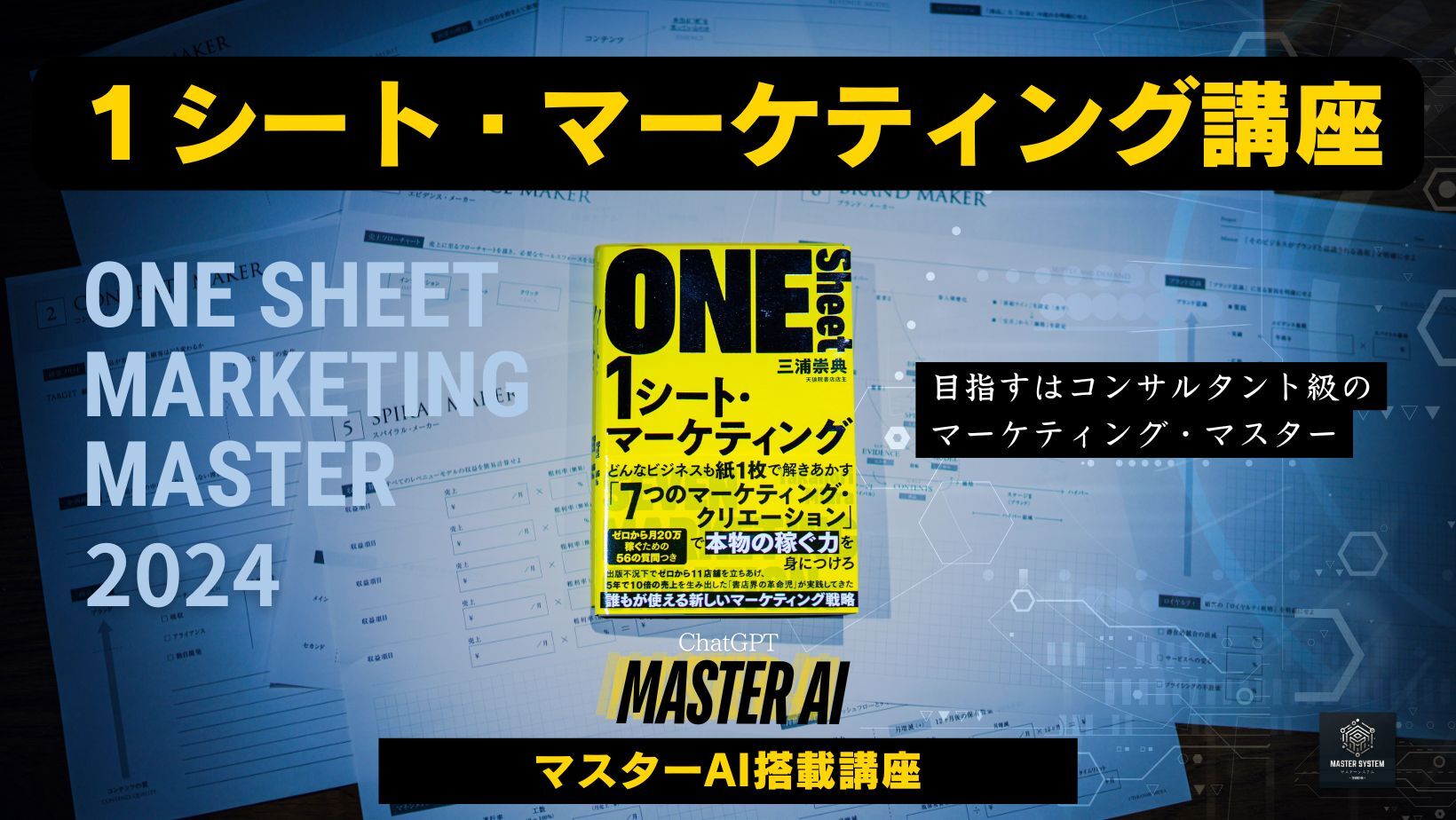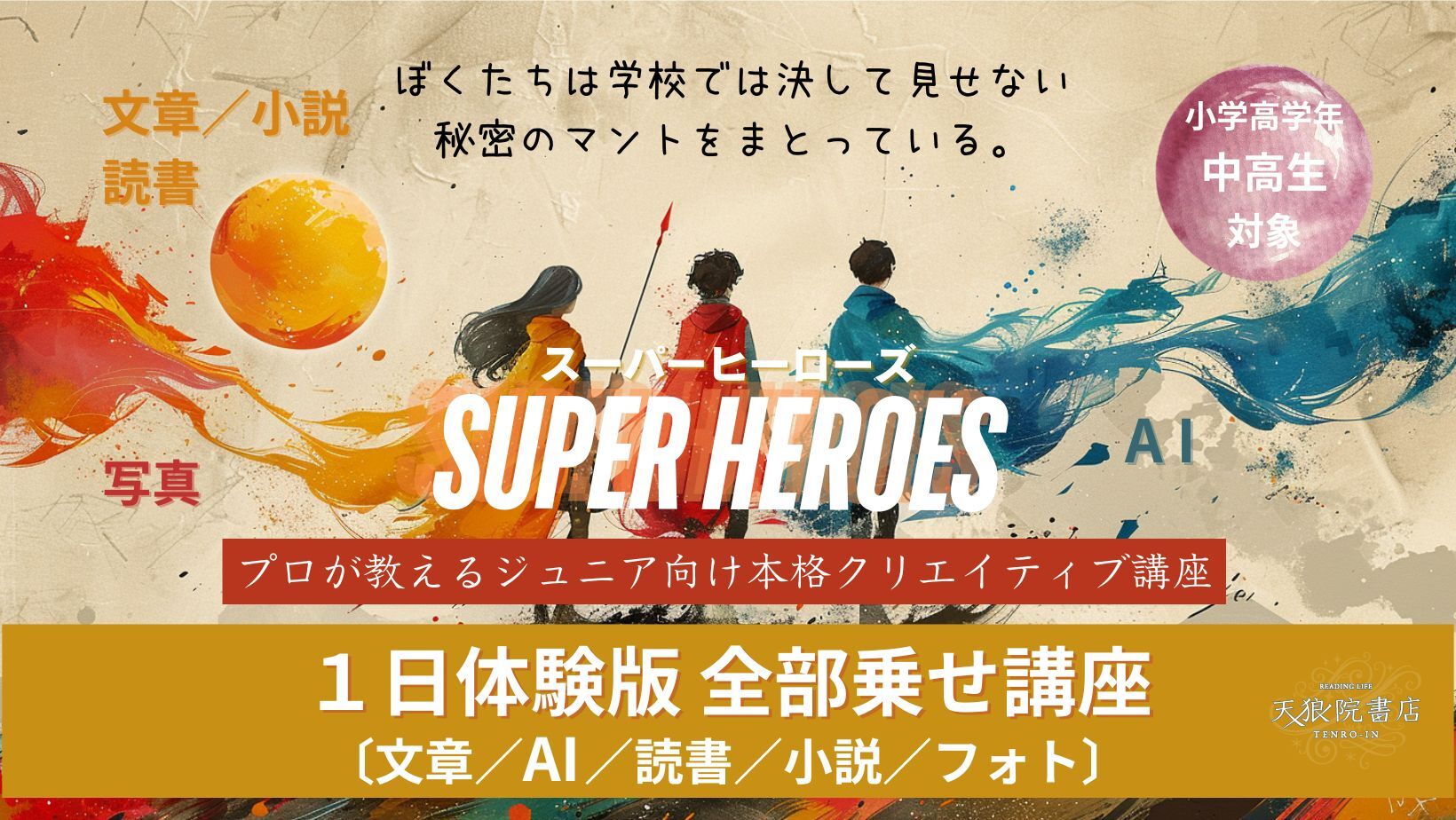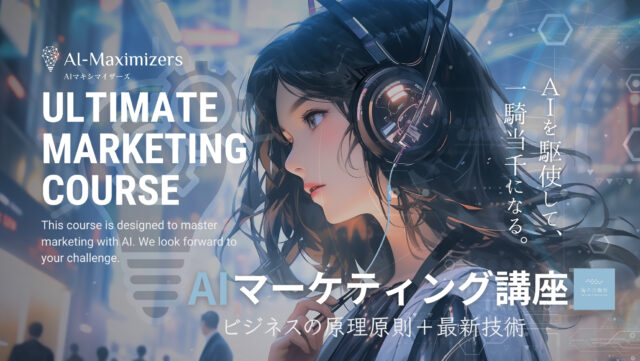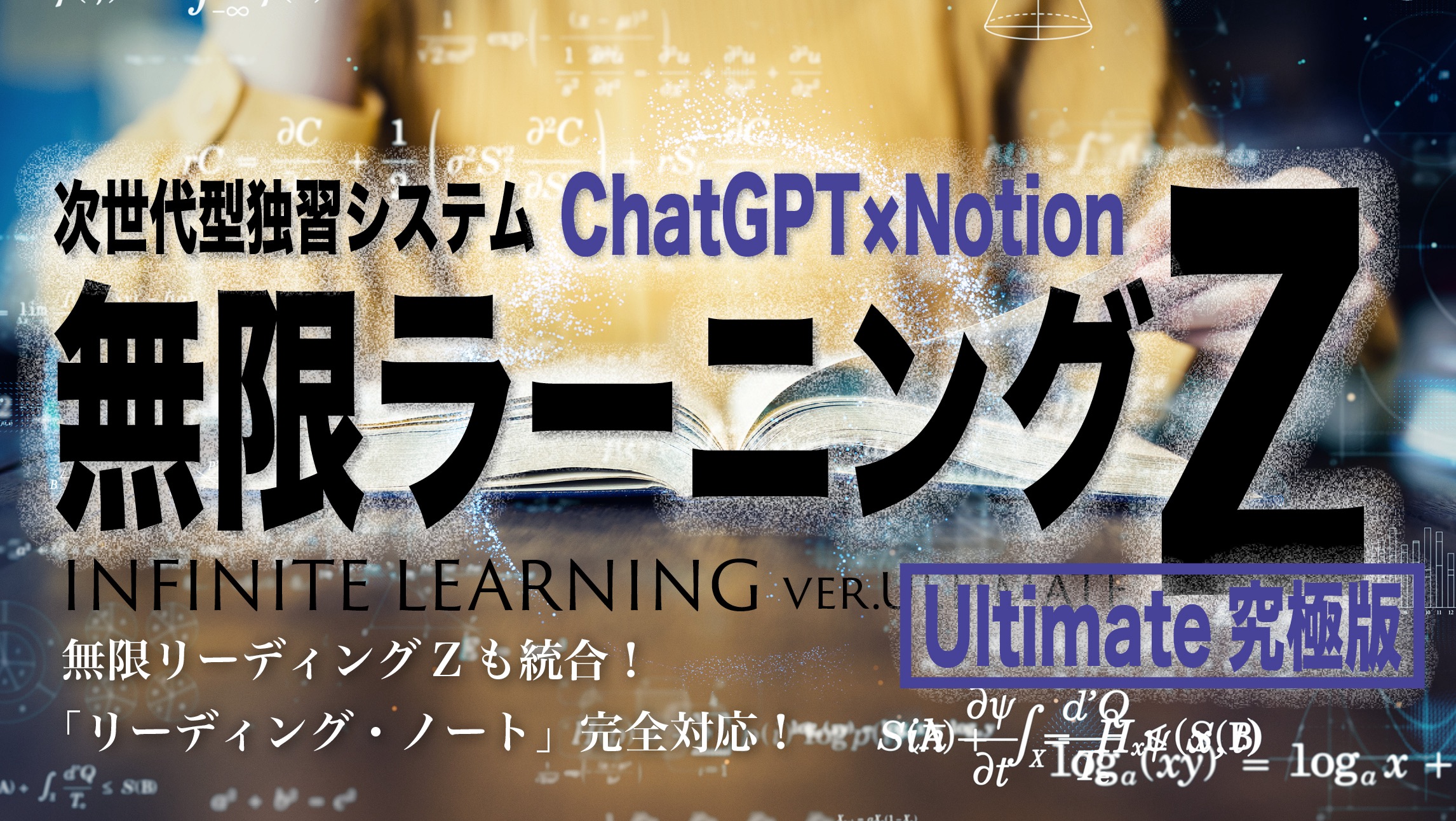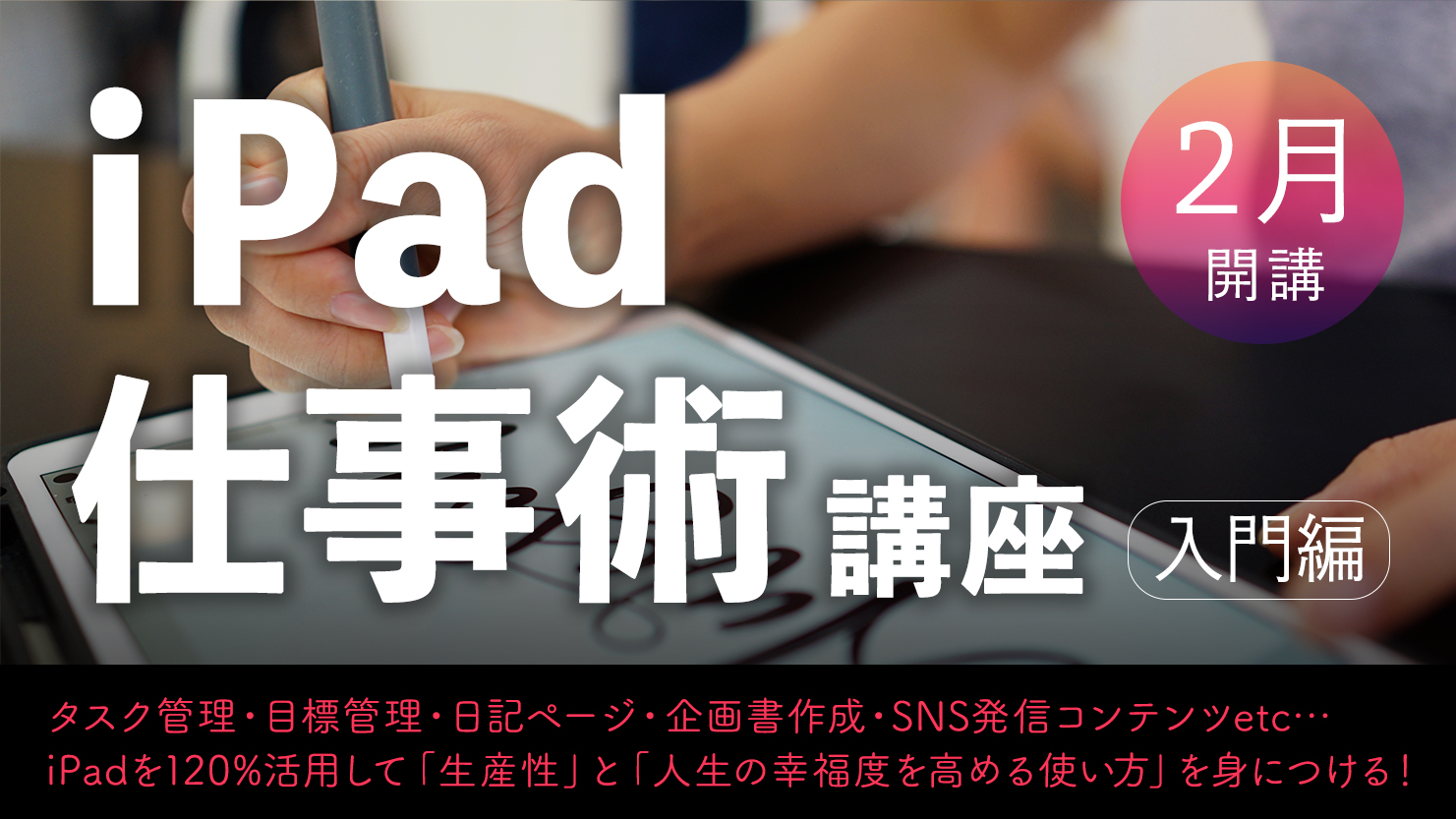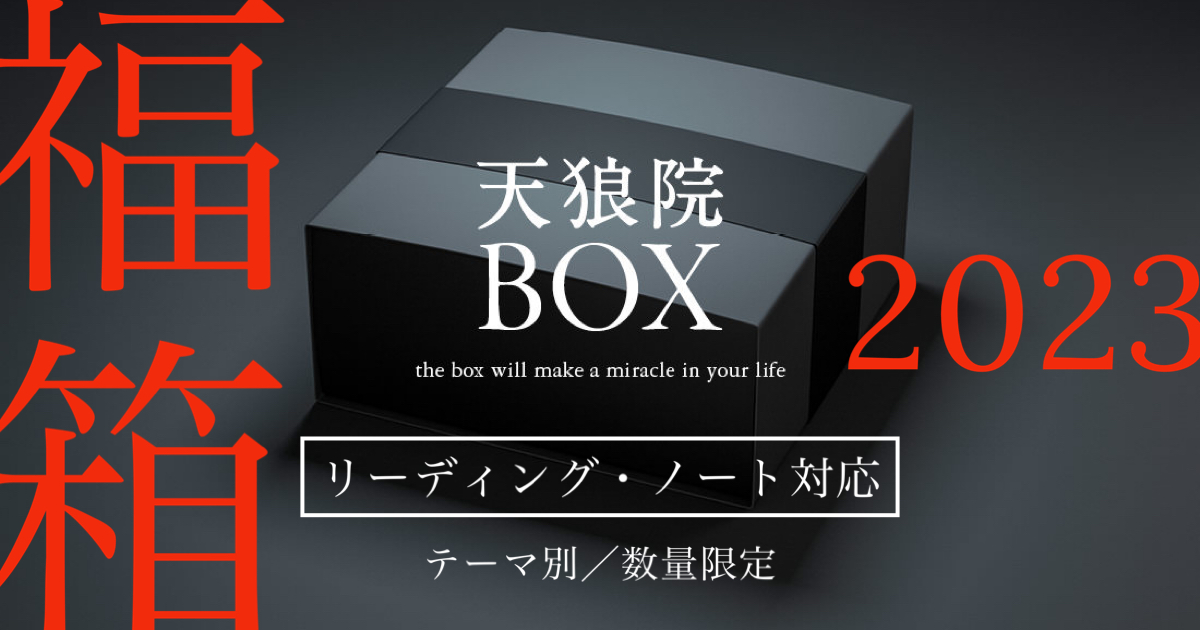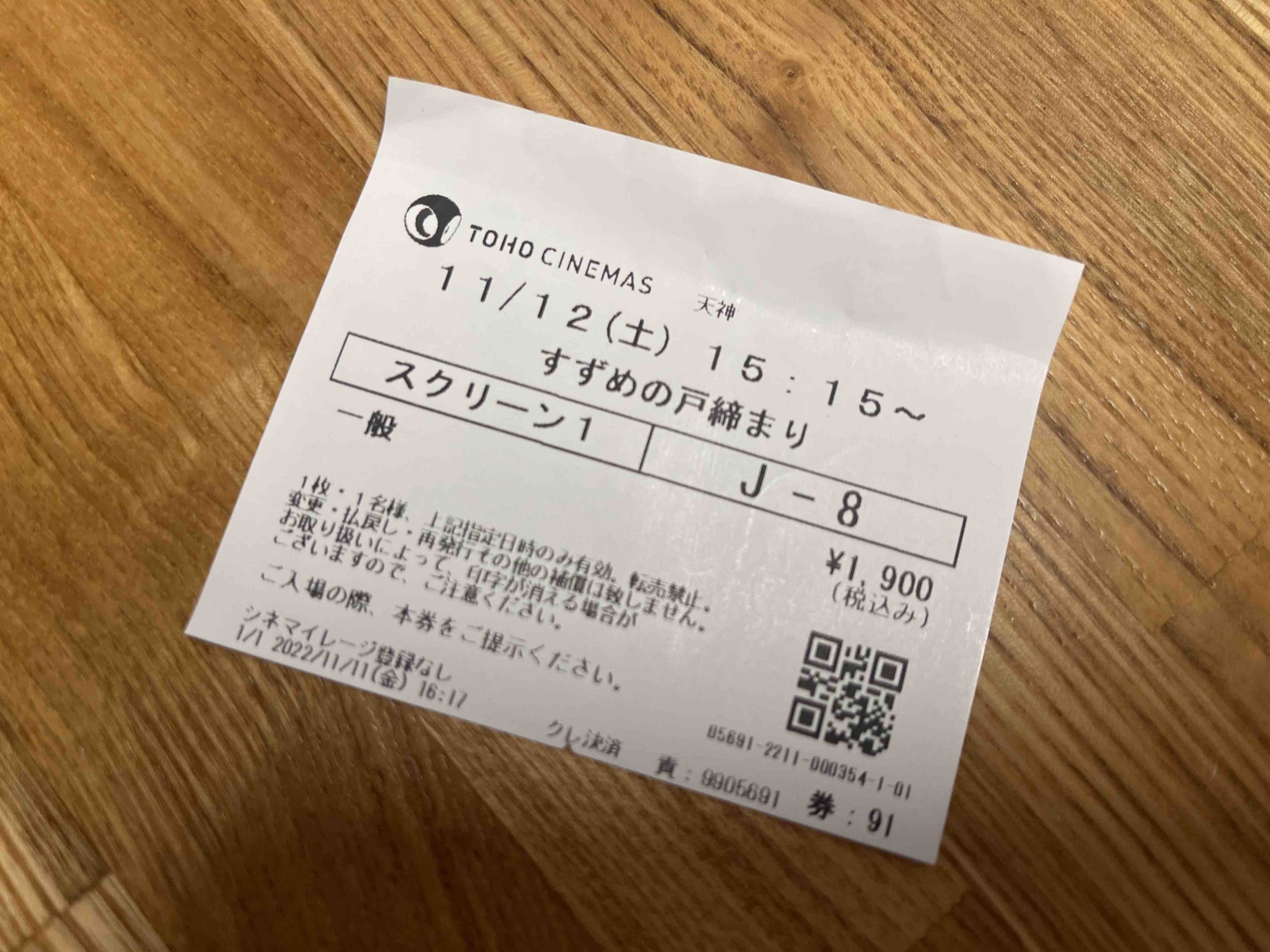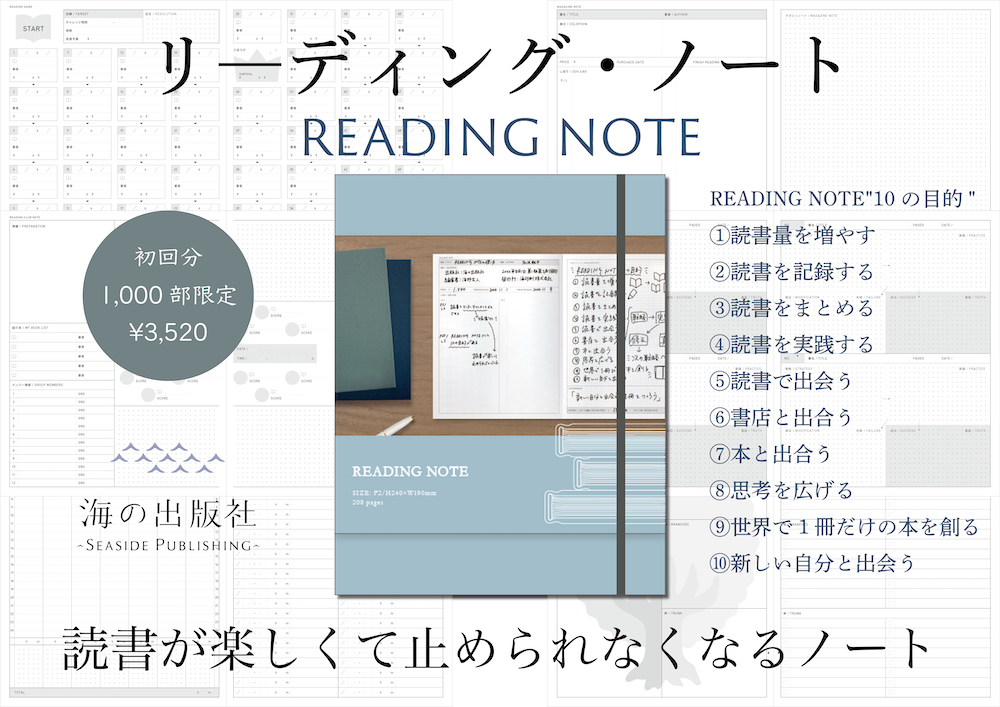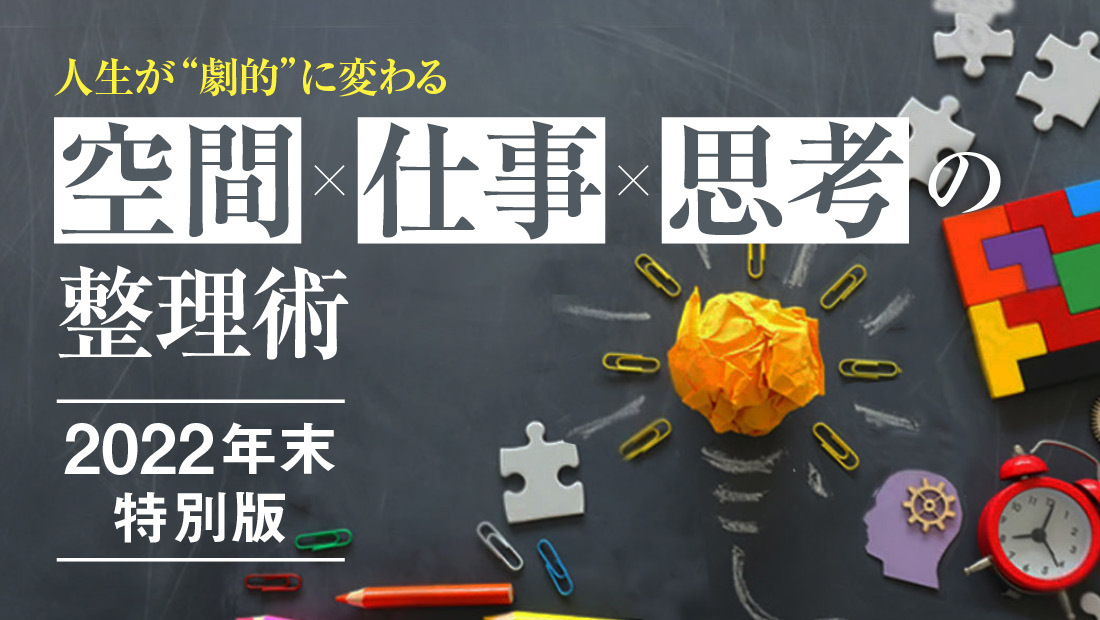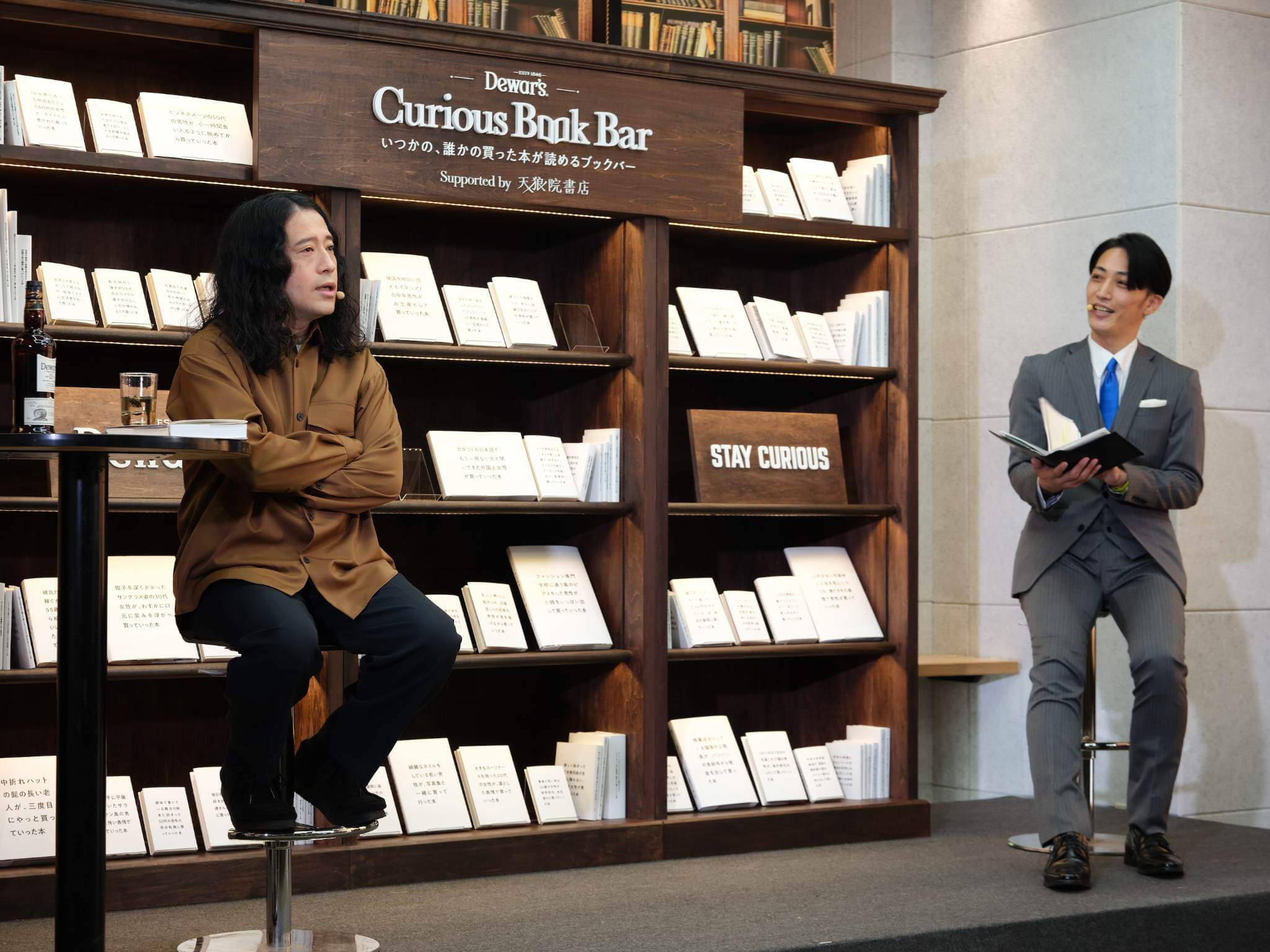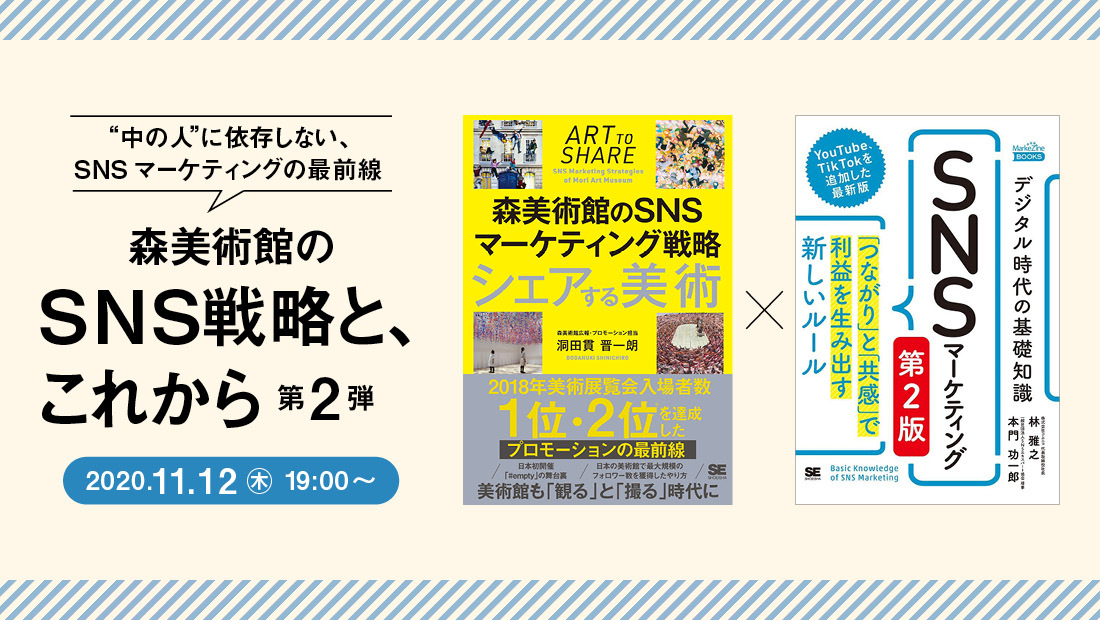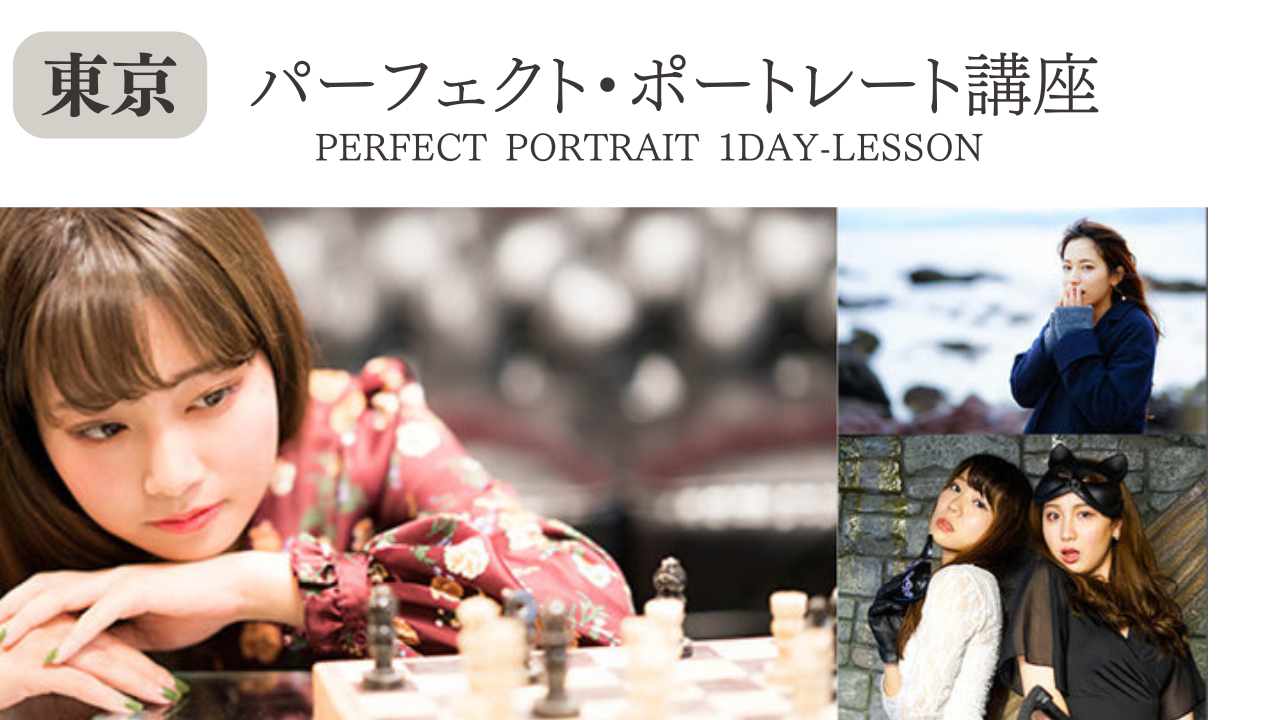書くことを盲信していた私が生まれてはじめて「書きたくない」と思ったときのこと《川代ノート》

「書きたくない」と思ったのはうまれて初めてのことだったので、正直、戸惑っていた。
大学生の頃に文章の面白さに目覚めてからというもの、私には常に「書きたい」というモチベーションがあって、暇さえあれば書きたい、書くという作業だけを行って生きていけるならばどんなに幸せだろうと、そんな風に思っていた。
思えば、私は幼い頃から書くことが大好きだった。一人っ子のため、留守番をしていることが多かった私には、自然と一人であれこれ妄想する癖がついていた。自分の頭の中で勝手にキャラクターをつくり、それを動かして物語を考えた。絵を描くのも好きだったから、私の部屋の本棚には、どんどん自分で作ったオリジナルの絵本が溜まっていった。
幼い私が何よりも求めていたのは、スケッチブックだった。常に何かを書き、描いていなければ気が済まなくて、真っ白なスケッチブックがないとそわそわして落ち着かなかった。サンタさんが実在し、魔法を使えるものだと信じていた頃に頼んだクリスマスプレゼントは、「永遠にページがなくならないスケッチブック」だった。あいにく魔法が使えない私の親は途方に暮れて、結局質の良いサイズの大きなスケッチブックを用意してくれた。
だから、書くことに対する苦手意識があったことは、これまでの人生で一度もなかったのだ。中学に入学し、作文の課題が出てみんなが嫌だ嫌だとわめいているときも、どうしてそんなに嫌なのか理解できなかったし、みんなが3時間も5時間もかけて取り組む作文の課題を、私は30分程度で終わらせていた。私にとって文章を書くということは、何かを話すことよりもはるかに簡単なことだった。文章を書かずに何かを考えることの方がずっと難しく思えた。
進路に迷って途方に暮れていた頃、文章を書く道を見つけた。ああ、これなら戦える、と私は思った。書くということは私にとって、唯一自信を持てる部分だったからだ。「私にはこれができます」と胸をはって言えるものは何もないけど、それでも、書くことでなら、私は役に立てるかもしれないと思った。
書くことは、私にとって、救いだった。だから迷うことなく、その道に飛び込んだ。
そう信じきっていたからかもしれない。自分が「書きたくない」と思っているという事実が、信じられなかった。
キーボードを前にすれば、勝手に動きだすはずの手が、全然動かなかった。何も反応しなかった。脳がフリーズして、ぼんやりとして、眠くなってくる。
私の中には常に「書きたいこと」のストックがあって、自分がキーボードを打つスピードがそれを追い抜けないのが歯がゆいくらいだと思っていたのに、ふとパソコンを目の前にしても、何も書けなかった。何も書きたいことが思い浮かばなかった。
私は冷や汗をかいた。何が。何がおかしい? どうしてこんなことが起こった? よくわからなかった。寒気がした。大事な何かを抜かれてしまったような気さえした。私の中にある、とても大事な何かが、失われている。どこかに行ってしまった。どうして?
書きたくない、と私は思った。そう思ったのは産まれて初めてのことだった。「書きたくない」私は口にした。「書きたくない。書きたくない、書きたくない、書きたくない」
そう呟くと、指の先の力が抜けて、まるで金縛りにあったように、動けなくなった。自分が自分でなくなったみたいだった。書きたくなかった。本当に書きたくなかった。何も書けないし、何も表現したくないし、表現したいものも存在しない。私の中には、何もない。
私は、誰かの役に立てる「何か」を今、胸の中に何も持てていないのだと、そのとき初めて、気がついた。
自分が空っぽになってしまったような気がした。苦しかった。それまで抱えていた苦しみが嘘のように、味わったことのない苦しみが襲ってきた。私はこれまで自分の悩みや苦しみを文章にしてきたから、新しい悩みがやってくるたびに「これでネタが増える」と喜んでいたけれど、今回の悩みはそんなものじゃなかった。生半可な苦しみではなかった。心の奥底から湧いてくる、本当の苦しみであり、孤独だった。「ネタなんか一切いらない、だから誰か、頼むから、この苦しみを消してくれ」と心の底から思った。
逃げたかった。この場から逃げ出したかった。川代紗生ではない別の何者かになりたかった。川代紗生でいることをやめてしまいたいとすら思った。
もう誰も自分のことを知らないどこかに行ってしまいたい。倒れて病院に運ばれて、1ヶ月くらい気を失っていたい。何も見たくないし、何も聞きたくない。何も考えたくない。
ただただ無気力な時間を過ごしたかった。でももちろんそんなことはできなかった。生きていかなければならない。ここで逃げ出すわけにはいかない。
私は自分のことを買い被っていたのかもしれない、と私は思った。所詮私はそこまでの人間ではなかったのだ。あくまでも私はもともと想定していた通りのクズだった。優秀で、みんなに認めてもらえるようなかっこいい大人になんて到底なりきれていなかった。才能も実力もない、何も持たないクズだった。
気持ちが悪いと思った。今の状況が気持ち悪い。自分の実力と、掲げている理想とのギャップに吐き気がしそうだった。
自分が自分であるということがこれほど嫌だと思ったことは、あれがはじめてだった。本気で嫌だったのだ。
期待を裏切ってしまうのが怖かった。嫌だった。
みんなに嫌われるのが嫌だった。
私の周りにいる全員が敵のように思えた。にこやかに話しかけてくる人。気遣ってくれる人。私を助けてくれる人。周りにいる人間みんなが何を考えているんだろうと常に疑った。私に優しくしてくる人は、私への憎しみを隠すためのように思えたし、私を助けてくれる人は、私のことをひどく頼りない存在だと思っているのだろうと想像した。私の味方になってくれる人なんてこの世のどこにも存在しないんじゃないかと思った。
苦しい時間が、しばらく続いた。変だな、と私は思った。そろそろ回復してもよさそうなものなのに。
私はときたま唐突に落ち込んでしまうことがあったりするけれど、それは大抵1日もあればおさまっていた。しばらく寝たり、気の置けない友人と話をしたりして、放っておけばすぐに治った。今回もたまにくるいつものやつだろうと、タカをくくっていた。それなのに。
なのに、そのときの私は、苦しい期間が1ヶ月くらい続いていた。おかしい、と私は思った。本当に苦しかったのだ。文章を書くのが楽しくないということが、これほど苦しいものなのかと思った。考えれば考えるほど思考は暗く、ネガティブになっていった。いくらやっても結果の出ない自分。何をやっても無能な自分。書く書くと言っておきながらちっとも書き進められない自分の根性のなさにも、自分のクズっぷりにも嫌気がさしていた。
「自分として生きる」ということに、疲れ切ってしまっていたのかもしれない。
とにかく、私はそのとき、「川代紗生」としての能力値に、限界を感じていた。このままではいけないと思った。朝起きるのが嫌だった。起きたくないと思った。夜は永遠に夜更かしをしていたいと思った。深夜、誰も起きていない時間が恋しく、1日が早く過ぎることだけを常に祈りながら生きていた。朝が来るのが怖かった。誰も永遠に目覚めないでほしいと思いながら常に生きていた。
もっと器用に生きられたらよかった。もっと自由に生きられたらよかった。もっと楽しく、もっと周りの目なんか気にしないで、楽しいことばかり考えて生きていられたらよかった。どうして自分には、みんなが当然のようにできていることができていないんだろうと思った。気持ちが悪かった。自分と周りとのギャップに吐き気がした。
次の日、目覚めたとき、自分が自分じゃなくなっていたら、どんなに幸せだろうと思いながら眠りについた。
そんな日々が、1ヶ月近く続いていた。先は見えなかった。相変わらず書きたいという欲求は湧いてこなかった。
そうしているとき、ふと、こう言った人がいた。
「さきは、何のために書くの?」
三浦さんだった。
「さきと、僕の違いは、書くためのヴィジョンが明確であるかどうか、これだけなんじゃないかな」
何のために、書くのか。
はっとした。
私は、何のために、文章を書きたいと思ってきたんだろうか。
思えば、私は文章を書きたい理由など、考えたことが一度もなかった。だって、私が「書きたい」と思うことは当たり前のことだったからだ。それは、「どうして寝るのか」「どうして食べるのか」と聞かれているのと同じことだった。「どうして生きるのか」と聞かれているのと、同じことだった。
「どんな風に書くかというのは、どんな風に生きるかというのとだいたい同じだ」と、村上春樹が何かの本で書いていたことを思い出した。本当にそうだな、と私は思った。私にとって書くこととは、生きることだった。書かずにいる人生など、死ぬことに等しかった。
そうか、だからか。
だから、私は、書かずにいると、死んだような気がしてしまっていたのだ。
その1ヶ月間、私は全く書くことをしなかった。書きたいと思わなかった。それはつまり、生きたいと思わなかったということと、だいたい同じじゃないのか?
生きたい、と私は思った。生きたい。私は生きたい。生きたいから書く。生きるために、私は書く。
書かないのならば、死んでいるのと、同じ。
「さきは、どうして書くの? 何のために書くの?」
三浦さんの言葉が、なんども頭の中で繰り返された。
そして、その言葉は、私の脳みその中で、こう変換されていた。
「さきは、どうして生きるの? 何のために生きるの?」
つまり、私は、生きる理由を、考えてこなかった、ということになる。
私にとって、書くことは当たり前で、生きることは当たり前で、それについて、問いただしたことなど、これまでになかったのだ。だからこそ、ふとこうして、路頭に迷っている。
私は自分のことを、もっと知るべきなのかもしれない。
私は、以前もこんな風に、生きることについて、悩んだことがあったのを思い出した。就活をしていたときだ。自分が何をしたいのかがわからなくて、自分の進路が見えなくて、どんな大人になって、どんな死に方をすれば自分が満足できるのかが、わからなかった。理解できなかった。だから、苦しかった。そんなときに出会ったのが、天狼院であり、三浦さんだった。そして、私はそこで文章を書くということに出会った。「私は書くために生きる」、それがそのときの私が出した結論だった。
二度目だ、と私は思った。
私は、人生で二度目の決断のときに出くわしていることになる。
これからどう生きていくかということを、考える時期に、直面しているのだ。
この、25歳になる節目の歳に。
私は、なぜ書きたいのだろうか。
何をするために書きたいのだろうか。
何を成し遂げたいと思っているのだろうか。
深く、奥深くまで掘り下げて、私は考えた。考えて考えて考えた。
そして、こう思った。
私は、認めることができる人間になりたい、と。
私は、人を愛するために、誰かを認めるために、肯定するために、文章を書きたい。
包んで、愛して、そのままでいいよと言ってあげられるような、そんな文章を書き続けるために、私は生きていきたいと思った。
思えば、私はこれまでの人生でずっと、ずっとずっとずっと、愛されることばかり考えて生きてきた。
好きになってほしい。
認めてほしい。
愛してほしい。
大切にされたい。
承認してほしい。
異常なほどの承認欲求に支配されて、ただ、周りを幸せにすることではなく、自分が幸せになる道ばかりを探していた。
でも、これまで文章を書いてきて、ずっと愛されたいという感情と戦ってきて、そして、ようやく見えてきたものは。
どれだけ愛されても、愛されても、私は本当に幸せになることなど、できないということだった。
認められたいという気持ちを増幅されて、もっともっとと、どんどん欲深くなっていく。気持ちが強くなっていく。
私はきっと、これは欲求不満であって、この承認欲求が満たされさえすれば、私は幸せになれるのだろうと、そう思っていた。
思っていたけれど、違った。
私は、与えることでしか、幸せになることはできない。
本当に満たされたいと思うのであれば、私は、愛される方法を考えるのではなくて、誰かを愛する方法を考えなければ、いつまでたっても、この状況から抜け出すことはできない。
なぜなら、いくら認められ、尊敬され、すごいと言われたところで、自分に返ってくるものは、何もないからだ。
承認欲求とは、そこで行き止まりの感情であって、誰かを巻き込んでいくことなどできないからだ。
たとえ多くの人に認められたとしても、その先に生まれるものは、さらに深い承認欲求でしかない。
誰かを愛し、誰かの役に立つことができたと、本気で思えたときにこそ、私は満足することができるのだ。
自分じゃなく、別の誰かを幸せにしたいとか、役に立ちたいとか、そんな風に思えることは、どんなに幸せなことだろう。
自分なんか放っておいて、もっともっと幸せにしたい存在がいるということよりも、幸せなことが、この世の中にあるのだろうか。
きっと、そうやって、自分ではない誰かに「認めてもらう」ことではなく、自分ではない誰かを愛し、認めるために書くことこそ、私が目指すべきものではないのだろうか。
私は、与えることを学ぶために、文章を書くべきなのではないだろうか。
長い、長いトンネルを抜けて、ようやく、私はその結論に至った。
それを思いついたとき、私には、強い確信があった。
間違いない。
もしかしたら未来に、考えが変わるかもしれないけれど、おそらく、私が出したこの結論には、間違いはないだろう。
私は認められることではなく、誰かを認める人生を歩むために、これから書いていくことになるのだと、そのときはっきりと、確信した。
そう気がついた途端、私には、書きたいことが、次から次へと浮かんできた。
湧き上がる感情が溢れて、止まらなかった。そうだ、私には、書きたいことがこんなにもあったのだ。
私は、やっぱり書くべき人間なのだと、そのとき心の底から思い、そして、幸せとはおそらくこういうところからはじまるのだろうと、心の中でひとり、つぶやいた。
***
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/zemi/38451
夏の特別イベント開催予定!
http://tenro-in.com/event/39357
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」2017.1.27 OPEN
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】
天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。