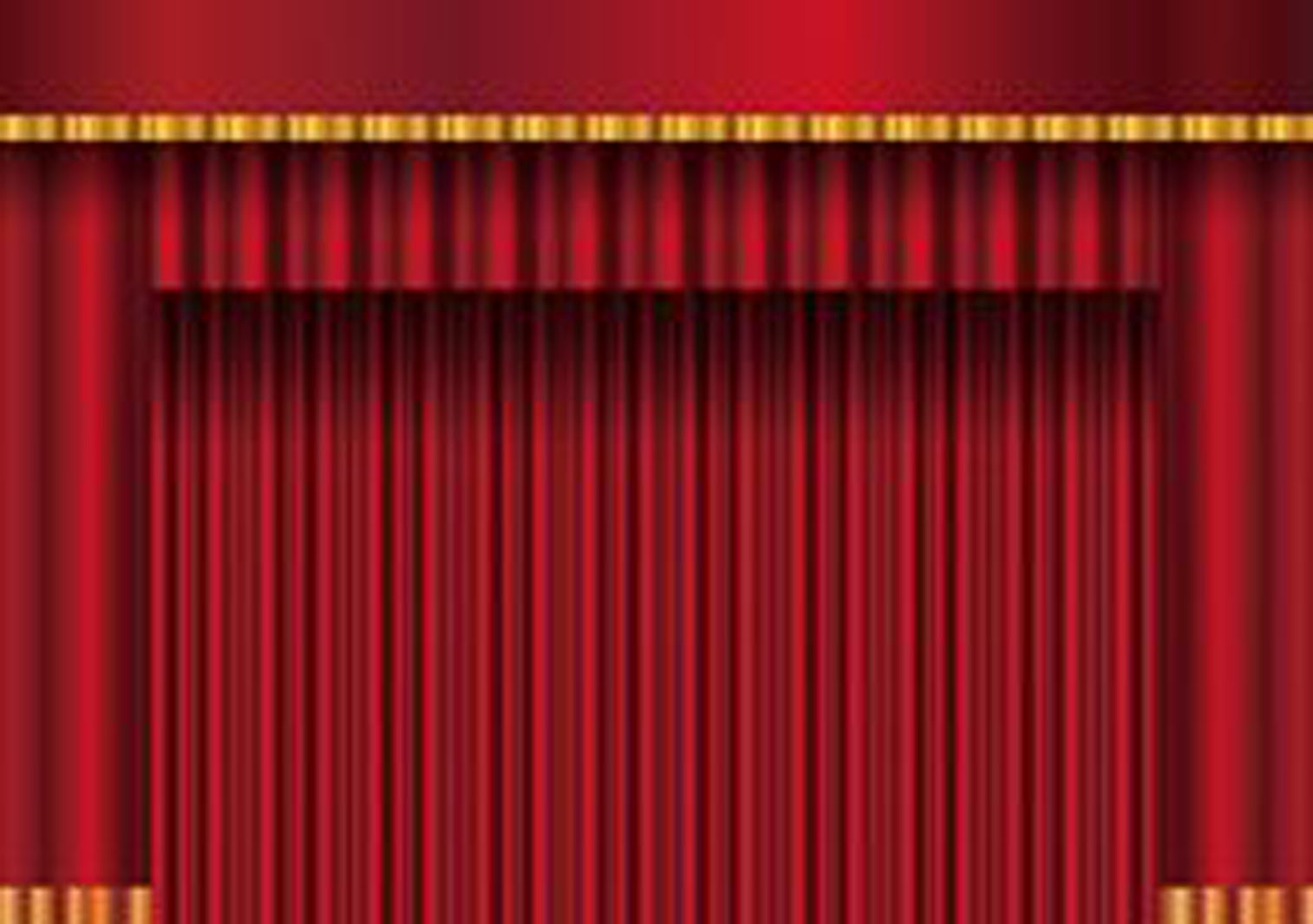十八歳の処女だったわたしが同い年の男子に授乳していた日々について。《プロフェッショナル・ゼミ》

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【お申し込み受付中!】ライティング・ゼミについてはこちら→ http://tenro-in.com/writing-20190802-4/
記事:安達美和(ライティング・プロ)
わたしは未婚の三十一歳だ。結婚の予定もなければ、妊娠の予定もない。子どももいない。
しかし、十八歳の終わりからから二十歳の直前までの一年間、授乳していた体験がある。まだ処女だったくせに。しかも相手は同い年の男子だった。ちなみに彼は恋人ではない。
あまりにおかしな体験だから、未だに、あれは夢だったのかなぁと思うことがある。でも、
むき出しの肩の一部に西日が当たって、うぶ毛がオレンジがかった金色に染まっている様子も、彼が玉の汗をかきながらひどく神妙に乳房に吸い付いていた様子も、よく覚えている。
お相手は柿田君といった。彼は他校の演劇部に所属していたが、顧問の先生の意向で高校演劇連盟には加盟していなかったから、大会に出ることはなかった。それでも、地区大会や演劇祭はよく見にきてくれていて、彼の存在を知る人間は多かった。
柿田君は背が高くて目立った。クリンクリンで真っ黒の天然パーマに、瞬きの少ない大きな目をしていた。初めて彼を見た時、わたしは自分の舞台を終えて、楽屋へ戻るところだった。目が合うと、彼は深々と頭を下げた。なぜかつられて、わたしも同じようにした。
大学へ進学したわたしは、ある映画サークルに入った。新入生歓迎会で、おやと思った。少し離れたところに柿田君が座っていた。目が合うと、彼はまた深々とお辞儀した。なので、わたしもそうした。
わたし達はサークル仲間として言葉を交わすようになった。
柿田君がラブレターをくれたのは初めてふたりきりで会った時だった。全くそんな素振りがなかったので、内心面食らった。あまりの分厚さに小説かと思うほどのボリュームあるラブレターだった。そこには、初めてわたしを見たのが舞台で少年役を演じている姿だったことや、最初は本当に男子だと思ったということ、ちっとも美人じゃないのに好きだということが、どんぐりみたいな字で綴られていた。ちなみに、「ちっとも美人じゃないのに」というフレーズは合計で七回も出てきて、なぜラブレターでこんなにへこまされないといけないのだろうか、と暗い気分になった。
それでも、初めて人から好意を寄せられたことは嬉しくて、何度もそのラブレターを読み返してしまった。しかし、何度目かそれを読んだ時、明らかに違和感を感じる数行があることに気づいた。それはラブレターの終盤近くに出てきた文章で、彼がわたしと恋人になれたら、こんなことをしてみたいと綴った箇所だった。正確に言うと、それは「こんなことをしてみたい」ではなく、「こんなことをしてほしい」だったが。
もし付き合うことができたら、キミにお願いしたいことがあるんだ、と彼は綴った。
僕の髪を洗ってほしいんだ。
やさしく爪を切ってほしいんだ。
ゆっくり服を着させてほしいんだ。
よく意味が分からなかった。わたしが今読まされているものは一体何だろうと、他人事のように思った。
しかし、悲しいことにモテた試しがなかったので、「普通のラブレター」というものが一体どんなものなのか、何が書いてあれば正常で、何が書いてあれば異常なのか分からなかった。
ただ、なんだか変だな、という気持ちだけが残った。
君の作った味噌汁が飲みたいんだ、みたいなノリかなぁと思ったが、それとも違う気がした。
次に彼と会った時、わたしはラブレターのお礼とお付き合いは辞退したい旨を伝えた。もちろん、好いてもらえたのは嬉しかったけど、この人頭がどうかしてるなと思ったのも事実だった。
友達にならない? と提案してみた。恋人としてはイヤだけど、友達としてなら抜群に面白そうだったから。すると意外なことに彼は、分かった、とすぐに返事をしてくれた。「まずは友達になろう」と、少し言葉は変えたけれど。
「じゃあ、友達としてキミにお願いがあるんだ」
「え、なに。わたしができることなら」
彼はひどく真面目な顔で、わたしの目を見てキッパリとこう言い放った。
「おっぱいを吸わせてくれないか」
とりあえず殴った。こんなにためらいなく人を殴れるものかと驚いた。
「痛いじゃないか」
「ごめん。でも、今のは柿田君が悪いよ」
「要求はハッキリ伝えた方が誤解がないから」
「え、だって、わたし達は友達になるんでしょ? そういうことは友達同士でするもんじゃないよね?」
「誰がそんなこと言ったんだ」
はて、改めて聞かれると誰がそんなことを言ったんだろう。分からない。
一瞬考え込んだわたしを見て、柿田君は「勝機アリ」と睨んだようだった。
わたしは全くもって幼かった。見た目が幼いだけではなく、性的な知識も経験もほぼないと言って良かった。というのも、わたしには性知識にまつわるあるトラウマがあるからで、そのことを思い出すだけで顔から火を噴きそうになる。
小学校五年生の時だったと思う。
放課後、クラスメイトの悠里ちゃんにおそるおそるこう聞かれた。
「ねえ、美和ちゃん。コンドームって何に使うものなの?」
学校では、初めての性教育を受けたばかりで、授業後、数名の女子が図書館で性教育にまつわる絵本を借りてきた様子だった。
その中に、「コンドーム」という言葉が出てきたらしい。しかし、その本にはコンドームの使い方は書いてあっても、なぜコンドームを使うのかその理由は分かるような分からないようなもごもごした記述しかなかった。
わたしはその時分から己の価値を「知識」だと思っていた節があった。だから、彼女からのこの真剣な問いに答えないわけにはいかなかった。
しかし、困った。何が困ったって、知らないのだ。コンドームってのは、一体、どうして使うものなんだ? 必死に考えた。
セックスとは、子供を作るための行為である。ならば、コンドームの使い道はただひとつだ。
わたしはなるべく賢く見えるように厳かな口調で悠里ちゃんにこう伝えた。
「コンドームっていうのはね、確実に赤ちゃんを作るためにあるんだよ」
悠里ちゃんは、謎が解けたと言わんばかりに顔をパッと輝かせ、そっか! やっぱり物知りだね! と、わたしが最も欲しかった言葉をくれた。
「じゃあ、みんな赤ちゃんが欲しくなったらコンドームを使うんだね!」
「そうだよ、悠里ちゃん」
「すごいね、コンドーム!」
「そう、コンドームはすごいんだよ、悠里ちゃん」
「わたしね、弟が欲しいの。今度お母さんにコンドームあげようかな」
「そうしなよ、悠里ちゃん」
その後、中学に入学してもう一度性教育の授業を受けた時には、心底、「ごめん、悠里ちゃん」と思ったものだ。
よりによって、正反対だったとは。そもそも、セックスに子作り以外の目的があるなんて夢にも思わなかったから、全くもってショックだった。そして、そのことをきっかけに、性知識というものはわたしにとって別の意味で恥ずかしいものになってしまった。自分の無知を思い知るはめになった出来事として。
そんな過去があるものだから、わたしは恋をすることはあっても、ありとあらゆる性知識を避けた。
それから、彼は非常にフランクにわたしの胸に触れるようになった。それまでも、わたしがボケると彼が必ずツッコんでくれたが、そのツッコミを入れる位置が徐々におかしくなっていった。今までは手の甲で肩の辺りをポンと叩いていたのが、徐々に下へ下がるようになってきたのだった。わたしの女性の自覚が希薄なせいか、あれ、おかしいなと思うまでにずいぶん時間がかかった。
そして、気がついた時には彼はまるで肩を叩くようにごく自然に、わたしの胸に触れるようになっていた。もう今さら怒ったところで、ポーズにしかならないと観念した。
サークル仲間とみんなで、柿田君のひとり暮らしの家で飲み会をしようという企画が持ち上がったのは秋も終わりの頃だ。大学からほど近い彼の狭いアパートはたまり場としてちょうど良く、終電を逃した友人の駆け込み寺のようにもなっていた。
男女八人でにぎやかに飲み会は始まり、夕方から夜中まで映画談義に花が咲いた。
そんな中、わたしはひとりだけ奇妙な緊張感に包まれていた。柿田君とは極力、近づかないように注意した。
ふたりになったら、絶対に吸われる。それだけは避けたい。
じゃあ飲み会自体出なければ良いのだが、その時は同学年の中で最もセンスの良い女子が初めて監督した映画を鑑賞することになっていて、どうしても参加したかった。映画の出来は素晴らしく、わたし達は彼女の果敢な挑戦を称えたり、こっそりコンプレックスを噛み締めたりと忙しかった。
わたしは、ほとんど話したことのないゆきちゃんという女子とピッタリくっついて飲んだ。普段、ひとりでいることの多いわたしのその振る舞いに、彼女は驚いているようだった。彼女とは帰る方面が一緒だった。
終電の二本前にゆっくり間に合うよう、わたし達は腰を上げた。アパートの廊下へ出てホッとしながら歩いていると、彼女がぽつんと言った。
「あだっちゃん」
「なに?」
アルコールでふやけたような表情でにへっと笑った。わたしもつられて笑った。可愛い子だなと思った。そして、彼女は吐いた。わたしの肩に。
「うわーっ! この、バカヤロー!」
わたしの罵声に驚いて、みんなが部屋からドヤドヤ出てきた。あーあ、と誰かが言った。またかよ、ゆきちゃん~。
柿田君の部屋へUターンしたわたしは、とりあえず服を脱いでお風呂を貸してもらった。わたしの肩に吐いたゆきちゃんは仲間に介抱されながら無事に終電で帰った。お風呂場には、彼が普段使っているであろう鮮やかなブルーの男性用シャンプーがあった。ひげ剃りも。
お風呂から上がると、仕方なく飲み会の輪に再度加わった。貸してもらった柿田君のTシャツは大きすぎてスースーと全く心許なく、しかも柄は古いドラキュラ映画のワンシーンを切り取ったもので、美女がドラキュラに噛み付かれているという不安なものだった。
朝まで決して眠ってはいけないと気を引き締めた。
どれくらい経ったろうか。ふっと目が覚めると、誰もいなかった
身を硬くしていたのが災いして寝こけてしまったらしい。間抜けすぎる。ぼんやりと濁った視界に、黒い頭のようなものが見えた。鎖骨の下辺りがもぞもぞする。
ドラキュラのTシャツをたくしあげて、彼がわたしの乳を吸っていた。
上から見ると、両手に持ったおまんじゅうのひとつにかぶりついているように見えた。三時のおやつのような、のんびりした間抜けな光景。
彼と目線が合った。柿田君は、おはよう、と真顔で言った。とりあえず、頭を一発ゴンと殴った。でも、想像していたよりもイヤではなかった。
それから、わたしと柿田君の奇妙な関係が始まった。わたしは元々の性格が生真面目なせいか、一度目は受け入れたものを二度目に拒むのも矛盾していると思ったから、柿田君に自分の鎖骨の辺りをトントンと叩かれると、素直に身体を差し出すようになった。
柿田君は今日は大きいとか今日は小さいとか勝手なことを言いながら、乳を吸っていた。
夏のある時など、クーラーだとかえって身体を冷やすからという彼の妙な気遣いによって、うだるような暑さの中、扇風機だけを付けていた。風は届いたが涼しくもなんともなかった。
わたしも彼も玉の汗をかいていた。額と言わず、肩と言わず、胸と言わず。鼻の頭に汗をかいて、柿田君はもくもくとわたしの乳を吸っていた。窓に夏の濃い緑が映っていた。バカみたいだった。
鏡にちらと映る自分たちの様子を見て、こりゃ犯罪だなぁ、とふと思ったことがある。
その実、わたし達ふたりは十九歳同士だったが、柿田君は老け顔でティーンエイジャーなのに三十歳くらいに見えたし、わたしはと言えば大学四年生の時に小学生に間違われるほど子供っぽい顔をしていた。本来であれば千円徴収されるはずの電車の特急料金を、五百円しか取られなかった衝撃は忘れることができない。
だから、柿田君がわたしの胸に吸い付いている様は、良い年をした大人の男が小学生にいたずらをしているように見えたのだ。
ある日、いつものようにわたしの鎖骨を叩いた柿田君が、行為の最中に、おなか減ったなとつぶやいたことがある。わたしはそれを聞くとなぜか申し訳ない気持ちになって、神妙な顔をしている柿田君に呼びかけた。
「ごめんね、何も出なくて」
「え、何が?」
「おなか減ったんでしょ。吸ってても出ないからさ、母乳」
「出るわけないでしょ、ていうか出たらそれこそおかしいでしょ」
「まぁ、そうなんだけど。なんだか、申し訳ないと思ってね」
そう言うと、彼は一度胸から顔を離して真顔でまっすぐ抱きしめてきた。いつものようなふざけた調子はみじんもなく、ただ、しっかりと背中へ腕を回してきた。
乳を吸われている時より、抱きしめられた時の方がはるかに恥ずかしかったのは我ながら変だと思う。
不思議なことだが、柿田君は乳を吸うばかりで、それ以外のことは絶対にしなかった。彼はわたしを好きだと言う割には他の女の子とも付き合っていて、そちらの彼女とはしっかりと身体を結んでいるようだった。
「だってオレ、おっぱいを吸わせてくれないかとは言ったけど、セックスしようよとは言わなかったから」
友達だからね、約束は守るよと真剣な目で言った。
なるほど、彼はちょっと頭がおかしいけれど、律儀な男なのだなと思った。
「柿田君は意外と紳士なのかもしれないね」
「そうでしょ? あとね、勃たないの、キミといても」
「……なんか、それショックだな」
「結婚しようか」
「どんな流れだよ」
そんなやりとりをよくした。
彼はよくわたしに、結婚しよう、と言った。いえ、間に合ってます、とわたしは返した。その掛け合いは日常になっていた。
しかし、ある時彼はふと、家族になりたいんだ、といういつもとは違う言葉を使った。
そう言われた時、いつもとは違う何かを感じた。あの疑似授乳行為のことがふっと頭をかすめた。
家族になりたいって……
ああ、そういうことか。
彼は確かに、わたしと家族になりたいと言った。
でもそれは、わたしを妻にしたいという意味ではないのだ。
柿田君はわたしを、自分の母親にしたかったのだ。
そう考えると、あのラブレターの妙な三行にも合点がいった。
僕の髪を洗ってほしいんだ。
やさしく爪を切ってほしいんだ。
ゆっくり服を着させてほしいんだ。
キミに甘えたいと、オレの母親になってくれと、彼は最初からハッキリとわたしに告げていたのだ。
どうして、と思った。何も知らない、むしろかなり幼い同い年の女に、なぜそんな無茶な要求を。「母親」という言葉の持つあまりの重さにめまいがした。
「わしゃまだ処女やっちゅーねん」
思わず茶化してつぶやいた。
無理だよ、柿田君。
わたしは困り果てた。何をどうあがいたって、わたしは君の母親にはなれないよ。埋められないよ。もし仮に、わたしが本当に君の恋人だとしても、それは無理だよ。
彼がわたしに求めているものの正体が分かってしまってから、急にこころが離れていくのを感じた。自分の中に眠る母性の底の浅さも、知ったような気がした。
ほどなくして、わたしには恋人ができた。
その日もいつものように柿田君が乳を吸い、わたしはその様子を見ていた。三時のおやつにおまんじゅうをほおばるような間抜けな光景。窓の外では秋風が吹くようになっていた。一年は早いなと思った。彼がわたしの肌から口を離した時、努めてさりげなくこう切り出した。
「恋人ができたよ」
声が裏返ってしまった。何を一体こんなに緊張しているんだろう、わたしは。血液が濁流のように身体の中を駆け巡っているのが分かった。怖かった。裸の上半身に鳥肌がプツプツと浮き立っていくのが見えるようだった。
柿田君は何も言わず、そのままごろんと畳の上へ寝転がった。まばたきが少ないまんまるな目を見開いて、黙っていた。何を考えているんだろう。
わたしはせかせかと下着を身につけながら、わざとふざけたぞんざいな口調で言ってやった。
「できたよ、恋人。美人じゃないわたしでもできたよ。柿田君、七回も、美人じゃない、って書きやがって。わたし、けっこうしつこいからね。あのラブレターのこと絶対忘れませんよ」
早くこの部屋から出たかった。
柿田君は一度はずみをつけてあぐらをかいた状態で起き上がり、くりっと顔をこちらへ向けた。
「全部脱げよ」
と彼は言った。いつものひょうひょうとした口調で。でも、目が笑っていなかった。
今からキミとセックスするよ。
ねえ、忘れてる? と柿田君はまた言った。
「結婚したいと思うくらい、オレがキミのこと好きってこと、忘れてる?」
わたしは驚いて声が出なかった。石膏で固められたように動けなかった。
キミが脱がないならオレが脱ぐね、そう言って彼はテキパキと服を脱ぎ始めた。あらあら、まあそんな、あんた、なんて茶化した口調でこの緊迫感を和らげようとしたが、わたしの声はかすれていたし、彼は笑ってくれなかった。脱いだ服を軽く畳んで置いていくのが、柿田君らしくておかしいな、などと思った。いや、違う。わざとおかしなことを考えて、恐怖から逃げたかっただけだ。
「でも、だって、わたしとじゃ、その、使い物にならないんだよね?」
彼が下着を下した。それは激怒しているように見えた。同時に、彼が体格の良い大人の男性で、わたしが小柄な女性だということを痛いくらい感じた。
「え、だって、わたし達は友達なんでしょ? そういうことは友達同士でするもんじゃないよね?」
「誰がそんなこと言ったんだ」
はて、改めて聞かれると誰がそんなことを言ったんだろう、とは思わなかった。自分の肩にかかった彼の手があまりに大きくて、ほとんど瞬きをしない真ん丸な目が怖くてしょうがなかった。彼に必死に頼んだ。情けなくて涙が出た。
「おねがいだから、やめて、柿田君、おねがいだから」
わたしが心底怯えているのが伝わったらしく、彼はそれ以上は何もしないでくれた。下着とTシャツを身に付け、キッチンへ向かったかと思うと、小さな冷蔵庫には不釣り合いな立派な木の箱を、テーブルの上へ乱暴に置いた。
持っていきなよ、と彼は言った。
松坂牛だってさ。
意味が分からなくて黙っていると、柿田君はぼそっとつぶやいた。
誕生日プレゼントらしいよ、オレの。
あれ、この人の誕生日は確か先月のはずだ。誰から? と聞くと、母親、と返された。松坂牛の木の箱からは、お中元やお歳暮のようなよそよそしさが立ち昇っていた。
息子の誕生日くらい覚えててほしいよね、と柿田君はつぶやいた。その表情を見ていたら、もう別にセックスくらいしても良いかと、一瞬思った。彼の口に自ら乳房を含ませてやろうかと。もちろん、そうはしなかったけど。
その後どうやって家まで帰ったかよく覚えていない。
わたしは映画サークルをやめた。前後して、柿田君もやめたらしい。広い大学内で彼と会うことはほとんどなくなった。それでもたまに互いを見かけると、わたし達は初めて会った時そうしたように深々とお辞儀をしあった。
わたしは、彼の気持ちにも期待にも応えられなかった。それは仕方のないことだし、自分を責める気は起らない。
だとしても、彼がわたしの乳を吸っていたあの一年の日々には、何かしら意味があったと思いたい。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。 「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
【お申し込み受付中!】ライティング・ゼミについてはこちら→ http://tenro-in.com/writing-20190802-4/
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」2017.1.27 OPEN
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】
天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
***
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】
天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。