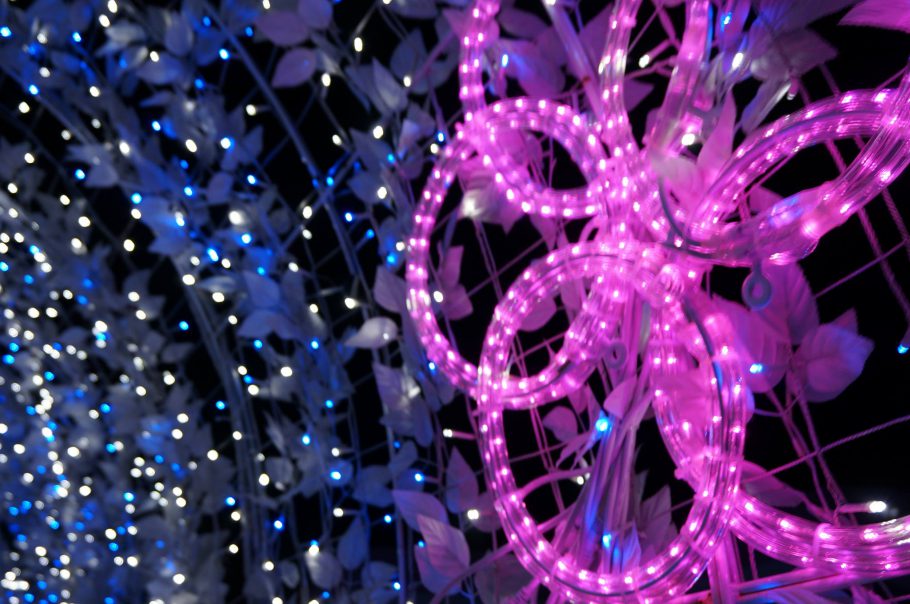男のひとの一人称には悲しみが詰まっている。《プロフェッショナル・ゼミ》
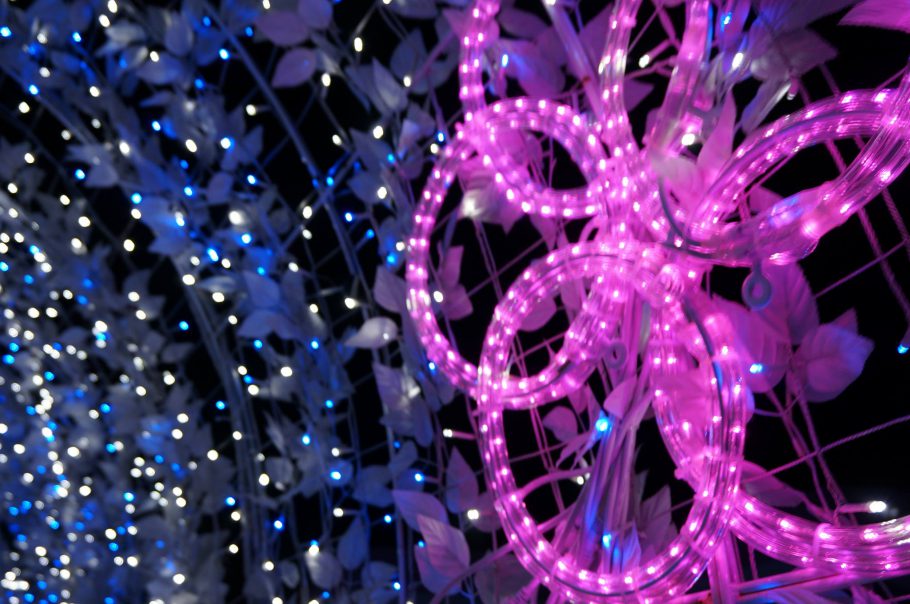
*この記事は、「ライティング・ゼミプロフェッショナル」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【10月開講/東京・福岡・全国通信対応】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜《初回振替講座有》
→【東京・福岡・全国通信対応】《平日コース》
【東京/通信】未来を変えるマーケティング教室「天狼院マーケティング・ゼミ」開講!「通信販売」も「集客」も「自社メディア構築」も「PR」も、たったひとつの法則「ABCユニット」で極める!《全国通信受講対応》
【9月開講/東京・通信/入試受付ページ】本気でプロを目指す「ライティング・ゼミ プロフェッショナルコース」入試要項発表!大人気「ライティング・ゼミ」の上級コースが9月ついに開講!
記事:永尾 文(プロフェッショナル・ゼミ)
ありがちな性癖で恐縮ですが、私は声フェチです。
よく響くバリトンもいいけれど、特に弱いのはかすれた中低音です。かすれ声の、どことなくざらっとした音が、鼓膜にひっかかりこまかな傷をつけていくのだと思います。鼓膜から全身へ、ぞくりと寒気に似た快楽が走って、私はその声を忘れられなくなってしまうのです。
だから、デスクの百合根さんに初めてお会いしたときも、からだのどこよりも先に耳が反応していました。
あ、今、鼓膜に傷がついた。と、思いました。
これからよろしくお願いしますと笑う百合根さんは、髪は豊かですが白髪まじりで、ださい銀のフレームの眼鏡をかけていて、新聞記者にしてはとても穏やかで優しい人に見えたのだけれど、なぜか、私はこの先この人にもっと大きな傷をつけられるのだろうとそのとき既に予感していました。
平静を装って、こちらこそよろしくお願いします、と一瞬下げた顔を上げたときには、百合根さんはもう仕事を始めていました。私のほうなんか見向きもしません。仕方がないので、黙ってちょんちょんに研いだ鉛筆を握り、私も自分の仕事にとりかかりました。
A新聞社西部支社、3階の編集局は今日もにぎやかです。ひっきりなしに送られてくる記事をデスクに渡し、モニターリリースを記者に送り、その間にかかってくる電話をいなし、記事をスクラップし、大量に鉛筆を研ぐ。当時、学生アルバイトだった私はデスクのそばにいる黒子のような存在でした。身の回りの雑務はすべて引き受けました。
スポーツ部の島なので、頭上に設置されたテレビはニュースではなく、プロ野球中継を流しています。仕事中、時折百合根さんは顔を上げて、テレビで試合の状況を確認していました。そのときの退屈そうな顔と言ったら。ホークスが負けても、アビスパが勝っても、私が自分の仕事を終え、何かやることはありますかと尋ねたときも終始変わらず乾ききった目をしていました。
「特にありません。お疲れさまでした」
午前3時。終電なんかとっくに出ています。始発を待つほうが早い時間帯になってようやく、3階の編集局はフロアにいる人もまばらになり、眠りに就こうとしています。
受付でタクシーチケットを手渡されても、まだ帰りたくないと思ったのはこれが初めてでした。
自動ドアを出ると、あくびをしながら社へ戻る百合根さんとすれ違いました。
新聞社には当番というものがあり、部署ごとに記者が泊まり込みで待機をしています。東京から赴任してきたばかりのデスクが当番になるのはとても珍しいことです。まして百合根さんはそんなガツガツしたタイプには見えませんでした。買い出しに行ったのでしょうか、1階にあるセブンイレブンの袋を提げて、百合根さんはふらふらと歩いてきます。
声と同じく、水分量の少ない肌。褪せた白髪。背はそんなに高くなく、胴回りは多少太い。
推定年齢、48歳。指輪は、なし――。
「――さん」
すれ違いざま、百合根さんに呼ばれた自分の苗字は他人のもののように思えました。
はっとして、振り返ると彼もこちらを見ています。
ださい眼鏡。微笑んでいるのに、乾いた目。
あの声。
「気をつけて帰ってください」
私の返事も聞かず、百合根さんはエレベーターに吸い込まれていきました。これから4階の仮眠室で浅い眠りに就くのでしょう。
これが百合根さんと私の恋愛小説だったらどんなにいいかと思います。名だたる女流作家の筆をもってすればもしかすると、50近い年上の男性と女子大生のきれいな恋の物語になったのかもしれません。私の好きな、江國香織なら。山田詠美なら。島本理央なら。西加奈子なら。あるいは、有川浩なら。
しかし、現実には私が百合根さんに抱いた感情は恋愛感情と言えるものではなく、また百合根さんが私に感じていたものもそうではなかったのだと思います。
あの夜、二人きりでタクシーに乗った夜、それまで無言だった百合根さんが「俺は……」と言ったきり口を噤んでしまった夜。
私はかすれ声に鼓膜を犯されながら、はっきりと悟ったのです。
――私はこの人に何も望めない、と。
『今日はバイトないの?』
ないよ、と返すと即座に電話がかかってきました。表示された名前を見て私はため息をつき、慌てて飲み込みます。
めんどくさいなぁ、なんて決して思ってはいけないのです。
『お前、働きすぎ』
付き合ってもいないのに私を「お前」と呼ぶ男の、にやつく顔が目に浮かぶよう。雑音交じりの声は絶妙に苛立ちを加速させる響きで、嫌いではないけれど好きにもなれませんでした。
大学で同じサークルの彼とは、何度か映画を見に行きました。邦画は面白くないから洋画しか見ない。吹き替えは認めない。こだわりの強い彼の選ぶ映画はことごとく私の好みではありませんでした。映画館を出てから、今日の映画はあまり好きではなかった、面白く思えなかったと言うたびに彼は私をわかってない女だと笑います。そんな付き合いの何が楽しいのかわからないけれど、彼は私を誘い続け、断る理由のない私もそれを受け続けました。
ついこの間までは、このまま彼と付き合うのかな、と思っていました。
『全然会えねえじゃん。今日これから飯行かね?』
「ごめん、お金ない」
『奢るし』
「たまの休みくらいゆっくりしたいの」
『日曜日のお父さんかよ。“夜のお仕事”は大変ですね』
彼は、私の仕事をおもしろがってそう呼びました。17時から翌3時まで働いているので何も間違っていないのですが、彼の言うそれは、明らかに皮肉を含んでおり的確に私を怒らせるためのものでした。
『なんでそんなに必死になって働いてんの?』
バイト先にいい男でもいんの? 冗談めかしてはいますが、彼の声に焦りがにじんでいました。最高に底の浅い発想に、私は思わずうふふと笑いました。
『なに、ガチ?』
「いい男ならいるよ。最近赴任してきた、スポーツデスクの百合根さん。抜群にいい声してて、白髪まで素敵なの」
『はぁ? 白髪? いくつよ、そのユリネってやつ』
「わかんないけど、50歳前後?」
今度は電話の向こう側で彼が笑う番でした。
なぜか、勝ち誇ったように。
『なんだよ、オヤジじゃん』
その声を聴いて、自分でもよくわからないけれど激しい怒りに包まれたのは確かです。
彼が百合根さんに勝てるところなんて、底の浅さくらいしかないくせに。
「そろそろ切るね」
『なぁ、会いたいんだよ。少しは察しろよ』
必死な言葉も、傷のついた鼓膜に引っかかることはなく、うわっ滑りして消えていきました。強引に電話を切るとすぐにメールが届きます。彼からです。平謝りするくらいなら虚勢をはらなくていいのに、男のひとって弱い生き物ですね。
もちろん、彼だって悪いひとではないのです。サークルでは明るくてリーダータイプで、よく気を遣うひとで、本当はすごくさみしがり屋で。ちょっと偉そうなところも、映画の趣味が合わないところもひっくるめて、彼と一緒にいるのもいいかな、と思っていました。
百合根さんとは並んで座って無言で鉛筆を動かすだけの日々が続きました。スポーツ部以外にも社会部、経済部、地域面編集といろいろな部署にアシスタントとして入っていましたが、百合根さんの隣が一番安心でき、反対に居たたまれなさで逃げ出したくもなりました。
彼は青いシャツを好んで着ていました。その色が目に焼き付いて、どうしても離れなくて、私も青い色が好きになりました。
百合根さんがやってくるまで、デスクは記者を怒鳴りつけるのが仕事なのだと思っていました。新聞記者はとにかくエネルギーの塊で、フロアには常に怒号と電話のベルの音が渦巻いていました。
怒られるのは私たち、学生アルバイトも同じです。ミスをしたら鉛筆やらペンが飛んでくるわ、片づけたばかりのスクラップ帳を荒らされるわ、虫の居所が落ち着くまで当たり散らされるのは日常茶飯事で、「コーヒー」と一言言われたらコンビニまで走りました。学生だけの有償インターンシップといえば聞こえはいいものの、17時から3時まで怒鳴り声の中ひたすら雑務をこなすのはしんどいと思っていた時期もありました。
百合根さんは、まったく怒鳴りませんでした。たったそれだけで優しいデスクだとアルバイトの間で評判になりました。
百合根さんは、器用でした。記者と電話をしながら左手でマウスを動かし、右手ではメモをとり、そのくせ電話が終わった瞬間に隣の部署のデスクに頭上のテレビの話題を振って笑い合うのです。
百合根さんは自分のことを、「私」と言いました。
男のひとは不思議ですね。一人称をいくつも持っている。巧みに使い分けて、相手との関係性を築く。「その書類は私の机に置いておいてください」とか、「私の鉛筆を補充してもらってもいいですか」とか、私には言うくせに、他の記者さんと話すときはごくたまにですが、親し気に「僕」と言いました。
私はいつまで経っても誰に対しても「私」でしかないのに、百合根さんは「私」ではない顔を他のひとにちらつかせたりもするのです。
プロ野球の試合が終わる、午後9時。仕事が一段落するころ、ホッチキスの芯を補充しながら私は妄想します。「私」でもなく、「僕」でもなく、「俺」と言う百合根さんを。新聞記者らしくない優しいデスクの、不遜な物言いを。
あのかすれた中低音で「俺」と言ってほしい。私の前で聞かせてほしい。
もし、この欲望を口に出したらどうなるのでしょうか。
乾いた目で射抜かれて、からからに干からびて死んでしまいそう。それもいいかもしれない、百合根さんに傷つけられたい、そんなことを考えていました。
――がしょん。
間の抜けた鈍い音と、一拍遅れて鋭い痛みが走り、私は手を押さえました。手元をよく見ずに仕事をしていたから罰が当たったのです。ホッチキスの芯が左手の人差し指に刺さっていました。
人差し指がどくどくと音を立てていました。まるで心臓がそこに移ったみたいに、うるさくて。閉口してしまいます。あぁ、これを抜いたら血がたくさん出るんだろうか。
「……どうか、しましたか?」
声をかけられて、肩がふるえました。百合根さんがこちらを見ています。彼が仕事中、アルバイトの座るこの席に目を向けるのは、もしかしたらこれが初めてではないでしょうか。優しいなんて評判は好意的解釈に過ぎず、百合根さんは他人に興味がないだけなのだと思っていました。
こんな状況にもかかわらず、私は百合根さんの目に釘付けになっていました。
初めて見る、熱のこもった目。
「貸してごらん」
この芯は少し錆びている、下手したら破傷風になるよ、と早口で少しきつく言いながら、彼は私の左手を取りました。
「痛むかもしれない」
百合根さんの冷たい手が、芯に触れ、力を入れて引き抜きました。
その瞬間、芯の刺さっていた傷口から血が玉になってあふれ出し、大きくなったところでぷつりと割れて滴ります。百合根さんは自らの手で私の血を受け止めてくれました。
「百合根さん、血が」
「救護室に行って、消毒してもらいなさい」
机の上のティッシュを何枚か取り、私の指にかぶせ、百合根さんはそう言いました
どくどくと元気よく血を吹き出す人差し指をぎゅっと押さえて、私は席を立ちました。
人差し指がひどく熱くて、たまらなくて。あふれてしまったのは私の血なのか、それとも、赤い色をした別のものだったのか、わからなくなるほどに頭の中がぐちゃぐちゃになっていました。
なのに、一方で理性はさらさらと乾いていて、百合根さんの熱のこもった瞳をひどく冷静に見ている自分もいたのです。
あぁ、このひともこんな目をするんだ、と思いました。
できるんだ、と思いました。
人差し指は確かにどくどくと音を鳴らして痛むのに、私は確かな快感を得ていました。
それからです。百合根さんの、私を見る目に熱を感じるようになったのは。
気づかないふりで黙って雑務をこなしました。けれど、たまに、今視線に気づきましたという顔をして「どうしたんですか?」と笑うようにしました。こちらから話しかけると目をそらされることもあったし、会話が続くこともありました。
百合根さんは基本的にひとに興味がないのです。水分の足りないひとなのです。
私は小娘ながら、したたかに電卓を叩き、百合根さんの言葉を引き出していました。
その日もタクシーチケットを受け取り、1階の乗り場に向かっていると当番の百合根さんとすれ違いました。
「君はほとんど毎日バイトをしているね」
百合根さんは仮眠室へ向きかけた足を止め、エレベーター待ちの私に話しかけてきました。困ったように、白髪のまじる眉を下げて。確かに17時から3時まで、学生でありながら深夜まで長時間働く女の子はそういません。
「ええ。いい男がバイト先にいますから」
ますます困った顔をするので、ついつい口を滑らせてしまいます。長い付き合いのある恋人未満の彼にも言えなかった本当の理由を。
「私には父がいません」
長年店をやっていた祖父は去年倒れて、店を閉めることになりました。だから、私、学費と生活費を自分で稼いでるんですよ。先輩の紹介で入ったここのバイトは、時給が高くて。それに、まぁ、新聞社で働いていると社会勉強にもなりますから。
明るい口調ならば、同情もされまい。チン、と音がしてエレベーターのドアがゆっくりと開いていきます。
ださい銀の眼鏡の奥で、百合根さんの目は湿っているように見えました。
このひとにこんな顔をさせられる自分、に酔っていればよかった、しかし、エレベーターに据え付けられた鏡を見て、襲ってきたのは津波のような後悔でした。
「僕には、別れた妻と娘がいるよ。娘は、そうだね、ちょうど君と同じくらいの年の」
初めて百合根さんが「僕」と言うのを聞きました。
「君は、かわいそうな子だね」
ドアが閉まる直前、鏡越しに彼はそう言いました。
私は――ひどい顔をしていました。ひどく、泣きそうな顔で笑っていました。
百合根さんのかすれた声。
乾いた目。褪せた白髪。
青いシャツ。ださい眼鏡。
私はその一つひとつに傷つけられたいと願い、また切実に、傷つけてしまいたくもありました。かすれた声に傷をつけられれば痛みに快感を覚え、乾いていた瞳が熱を持って揺れるたびに支配欲が満たされました。
「かわいそうだ」と言われたことにすら、不思議な幸福を味わっていました。
百合根さんはおそらく、私のことを自分の娘に重ね合わせていたのでしょう。ですが、私には「可愛そう」という言葉が「可愛い」に変換されて聞こえてきたのです。
誰かに憐れまれるのは初めてでした。馬鹿にされても蔑まれても、金銭的に肉体的に精神的に疲労しても、笑う癖がついていました。あぁ、憐れまれるのは、こんなにも気持ちの良いことなのですか。百合根さん、教えてください。
私は、「お父さん」に憐れんでほしかったのですか。
それとも、「あなた」に愛されたかったのでしょうか。
百合根さんが赴任してきた4月から、もう1年経とうとしています。
この春で大学を卒業する私は、学生限定のアルバイトを辞めることになりました。卒業後は地元に帰って、いずれは母や親せきと力を合わせて祖父が営んでいた店を再建するつもりでいます。恋人未満だった彼とも、距離を置くうちにただのサークル仲間に戻りました。もうここに、何の未練もありません。
スポーツ部の仕事に入る最後の日に、百合根さんに退職することを報告しました。
「そうですか。今までお疲れさまでした」
あくまで他人行儀な百合根さんの言葉に肩を落としながら仕事をしていると、横からメモが飛んできました。百合根さんは当たり散らしてものを投げたりしないのに、と不思議に思って開いてみると、赤鉛筆で「明日、19時博多口」と走り書きされていました。
了解です、とだけ書いて書類と一緒にメモを渡しました。
左手の人差し指は怪我もしていないのに、どくどくと音を立て、痛みました。
翌日19時。花の金曜日の夜ですから、博多駅は帰宅途中のサラリーマンでごった返していいます。無事にお互いの姿を認めて合流してから、今日も青いシャツを着た百合根さんと映画を見に行きました。最近話題になっている洋画は公開されてから日数も経っているのに、それなりに席が埋まっていました。
「百合根さん、私、吹き替えで見たいんですけどいいですか」
「いいよ。けど、珍しいね。君は吹き替え派なの?」
「あんまり理解してもらえないんですけど、耳から英語が入ってきて目で日本語を追う、っていうのがどうしても苦手なんですよ」
へぇ、と笑う百合根さんは、席に座っているときとは違って幼い少年のようでした。自分の親と変わらない年の、大人の男のひとには到底見えないくらい。大人ぶって見せたがったサークル仲間の彼とは、正反対でした。
映画の最中、彼は何度か鼻をすすりあげていました。私は一度も泣かなかったのに。泣いたり笑ったり忙しいひとだと思いました。仕事中は何事にも興味のなさそうな顔をしているくせに、こんなに感情豊かだったなんて、4月の私には知りえなかった嬉しい誤算でした。
2時間の映画の後は、もつ鍋を食べに行きました。
「何が食べたい?」と聞かれたから、素直にそのとき食べたいものを答えたまでです。
百合根さんは腹を抱えて、「絶妙に色気がなくていいね」と言いました。わかんないじゃないですか、にんにくとビールのにおいに欲情するひとだって、いるかもしれないじゃないですか。とは、勿論言いませんでしたけど。
もつ鍋をつつきながら、ビールをしこたま飲みながら、百合根さんはぽとりぽとりと血を落とすように、昔話をしてくれました。
学生時代はラグビーをしていたこと。スポーツライターになりたかったこと。大学を卒業してから2年海外に行っていたこと。記者になってからは仕事に燃えていたこと。合コンで知り合った女の子と結婚したこと。女の子が生まれたこと。それでも仕事が一番だったこと。離婚したこと。仕事で挫折を味わったこと。ひどい裏切りに遭ったこと。
時系列をも無視してこぼされる昔話はパズルのピースのようで、私はそれを目の前にいる白髪まじりのおじさんのフレームにあてこむことで「百合根さん」を知ろうと試みました。たぶんその行為に意味などなくて、ただの自己満足にすぎないのでしょう。百合根さんを過去から丸ごと理解できたとして、私は何もできないのだとわかっていました。
「どこで間違えたんだろうな、って思うよ。でも、たぶん過去をやり直せるとしても、僕は同じ道を歩むんだろうね」
悲しいことを言う百合根さんのグラスに、なみなみのビールを注ぐくらいで。
「恨まれているんだろうなぁ」
「わかりませんよ。私、お父さんの顔も名前も覚えてないので、恨むとか全然ないですもん」
「覚えられてないのは、それはそれで悲しいだろう」
「もう。恨まれていたいのか、恨まれていたくないのか、どっちなんですか」
軽口をたたきながら、私はずっと考えていました。
恨みたいのか、恨みたくないのか。
傷つけられたいのか、傷つけたいのか。
アサヒの瓶ビールはきりっと冷えているのに、どうして飲むとからだが熱を帯びてくるのでしょう。考えれば考えるほどにどうでも良くなってくるのでした。些末な問題だと思えるのでした。
男のひとはほんとうに弱いですね。見えないひとの気持ちに、縛られ続けて。
百合根さんの乾いた目は、どんなに熱を持って揺れていても、決して目の前の私を見ているわけではないのです。鼓膜から血を流しても、人差し指から血を流しても、気づいてはくれないのです。
タクシーに乗り込む前、もつ鍋屋さんのおかみさんから「もしかして、娘さんですか?」と耳打ちされました。どうやらここは百合根さんの御用達のお店だったらしいのです。
お会計中の百合根さんを見て、私は笑います。
「あぁ、違います。私はA新聞のバイトで――」
「あ、もしかしてあの子ですか? 大学生で、毎日バイト頑張ってるっていう女の子」
え、と顔を上げると、おかみさんは「いい子がいるんだよ、娘がああいう子に育ってたら嬉しい、って百合根さん、酔っぱらっていつもおっしゃってたので」といたずらっぽくささやきました。
タクシーのドアが音を立てて閉まって、百合根さんは私の家の住所を告げるように促しました。先に家まで送っていってくれるようです。お言葉に、甘えることにしました。
走り出したタクシーの中で、百合根さんと会うのはこれが最後になるだろうとわかっていました。別れを惜しむ言葉のひとつやふたつ、出てきそうなものなのに、私は黙っていました。
百合根さんも、感情の見えないいつもの乾いた目に戻っていました。
光のともる街を抜けて、タクシーは住宅街へと走ります。上から見ると私たちも今この瞬間、夜景の一部になっているのでしょう。金曜日の夜だから、恋人たちは寄り添って私たちを見ているのだと思います。同じ車内にいながら、隣のシートに乗っていながら、距離をつかめないでいる私たちを。
私が百合根さんに抱いていた感情は恋愛感情ではなかったし、百合根さんにとってもきっとそうではなかった。
男女的な関係になれなかったのは、私たちがあまりに同質の寂しさを抱えていたからなのだと思います。年の離れた恋人にもなれず、上司と部下にもなれず、かといって父と娘にもなれない中途半端な私たち。
信号待ちで、ゆっくりと車が止まり。
静寂を重く受け止めていると、たった一言だけ、彼は口にしました。
私が妄想し、恋い焦がれてやまなかったその声を、最後に。
「俺は……」
赤から青へ。百合根さんの好きなシャツの色へ。車のエンジン音に、彼は口を噤んでしまいました。私がタクシーを降りて、「今日はありがとうございました」と言うまで、何も言ってはくれませんでした。
「お元気で」
と、突き放すように笑いました。私の大好きな、かすれた中低音で。
それが最後でした。
あの夜、百合根さんは最後に何が言いたかったのでしょうか。
考えても考えても答えは出ないし、アサヒの瓶ビールを飲めばどうでも良くなるくらい些末なことなのです。
けれど寂しさを紛らわせない夜だけは、「俺は」の後に都合のいい言葉をくっつけて、私は愛された気分だけを味わうことにしています。
『俺は……』
憐れまれる快感を。
*この記事は、「ライティング・ゼミプロフェッショナル」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、店主三浦のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
【10月開講/東京・福岡・全国通信対応】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜《初回振替講座有》
→【東京・福岡・全国通信対応】《平日コース》
【東京/通信】未来を変えるマーケティング教室「天狼院マーケティング・ゼミ」開講!「通信販売」も「集客」も「自社メディア構築」も「PR」も、たったひとつの法則「ABCユニット」で極める!《全国通信受講対応》
【9月開講/東京・通信/入試受付ページ】本気でプロを目指す「ライティング・ゼミ プロフェッショナルコース」入試要項発表!大人気「ライティング・ゼミ」の上級コースが9月ついに開講!
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021
福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL 092-518-7435 FAX 092-518-4941
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】