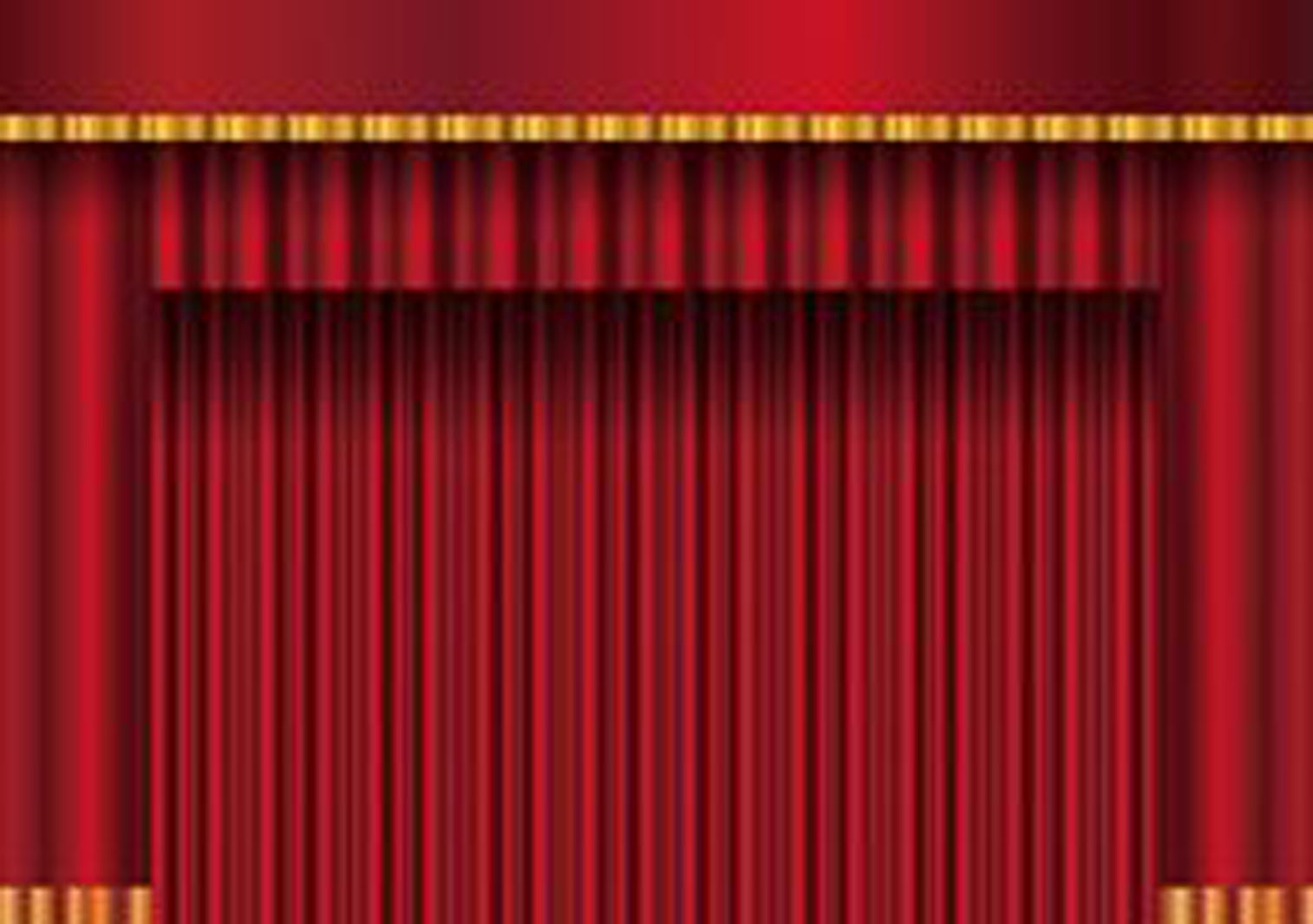コ・ド・モ《プロフェッショナル・ゼミ》

*この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【12月開講申込みページ/東京・福岡・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
→【東京・福岡・全国通信対応】《日曜コース》
わたしには様々なニックネームがある。あだち、あだっちゃん、こみさん、みーこへーなど、挙げていけばキリがない。家族から付けられたものあれば、友人から付けられたものもある。
しかし、その中でも一際、奇妙なニックネームがある。
わたしをそう呼ぶのはこの世でたったひとりだった。
そしてそのニックネームを思い出すと、人知れず胸が痛くなる。誰にも言えなかった想い出につながるから。
***
あなたが後方のドアを開けた時、何人かがそちらを振り返った。
わたしもその中のひとりだった。
まだにきび跡の残る十代後半の男性。
三十才くらいのスーツをきちんと着込んだ女性。
老眼鏡をずらしたのはどう見ても六十才を超えたご婦人。
あなたは乱れる息を整えながら、前から三列目の席を確保した。わたしの斜め前だった。
わたしはあなたの薄い頭髪をなんとなく見つめていた。蛍光灯の白々した明かりに、あなたの薄い銀髪が透けていた。
先ほどあなたが通り抜けたドアが再び開いた。
のんびりと入ってきたのはおまんじゅうのような茫洋とした顔立ちの中年男性だった。
あ。この人、サスペンダーしてる……マジかよ。いるんだ、アメリカの刑事以外で日常的にサスペンダーしてる大人って、とわたしは密かに息を飲んだ。また妙によく似合うこと。
男性は黒板の前の教卓にドサリと数冊の英和辞書を置くと、チラと教室全体に目を走らせ、そこに座る人々の数を数えた。
では、前期講義一回目を始めます。
男性が見た目どおりのユーモラスな声で告げた。
年齢も性別もバラバラのわたし達、文学部二部の学生は、これから数ヶ月共に学ぶ仲間になる。
おまんじゅう顔の男性は鬼塚先生といって舞台の脚本翻訳なども仕事にしていた。彼の舞台翻訳の講義はなかなか人気だった。
ひとつには、先生のキャラクターが親しみがあるというのもそうだし、教え方が良いこともある。扱う舞台脚本がなかなか面白かったこともある。教材に使われるのは全て先生が実際に翻訳を手がけた脚本ばかりで、中には近々実際の舞台で上演されるものもあって、わたしも何度か劇場へ足を運んだ。教室の蛍光灯の下、紙の上で学んでいた言葉どもが、人間の身体を通して声になり、それが自分の耳に届いて胸を揺すぶられるのが快感だった。
わたしは鬼塚先生に気に入られたくて、大学の図書館でせっせと慣れない翻訳に励んだ。ピンとくる和訳が浮かぶといっぺんに有頂天になっり、帰りに学食などでその季節限定のラーメンを食べた。
ふと見ると、学食の隅っこで本を読むあなたがいた。老眼鏡を掛けていた。読んでいるのは図書館で借りてきた本のようだった。こうやって改めて見ると、どこからどう見てもおじいさんだなぁと、ラーメンのスープを飲み干しながら思った。
あんなおじいさんが、彼よりはるかに若いわたし達の脳みそについてこられるんだろうか。失礼ながら、そんなことも考えた。
しかし、そんな考えはすぐに間違いと分かった。それどころか、あなたは素晴らしく優秀だった。課題も必ずやってきたし、翻訳は常にほぼ完璧だし、いつも最前列に陣取っていた。使いこまれた辞書が印象的だった。初回講義時は、始業直前に駆け込んできたのが恥ずかしくて、一番前に座れなかったそうだ。
あなたは都電に乗って通学していたが、乗車中は必ず本を読んでいた。なんでそんなことを知っているかというと、あなたが「本に夢中になっていたら電車を降りそこなった」と何度か報告してくれたからだ。今こんな本を読んでいて、それがどんなに面白いか、登場人物がいかに魅力的かなどをよく話してくれた。あまりにその話が面白いので今度その本を読んでみようとわたしが思っていると、熱が入りすぎてオチや真犯人までバラされてしまうのはいただけなかったが。
わたし達若者が、「エナメル加工のテーブル」と翻訳した英文を「ほうろう引きの文机」とするなど、ごまかしようもなくおじいさんなことも多かったが、そんなことはどうでもよくて、あなたは素晴らしい学生だった。
学びの喜びが、目尻のしわから、柔軟性の乏しい膝から、淋しい頭髪から、立ち昇っていた。こんな風に何かを学ぶあなたは、このキャンパスに溢れるハタチ前後の若者よりも、はるかに「学生」だ。そのことを考えると、なぜか胸がジンとして、うっすら涙がにじんできた。
舞台翻訳の前期の講義が中盤に差し掛かった時、飲み会の話が持ち上がった。わたしも、もちろん参加することにした。そしてあなたも。
大学の近くのその居酒屋はいわゆるチェーン系のお店ではなく、鬼塚先生がよく飲みに行くというこじんまりとして静かなところで、わたし達は落ち着いて話をすることができた。二部の学生は社会人の人も多いから、ちょうど良かった。十名ほどの老若男女が言葉を交わしてお酒を楽しんだ。
あなたはわたしのはす向かいに座っていて、横にいる女性と話していた。彼女は異様に色っぽい社会人の学生で、わたしは周りの人とおしゃべりを楽しみつつも、教室では見られないあなたのデレデレした表情にひそかにニヤついていた。じじいめ、楽しんでるな。大学来て良かったな! などと思っていた。
ふと、あなたと目が合った。
あなたはわたしの様子を一瞬まじまじと見つめると、ニコニコしだした。しきりと何かつぶやいている。全然聞こえない。
「え、なに、何て言ってるんですか?」
わたしはハイボール片手にあなたの横まで行って、その口元へ耳を寄せた。
「……ども」と聞こえた。
ども? なんだ、「ども」って。きょとんとして首をかしげてみせると、あなたはもうたまらないといった風に笑い声を上げながら、ハッキリとこう言った。
「こ・ど・も!」
え! 子供? その時、私たちの向いに座った40才くらいの社会人学生の女性が笑い出した。
「ホント、ふたりが並んで座ってると、孫とおじいちゃんみたいねぇ」
ハッとした。確かに、わたしはかなり幼い顔立ちをしている。大学四年生の時に、小学生に間違われるほどには幼かった。
見た目の幼さがコンプレックスなら、メイクや服で大人っぽくしよう! そういう選択をする女性もいれば、わたしのように見た目の幼さよりもメイクや服に取られる時間とお金の方を気にする女性もいるもので、その日の飲み会のわたしの出で立ちといったら、父親のお下がりの真っ赤なパーカーにジーンズというものだった。カジュアルが過ぎる。しかも胸にはデカデカと「Discovery Channel」とプリントされている。さらに顔面には粉のひとつもはたいていない。紅も差してない。眉毛は野生やしである。確かに、どう見たって、あなたの言うようにわたしは子供なのだった。
「子供がこんな夜中に居酒屋なんかいたら、ダメだろう!」
あなたは梅酒を飲みながら、紅玉のようなピカピカした頬をゆるませていた。あまりに嬉しそうなものだから、なんだかこちらも良い気分になって、えへへ、と笑った。
ははは、子供。えへへ、なんですか。
こんな無意味なやり取りが心地よかった。妙に幸せだった。
その飲み会以来、あなたは学内でわたしを見つけると「おーい、子供」と呼ぶようになった。
子供、ここの英文はどう翻訳した? ちょっと教えてくれ。
子供、次の講義は休講だそうだ。
子供、腹減ったか? パンやろうか?
あなた、ちょっと、パンて。
もちろん、ありがたくいただいたが。
休講の時などは、たまに学食で一緒にお茶をした。あなたが買ってくれたパンを一緒に食べて、わたしはお返しにふたり分のコーヒーを購入した。同時にコーヒーをすすった時、これもまた同時に舌をやけどして、アヂッ、と顔をしかめるのまでそろってしまった時は、ちょっと恥ずかしかった。
ある時、あなたはわたしに、
「子供はどこの出身なんだ? 家から通ってるのか?」
と尋ねた。埼玉県の熊谷というところです、とわたしは答えた。あなたの様子が一瞬おかしかった。もしかして熊谷という場所を知らないのかもしれない。
「熊谷というのは、埼玉県の北の方にあるんです。ちょっと遠いけど通える範囲なので、実家から通ってて、あ、一応新幹線も止まります」
知ってるよ、とあなたは呆れたように笑った。熊谷だろ、よく知ってるよ。じゃあ、さっきの変な間は何だったんだろうか。その時はそんなに深い意味もないと、流してしまったけれど。
最終講義が終わるとキャンパスはとっぷりと夜にくるまれて、少し物悲しいような気分になる。教室のある建物から校門まではゆるやかな坂になっている。あなたは講義が終わると、サッサと資料や辞書を大きなトートバッグに放り込んで、長い坂をとっと、とっと、と下っていく。小走りで。もうあなたの膝は柔軟性が乏しいのだから、あんまりそういうことはしてほしくないが、その様子がいつもいそいそしているから、言えない。家で待ってくれている人がいるのだと思う。
わたしは、たまにはあなたと夕食でもお酒でもご一緒したかったけど、あまりにサッサと帰るものだから声がかけられなかった。仕方なく、大学の近くにある盛りの良いうどん屋で、ざるうどんをすすり込んでひとり帰った。
後期の舞台翻訳の講義でも、あなたとクラスメイトになれた。教室に入った時、無意識にあなたを目で探している自分に気づいた。あなたは最前列に座っていて、わたしがそのとなりに陣取ると、「お、子供、来たか」と喜んでくれた。後期もよろしくお願いします、と頭を下げると、「よしよし」と頭をなでてくれた。これじゃ本当に子供だ。無性に照れてしまって、思わず抗議した。
「ちょっと、もしもここがタイだったら大変でしたよ。子供の頭には神様がついてるって言われてて、むやみに触っちゃいけないんです」
あなたは全く取り合わず、子供は物知りだなぁ、と笑っていた。
後期の講義も歯ごたえ十分で、面白く充実していた。あなたは相変わらず、最終講義が終わると脱兎のごとくあの長い坂を駆け下りていったけど、それももうすっかり普通のことになっていた。背中を見送る時、あなたをそんな風に走らせてしまうほどの相手が、少しうらやましいようにも感じた。
それからしばらくして、わたしが十九歳の誕生日を迎えた直後だから、秋頃だったと思う。わたしは所属していた映画サークルの集まりに出るため、いつもより早めに大学にいた。わたし達二部の学生は、サークルに顔を出してから講義に出席することも珍しくなかった。
図書館の前で、バッタリあなたに会った。あれ、この曜日のこの時間にあなたに会うなんて、と思った。二部の学生でも他学部の昼間の講義を受講することが可能だが、あなたが受講しているのはほとんど二部の講義だったから。それに、このひと月ほどはあなたは舞台翻訳の講義を欠席していた。
「あれ、なんか久しぶりですね。図書館で勉強ですか」
「本を返しにきたんだよ」
あなたはどこか上の空だった。そして、
「子供、ちょっと付き合ってくれないか」
てっきり学食へ行くものと思ったら、あなたは校門までの長い坂をゆらゆらした足取りで下り始めた。ひと月前まで、柔軟性の乏しい膝にも関わらず一目散に駆け下りていった坂を、こんなにゆらゆらと。どこへ行く気だろう。
「都電で三駅だから」
あなたはわたしの都合も聞かずにそのまま坂を下っていった。サークルの集まりに遅れると一瞬だけ思ったが、本当に一瞬だけだった。
あなたの住む家を見てみたいと思った。そして、あなたに坂を走らせるひとを見たかった。
都電を下りてしばらく歩くと、大きな団地が見えた。あなたはしんどそうに四階まで階段で上った。鉄の扉をギイと開けると、どうぞ、といつになく丁寧な口調でわたしを促した。
部屋は狭く、物が少なかった。椅子をすすめられたので座った。
他にひとの気配はなかった。
あなたは使いこまれた急須でゆっくりお茶を淹れてくれた。キャンパスで見るあなたは立派な学生なのに、この狭い部屋でお茶を淹れる様子は、本当にただのおじいさんだった。それが悪いという意味ではないんだけど。
「子供、翻訳の講義はだいぶ進んだか」
「はい、もう第三幕までいってますよ」
「それは追いつくのが大変だなぁ」
「大丈夫ですよ、優秀だもん。あんなに使い込んだ辞書持ってる人、他にいませんもん」
あなたはひっそり笑った。「そうか」と。
お茶をいただこうとしたら、あなたは突然口を開いた。
「うちの母ちゃん、死んじゃったんだよ」
いつだったか、初めての飲み会で梅酒を片手にわたしを「子供」と呼んで頬を紅玉のように光らせていた時と同じように。不思議なくらいに、あの時と同じトーンだった。
うちの母ちゃん。
あなたの年齢から考えて、この「母ちゃん」は母親ではなく、奥さんという意味だと分かった。
「大学へ行けってオレに言ってくれたのも、母ちゃんだったんだよ。子供がやっと独立して、ウチは子供ができたのも遅かったから、本当やっとでさ。さぁ、どうしようと思ってたら、母ちゃんが、オレに大学行け、って。本当はずっと勉強したかったんでしょ、って言ってさ。自分が学生の時使ってた英和辞書をさ、オレにくれたんだよ。頑張ってね、なんて言ってさ」
あなたは明るいひとだったけど、決して饒舌ではなかった。こんなによく喋るあなたは初めて見た。
「それで、母ちゃんが、熊谷の人によろしく、って言ってたよ」
熊谷の人?
「わたしのこと、熊谷の人って奥様に言ってたんですか? ていうかわたしのこと話してたんですか?」
「大学で友達はできたか、って聞いたきたもんだからさ」
あなたは、急に笑ったような困惑したような複雑な表情を浮かべると、もう言っても良いか、とつぶやいた。
「オレは再婚でな、前の奥さんには浮気されて別れたんだよ。その浮気相手っていうのが、熊谷のやつだったんだ。今でも、オレの前の奥さんは熊谷に住んでるはずだよ」
だからか。だからあの時、「熊谷」という単語に反応したのか。
「そういうことがあったもんだからさ、それで笑っちゃうんだけど、母ちゃん、子供にやきもち焼いてたみたいなんだよ」
え。やきもち。
「少しでも大学からの帰りが遅いと、あら、熊谷の人ですか? って聞くんだよ。だからいつも一目散に帰ってやってたんだけど……バカだよなぁ、相手は子供なのに」
あなたは、年甲斐もなくやきもちを焼く奥さんへの愛しさが高まってしまったのか、目を潤ませた。あー、おかしいと手で目をぬぐいながら、でも笑い涙にしてはずいぶん粒が大きかった。
やきもちを焼かれていたなんて。イヤな気はしなかった。あなたはさっぱり気づいてなかったけど、奥さんはやっぱり女だ。
あなたは、いきなり自宅へ連れてこられてビックリしたろう、悪かったな、と謝ってくれた。
外でうっかり泣くのが嫌でな、とまた目を拭った。
わたしはあなたの背をさすりたかった。肩を抱きたかったし、手を握りたかった。
別にそうしたって良いけど、もしも触れたら、それが子供の触れ方じゃないと、あなたに分かってしまう気がして、できなかった。
「また頑張って勉強しないとなぁ……」
あなたは鼻をすすった。
「一緒に卒業しような、子供」
まっすぐにわたしの目を見てきた。
わたしは、あなたとまた机を並べて学べる日々のことを考えて、幸せな気分になった。別にわたしは子供でかまわない。子供だから、あなたと卒業まで一緒にいられる。
わたしはあなたに言う。
「はい。卒業まで一緒に頑張りましょうね、菊池さん」
***
この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、店主三浦のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
【12月開講申込みページ/東京・福岡・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
→【東京・福岡・全国通信対応】《日曜コース》
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL 092-518-7435 FAX 092-518-4941
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】