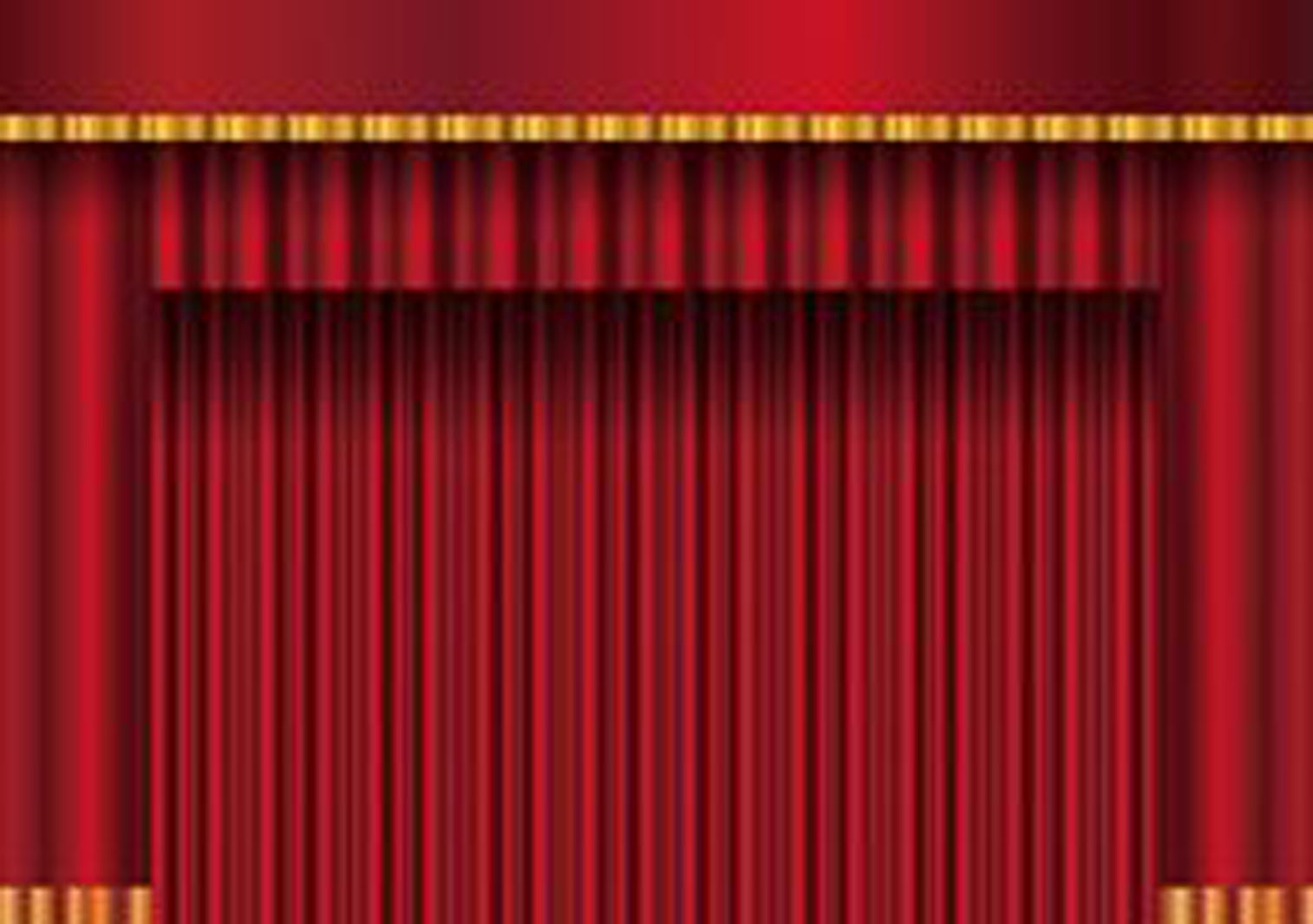まだ大人の階段をのぼっていた頃、デート終盤で必ず迷っていたこと《プロフェッショナル・ゼミ》

記事:田沼明狸(プロフェッショナル・ゼミ)
「……村田さん! 今です! 早くッ!!」
そう広くはないBARの店内を全力疾走したのは、後にも先にもあの夜だけだ。
苦さと甘さを知って、自分がひとつ、大人になった夜。
* * *
当時の僕には、世の中で最も苦手な行為がハッキリしていた。
あなたにも共感してもらえるだろうか、ちょっとイメージして頂きたい。
懸命に誘い続けて何度目かのデートに連れ出した、憧れの相手。
恋人ではないけどコチラの気持ちは既に伝わっている状態。
一緒に映画に行ったところで隣が気になって内容なんか入ってこない。
彼女が満足すれば監督に「いい作品をありがとう」と感謝するし、彼女がカッコ良かったと話す主人公には「いい演技をありがとう、でも早めに人気なくなってください」と嫉妬する。
こんな、気を抜けばドッと溢れ出しそうな気持ちをこぼさないように慎重に歩き、夕飯に行く。
入念に調べた通り店は美味しい料理を出してくれて、満腹で幸せそうに緩んだ表情を見るとこの店に入る前より少し仲良くなれた気がする。
店を出て考える。
夜も深いがまだ終電には時間があるし、さらに言えば、明日は休日だ。
会話の中で翌朝早くからの予定はない、という情報は提示されている。
さあ、次の動きはどうする。
……という、ここの問題まで進める人は、僕とはレベルが違います。
是非教えて頂きたいのです。
どうやったんですか。夕飯のお会計を。
僕の場合は、店を出る頃には頭の中はオーバーヒートで使い物にならない。
ご馳走していいのか? 払って問題ないなら払いたい。
でもこっちが相手の意向を無視して払ったら「数千円で恩を着せられた気分にはなりたくない」って思わないだろうか。
彼女だってしっかり働いてちゃんと稼いでるんだ。
敬意を表するなら割り勘なのだろうか。相手に聞けば間違いないだろうけど、切羽詰まった真剣な顔で「ご馳走していい?」なんて尋ねたら「お願い!」なんて答えづらいに決まっている。
そんな常識を利用して僕が支払う状況をなくそうとしていると思われるのも嫌だ。ゲームっぽくするならLOFTでお守り代わりに買った「I PAY YOU PAYサイコロ」を本気で使うべきか。でも支払う人間を決めるためにサイコロまで準備して「さぁ振って」とか、さすがに異常な展開じゃないだろうか。サラっとやりたいんだ。相手が、率直に喜んでくれることを。
今回も失敗した。オロオロしている間に彼女が半分の金額を出してくれた。
お釣りを受け取り、忸怩たる思いでサイフを握りしめて、カバンに戻した。
彼女を駅まで見送り、ひとり帰路につき、翌日出社しても落とした肩はあがらなかった。
こんな問題で足止めされたくないのに。どうにかしなくてはいけない。
会社では部長が「村田がせっかく落ち込んでるから、からかうだけからかっといてやろう」という宣言をして、で社食に誘ってくれた。
「またへこんでんの?」
「はい、また次のデート誘ってるんですが……」
「……あのね。聞く限り、君はもうゲームセットです。相手が既にコートを離れてるのに気付かないままサーブ打ってる感じです。見てて辛い」
「でも……会ってくれるなら好転するかもしれません。でも、どうしても会計がうまくいかないんです」
部長は「独身貴族」という言葉がぴったりの男だ。
立場上仕方なくジャケットを着てはいるが、40過ぎても髪の色は明るく、目は細くて口が大きく、大きな声でよく笑う。身振り手振りが大きいので、その日も人差し指のドクロのシルバーリングが空中をよく動いた。
「迷わず君が払えばいいの。何を迷うの? 給料ちゃんともらってんだろ」
「相手の目の前で支払う瞬間にいろいろ考えちゃうんです。映画のチケットは先に買っておいて渡せばいいから楽だけど、食事は相手の頼みたいものがあるからリアルタイムで金額が変わる。
あっ……! 店にクレジットカードを渡しておけばいいんですかね?」
部長は口に運びかけた食事の手を止めて僕を見た。
もしまだ「呆れる」という言葉の意味を知らない人がいたら是非、この表情を見ておくべきだと思った。
これが「呆れる」ですよ。混じりっけなし100%の「呆れる」。
人差し指のドクロも中に浮いてこっちを見てる。
よく見るとこの銀色の骨も呆れているようですね。
「村田君。気持ち悪いよ。事前にカード預けるなんて支払い方法、聞いたことある?」
「ないです」
「例えばな、デートで午後に集合するとするだろ」
「はい」
「その時点でもう、相手の子はお前よりお金使ってるの」
「え?」
「化粧品代で金はかかるし、その手間で時間もかかる。すっぴん部屋着で来られたら話は別な。それはそれで相手の気持ちを汲み取るべき事態だけど、その日はちゃんとおめかしして来てくれたんだろ?」
「はい」
「じゃあ覚えとけ。女の子は生きてくだけで俺らより大変なの。ややこしい話じゃなくて、少なくとも女性が化粧やら脱毛やらする風習になってるだけでもう、それは事実なの。だから、今日も来てくれてありがとう、って感謝を込めて食事代くらい払うんだよ。わかるか」
「……超納得しました」
払うべき理由がわかった。
理由があれば戦える。これは大きい。
タイミングよくファンファーレのように携帯が鳴り、彼女から日程の返事がきた。
「次の日程、来ました」
「迷うなよ」
「はい」
「彼女もマナーとして『払うよ』って言うかもしれないけど、『ただ自分が払いたいだけだ』って言え」
「なるほど……」
そうして初めて前向きに行動が決まってから、数日前までシミュレーションを重ねた。
コンセプトはわかった。……でも、具体的な実現方法は?
部長のおかげで、自分の頭では正解にたどり着けないことを知っていた。
しかし部長は二度同じ質問をされるのが嫌いだった。
だから、別の師匠に聞きにいった。
自分にとっては切り札とも呼べる、1度しか行ってないが絶大な信頼を寄せる酒場。
そしてそれは、今回のデート本番で訪れる予定の、決戦の地。
あそこならきっと、教えてくれる。そう思えるだけの実積があった。
店はBAR酒場、という名前だ。
新入社員の頃、通勤路で見つけてその清々しい名前に驚き、ふらりと一人で入ったことがあった。
当時、店に入ると、爽やかな笑顔で30代後半とおぼしき男性店員が迎えてくれた。
その柔らかい表情に安心した僕は、本心を伝えた。
「初めて来たんですが、お酒に詳しくなくて。でも今後仕事でもお酒の場があると思うので、勉強したいんです」
「なるほど、前向きで素敵です」
「一杯目は何を頼むといいんですか?」
「ははぁ、なるほど、そうですね……お酒はあまり強くないですか?」
「弱いです」
「かしこまりました」
笑顔を見せてから奥へ引っ込んだバーテンダーは、水色にキラキラと光るボトルを持って帰って来た。
「こちら『ボンベイサファイア』と言って、ジンという種類のお酒です」
「ジンってお酒の種類のことだったんですか。きれいですね」
「そうなんです。これはちょっと独特の草っぽい香りがするんですけど、だから覚えやすいかもしれません。それで一杯目なんですが、ジンソニックはいかがでしょう」
「あ、ジンソニック、っていう発音が正しいんですか? ジントニックではなくて」
「おっしゃる通り、ジントニックもあるんです。ジントニックは、ジンをトニックウォーターで割ったもの。ジンソニックはトニックウォーターだけでなく、ソーダで割ったもの」
「だからトとソが違うんですね」
「ええ。ジントニックは『とりあえずビール』のように一杯目の水代わりで頼む人が多いポピュラーなカクテルです。ソーダで割るとトニックウォーターの甘みが弱まって、スッキリと飲めるんですよ。もっとドライに飲みたい時は、ソーダだけの『ジンソーダ』もオススメです。落ち込むことがあってスカっとしたい時とかに」
「勉強になります。では今回は、ジンソニックをお願いします」
「かしこまりました!」
こんなにハッキリとどんなお酒が来るか認識して注文したのは初めてだった。
出された端正な円柱グラスは、ひと噛みすれば簡単にくだけそうなほど薄かった。
手に取って口に運ぼうとすると氷が傾いて、とても繊細な音と振動を響かせた。
口を付けると、想像以上に冷たい、爽やかな液体が流れ込んで来た。
いつも朦朧とさせられるだけの酒で、初めて頭が冴える気がした。
RPGの回復薬って、こんな味かもしれない。
「美味しいです! 本当に」
「良かったです」
「覚えておきます。いざという時のために。ありがとうございます」
話を聞くと、このBAR酒場は飲み屋で働く人達が自分の店を閉めた後に集まる、酒好きの店なのだそうだ。
BARの割にフードメニューはかなり充実していて、肉料理もパスタもどれも美味しかった。
プルプルと豆腐にしか見えないのに口に入れるとチーズとして溶け出す「ゴルゴンゾーラ豆腐」は感動して2皿も頼んでしまった。
焼きそばはあえて「日清焼きそば」と表記したり、ポッキーに「銀座のポッキー」というメニュー名を付けて割高さをウリにするなど、散見されるユーモアも、本格的なフードメニューとのギャップで大いに笑えた。
結局最初の一杯で顔を赤くして2杯目以降の講義には進めなかったが、またお願いしたいと伝えて帰りに名詞をもらった。相手をしてくれていたのは店長だった。
その後、通勤路を変えたために顔を出ずにいたが、ずっと心に残った名店だった。
そして、いざという時がきた。
久々に酒場のドアを開けると、懐かしい顔がまた出迎えてくれた。
「何年か前、一度だけお酒を習ったんです。こちらで」
「ああ、やっぱり! お久しぶりです」
「1週間後にこちらに、二人でこようと思うんですが、席は空いてますか?」
「確認しますので、おかけください」
「はい。あと、ジンソニックをひとつ、ボンベイサファイアで、お願いします」
「かしこまりました」
懐かしいカクテルを半分まで飲んだ所で、機嫌良くグラスを拭く店長に問いかけた。
「店長」
「はい」
「相談があるんですが」
「はい」
「僕はお会計が苦手なんです」
「えっ」
笑顔を絶やさない店長の笑顔が、絶えた。
冷静に考えれば確かに、「だから払いません」という犯罪予告にもとれる。
映画のシナリオによっては「だから皆さんには死んでもらいます」のフリにも使えるかもしれない。
混乱9割、恐怖1割の店長に向かって慌てて付け足した。
「いえ、あの、1週間後にですね。連れてくる人のこと、何度かデートに誘ってるんです。でも、毎回お会計になるとスマートに支払えないんです。なんか、恩着せがましいかなとかオロオロしてたら、相手が『はい!』って半分の金額をもう、トレーに乗せてくれちゃうんです」
「ああ、そういうことですか」
「もう次回は僕が払うって決めてるんですけど、逆に偉そうになったりして『……そんな払い方、ある?』って思われるような変な態度とっちゃったらどうしようかと思いまして」
「なるほど」
「他のお客さんって皆、どうしてるんですか?」
意図が通じて笑顔が戻った店長は、丁寧に事例を紹介してくれた。
「お客様によって様々ですが、多いのは女性がお手洗いに立たれた時に男性が支払われるパターンですかね。会計の時に『いいよ』って言って女性が出しかけたお財布をしまってもらう人もいますし。慣れた仲の男女は、もうお支払いする側が決まってる様子もありますね」
「相手の方のお手洗いのタイミングっていうのもスマートですが、行かれないことはあるかもしれません」
「そうですね……」
「ええ」
「もう、呼んでもらえませんか?」
「あ、お会計にですか?」
「トイレタイムがあればそこで。でもトイレタイムがなければ、『ここ!』と思ったら、僕を、呼んでもらえませんか?」
「かしこまりました」
「お手間をおかけしてすみません。本当に」
「いえいえとんでもない。もし困っても、『僕が払いたいんだ』って言えば、たいていは払わせてくれると思います」
「なるほど、上司にも言われましたが、それは大切なポイントですね」
「ええ、頑張りましょう」
両腕をぐっと握った店長の励ましのポーズを見て、今度こそうまく行く気がした。
迎えたデート当日。BAR酒場の扉を開けた。
「村田さん! お待ちしておりました!」
相手女性の前でいかにもVIPのように迎えてくれる店長の心意気には最初から感服した。
店の一番奥の窓に面したソファ席からは、控えめにイルミネーションが見え、寒々とした夜の気配が店内の安心感とギャップを作って、この上なく居心地のよい席だった。
彼女もソファに身体を沈めてくつろいでいる。
教え通り「ジンソニック」を頼み、僕同様に酒に弱い彼女にも好みを伝えて弱いカクテルを出してもらった。
店長が勧めてくれた料理はどれも美味しかったし、彼女も満足そうだった。
ゴルゴンゾーラ豆腐を食べた時の「うわ!チーズ!」という感想は妄想の通りだった。
すべてが順調だった。
彼女が「ちょっと失礼、へへ、酔った」と機嫌よく席をたった。
一番奥のソファ席から、レジを抜けて、さらに奥にあるトイレへ。
……これはまさか。
振り返ってレジを見ると、店長が既にそこにいた。
レジから、リレーでバトンを待つランナーのように手をブンブン振って煽っている。
「……村田さん! 今です! 早くッ!!」
彼女がもしトイレから出て来たら一発で目に入る場所にレジはあった。
残された時間はそう長くはない。
僕はソファから飛び起きて走った。
レジ直前で財布を忘れたことに気付いてソファに駆け戻った。
再びレジに着く頃には息が切れていた。
店長は手際よく会計を進めながら、急なシャトルランで息を切らす僕を見て「後でお水もっていきますね」と笑ってくれた。
僕は頷きながら、もし彼女がトイレから出て見つかった時のために「僕が払いたいんだ」「僕が払いたいんだ」「僕が払いたいんだ」と自然に言えるよう唱えていた。
お釣りを受け取ってラスト一本を駆けてソファに戻り、トイレの方を見ると、ちょうど開く気配がしたので顔を戻した。
運ばれた水を二人で飲み、席を立ち、店を出る所で彼女は「お会計は?」と尋ねた。
「大丈夫」
とだけ答えて、「え、いいの?」と不思議がる彼女を店の外へ誘導した。
店長が「ありがとうございました!」と言いながら見送りに来てくれた。
万感の思いで店長と目を合わせ、深々とお辞儀をして店を出た。
彼女が「ありがとう、ごちそうさま!」と笑った。
……できた!払えた!
シンプルに、当然のように、難関を突破した!!
やっと大人の男になった!!!
ところがその後、「支払い」に関する記憶は思い出したくもないものに変わってしまった。
そのままレイトショーを観に行くことになったので、タクシーで移動した。
暗がりで隠れて財布を見たところ、万札しかなかった。
先日、万札を出して運転手に舌打ちをされたことを思い出した。
せっかく楽しい日なのにそんなことになったらイヤだ。
僕は聞いてしまった。
「細かいのがないんだ。千円札、もってる?」
僕が財布を広げて彼女に尋ねると、彼女は一瞬だけ驚いた顔をしてから「あるよ!」と笑った。
「小銭はあるんだ」と出そうとしたが、「いいの!」と彼女は言った。
支払いのために明るくなった車内で自分の財布をよくみると、バッチリと千円札があった。
2カ所に別れた札入れの、片方だけしか暗くて見えなかったようだ。
だから彼女は驚いたのか。
確かに千円札を見せながら、千円札がないと言われたら、意図がわからない。
慌てて「ごめん!あった!払う!」と言ったが、彼女は、さらりと、当然のように、あの魔法の言葉を使ったのだった。
「いいんだ、私が払いたい気分!」
経験知の差を思い知り、打ちひしがれた。
やっぱり相手を傷つけない、良い台詞ですね。「自分が払いたいから」か。
映画館は僕をあざ笑うあのように「イベントのために休館」という張り紙で封鎖されていた。
「イベントのために休館、だね」
「うん、イベントのために休館」
「この後どうしようか」
「きょうは帰ろうかな!」
「そっか。じゃあ、送るよ」
駅で解散して帰路につき、自分はその足でBAR酒場に行った。
一瞬、目を丸くした店長がカウンターへ迎え入れてくれた。
「えっと、すみません。今日はありがとうございました。あれをお願いします。苦いやつ」
「ジンソーダですね」
「お願いします」
「かしこまりました」
まだまだ大人の男になれていないことを知った夜。
そんな夜を重ねることが、少しずつ大人になることだとは、まだ知らない夜。
ジンソーダは想像以上に苦く、サービスで出されたガトーショコラは思い出すと今でも安心するほど、甘かった。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、店主三浦のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
【12月開講申込みページ/東京・福岡・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
→【東京・福岡・全国通信対応】《日曜コース》
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL 092-518-7435 FAX 092-518-4941
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】