そばかすと、本の香りと、鉛筆と。
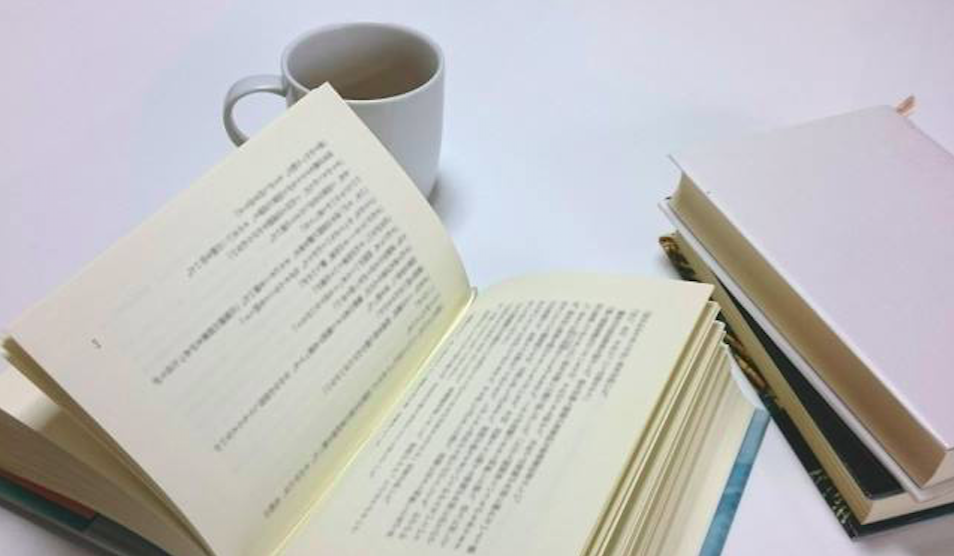
*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【4月開講申込みページ/東京・福岡・京都・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
→【東京・福岡・京都・全国通信対応】《日曜コース》
オールイン・関谷(ライティング・ゼミ平日コース)
僕の人生で初めて、女性不信というものに陥らされた、その張本人が目の前にいる。
彼女は、26年前の2月と同じように、そばかす顔でちょっと上目遣いで。
鼻にちょっと小じわを寄せながら可愛らしく笑う表情は小学校6年生のころのままだった。
「担任の丹藤先生、だいぶ髪の毛無くなってたね〜」
「そうそう、私たちの頃はフサフサだったよね」
「あと3年で定年らしいからまあ、だいぶ変わったよね」
「そうか。私たちもそれだけ、年を重ねてきたってことか」
なんて同窓会では良くある会話を交わしながら、彼女は笑顔で僕にほほえむ。
長澤真由美さん。僕が人生で初めて告白された相手だ。
長澤さんはこの春休みに行われた同窓会の2次会で居酒屋の掘りごたつ式の席で僕の正面に座り、レモンサワーのグラスを傾けていた。
「関谷君ってあの頃とはだいぶ変わったね」
「まあね。だいぶ太ったし」
「ははは。確かに。苦労してる? 『貫禄出たね』って言えば傷つかない?」
「うーん。微妙に凹むわ〜」
さりげなくこちらを揶揄しながらも親近感を感じさせる言い方に、当時と変わらない彼女らしい優しさが感じられて、決して悪い気分ではなかった。
ちょっと都会的で、洗練されていて。
それでいて、明るく元気者の彼女。ころころっとしたしゃべり方に独特のリズムがあり、当時僕は「可愛らしいリスのような子だな」と思っていた。
その話し方のリズムはこの日も全く変わっていなかった。
彼女とはいろんな話をした。お互いの仕事のこと、結婚をしたこと。そして訳あって今は独りで楽しく過ごしているということ……。
僕は、レモンサワーを飲むたびにほんのり桜色に染まっていく彼女のそばかす顔を見ながら、26年前の出来事を思い返していた。
・ ・ ・
僕らが通っていた小学校は東京都ではあったけれど、西の外れの本当に田舎で、校庭の隣は桑畑と茶畑が段々になってずっと先まで緑のじゅうたんが続く、そんなのどかな場所だった。
そんな小学校5年生の時、長澤さんは都心の方から転校生としてやってきた。
たしか、公務員をしている両親の転勤の関係でこの学校に来たのだと記憶している。
目がくりくりとして可愛らしく、そばかすだらけだったけど、そのそばかす顔は日の光にきらめく水面のような笑顔に輝いていて、逆にそれがとっても魅力的な女の子だった。
僕ら地元の子は学校では上下ジャージがデフォルトだったけど、長澤さんは都心から来ただけあって、時々春を連れてくるような黄色い花柄のスカートをはきこなしてもいたし、ジーンズと合わせた桜色のトップスのコーデなどもとても似合っていて、どこか都会的な感じがした。
休み時間には奇麗な桜色のカバーをかけた文庫本を静かに読んでいるような長澤さん。それでいて、社交的な性格だったので、クラスの女子の間でも人気者だった。
・ ・ ・
そんな彼女と僕が放課後に遭遇するのは、いつも図書室だった。
僕は、冒険もののリアルな伝記が好きで、南極を探検してアムンゼンに負けたマゼランとか、マッキンリーに消えた植村直己とか、アフリカのジャングルを分け入って奥地の湖を発見して散ったリヴィングストンとかそんな冒険譚を毎日読みあさっては、いつか僕もこんな風に誰も知らないところを旅してみたいと夢想するような少年だった。
長澤さんはいつも僕から見て、右斜め前の席に座り、たぶん文学書だったと思うけど、静かに座ってページをめくっていた。
お互いに本をめくる、ぱらりという音が図書室に音の波紋を広げるように響きあっていたのを何となく覚えている。
ただ一緒の空間でお互いに好きな本を読んでいるだけだったけど、その時間は僕にとって、彼女となんとなく心が繋がっているような、そうでないような、でもたぶんこんな時間はもう二度と来ないだろうな、と思えるほど大切な時間だと感じていて、図書室に行くのが大好きだった。
2月初旬のある日のこと。
クラスで同じ班になった僕と真由美ちゃんは図書室の掃除係を仰せつかっていた。
図書室に漂う古い本の香りを感じながら、本棚と本棚の間をほうきで静かに掃いていく。
図書室の窓の外には葉を全て落としたイチョウの木が木枯らしに揺れていた。
そして、少し前に降った雪が茶畑のところどころできらめき、冬の装いを醸し出していた。
僕はその様子に少し見とれてしまっていたようだ。
不意に長澤さんの声がした。
「関谷君、何見てるの!」
ちょっと強い口調で、彼女は僕を呼び止めた。
掃除をさぼっていた僕は怒られると思って、カメのようにすこしだけ首をすくめた。
すると真由美ちゃんはそばかす顔を少し僕に近づけると、くりっとした目でしっかり僕の方を向いて、こう言ったのだ。
「私は君のそういうところ、すっごくいいと思うよ」
その言葉を最後に、真由美ちゃんはきびすを返すと風に吹かれたイチョウの葉のようにあっという間に本棚の間を走り去ってしまった。
右手にほうき、左手にちりとりを持った僕は、呆然と立ち尽くしていた。
彼女が走り去った後には、大きな窓から午後の陽が差し込み、枝だけになったイチョウが風に揺れていた。
彼女の笑顔は午後の日差しのように暖かだった。
・ ・ ・
その4日後、僕らの所属する6年3組の教室で事件が起きた。
「うわっ、何すんだ? ぎょわっつ、痛ぇーーーー」
国語の授業中だった教室に、野球大好き少年だった岩木くんの叫び声が響きわたった。
先生の真正面、1列目の席だった僕がそのあまりにも悲痛な叫びに思わず振り向くと、4列目に座っていた岩木君の額からみけんにかけて2本の真っ赤な血がだらだらと流れている。
岩木君の隣の席には、長澤さんが、鉛筆をグーの手で握りしめた腕を頭上にかかげたまま静止している。
その鉛筆の先は、見事にぽっきりと折れていた。
彼女の表情は日だまりのようだったあの時の笑顔はなく、吹雪のなかで獲物を狙うハンターのような目をしていた。
僕も含めていったい何が起きたのか分からなかったクラスメイトたちが、事態を飲み込めたのはその15秒後くらいか。
くりくり坊主頭だった岩木君の頭のてっぺんに鉛筆の先が見事に刺さっていたのだ。
静まりかえる教室。
まったく何が起きたのか、誰もが戸惑う中、岩木君は先生に抱きかかえられながら保健室へと連れ去られた。
ものすごい形相で岩木君をにらんでいた長澤さんは何事も無かったかのように、国語の教科書をぱらりと開いて静かに見つめていた。
僕は狼狽した。
長澤さんがあの一瞬で見せた、鬼気迫った表情。
小6だった僕は、いったい彼女がどういう理由で、どんな想いで岩木君の頭に鉛筆を突き刺したのか、全く見当も付かなかったのだ。
授業が終わった後、職員室で彼女と話していた担任の先生にその理由を聞いても「それは僕にも分からないよ」と言われ、そこから進展することもなく。
結局、子どもだった僕はその理由をまったく思いつくことが出来ず、少ない脳みそで出した結論がこれだった。
「きっと女の子は豹変する生き物なんだ」
混乱の極みだった。
どうしてあんな天使のようなほほえみと悪魔のような表情を同じ女の子が出来るのだろう。
その答えを探しに僕は図書室へ掛けこんだが、伝記ばっかり読んでいた男子の頭では、本棚に並ぶ多くのタイトルから道を指し示してくれる本を見つけることはできなかった。
・ ・ ・
その1週間後に訪れたのは、小学生なら誰もが気になる大イベント、バレンタインデー。
僕は教室で、長澤さんから生まれて初めてチョコレートを手渡された。
彼女は無言でうつむいていた。そして僕も無言だった。
それを受け取りながら、僕の脳裏には長澤さんが見せた図書室で笑顔と、1週間前の事件の時の表情がぐるぐると駆け巡っていた。
僕はその時、あの事件の衝撃で、女性というものがいったいどんな存在なのか、どんなことを考えているのか、まったく分からなくなっていたのだ。
照れくささもあったし、その混乱を整理できなかった僕はホワイトデーでお返しを渡す時に、
「君のことはなんとも思ってないから」
という言葉をつぶやいてしまった。
その悲しい言葉は、口から出た瞬間、まるで船をつなぎ止めるもやいをぶった切る斧ののように、淡く繋がっていた2人の間を切り裂いた……のだろう。
卒業まで僕はその答えを知ることもなく、いつしかお互いがそれぞれの道を歩んでいき、その後彼女の姿を見る機会もなくなっていった。
・ ・ ・
同窓会は楽しかった。
2次会も終わり、帰りの駅へほろ酔い加減でみんな一緒に歩いて行く道すがら、僕は長澤さんと並んで歩いていた。
この時間がとても愛おしいような気がして、僕はいつもよりゆっくり歩いていたようだ。少しみんなと離れてしまった。
すると長澤さんがふと、つぶやくように言い出した。
「私ね、小学校の時、すっごく後悔していることがあるの」
「えっ、どうしたの? 長澤さん」
僕は彼女の顔を見た。
長澤さんは少し困ったような顔を僕に見せてこう話した。
「岩木君の頭に鉛筆刺したことがあったよね……」
「あった。そんなこと。あれ、教室中みんな凍り付いたよ」
さっきまで考えていたことが話題に出て僕は不意を突かれ、あまりにも無粋な言葉が出てしまった。怒られるだろうか?
カメのように首をすくめた僕の正面に長澤さんはくるりと身を翻し、少し間をおいて、こう言った。
「関谷君、何言ってるの!」
長澤さんはちょっと強い口調でそう言うと、いたずらっぽく、昔のままのころころっとした口調でこう続けた。
「相変わらず君は鈍いなっ。あれはあのとき、岩木君にずっとからかわれてたの。『長澤さん、関谷くんのことずっと見てるね。好きなんでしょー』って。だから思わず『えいっ』って。その時のぽか〜んとした君の表情、忘れてないよ」
いたずらっぽくそう言うと、そばかすの残る顔ちょっと桜色に染めて、笑った。
「なんであんなコトしちゃったのかな。ほんとバカだった……」
そういう彼女を目の前に、僕はまた小学6年生の、あのチョコをもらった時のように固まって、頭の中は混乱の極み。考えがぐるぐると走り回っていた。
『え、あの行為は……?』『なんでいま僕にそんなことを話すの?』『じゃあ、あのとき、僕がもっと素直だったら?』……。
26年の時を経て、長澤さんの桜色の笑顔はまた僕を困惑させた。
少し前髪をかき上げた彼女の前を、どこからか舞ってきた桜の花びらがひらひらと通り過ぎていく。
「長澤さん、今でも本は好き?」
僕の口から出たのはその言葉だった。
「うん。結構好きだよ。そういえば君も結構本読んでたよね〜」
長澤さんはそう言うと、
「君の読んでる本、教えて欲しいな」
と、スマートフォンを操作してSNSの画面を僕に見せて、そばかす顔で微笑んだ。
・ ・ ・
この後、僕と長澤さんとの間がどうなるか、は別の物語になるのだろう。
でも、いつか、また。
彼女と一緒に本を読む時間を過ごせるならば、この間知った、京都にあるカフェのような素敵な本屋でゆっくり時間を過ごそう。
そして、読んできたあまたの本のこと、そして考えてきたことを京都の街を歩きながら少しずつ話しをしていこう。
素直になれた今、26年分の距離を少しずつ、少しずつ縮めていきたい。
本をめくる紙の音と本の放つ素敵な香りに包まれながら。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/fukuten/33767
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」2017.1.27 OPEN
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】
天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。













































































