よろこんで虫になる《週刊READING LIFE vol.75「人には言えない、ちょっと恥ずかしい話」》
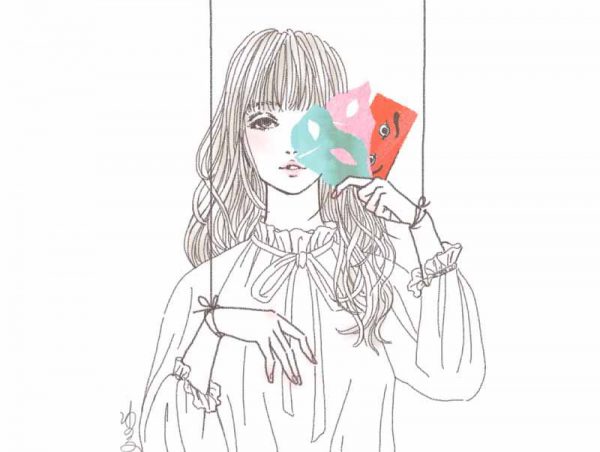
記事:綾 乃(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
物語を書く人には空想力があり、度が過ぎると妄想癖となる。
妄想癖が激しいと、理解に苦しむ友人は去り、社会に出て困ることがある。
私も妄想癖がひどいので、友人は少なく、勤めている会社でも出世とは無縁だ。しかも私の場合、書いている小説が、誰からも評価されないときているから、余計にかなしい。
でもここまでなら「ああ、気の毒ね」で済む。問題はこの先だ。
私は、その誰からも評価されない自作のキャラクターに振り回され、取りつかれてしまうのだ。
例えば、こうだ。
長いこと、私は自分の性格を小心者だと思っていた。
いつも人の顔色をうかがい、何をするにも他人の目を気にし、できないことや言えないことが多く、そのくせそれを必ず後悔する。
そう自己分析していた。
しかしその間は、今考えると、ひ弱な主人公ばかりを書いていた。いじめがきっかけでひきこもりになる中高生とか、首から上をなくして自信無げに旅をする人の話とか。
無意識のうちに、私は自分で作りだしたキャラクターになって、小さく丸まり、細々と生きていたわけだ。
なんと、無駄に日々を送ってしまったことか。
だがある日、何を思ったか、俺様キャラの主人公を書いた。
自信家で頭は切れるが、他人のことを顧みず、蹴落としてナンボと思っている男だ。
自分にはない性質が満載で、よくもまあ、これほど傲慢になれるものだと思いながら、セコい努力を積み重ねて他人を出し抜く彼の性格を、案外楽しみながら書いた。そのことは今でもよく覚えている。
そうしたところ、気づくと自分の性格も図々しく、横暴になっていた。
自分はできる、と変な自信がわいてきて、思考も鋭くなった気がした。
考えだけでなく、行動にも変化が現れた。混雑している道で、他人に構わず、我先にと闊歩するようになった。
それまでは、通勤で利用する乗換駅では小さくなって歩いていた。それでも、すれ違う人々にぶつかられ、痛い思いをすることが多かった。
それなのに、いきなり、人の行き来が激しいコンコースで、ガツガツと早歩きを始めたのである。
無謀である。血を見るかもしれない!
そう心が警告をした。
だが結果は、誰とも接触しなかった。しかも、その突進ぶりは、妙に板についていた。
「人は石垣」と言った武田信玄みたいに、「人はパイロン」と心で呟きながら、サッサッと風を切り、立ちはだかる人をよけていた。
これには自分でも驚いた。
一体何が起きたのかと怪しんだ。
その時はまだ、どういうわけで自分がいきなり図太くなったのか見当をつけられないでいた。
けれども私はその時、自分が作った傍若無人キャラの彼になりきり、世界を謳歌していたのだ。
「自分は今、そのキャラになりきっている」
そうわかって演じられるのであれば、それはそれで素晴らしいと思う。
さらに、置かれている場面によって、キャラを使い分けることができれば、物事に臨機応変に対応できるスマートな人間になれる。鈍くさい私にとっては、夢のような話だ。
自分が生んだ登場人物に助けられて、楽しく幸せに一生を過ごせるだなんて、クリエイター冥利につきるではないか。
しかし私の場合、そうはならない。演じている、という意識がないのだ。
書いているうちに、心や行動がその人物と同一になってしまうだけなのだ。
まるで擬態だ。虫が葉っぱそっくりに化けて、いつのまにか葉っぱと同一化する、あれだ。
カモフラージュに成功して、天敵から逃れられることはいい。けれども下手をすると、そのまま雑草と間違われて、引っこ抜かれてゴミ袋にポイっとされる可能性だってある。
なりきりすぎて、「自分」が見えなくなる私に、本来の使命を忘れ、引っこ抜かれて捨てられる虫の姿が重なる。
それでも私の擬態はとまらなかった。
そうしてようやく、自分の性格が書くキャラクターに乗っ取られているのではないかという疑いを持ち始めた。
それは、同性に思いを寄せ始めた時だった。
それまでの私の恋愛対象は異性だけだった。私は女であるので、好きになるのは男性ということだ。
それは結構、頑なだった。
思春期の女子の中には、同性の格好いい女子に憧れる子もいる。とても自然なことだ。
中学時代の私の友人も、同じ学年にいた高身長で凛とした、同性のKさんのことが「好きなの~」とわざわざ私にのろけていた。しかし私はふーんとしか思わなかった。
「ベルサイユのばら」がクラスで大ブームになった時も、大半の女子がオスカルに熱をあげたが、私はアンドレ一筋で、少数派だった。オスカルは確かに格好よかったかもしれないが、同性というだけで、興味を抱くことができなかった。
つまり、幼い頃から私の恋愛対象は男性で、それはずっと変わらない。そう思っていた。
ところが、である。
ある日突然、私は同性が気になり始めた。
相手は私が勤務する会社の先輩だ。
10年近く同じフロアで働いていたが、それまでは、まったく何も感じていなかった。
でも、急に彼女のことをちらちらと視るようになり、彼女のことばかり考えるようになった。
そうして思いはどんどん募り、先輩を見れば見るうち、ふっくらとした体型や乙女な性格がかわいらしく見えてきた。
彼女から声を掛けられると幸せな気分になり、そのふくよかな身体を抱きしめたら柔らかいだろうなぁと、先輩に対して失礼なことまで想像まで抱くようになった。
それから、彼女が好きだと言っている同じ会社の男性に対し、「私の方があなたへの理解があるのに」とナゾの敵対心まで持つに至った。
これには私も戸惑った。
それに、私の熱い視線の対象は、会社の先輩だけにとどまらなかった。
街で必死に歩いているコロンとした体格の女性を見つけると、守ってあげたい……と思うようになり、気づくと目で追っていた。
女性への思慕が段々エスカレートしていった。
これは一体、どうしたことか。
私は生まれてこの方ずっと、男性しか好きになったことがなかったのに。
LGBTの人たちが、自分のセクシュアリティを認識する年齢は、人それぞれであるしい。幼稚園の頃に違和感を持ち始める人もいれば、学生時代に自覚する人もいる。また異性と結婚して家庭を持った後に気づく人もいる。経済評論家の勝間和代氏も、自分が好きなのが女性だと気づき、同性パートナーと同棲を始めたのは40代の時と言う。
だから、いい年をしている私が、本当はレズビアン、もしくはトランスジェンダーであると、今更気づいても、何も遅くはない。
そう、疑い始め出した。
ただ、気になる女性の体型が、みな同じでふくよかなことである。
私は今まで、スレンダーな女性にあこがれていた。なのに、である。
そこでようやく気がついた。
その時私は、女性が女性を好きになる話を書いていた。
そして彼女が好きになる同性は、必ずふっくらとしていた。
私が目で追い求めた女性と同じではないか!
私は知らないうちに、自分でこしらえたキャラクターそのものになり、感情や行動まで振り回されてしまっていたのだ。
創造主であるはずの作者が、作中人物に憑依され、操られるとは、なんとも情けない話だ。
しかも、その話を書き終えた後も、私の女性への思いはしばらく続いた。
乗り移られたまま、虚構のキャラにずるずると引きずられていたのである。
それは実はよくないことなのだ。
漫画「ガラスの仮面」の中で、「嵐が丘」の舞台を主人公が演じるシーンがある。
「嵐が丘」はキャサリンとヒースクリフの悲恋物語だ。子供時代のキャサリンを演じる主人公・北島マヤが、同じく子供時代のヒースクリフを演じる真島という男子を相手に、情感を込めて熱演し、そのせいで真島がマヤのことを好きになってしまう。
ただ、マヤは舞台が終わると先ほどまで劇の中で大恋愛をしていた相手のことを何とも思っていない。一方、ヒースクリフを演じた真島は幕がおりても相手のことを忘れられず、マヤに告白するが拒絶され、思いを引きずる、という話だ。
漫画では、男のことを忘れて、しれっと素に戻っているマヤをプロとして描いている。
そうなのだ。
役が終わった後も、登場人物になりきったまま、オンとオフを切り替えられないのはシロウトなのだ。
そうなると、自作のキャラに性格を乗っ取られ、物語を書き終えても、いつまでもそのキャラにずるずると引きずられている私は、プロには程遠い、ということなのだろうか。
そう考えると、自分の小説が誰からも認めてもらえないのも道理だと、妙に納得がゆく。
自分で生んだ虚構の人物を操るはずが操られてしまうとは、私はよほど単純にできているのだろう。
なんとも情けなく、恥ずかしい話である。
だが、普段の私の生活は何の変哲もない、地味で無味無臭の平凡なものだ。それがキャラクターになりきるおかげで、風味豊かな人生になるのであれば、私はよろこんで擬態する虫になろうと思う。
だって私は強くもなれたし、恋愛もできた。
特に身近な人への恋愛感情は、本当に久しぶりだったため、距離の近さで心のときめきも痛烈だった。学生時代の甘酸っぱい思い出をリピートしたようで、身も心も浄化された気がした。
それに女性に思いを寄せるという初体験もできた。いつになっても人生初の経験は世界がぱあーっと開けて、いいものだ。
ただ、ひとつだけ気になることがある。
また漫画の話になるが、巨匠・楳図かずお氏の「恐怖」という作品集の中に
「とりつかれた主役」という短編がある。
高校の演劇部に所属する男子高校生が普段は大人しいのに、メイクをすると、その役の気持ちになり自然に演じることができると言うのだ。
話の中で、彼は、演劇部の公演で病気になった女子のかわりに女性メイクをして、代役を見事に果たす。ここまではいい話だ。
しかし物語のラストシーンで、彼は仲間からふざけて歌舞伎の荒事のような化粧を施される。そうしたところ、性格が荒ぶり、人を襲ってしまうと言う落ちだ。
だから、というわけではないが、私はいまだに根っからの殺人鬼の話をうまく書くことができないでいる。
□ライターズプロフィール
綾 乃(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
小説家を夢見る広島生まれの東京在住者。
毎年、3月31日締切(当日消印有効)のとある新人賞に応募するのを目標としているが、書き終わるのはいつもぎりぎり。
今年も日付が変わるほんの少し前に、郵便局の「ゆうゆう窓口」に駆け込んだ。
しかし新型コロナウィルスの流行による営業時間短縮となっていて、すごすごと帰宅した。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/103447















































































