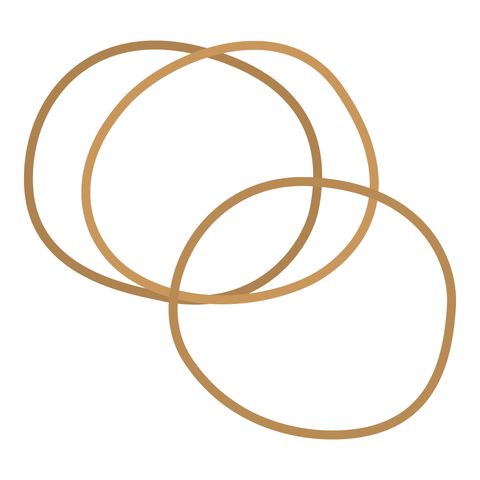パワースポット、りんちゃんの純情

記事:諸星 久美さま (ライティング・ゼミ)
「川上さん、どこ行くの?」
「あ、えっと、バレーボールです」
「バレーボールって、どこでやってんの?」
「小学校の体育館です」
「ふ~ん。それって、楽しい?」
「あ、はい、まぁ……」
「ふ~ん」
その後、30年来の友人になるりんちゃんとの初めての会話は、私が一方的に進め、同級生だというのに、りんちゃんは敬語で返すという形で終始続いた。
「カバンの中、見せて」
「え? あ、はい……」
りんちゃんはカバンをアスファルトに下ろし、ジーっとチャックを開けて、私のぶしつけな質問に答えてくれた。
赤いライン入りのアシックスのバレーボールシューズに、白いサポーター。水筒に、タオル。
「これだけ?」
「これだけです」
「それだけあれば、私もバレーボールできる?」
「たぶん……」
「ふ~ん、ありがとう。じゃあね」
ぺこぺことお辞儀をして練習に向かって行くりんちゃんに手を振り、母が帰ってくるのを待って、
「お母さん。私、バレーボールしたい」
と告げたのは、4年生の5月頃だったと思う。
同じ小学校に通う同級生のりんちゃんとは、一度も同じクラスになったことはなかった。
4年間、一度もだ。
それでも彼女に声を掛けたのは、彼女の持っているカバンに惚れたからだった。
60年代~70年代に一世を風靡したらしい、マジソンバック。
色が白く、背の小さなりんちゃんの肩にかかる、白地に黒の英語が書かれたそのバッグは、私にとって、どうしても触れてみたいと思えるほどに心ときめく一品だった。
そのバッグを近くで見たいという一心で、私はりんちゃんに声を掛けたのだ。
母に報告した次の日には、街にあるスポーツショップで、りんちゃんと同じアシックスのシューズとサポーターを父に買ってもらった。
次いで、りんちゃんと同じカバンを探したが、街の小さなスポーツショップに、それは見当たらなかった。
バレーボールをすることになれば、あの素敵なバッグを手に入れられる、と期待していた私は、悔しくて、唇を尖らせながら帰宅した。
けれど、家に着き、サポーターを両膝にはめ、紐を通したシューズを履いてみると、俄然テンションがあがり、りんちゃんと同じバッグが欲しいという欲求は、あっという間に私の中から消えていった。
りんちゃんとは、その後6年間バレーを通して親密になった。
正月の三が日以外はほぼ毎日練習という環境下において、親よりも長く時間を共有する思春期の女の子同士が仲良くなるのは、それほど難しいことではなかった。
*
高校卒業と同時に、某化粧品会社に勤め始めたりんちゃんは、小学校の4年生当時、私が初めて声をかけた時の、清楚さとか、おしとやかさだという面影を抹殺しながら、すくすくと変貌を遂げていった。
美容部員たるもの、常に化粧はばっちりが鉄則。
爪のケアも、髪のケアも怠らず、香水はマストで、浴びるように振りかける。
家のベランダに出る際も、季節問わずに日焼け止めを塗りたくり、太陽の出ている日にはサングラスは欠かさない。
そんなりんちゃんの徹底ぶりに、同じバレー部つながりのY子やE子は、呆れ気味に、
「ねぇ、りん。頬のシャドーが濃すぎて、デーモンみたいだよ」
だの、
「りん乗せると、一ヶ月くらい香水の匂い消えないから、もう私の車乗らないでね」
などと告げるのに、りんちゃんはまったく意に介さず、
「また、また~」
と、丸っこい指をピンと揃えて手のひらを上にくるりと返し、
「YちゃんとEちゃんも綺麗にしてあげようか?」
と、営業スマイルを浮かべるのだった。
そんなりんちゃんとの面白エピソードは数々あるのだが、
「あぁ~、その場にいたかったな~」
と悔しい思いをした日のことを、今回はここに記そうと思う。
*
時は20年ほど前。
成人式を終えて冬が過ぎ、ソメイヨシノが散って、八重桜が咲き誇る頃のお話である。
*
「ねぇ、くみ~。今度の土曜日空いてる? 一緒に行って欲しいところがあるんだけど」
「あ、無理、バイト」
「え~、じゃあ、Y子ちゃんは?」
「いいよ」
「ありがと~う」とY子に抱きつくりんちゃん。
話を聞けば、最近りんちゃんに、ある男の子から、どうしても会って話がしたいという電話があったそう。
電話の相手は、小学校の同級生とのこと。
名前を聞いても、顔の輪郭すら思い出せずにいるところ、
「四角い顔のあいつでしょ?」
とY子。
「四角い顔はどうでもいいんだけど、話があるって、やっぱり告白とかかな? 『何かの勧誘?』って聞いても、違うって言ってたし」
とウキウキ気分のりんちゃん。
「そうじゃな~い」と、適当な返事を返したY子が、
「でも、告白なら、私行く必要なくな~い?」
と、ごもっともな意見をりんちゃんに向ける。
「なんか、あっちも2人でくるみたいで~、『ぜひ、お友だちも』って言われてるし。Y子ちゃんも、その子と仲良くなれるかもしれないしさ~。ね、お願いっ」
りんちゃんはそう言って、両手を鼻の前で合わせて首を傾げた。
*
そして、りんちゃんとY子は、約束通り、その週の土曜の昼過ぎに、待ち合せ場所のファミリーレストランに向かったのだ。
*
バイトが終わり、携帯を見ると、Y子からの着信アリ。
すぐにY子に電話をかけると、耳元にヒッ、ヒッ、ヒッと、Y子の声。
「何? 泣いてるの?」
と尋ねる私に、
「くみ~、泣いてるよ~、泣いてる~。ヒッ、ヒッ、話は……、ヒッ、ヒッ、着いたらするから~、とにかく、ヒッ、ヒッ、急いでね~、ウヒャッ、ヒャッ、ヒャ~」
爆笑とともに電話は切られ、置いてきぼり気分の私は、ファミリーレストランへと急いだ。
着いてみると、店外から見てもりんちゃんが酔っているのが分かる。
色白のりんちゃんは、お酒をのむと、頬を綺麗なピンク色に染めるのだ。
そんなりんちゃんの隣で、Y子が手を叩きながら、涙を流して笑っている。
彼女たちのテーブルに、メンズ2人の姿は見えない。
「どうしたの?」
そう言って席につく私に、
「聞いてよ、くみ~」
と、りんちゃんの憤慨気味の声。
状況がつかめぬまま、ドリンクバーでアイスティーを調達して席に戻ると、私は、耳を傾ける準備を整えた。
話はこうだ。
*
土曜のランチタイム。
緊張気味に、ひとつのテーブルについた4人は、各々自己紹介を始め、それなりに、和気あいあいと小一時間を過ごした。
そして、ランチを食べ終わり、さて本題へ、という時間が訪れる。
「初めてだから、緊張するな……」と四角い顔の男。
「大丈夫、自信をもって」と励ます、付き添いの眼鏡男子。
やっぱり告白だね、と、目配せをし合うりんちゃんとY子。
「私、席外そうか?」と、気を利かすY子。
「いや。むしろ2人の方がいいよ」と眼鏡男子。
しばしの沈黙。
高鳴るりんちゃんの鼓動。
ごくりと、唾を呑み込む四角い顔に、頷いて見せる眼鏡男子。
「あのですね……」
「えっと……」
「川上さんは……」
「神様を信じていますか?」
「へ?」と「え?」の混ざりあったような声が、りんちゃんの口から洩れる。
「いや、僕も、神様なんて信じてなかったんです……。でも、彼に会って……」
と、四角い顔は眼鏡男子に視線をちらりと送る。
「本気で考え方が変わったんです。導きを受けたというか、自分の人生が開けたというか。それで……、成人式で川上さんを見かけて、何となく、川上さんにも、是非この話をしてあげたいなって本気で思って、川上さんのためになるかなって本気で考えて、それで、連絡させてもらって……」
ピンと張りつめる空気。
小刻みに震えだす、りんちゃんの丸めた拳。
数秒後、フロアに響きわたるY子の爆笑に、
「すみませ~~~ん」
と、店員を呼ぶりんちゃんの声が重なる。
いそいそと駆けつけた店員に、「これと、これと、これと。あと、これも。グラスは2つで」
と、メニューブックを指さすりんちゃん。
明らかに変わった空気に、目を泳がせる四角い顔と眼鏡。
凍りついたテーブルの中で、1人爆笑のY子。
「おまたせしました~」
テーブルに赤ワインと、グラスが2つ置かれる。
りんちゃんは、2つのグラスに並々とワインを注ぎ、1つをY子の前に置くと、もう1つを一気に飲み干した。
ふぅと息を吐きだして髪をかき上げ、頬杖をついて男たちを見据えるりんちゃん。
「で? そんなこと話すために、今日私を呼んだわけ?」
りんちゃんの静かな声が、四角い顔に向けられる。
「いや……、え? あ、はい……」
「チッ」
りんちゃんは、四角い顔を一瞥したまま舌打ちをすると、
「じゃあ何? 成人式の私は、神の救いが必要そうな女にでも見えたってわけ?」
と、初めて声を荒げた。
怯んで肩をこわばらせる四角い顔。
その横で、おたつく眼鏡。
「もし私が、あんたのその話に耳を傾けて、あんたと同じように、その神様を信じるようになったら、あんたの位か何かが上がるわけ?」
「……」
「私のためとか何とか言って、結局は、あんたの願望だかノルマだかを満たすためじゃないの?」
「……」
「私はね、自分の目で見て、納得したものしか自分の中に入れないことにしてんのっ。何年も会ってなかったような、知り合いとも言えないあんたの誘いにのった私も私だけどさ、本気で、自分が信じてるものを誰かに教えたくなるのってさ、その人を十分に知り尽くした上で、その人がそれを必要かどうかって散々考えた上で、切り出すもんじゃないの?」
「……」
りんちゃんの説教に、ぐうの音も出ないメンズ2人。
りんちゃんは、手酌でなみなみに注いだワインを一気に飲み干すと、
「本気、本気って軽々しく言いやがってよぅ」
と、低い声で言い放った。
口調の変わったりんちゃんを前に、目を見開く2人。
「じゃあいいよ、もしここで、あんたが空中浮遊とかして見せたら、その、何とか教とやらに入ってやるよ。私は本気の覚悟で言ってるんだから、あんたも本気見せてみろよっ。ほら、浮いてみろよっ。もちろん胡坐だかんなっ!」
「いや、りん、それ、違うやつだから……」
「Y子ちゃんは黙ってて」
「は~い」
「浮いてみろって、言ってんだろーがっ!」
りんちゃんの剣幕に、見る間に蒼白していく2人の男と、隣で爆笑を続けるY子。
そうなのだ。
りんちゃんが、浮かれ気分で向かった男たちとの会合は、愛の告白ではなく、宗教(教祖が空中浮遊するあれとは別の、全く聞いたこともないもの)の勧誘だったのだ。
*
泣きはらした目で、一部始終を話してくれたY子に、
「で、そいつらどうしたの?」と尋ねる私。
「さっき、これ置いて、頭下げて帰っていったよ」
テーブルに置かれた、数枚のお札を指さして、Y子は、目じりの涙をおしぼりで拭う。
「ま、これ全部あいつらのおごりだから、くみちゃんも何かたのんで~」
と、メニューブックを差し出すりんちゃんは、普段の穏やかさを取り戻している様子だった。
*
その後、合流したE子に、また泣きながら、一部始終を語り聞かせるY子。
「っていうか、成人式のりんを見て、っていうのは嘘だね」
全ての話が終わったところで、確信気味にE子が呟く。
「だってあの日、あの会場で、一番化粧が濃くて、頭もモリモリで、どうみても成人には見えない風貌でぎらついてたの、りんだったじゃん? デーモンシャドーに、花魁みたいに首元もはだけてさ。あれ見て、宗教の勧誘を試みるやつがいたら、そうとう足りない奴だよ」
人差し指でトントンとこめかみを指すE子に、そうだ、そうだと、涙目で頷くY子。
「私の推測だけどさ……」
と、E子は前置きをし、
「小学校のりんの印象のままで電話してきたんじゃない? あの頃のりん、今とは180度別人じゃん?」
「確かに……」と賛同を示すY子。
「あんた、変わり過ぎたんだよ。ある意味、あっちだって被害者じゃん。あんたの豹変ぶりに翻弄されて、人前で、散々暴言はかれて、こんなお金払わされてさ」
「E子ちゃん、相変わらず厳し~い」
そう言いながらも、りんちゃんはE子のグラスにもワインを注いでいる。
そんな会話をぼんやりと聞きながら、私は、初めてりんちゃんと会話した日のことを思い出していた。
おどおどと私の質問に敬語で応えていた、小さなりんちゃん。
おしとやかとか、清楚とかを連想させるような、色白の女の子だったりんちゃんは、確かに、押せば容易になびくような儚さを漂わせていた。
でも……と私は思う。
風貌は180度変わったとしても、こんなことに、心をアップダウンさせる純粋さの中に、あの頃の、小さなりんちゃんが垣間見えるのだ。
りんちゃんは、四角い顔の電話から、ささやかながらも心をソワソワと動かしただろう。
洋服も新調したかもしれないし、その日の化粧は、いつもより時間をかけてしたかもしれない(だとしたら、もうお面(おめん)レベルだが……)。
曖昧な誘い方で、りんちゃんの純情を翻弄した四角い顔に、今更怒りがこみあげてくる。
電話口で詳細を語れない誘いなど、本人すら、その勧誘にどこか後ろめたさを抱いているのではないか? と鼻息が荒くなる。
「そんな奴らのお金で、食べたり飲んだりしたくない」
ぼそりとそう呟いた私に、3人の視線が集まる。
しばしの沈黙。
「も~、くみ真面目~」とY子。
「ウブ過ぎる」とE子。
「くみらしいね」
と、りんちゃんは私を見つめて微笑み、次の瞬間、
「でも、これはモニター料としてもらったものだから、気兼ねなく~」
と、いつもの営業スマイルを見せたのだ。
その瞬間、私は初めて、りんちゃんに暴言を吐かれて怯えていたであろうメンズ2人に、僅かな、憐れみと同情の混ざりあった感情を抱いたものだった。
*
「私はね、別に宗教信者をバカにしてるわけじゃないの」
りんちゃんが、手酌で自分のグラスにワインを注ぎながら呟く。
「日本に生まれた身としては、神を崇めるって行為は、自分の中で、必要な時に必要なだけすればいいって私は考えてるの。だから、それを勧誘して広めるってことが、なんか、違うかな? って思うんだよね。もちろん、悩みを抱えた人が、目に見えない何かを信じることで救われていくことってあると思うし、そうしている人たちを否定する気持ちはサラサラないんだよ。でも本来はさ、病院だって、自分の足で選んで、そこの門をたたきに行くっていうのが常だし、『あ、ここの先生嫌だな……』とか思えば、自由に変えられるわけじゃん? でも、宗教ってさ、なんか一度入ったら抜け出せないっていう印象強いし、神様に近づくためにしなきゃいけないことが、何だかんだ沢山ありそうだし……。完全に偏見かもしれないけど、粘着質な空気間が、その集った人たちの間に浮遊してるような気がするんだよね。だから尚更、自らそこに足を運んで集った人たちだけで、存分に崇めてればいいじゃんって思うから、やっぱり、知り合いとも呼べないような誰かを勧誘するって、なんか違う気がするんだ。……あ、これって、完全に私の個人的意見だから、真面目に聞かないでね」
「うん、もう、途中から聞いてない」とY子。
「ねぇ、ピザ頼んでいい?」とE子。
ははっ、とりんちゃんは高い笑い声を上げると、
「私は、こういう乾いた感じが好きなのよ~。ねぇ、くみ? 本当はこういう場所にこそ、神様っている気がしない?」
と、私を見つめてくる。
「そうかもね」
私は苦笑しながらそう答えると、E子にメニューブックを手渡した。
*
そんなりんちゃんと、いまだ交友関係を続けている理由は、私がりんちゃんの潔さに惚れているというところがあると思う。
彼女はあの時、怒りのままに相手に暴言を吐いたけれど、そのことを、その場にいなかったどこぞの誰かに、安易に吹聴することは一度もなかった(E子と私はどこぞの誰かではない)。
無論、その話をすれば、自分の浅はかな心情も吐露しなければならない、ということもあるかもしれない。
けれど、振り返ってみれば、それまでも、りんちゃんは、怒りはそのままその対象にぶつけるタイプで、ぶつけてしまえばそれで終わり、という潔い一面を持っているということに思いあたる。
しかも、怒りを放出するのはいつも一人。
意見を言うのに誰かを誘うことは皆無で、いつだって一人で真っ向勝負だ。
みんなが言うから。
みんなが、そうしてるから。
そんなちんけな判断は、いつも自分と対話し、自分の心のままに動いている彼女の中には存在しない。
そう思うと、小学4年生の時に、学年でただ一人バレー部に所属し、一人で練習に向かっていた姿にも納得がいく。
嘘がなく、ユーモアたっぷりの彼女は、私の大切なソウルメイトで、私は、彼女と過ごした後に、ほとほと疲れた……というような経験を、30年間一度たりともしたことがない。
疲れるどころか、沢山笑って、そんな考え方もあるんだ~と驚いて、解放された心持ちで彼女に手を振ることが、毎度と思えるほどに、彼女は私のパワースポット的存在なのだ。
外国人の夫とともに海外に移り住み、そこで男の子を産んだりんちゃんとは、数年に一度、彼女が帰国する時にしか会えなくなってしまったけれど、会えば、秒殺で心を開ける相手だということには変わりない。
*
「くみ~、アリゾナってさ、蛇がいっぱいいるの。種類多すぎて覚えられない位。だから噛まれる人も多いんだけど、噛まれたらどうすると思う?」
「急いで病院?」
りんちゃんは、白く短い指を私の前でカチカチと横に振る。
「その前に、その蛇を捕まえて、殺して、病院に持ってくの。『この蛇に噛まれました~』って。迅速に正しい対処をしてもらうため、というか、命を落とさないために、そうしなくちゃいけないんだって」
「過酷だね。でもどうやって?」
「尻尾を掴んで……、こう」
りんちゃんはタオルをねじって蛇に見立て、大きく振りかぶって床にぶつけた。
「……えげつないね」
「でも、良いところだから、遊びにおいでよ~」
数年前に会った時に、りんちゃんはそう言って笑っていた。
その話が真実であるかどうかは分からない。
写メを撮って、急いで退散が安全なんじゃないかとも思う。
けれど、時折心が沈んでしまう時などに、異国の地で蛇に噛まれたりんちゃんが、命を守るために、蛇の尻尾を掴んで地面に叩きつけるシーンを想像すると、私は、何となく元気を取り戻せそうな気持ちになるから、その話は、そのまま大切に私の中にストックされている。
アリゾナからジョージアに移り住んだ彼女は、めちゃくちゃキュートな男の子を連れて、今週末帰国する。
「ったく、香水臭いよっ」
と窓を全開にして愚痴を言いながらも、E子はりんちゃんを車で迎えに行くだろう。
共有してきた数々の思い出を辿りながら、Y子は、笑い過ぎて何度も涙を流すだろう。
私は、そんな彼女たちをぼんやりと眺めて、「変わらないな」と安堵しながら、ポロポロとりんちゃんが落としていくネタを拾い集めるだろう。
そして、思春期に、家族よりも長く時間を共有した友人たちが生みだす解放感の中で、私は、その頃の私に出会うのだ。
各々の子どもたちが庭を駆け回る声を聴きながら過ごすそんな時間は、私の心を浄化してくれるだろう。
ああ、楽しみでしかたない。
*作中の人物名は偽名です。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、店主三浦のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
【平日コース開講】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ2.0《平日コース》」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜《6月開講/初回振替講座有/東京・福岡・全国通信対応》
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】
【有料メルマガのご登録はこちらから】