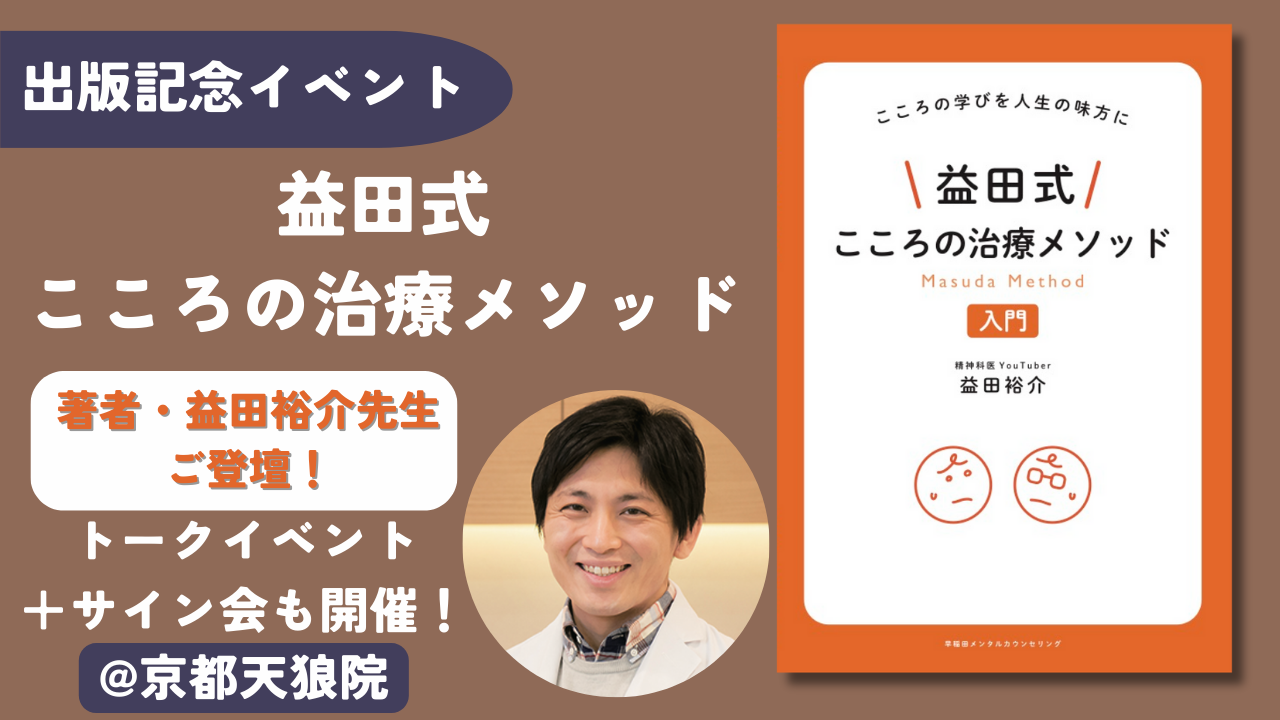一番なりたいものになれなかった私の夢の叶えかた《プロフェッショナル・ゼミ》

*この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【8月開講】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ《日曜コース》」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
記事:ノリ(プロフェッショナル・ゼミ)※この話はフィクションです。
「うるさい!! 私の人生は私のもんだ!」
「親に向かってなんだその口の聞き方は!」
「親だからってなんでも決めていいワケじゃない!」
「予備校にまで行かせておいて、勝手に大学中退とはなんだ!」
「教師になんて、なりたくなかったんだ! 勝手に決めたのはそっちでしょうが!」
「教師に決まっているだろう! うちはずっとそうなんだから。お前もそうなるのが一番の幸せなんだよ!」
「ねえ、ねえ青柳さん、ねえってば!」
パン屋のカウンターの中で、私は思い出していた。はっとして横を見ると、同じシフトの水野さんが、むくれた顔をしている。相当長い間、話を聞いていなかったらしい。
「わ、ごめんごめん」
ぼーっとすると、すぐこれだ。もう、何年も経つのに。今にも唾が飛んできそうな父の赤い顔が、目の前に思い出されてしまう。
「センセイお元気? 昔とてもお世話になって……」
「あら、センセイのところのお嬢さん」
「センセイはいいわねえ。お子さんの将来も安泰で」
道を歩けば、こんな声ばかり。
教師か公務員。いまだにそれが、幸福の条件のように言われる田舎で、私は曽祖父の代から教師の家に生まれた。父と母に至っては、両方が中学の教師をしている。いつからだろうか、もう覚えてもいない。周りの人も、両親も、そして私も、私は将来、先生になるのだと、信じて疑わずに育ってきた。
しかし学校の成績がよくない「センセイのお嬢さん」がたどった道は、地元の国公立大学不合格、予備校で浪人、一年遅れて大学合格、入学するも、ついていけなくなり、一年の夏を待たずに、大学を中退したのだった。
なりたくないけど親が言うから仕方ない。それならそれで、親を恨めば済む話だった。しかし、大学の勉強に失敗した私にとって、教師は「なりたくない」のではなく、「なれない」職業になった。
何もやる気が起きず、昼すぎまで寝て、夕方になると近所をふらふらする私は、狭い田舎の中で、恰好の噂の的となった。すれ違う近所の人や、かつての同級生は、あることないこと私に関する悪事をでっち上げ、人から人へと大きくなって伝わっていった。しばらくは何も言わなかった両親の耳にもそれが届いたのだろう。相談もせずに大学を中退し、何もするでもない私に、とうとう父親がしびれを切らしたのだった。
父と激しく言い争った後、私はわずかな貯金を持って、上京した。とにかくここではないところに行かなければならないと思った。昔読んだ本の中に出てきた駅に降り立った私は、小さなアパートを借りて、近所のパン屋でバイトをした。パン屋を選んだのには特に意味はない。家が近かったから、ということと、いらないパンをもらえるか安く買えるか、しそうだったから。
パン屋は脱サラした店主夫妻が開いたお店だった。昔からの夢だったという。都内にしては珍しく大きなお店で、何人も人を雇い、お客さんも多かった。夫妻は私が、田舎から出てきた、というだけで親切にしてくれた。同じバイト仲間も歳が近い人が多かった。特に水野さんとは同い歳で、お互い一人暮らしをしていることもあり、しばらくすると、部屋を行き来して、ごはんを一緒に食べる仲になっていた。
パン屋の給料は決して多いわけではなかったから、そんなに贅沢ができるわけではない。しかし、毎日のシフトをこなし、パンを買って帰る。毎晩家でパンをつまみながら、図書館で借りてきた本を読みふけるのは、幸せな時間だった。もう、教師になるため、大学に入るための勉強ではない。自分が好きな本を好きなだけ読んでいい。楽しんで読んでいい。
休みの日、街を歩けば、たくさんの人とすれ違った。そのどの人も、私を知らない。「センセイのお嬢さん」と声をかける人も、いない。親が気の毒だとか、負け犬だとか、聞こえるように陰口をたたく人も、いない。私は道端で肩がぶつかっても、電車で足を踏まれても、自分を知らない人がたくさんいることが、こんなにもうれしくて、生きやすいことなのだと知った。
「東京は怖い場所だ」そんなことを言ったのはおじいちゃんだろうか。けれど、そんなことはない。田舎でうまく生きられなかった私は、東京を好きになり始めていた。
「ねえ、青柳さんはお正月帰るの?」
「えっ……私は……帰らないけど」
「そっかー。うちはうるさくてさ、帰らないと。一緒に年越ししたかったんだけど、ごめんね」
「仕方ないよ」
東京には田舎と違って、季節感がない。毎日追われるように仕事するのは楽しかった。そうすれば、田舎のこと、親のこと、自分の過去のこと、嫌なことは全部忘れることができるからだ。
けれど東京にいても、強く田舎を思い出させる季節がある。それが、お盆と正月だ。定休日のないパン屋も、お盆と正月だけは4・5日休む。東京なんだから休まなくてもいいのにと、私は思うけれど、上京してくる人が多い東京だからこそ休みにしなければと、店主が言っていたのを聞いたことがある。そして水野さんも、実家の山梨に帰るという。
私には、東京から帰ってきた娘を迎える正月、というものが想像できない。食べきれないほどのごちそうが出てくるだとか、親戚のおばさんにしつこく見合いを勧められるだとか、本当に困ると言いながら、水野さんはどことなくうれしそうな顔をする。帰りには、たんまり食料やおみやげを持たせてくれるという。こういうのが、可愛がられている娘というのだろうか。私にはよくわからないのだった。
「これ、おみやげー!」
年末に買い込んで冷凍しておいたパンがなくなった頃、やっとパン屋は店を開けて、いつも通りの毎日が帰ってきた。実家でゆっくりできたという水野さんは、少しふっくらしたように見えた。
東京に出てから3度目かのお正月だった。今年のお正月も、実家に帰らず、連絡もせず、もちろん連絡がくることもなく、無事に過ぎた。しかし私は、正月を過ぎても、なんだかもやもやした気持ちが晴れることはなかった。水野さんがくれた、きな粉のかかったおいしいお餅をほおばりながら考えていた。
このまま私は一生、実家に帰らずに、東京で一人でお正月を迎えて、水野さんのくれるお餅を食べるだけなんだろうか。本当にそれでいいんだろうか。
『ライター募集! 未経験でも大歓迎』
ああ、そうだった。
そんな一文を、何気なく手に取った求人情報誌の中に見つけたとき、思い出した。
「先生になる」
いつしかそう自覚したとき、真っ先に思いついた教科は、国語だった。
母は数学、父は社会の教師だった。ならば、どちらかの教科ならなじみも深いはずだ。しかし私はどちらに惹かれることもなく、いつしか「国語」の教師を目指していたのだった。
小学校のときから、国語の授業が好きだった。知っている昔話や絵本で読んだことのある物語、魅力的な詩。漢字の書き取り、作文、読書感想文、国語辞書の引き方。私にとって、国語の授業は「好き」がたくさん詰まっていた。それは中学になって、「現代国語」と「古典」にわかれても、変わることはなかった。
親元から離れ、田舎のしがらみからも離れ、そうして「先生」という夢のラベルがはがれた今も、国語、言葉への気持ちは、まだ変わっていなかったようだ。
ライター。
これなら少しはカッコがつくかな。
親や地元への言い訳を一切考えていなかったと言えば、嘘になるだろう。それでも私には、自分で自分の仕事を決める、ということが、とても大切なことだった。
さっそく履歴書を送ると、「未経験歓迎」はウソではなかったみたいだ。私はすぐに求人広告をつくる編集社へと入社することになった。
私は慌ただしくパン屋を去ることになり、店主夫妻は、驚き、引き止めながらも、自分で決めた仕事だと、応援してくれた。水野さんも寂しいとは言ったが、これで終わりじゃないと自分に言い聞かせるようにして、納得してくれた。
そうして私のライターとしての毎日が始まった。週に一度発行される求人広告の現場は忙しかった。お客様である企業やお店の要望を聞き取り、原稿を制作し、再度お客様に内容を確認して、掲載する。スピート勝負でこなさなければいけない作業が山のようにあった。しかしマニュアルがしっかりしていて、先輩も親切に教えてくれた。なるほどこれなら、未経験でも歓迎なわけだ。
意外に向いていたのかもしれない。初めはページの1/8サイズの小さな求人広告一社を任されるのみだった私が、2年が経つころには、自分よりも早く入社していた人を追い越して、チームのリーダーになっていた。
毎日が充実していた。
親に、家に、決められた仕事ではない。自分で選んだ仕事。自分の「好き」をかなえた仕事。会社は決して大きくはない。ライターも社内に5人しかいない小さなチームだ。けれど私はうれしかった。初めて自分の居場所があると思えた。
しかし、この現状を、胸を張って堂々と実家に報告できるかというと、それは、また、別の問題だった。
「青柳さーん、青柳さん書いたこのコピー、すごく好きです!」
「ああ、ありがとう」
「どうしてこういうのが書けるんですか?」
「書けるっていうか、お客様の要望を聞いて、要望が実現するように書くんだよ」
「すごーい! どうしてこのコピーなんですか?」
「やる気のある人が欲しいって言うから、挑戦的にしたんだよ。このコピー見て、『俺が、私が、やってやろう!』って思うくらいの人を採用したいってこと」
「えー! すごーい!」
「すぐ書けるようになるよ」
メグミは、そんな時に入社してきた未経験者だった。私の書いた求人広告のコピーに感動したのが応募のきっかけだという。リーダーの私は、当然メグミの文章指導をすることになった。とはいえ、マニュアルがしっかりある。スピードが重視される毎週発行の求人情報誌。そこまでライティングのことを知らなくとも、それなりのものは書くことはできるのが現実だ。
しかしメグミは違った。新人教育をすることは初めてではなかったが、こんなにあれこれ質問してくるのはメグミが初めてだった。ライターの仕事がよほど面白いのだろう。コピーやライティングについて、いろんなことを質問してくる。聞かれれば私は答える。それだけの知識はあった。
『心をひっかくコピーライティング』
『広告コピーのキホンのキ』
『思わず読んでしまう文章術』
『伝わる文章を考える』
『あなたの文はここがイケナイ!』
一体、これまで何冊の本を読んできたのだろうか。もう、数え切れない。本屋に立ち寄っては、広告コピーや文章の書き方などの本を片っぱしから買っては読み、読んでは書いていた。
メグミの質問に対しての答えなんて、はっきり言えば、これまで読んだの本のどこかで見つけて、自分で実践してきたことだ。同じ本を読んでいれば、きっと誰でも答えられることだと思う。
けれどメグミはいつも、あれこれ教えるたびに、こっちが恥ずかしくなるくらい大げさなほどのリアクションで感動してくれる。悪い気はしない。それどころか、もっと勉強しなきゃ、なんて、思っちゃうほどだった。そうするうちに、メグミは私のアドバイスを素直に聞いて、どんどん腕を上げていった。メグミの成長は私の喜びでもあった。
「うん、いいね。すごくよく書けてる」
「わー! よかった!」
「そしてあえて言うと、惜しいのは、ここ」
「えっ、キャッチですか」
「キャッチコピーの『あなたは』、の、『は」」
「『は』ですか?」
「ここを『は』から『が』に変えたほうが、もっと『あなた』が、主役の感じが出ると思うんだ」
いつものように、メグミの書いたものを私がチェックして、いつものようにコピーについて話しているときのことだった。
次にメグミが発した言葉に、私はすぐに、トイレに駆け込むことになった。彼女にとっては、いつものリアクションの一つだったのだろう。けれど私には、これまでの人生が、すべて、意味を変えてしまった言葉だった。
あんなに嫌っていたのに。あんなに呪っていたのに。あんなに憎んでいたのに。それなのに。これじゃあまるで、ずっとずっと、素晴らしい人生だったみたいじゃない。もう、誰も恨むことができないじゃない。すべてが無駄じゃなかったみたいじゃない。
ホント、メグミったら、なにを言いだすんだろ。どうしてそんなキラキラした目で私を見るんだろ。困るじゃない! うれしくてうれしくて困るじゃない!
「うわー!! すごーい! 青柳さん、国語の先生みたーい!」
***
この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/zemi/38451
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】
天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。