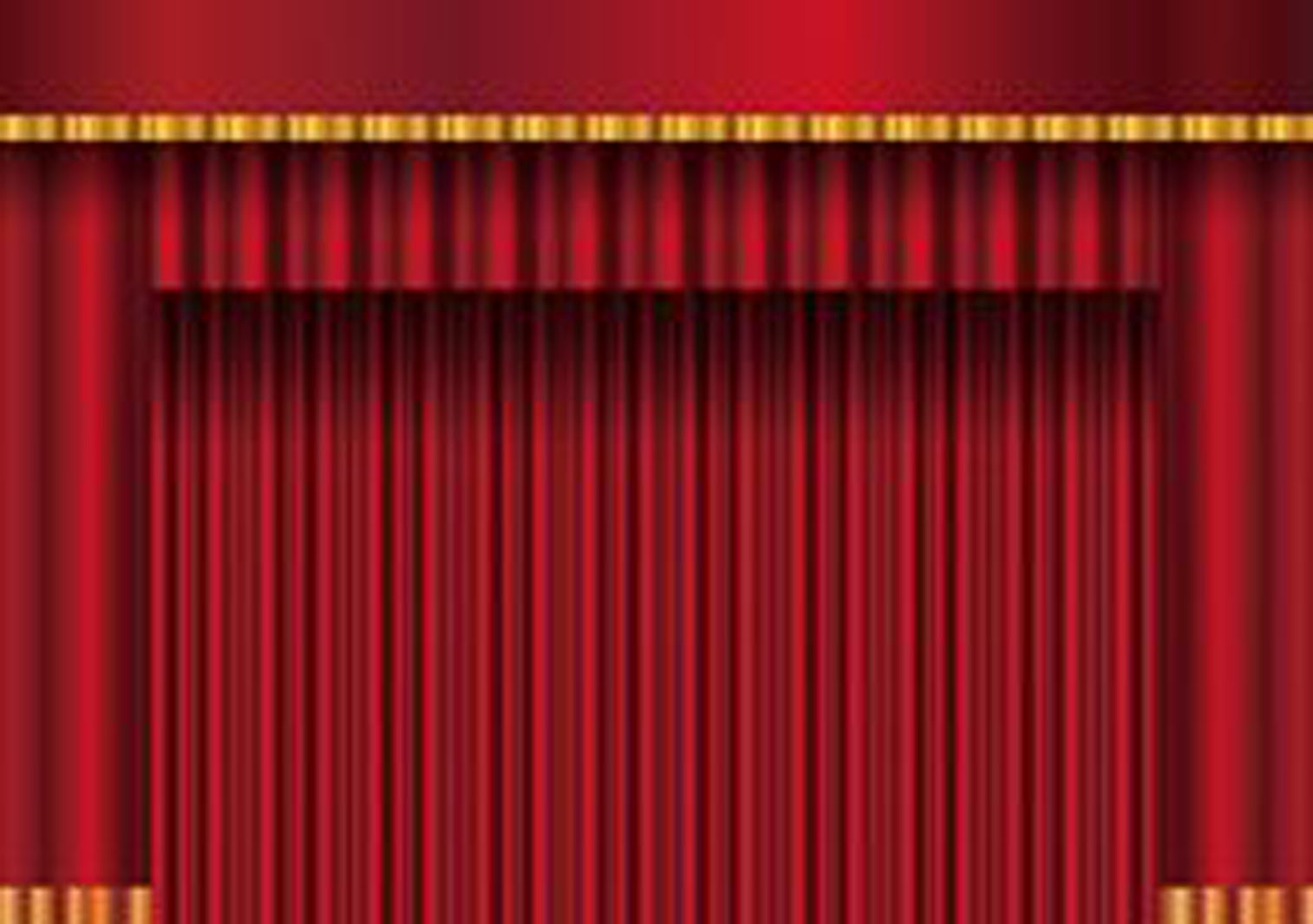拝啓 わたしの右肩に居るというあなたへ《プロフェッショナル・ゼミ》

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【12月開講申込みページ/東京・福岡・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
→【東京・福岡・全国通信対応】《日曜コース》
「え、いまなんて言ったの?」
先輩社員に聞き返された時、初めて自分がおかしなことを口走ったことに気が付いた。
しまった、考えていたことがそのまま口に出てしまった。
「いえ、あの、今日は受注フォローはできませんでした。ゼロ件でお願いします」
「ん、受注フォロー、ゼロね。分かった」
先輩社員が日報に、今日一日の行動記録を付けている。それにしても、なんでこのタイミングで思わず口走ってしまったんだろう。そこまで気にしていたわけじゃないんだけど。
帰り支度を整えて、車のキーを手に取った。真っ赤なMINIは母が以前乗っていたもので、今はわたしの愛車だ。丸くて赤くて愛くるしい。気に入っている。でも、最近エンジンの調子がおかしいのが気にかかる。明日のドライブは2時間ちょっと。少し不安だった。
ヘッドライドが秋の夕闇にまるく差し込む。ギアをドライブに入れて発進させる。会社の前の通りを走り出すと、ウォーキングをしている人が目に付いた。たすき掛けした蛍光テープが、ぼんやり光る。なんだかお化けみたいだ。お化け。お化けか……。
自分の右肩へちらっと視線を走らせた。
「わたしの守護霊って、一体誰なんだろうなぁ……」
***
次の日、わたしは念入りに洗車した車に乗り込んだ。目的地をカーナビに入力する。素敵な天気だし、良いドライブになりそうで嬉しかった。エンジンの調子も悪くない。
駐車場から車を出してしばらく走っていると、頭はどうしても2週間前のことを考えてしまう。不思議な女性に、ごく当たり前のように言われたことを。
年上の友人が「お茶会」をするという告知をしていたのは、9月だったと思う。彼女はジュエリーを販売する女性で、自身も非常に美人であり、まとう空気もファッションもラグジュアリーな人だった。あまりにラグジュアリーなので、わたしは彼女を「ラグ姉さん」と呼んでいる。
彼女とは普段SNSでつながっているが、ある時、変化に気づいた。以前から美しく天真爛漫な人ではあったけど、それが加速している。生きていること自体を深く楽しんでいるように見えた。どうしてだろうと思っていたら、どうやら彼女には「面白い友人」が付いているらしい。
その人がこの「お茶会」の主役であり、わたしが会いに来たひとだった。
待ち合わせのラグジュアリーなホテルラウンジに着くと、ふたりの女性が出迎えてくれた。
ラグ姉さんのとなりに、不思議な人がいた。森の奥に住んでいそうな女性だった。道に迷って、やっと一軒の家を見つけてドアを開けたら、「あなたが来ること前から分かってたわ」と微笑みそうな女性だった。彼女には「森の不思議さん」というニックネームを付けることにした。
不思議さんはヒプノセラピストだった。退行催眠という手法を使って前世を見る人らしい。わたしは退行催眠についてはよく分からないが、今回のお茶会では、「自分の中の強い思い込み」を破壊したいという目的でやってきた。わたしが抱いている「何をやっても結局うまくいかないのではないか」というおかしな思い込みを完全に捨てる為、不思議さんの力を借りにきたのだった。これから小説を書きたいし、舞台もやりたいし、イベントにも興味がある。思い切って様々なチャレンジをするのに、この思い込みをどうしても外したかった。
カウンターバーに3人で腰を落ち着け、飲み物を注文すると、不思議さんはわたしをじっと見て、自己否定がある人にはまったく見えない、とハッキリ言った。
え、そうなの? 確かに、ここ数年、自己流で色々やってはいたけど……それ、うまくいってたってこと? というか、「おかしな思い込みを持ってると思い込んでた」ってこと? お茶会開始2分にして、目的が達成されてしまった。拍子抜けである。でも身体は軽かった。
それから、彼女にふたつみっつ質問をされた。わたしの短い答えから、彼女はわたしの本質を即座につかみ、アドバイスをくれた。どれも思い当る節があることばかりなので驚いた。
「わたし、小説とか舞台とか、そういう活動をもっといっぱいやっていきたくて」
「そうなんだ。良いと思う。あなたの右肩にいる人も応援してるわよ」
……右肩にいる人?
「誰かいるんですか、わたしのここに」
「ええ、守護霊が。男性よ」
不思議さんはコーヒーをひとくち飲んだ。わたしはスピリチュアルなものにまったく触れたことはないが、自分を応援してくれる誰かが常にそばにいてくれるならありがたいので、そのまま受け取ることにした。もちろん、見えはしないが。
それにしても気になるのは、この守護霊が一体誰なのかということだ。
わたしはハッとした。もしや……あの人だろうか。
「あの、もしかしてここにいる人は、わたしの曽祖父じゃないでしょうか? わたしが勤める会社を興した人なんですけど、数年後にわたし会社を継ぐことになってて、それで、」
「うん、ひいおじい様じゃないみたい」
あっさり却下されてしまった。
「でもね、あなたのことが大好きなんですって」
思わず眉をひそめた。……誰だ? できるだけ目を凝らしたが、ムダだった。
「彼はお仕事よりも、あなたの創作活動の方を応援しているみたいよ」
え、そうなんだ。だとすると、曽祖父のはずがない。彼なら、わたしには何よりも仕事を頑張ってほしいはずだから。
不思議さんとラグ姉さんと分かれた後も、わたしはずっと自分の守護霊が誰なのか考え続けていた。考えたところで分かりはしないし、そもそも見えないのだから確かめようもないが、ああまでハッキリ言われると、やはり気になる。その場で不思議さんに聞けば良かったのかもしれないが、なんだか野暮な気がしてやめてしまった。
そんなことを考えていたら、もう半分の道のりを来てしまった。ありがたいことにエンジンの調子はずっと良い。問題なく目的地までたどりつけそうだ。しばらくぶりに、彼に会える。
花は準備してある。ライターもある。ビールは、向こうで買えば良いか。
休日なのに、高速はさほど混んでいない。これも、もしや守護霊のおかげだろうか。いや、それは関係ねーか。守護霊が渋滞を解消するなどという言われはない。
実はわたしには、もうひとり守護霊にこころあたりがある。
仕事より文化活動を応援してくれているというなら、きっとこの人だ。
4年前に亡くなった、父方の祖父ではないだろうか。
祖父は15歳で志願兵として海軍デビューした後、終戦後は銀行マンになったが、復員後しばらくは流しの歌手をやっていたという変わった人物だった。素晴らしく美しい形の鼻を持った良い男で、たまの夏休みなどに彼と会うと、幼いわたしは密かにため息をもらしたものだ。
祖父の美声は年を取っても衰えることを知らず、一緒にカラオケへ行くと、他の人間にはほぼマイクが回ってこなかった。祖父がマイクを離さないのではなく、あまりに歌がうまいので、周りの人間が自然とアンコールしてしまうのだ。彼は黙っていても目立つ男のくせに、本来は目立つのが苦手らしく、歌の合間に、キシシと照れて笑っていた。
そんな祖父だから、わたしが舞台で演じたり、歌が好きでよく歌っていることを存命中から非常に喜んでくれた。彼に誉められると、他の誰かに誉められるよりもなんだか誇らしかった。
じいちゃんなのかしら。わたしを応援してくれてる人は。
でも、不思議さんが言ったことも思い出される。
「守護霊は、肉親じゃないことが多いんです」
だとしたら、違うかもしれない。いや、確かめようがないから違うも何もないんだけど。はー、気になる。あなたは一体誰なんだ。
それから再びじっくり考えてみると、もしや大学の恩師では? とか、水泳教室のコーチかしら? あ、スナックのマスターかもしれないなど、数名候補が挙がった。自分が思っていたよりも、ずっとたくさんの人の名前が出てきたので、驚いた。しかし、決め手に欠ける。
車は、目的地に近づきつつあった。
東京ディズニーランドを素通りして、先を急ぐ。
もしも、ここにいるのが祖父でないなら、思い当たる人物はあとひとりしかいない。
でもなぁ……あの人がわたしを応援なんてしてくれるかしら。どちらかというと、神野くんとはライバル同士だったしなぁ。
わたしは車を駐車場に停めた。潮の香りがする。ここから彼のいる場所までは、少し距離がある。そのあいだにコンビニでビールを買おう。花を片手に歩き出した。
今でも、夢に見ることがある。神野くんが最後にわたしに言った言葉を。
「裏切り者だよね」と彼はわたしの目を見ずに吐き捨てた。
神野くんとは小学生の時からの友人だった。彼は図工と国語が得意科目で、わたしもそのふたつは得意だったから、ライバルだった。中学校まで同じ学校に通って、その後の高校では分かれたが、ある時地元の駅でバッタリ会った時、ふたりとも演劇部に所属していることが分かった。ついでに、彼は小説を書いていた。わたしも、周りの人間には誰にも言っていなかったが、彼と同じように小説を書き始めていたところだった。
「オレ、お前よりデビュー早くなっちゃうと思うけど、ごめんね」
なんて失礼な男だろうと腹が立ったが、その時読ませてもらった神野くんの小説は、確かによく書けていた。わたしは普段、ライトノベルは読まないが、それでも彼の書くものが面白いことは分かった。
その後、偶然にも同じ大学へ進学したわたし達は、それぞれ舞台創りや小説書きに励んだ。互いの作品を観に行ったり、小説にダメだしをしあったりした。でも、その頃には彼とわたしの創作力には格段の差がついていて、密かに惨めな気分だった。大学4年生の時に立ち上げた劇団を2年経った頃にたたみ、わたしは仕事を始めた。商売は思いのほか自分の性分に合っていたようで、素直に楽しかった。一方、神野くんは卒業後も就職せず、バイトをしながら作家デビューを目指していた。
彼から「呼び出し」を食らったのは、25歳の時だった。
待ち合わせのカフェに入ると、神野くんはすでに席についていた。
「お待たせ。あ、来月誕生日だよね、おめでと」
「遅いんだよ」
「だって、急に呼び出すから仕方ないでしょ。わたし働いてるんですから」
わたしの「働いてるんですから」の一言に彼の機嫌が明らかに悪くなったのが分かった。
神野くんは床の上を見つめたまま吐き捨てた。
「裏切り者だよね」
え、なに、裏切り者? 突然の激しい言葉に絶句してしまった。
「なんで書いてないわけ? なんで舞台やめたわけ? なにあっさり社会に順応してんだよ」
そう言われると確かに胸が痛んだが、そんなことなんで彼に責められないといけないんだろう。
「なにをちゃっかり仕事とかしてんだよ。小説書けよ、舞台やれよ。どうせまたつまんないんだろうけどさ」
なんだこの野郎と思って睨みつけようと思ったが、言葉と裏腹に神野くんの目のふちが赤いので、暴言はつつしんだ。
「ちゃんと書けよな。次会った時に何にも創ってなかったら、マジ軽蔑するからな」
神野くんは自分が言いたいことだけ言うと、さっさと席を立って店を出て行ってしまった。
わたしはイライラするのと、悲しいのと、屈辱が入り混じった気分でしばらく動けなかった。
その翌月に、神野くんは亡くなった。脳出血だった。
彼はその時言わなかったけど、とあるライトノベルの文学賞で最終選考まで残って、担当編集者も付いていたらしい。葬儀の席で、親御さんが教えてくれた。なんだよ、直接言ってくれれば良かったのに。
片手に花、片手にビールをぶら下げて、わたしは久しぶりに彼の元へ来た。相変わらず良い場所だ。海が近くて空が高い。
「ねー、神野くん。わたしの右肩にいる人って、キミかい?」
享年26歳と刻まれた墓碑に話しかけるが、答えはない。耳を済ませれば聞こえるかしらと思ったが、潮の香りがするばかりだった。持ってきた花を供えて、お線香をあげた。
もしもわたしの右肩にいてくれているのが神野くんなら、嬉しい。もしもそうなら、心強い。
まぁ、なんだかんだ考えたところで、結局分からないんだけどさ。
でも、こうやって考えてみて改めて嬉しかったことがある。
わたしには、自分を大事に思ってくれて守ってくれたと思える人が、過去にたくさんいたと気づいたことだ。
わたしの右肩にいる人が誰なのかは、結局分からない。でも、それが誰であっても、わたしを大切に思ってくれる人が確実にいるのだ。そう思うと、心強いし、胸があたたかいし、なんだか泣きそうになる。嬉しいなぁ、と。どうもありがとうね、と。
わたしは、神野くんの墓前にビールを供えながら、彼を含め過去にわたしを大事に思ってくれた人たちのことを考えて、手を合わせた。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、店主三浦のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
【12月開講申込みページ/東京・福岡・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
→【東京・福岡・全国通信対応】《日曜コース》
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL 092-518-7435 FAX 092-518-4941
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】