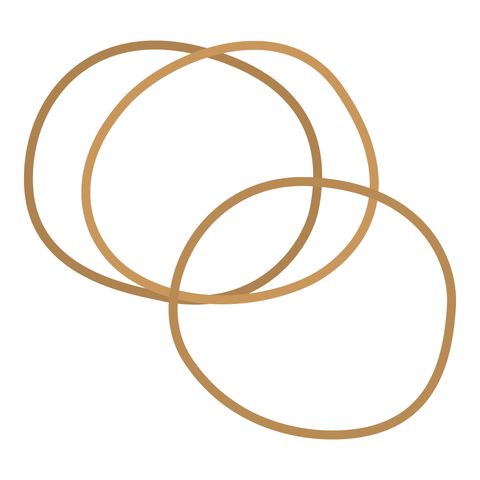君の指先に、心を奪われた日のこと

記事:西部直樹(ライティング・ゼミ)
「それで、手紙をもらったんだよ。帰り際に、フロントで」
友人は遠くを見るように視線を彷徨わせ、静かに語ったのだった。
「良かったじゃない、返事があったんだから」
妖艶な人妻は、スカートの深いスリットから覗く脚を巧みに組み替える。
「それで、なんて書いてあったんだよ」
わたしは、少し面白くないような気がしていた。
ビルの上階にある居酒屋で、窓から見える有楽町の夜景を背に、友人のほとんど自慢でしかない昔語りを聞いていた。
久しぶりに三人で会い、何かの話の流れから、各自の好みのことを話していた。
薄いあらごし梅酒ソーダ割りに早々に酔いはじめた友人は、
「俺って、眼鏡に弱いじゃん」と、馴れない若者言葉を使って話しはじめた。
「かぶれるとか」と妖艶な人妻。
「なんで、眼鏡と戦うんだよ」とわたし。
「はいはい、ありがとう、つまらないツッコミを。
まあ、それは、初恋のサイトウミカちゃんが、眼鏡をしていて、とても可愛かったからなんだけれども、まあ、そのかわいらしさは、子猫と子犬を足して二で割って、三を掛けたくらい可愛かったのだよ。彼女は、今はどうしているかなあ。もう少しで還暦だけど、可愛いままかな……」
「まあ、初恋は、宝物だからな……」わたしもつい、遠くを見るような目をしてしまった。
「それで、眼鏡に弱いから、どうしたのよ」と、妖艶な人妻は、綺麗に盛られた「チーズいろいろ」の皿から、モラレッツァチーズを箸で摘み、口に運びながら、さきを促す。
「眼鏡をしていて、髪が長いと、いうことないなあ、サトウミカちゃんがそうだったから」
「それで……」妖艶な人妻は、窓の外に広がる有楽町の夜景を見ながら、呟く。
「まあ、それで、出会ったんだよね、眼鏡を掛けていて、髪の長い女性に」
「いつ?」とは、わたし。
「どこで?」とは、妖艶な人妻。
「ふふ、あれは数年前、広島のホテルの部屋で」と、なぜかニヤついた笑いを浮かべる友人。
「待てよ、それはなんか順序が違わないか」
わたしは釈然としない。
「なに、それ、何かその方面の方を呼んだの、ホテルの部屋に、出張中をいいことに、ゲスいわね」と、妖艶な人妻は友人を軽く睨むように見ながらいった。
「そういう方面って、そういうのじゃないけど、部屋に呼んだんだよ。
そして、来たのが、眼鏡をした長い髪の女性だったんだ。いやあ、彼女を見た瞬間、痺れたね。
痺れたまま、ベッドに倒れて、あとはなすがまま。気がついたら、終わっていた。
出張で疲れていたから、途中から寝ちゃったんだけどね」
「それって、要するに、ホテルでマッサージをお願いしたら、来たマッサージ師の人が好みだった、ということ」
妖艶な人妻は、脚を組み替えた。
「まあ、そういうこと」
「それだけ? なんかつまんない」妖艶な人妻は、嘆息する。
「いや、これで終わったら、つまらんだろう?
この続きがあるんだよ。
このまま終わったら、それきりだからさ、勇気を出して名刺をもらっておいたんだな」
友人は得意そうだ。
「営業用の名刺をもらうくらい、勇気は必要ないでしょう」
含み笑いをしながら、妖艶な人妻は言う。
「でもさ、好みどんぴしゃだと、緊張するんだよな、なぜか」
「中学生でもあるまいし」
「おじさんは、純情なんだよ。それで名刺をもらったから、次の出張の時は迷わず彼女を指名したんだよ。来たら、やっぱり緊張して、受けるだけだったけどな。これが2回目」
「で、3回目は?」話を促す妖艶な人妻。
「それから3ヶ月後かな、また出張でいって、彼女を指名したんだよ。さすがに覚えていてくれたみたいでな、『まえにも、指名いただいた方ですよ、ね』てな。
それから話が弾んで、楽しかったなあ。
話をしてみると、彼女はなんか賢くてな。
おじさんの話しについて来てくれるし、話も面白いし。
それで、次の日も指名して、だいぶ仲良くなれたんだ。
けど、次の日で出張も終わり、当分広島には来られそうもない。
それで、彼女にも会えないなあ、終わりになるのが、なんか寂しくてな。好みだったから。
それで……」
「連絡先の交換を申し込んだのか?」と、わたし。
「いや、そのマッサージ店の方針として、お客さんと直接やり取りをすることはできないんだそうだ。だから、彼女に手紙を書いた」
「え、ラブレター、でも、不倫のラブレターだね、もう、ゲスなんだから」と、妖艶な人妻。
「まあ、ラブレターだけど、もう会えないのわかっているからな。彼女に癒された、ステキな施術に、心が奪われた、みたいなことを書いた」
「婉曲表現ね」妖艶な人妻が、合いの手を入れる。
「最後の夜、彼女が帰る際に渡したよ。まあ、好みのタイプの女性と、しばしの時間を過ごせたお礼だな」
「それで、おしまい、あまり盛り上がらない話題だな」渋面を作ってわたしが言った。
「それで、手紙をもらったんだよ。チェックアウトの帰り際に、フロントで」
友人は遠くを見るように視線を彷徨わせ、静かに語ったのだった。
「良かったじゃない、返事があったんだから」
妖艶な人妻は、スカートの深いスリットから覗く脚を巧みに組み替える。
「それで、なんて書いてあったんだよ」
わたしは、少し面白くないような気がしていた。
「中身は、ありがとうみたいな、でも、
『もっとはやくお話をしていればよかった』とか、
『そして、褒めていただいて、嬉しいです』とか、あったんだよ。
何より、手書きの手紙で、『褒める』が、漢字で書かれていたのに感動したな。
俺は書けないから」
「ちょっと難しい漢字を書ける人は、なぜか尊敬しちゃうね」と妖艶な人妻。
「その手紙、今でも持っているんだろう、奥さんに見つからないところに隠して」冗談めかしてわたしが言うと、友人は少しうろたえた。
その姿に、私たちは少し笑ってしまった。
好みのタイプではなく、少し踏み込んで交流できたことが、心に残っているのだろう。
人との繋がりが染みる年頃になったな、と夜景を見ながら思うのだった。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、店主三浦のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】
【有料メルマガのご登録はこちらから】