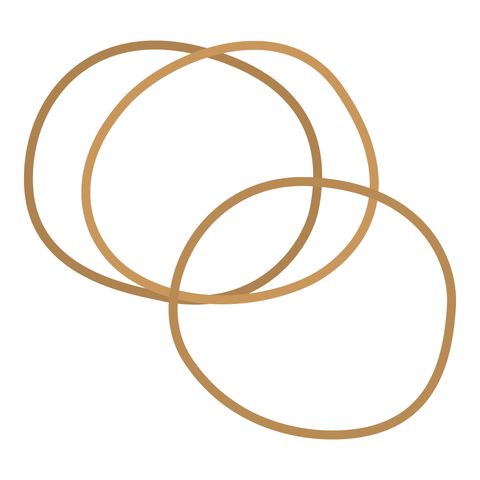目覚めの電話《プロフェッショナル・ゼミ》

*この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
【4月開講申込みページ/東京・福岡・京都・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
→
【東京・福岡・京都・全国通信対応】《日曜コース》
記事:和智弘子(プロフェッショナル・ゼミ)
*フィクション
「最近、なんか夜中にイタズラ電話がかかってきて、気持ちわるいんだよね」
真紀は彼氏の広太に、ここ最近頭を悩ませていることを打ち明けた。
「でもさ、おれが真紀のうちに泊まりにきてるときには、全然電話なんか、かかってこねーじゃん。いつかかってきてんの?」
そうなのだ。
広太が真紀のアパートに泊まりにきているときには、真夜中のイタズラ電話はぴたりと鳴らないのだ。まるで、「お楽しみの最中に、お邪魔は、いたしませんよ……」とでも言わんばかりに。
「うーん……。なんでなんだろう? 誰かに見られてるのかなあ? 私がひとり暮らしなのを見られてて、広太が来ていない日だけを選んで、電話してきてるのかも……」
そう言って、真紀は、ゾクリとした。
誰かに見張られているのだろうか?
それとも、近所の人が、うちに広太が来ているかどうかを覗き見しているのだろうか?
……どちらにしても、気味が悪い。
「ねえ、ちょっと気味が悪いから、なにか一緒にイタズラ電話の対策たててよー」
甘えるような声で、真紀は広太にお願いする。
「じゃあ、俺がしょっちゅう泊まりにくれば、問題なくね?」
そう言って、広太は真紀の身体に腕をまわした。
広太とは、大学1年生の秋から付き合い始めて、もうすぐ1年になろうとしている。学部は違うのだけれど、同じフットサルサークルに入ったことで仲良くなって、どちらからということなく付き合い始めた。広太は一浪しているため、真紀と同じ学年だけれどひとつ年上だった。カッコいい、とは言わないけれど、ムード―メーカー的な存在で面白かったし、いつも笑わせてくれた。
真紀は、長野からでてきて一人暮らしをしていた。付き合い始めると、すぐに広太は真紀のアパートに泊まりにくるようになった。泊まりにくる理由は決まっている。たっぷりとセックスをするためだ。広太は盛りのついたサルのように、真紀の身体をがつがつと求めていた。二十歳そこそこの、溢れ出さんばかりの性欲をもっていて、広太はいつでも臨戦態勢に入ることが出来た。好奇心と、健全な性欲は、男ばかりが持っているものではない。健全な性欲も真紀には、きちんと備わっていた。広太に求められるままにセックスを楽しんでいた。セックス自体は気持ちいいとは、思えないことも多かった。どちらかと言えば広太は自分だけが気持ちよくなって終わってしまうことが多かった。ひりひりとした摩擦による痛みを感じることも多かった。身体も、心も。
けれど、ふとんのなかで裸になって、肌と肌がふれあうことは好きだった。じゃれあいながら、くっつき合うことを肌が求めているのだと思っていた。まるで、冬眠前にリスたちが木のうろの中でくっつきあいながら、暖め合っているかのように。広太が喜んでくれているのを見ていると、セックスなんて、こんなものなんだと真紀は考えるようにしていた。
広太は実家暮らしなのだけれど、週末だけでなく、週の大半を真紀の借りているワンルームのアパートで過ごすようになっていた。広太の実家は大学からそれほど遠い場所にある訳ではない。けれど真紀のアパートは、大学から走って5分ほどの場所にある。ぎりぎりまで寝ていても遅刻しないことも気に入ったらしい。実家の近くにあるチェーン店の居酒屋でアルバイトをしているので、深夜までバイトに入っている日もあるし、バイト終わりに友達と飲みに行くことも多かったので、その日は実家に帰っていた。
イタズラ電話がかかってくるのは、広太が居酒屋のバイトに行っていて、アパートにきていない日だけを、きちんと選んでいるかのようだった。
携帯電話を持っているのだから、家には固定電話なんて必要ないと思うのだけれど、初めて娘が一人暮らしをするのに、いろいろと心配に思う真紀の両親が、むりやり設置してくれたのだった。
真夜中のこと。
プルルルルル。プルルルルル。プルルルルル。プルルルルル。
……まただ。
眠りを妨げられた真紀は、ふとんからむくりと起き上がった。
広太が泊まりにきていない日は、電話線を抜いてから、寝るようにしてたのに。
広太がバイト明けに、携帯代を浮かせるためだといって、実家の電話からかけてきたのだ。話し込んだ後、そのままうっかり、線を抜くのを忘れてしまっていた。
めんどくさいなあ……。
イタズラ電話がかかってきた、はじめのころに、なんどか電話に出てしまったことがあった。今思い返せば、それがダメだったんだろうな……。
寝ぼけた女の声なんて、受話器の先の主は、大好物に違いないだろうから……。
出たほうが、いいのか。
出ないほうが、いいのか。
鳴り続ける電話機を前にして、じっと見ていたけれど、一向に鳴り止む気配も感じられない。
ディスプレイに表示された、非通知のしらせが、暗闇の中に光り続ける。
すこし迷ったけれど、受話器をとることなく、電話線をカチリと抜いた。
部屋には再び、真夜中だけに感じられる、ひっそりとした静けさが訪れた。
時計に目をやると、深夜の2時をすこし、過ぎたところだった。
……どんな人がかけてきているんだろう?
考え出すと、怖くなってしまう。
けれど、一度目が覚めてしまっては、なかなかすぐには眠れない。
眠りにつくか、つかないか、何度も寝返りをしているうちに、朝を迎えることになった。
「また、イタ電かかってきたよー。もう、イヤだよー。ねむいよー」
大学の机に突っ伏しながら、友人の恵利についついグチをこぼす。
「もうさあ、家の固定電話なんか、処分しちゃえばいいじゃん。両親も、真紀がイタ電に悩まされてるんだって知ったら、スマホにかけてくるでしょ?」
「でもさあ、やっぱり実家に電話かけると、あっという間に一時間ぐらい過ぎてるから、通話料がやばいでしょ……」
「そっかー。まあ、それなら、寝る前に電話線抜き忘れないようにするしかないんじゃない?」
「だよね」
それにしても、いまどきイタ電なんて、相当ヒマ人だよねー、と恵利は心配してくれているんだか、いないんだか分からないような口調だった。
「人ごとだと思ってー。結構悩んでるんですけど!」
「ごめんごめん。でもさ、真夜中にわざわざ電話してきてさ、なにが楽しいのかねえ? ぜんっぜん、理解できない」
確かに、イタズラ電話を何のためにかけているのか、理解できない。
寝ぼけた女の声を聞きたいのか?
どんな下着を身に付けているのか、鼻息荒く、聞きたいのか?
何度か、電話に出てしまったときのことを思い出してみるけれど、受話器の先の相手は、終止無言だった。
シーンと、静まり返っていて、コトリ、とも音は聞こえなかったのだ。
「まあ、イタズラだから、理由なんて特にないんだろうけどねー」
恵利はそういって、スマホの画面をチラリと確認して、「じゃ、バイトだからー」といって、帰っていってしまった。
今日はバイト入ってないし、帰るとするか。
そう思いながら、スマホを確認すると、広太から連絡がきていた。
「今日、バイト終わってから家行くよ」
バイトに入ってる日に、うちにくるなんて珍しいな。
だけど、多分私が、昨夜もイタ電があったことを報告したから、心配してくれているんだろう。
よかった。
もしも、今日の夜中に電話がかかってきたら、広太に出てもらえばいいんだ。そうしたら、イタズラ電話も落ち着くかもしれないし。
夜に広太に会える嬉しさもあって、少しだけ楽観的に考えてながら、アパートに帰宅した。
ひとりだと、だらだらとテレビを見て過ごしてしまうことが多い。けれど、夜に広太がくるし、少しだけ片付けようかな? バイトの後だから12時くらいになるのか。……寝ちゃってそうだな。まあでも、寝てたら寝てたで、いいよね。
読み散らかしていた雑誌を片付けていたとき。
プルルルルル。プルルルルル。プルルルルル。プルルルルル。
電話が鳴った。
なんだろう?
実家からかな?
あれ、でも、番号が通知されている。
……非通知じゃないな。
勧誘の電話かな? 無視しちゃおっかな?
あれ? でも、なんか、見覚えがある番号のような……?
いっこうに鳴り止まないコール音は有無を言わさず「受話器をとりなさい」と威圧的な態度を示し続けていた。
無視してしまおうかと思っていたけれど、そのコール音は、それを許してはくれなかった。吸い込まれるようにして、真紀は、おそるおそる、受話器をとった。
「……もしもし」
「……」
「……もしもし?」
無言電話だ。
やっぱり、イタズラ電話だろうか?
そう思った。けれど、次の瞬間。
「もしもし。はじめまして」
無理矢理、落ち着いた声をだしている、女の声が聞こえてきた。
誰だろう?
全然、声に聞き覚えがない。
真紀は、また新手のイタズラ電話かもしれない、と思い、ギュッと受話器を握りしめ、相手の様子をうかがった。
「はじめまして。わたしは、広太の母親です」
「……」
「もしもし、聞こえてます? 返事していただかないと、こまるんですけれど」
「……はじめまして」
電話の先にいる人の自己紹介を、うまく理解できない。
背中の芯が、ヒヤリとした。
けれども、真紀はうながされるままに、返事をした。
これからなに言われるのか、理解できないまま、おびえた声で。
「はじめまして。あなた、広太とお付き合いしてますよね?」
「……はい。広太さんとお付き合いしています。真紀と申します」
「ええ。真紀さん、ね」
そこで、広太の母親は、ひとつ大きく息を吸い込んだようだった。湿り気を帯びた息遣いが、受話器をとおして、聞こえてくる。
「今日は、あなたに、お話があってお電話させていただきました。あなたの電話番号は、広太がうちの電話であなたにかけた履歴を見て、知ったんです」
「……はい」
「広太がずいぶん、あなたの家に泊まりにいっていると思うんですけど。あなたもまだ学生でしょ?」
「はい。広太さんと同じ大学へ通っています」
真紀は受話器を持つ手も、受話器を通して話している声も震えがとまらなかった。
「あんまりね、こんなこと言うのも嫌なんだけれど、学生のうちに何か問題があると……ねえ。万が一妊娠でもしたら、あなたに迷惑がかかるでしょ?」
「……はい」
「多分、広太が無理矢理あなたのお宅にお邪魔しているんだと思うんだけれど。アパートも大学から近くて、便利なんでしょうね。でも、あまり、褒められたことではない、というのは分かるでしょ?」
「……はい」
はい、としか答えようのない質問を、広太の母は投げかけてくる。
容赦のない、冷たい声で。
「お付き合いをやめろ、とは言っていないのよ? でも、あんまり泊まりにいくのは止めるように、真紀さん……でしたっけ? あなたからも、言ってくださる? お互い、まだ将来のことなんて、決められない年齢なんですから」
ずいぶんと、一方的な言い方で真紀を責める。けれど、反論できる材料も、気力も真紀は持ち合わせていなかった。
「……分かりました。広太さんにお伝えします」
あまりにも聞き分けがいいことが、逆に心配になったのか、広太の母は、慌てて付け加えた。
「ごめんなさいね。急に変なお電話かけてしまって。でもね、あなたのことも、心配だったから。ね? なにか問題があっても困るのはいつも女性側だから。ね?」
「……はい。ご心配いただいて、ありがとうございます。広太さんとは、よく話し合います」
受話器を持つ手も、声も、心も震え上がっていたけれど、そう、絞り出すように話した。
広太の母親は満足したらしく、「真紀さんみたいな、物わかりのいいお嬢さんだなんて、お電話する前は分からなかったんですけどね。お話しできて良かったわ。あらあら、もうこんな時間! 急にお電話しちゃって、ごめんさないね。じゃ、失礼します」
そういって、がちゃり。と受話器を置いた音が聞こえた。
一方的に。
真紀は受話器をもったまま、動けなかった。
ツーツーツー、と電話が切れた音が響いていていた。
受話器から、手を離そうとしても、強く握りしめてしまったせいか上手く離すことができない。
……イタズラ電話以上に、タチが悪すぎる。
ようやく、受話器を離すことができたけれど、あまりのできごとに、真紀はショックだった。
身体は相変わらず震えていたけれど、なぜか、悔しくて涙がこぼれた。
予想もしていなかった電話の相手と、その会話に、真紀はすぐに理解しきれなかった。
ぼうぜんと、電話の前で座り続けていた。
ふと、スマホが鳴った。
広太から「バイト早めに上がれたから行くぞー」と
まぬけな顔をした、キャラクターのスタンプと一緒にLINEが送られてきた。
なんだか、うんざりする。
真紀は、スマホの画面をちらりと見て、嫌なものを見るかのように、顔をしかめた。
広太は、さっきまで話していた、あの女から産まれた、子どもなんだ。
母親とも、広太自身とも、関わりをもちたくないと、本能的に感じ始めていた。
「ごめん、今、電話できる?」
真紀がLINEを送ると、すぐに広太から電話がかかってきた。
「おー、なんか、買っていこうか? 夕飯はもう、食った?」
真紀の話なんて、おかまいなしに、話し出す。
ずいぶんと、一方的に。
「あのね、ほんと、悪いんだけど」
「え? なに? 生理にでもなった? 行くのやめようか」
広太の頭の中は、セックスのことしか、考えられないのか。
真紀が生理になると、広太はすこしだけ、冷たい態度をとる。
広太自身は、無意識なのだろう。
真紀には、そのささやかな、けれど、決定的に違っている態度を、いつも手に取るように感じていた。
なんだ、そうか。
結局は、広太にとって、満足感を得られるかどうかだけの相手なんだ。
私は。
……気が付かなきゃ、良かったのかもしれないけれど。
もう、ダメだな。
もう一緒にいたいと、思えないな。
「ごめん、あのさ、電話では伝えにくいんだけど。もうさ、広太とは、別れたいんだよね」
「え……? なんだよ! いきなり! 意味わかんねー」
「うん。私も、ちょっとまだ、気持ちがまとまっていないんだけど……。でも、もう、だめなんだよ」
「は? 何言ってんの? とりあえず、家にいくから」
真紀はとっさに、少しだけ、嘘をついた。
「さっき、あなたのお母さんから、電話があったよ。息子と別れなさいって。……なんか、冷めちゃって」
なんか、もう無理だわーと、小さな声でつぶやいた。
自分自身を、守りたい気持ちで、いっぱいだった。
「……真紀がそういうなら、もう、いいよ。……なんか、いろいろ、ごめん」
広太は、それ以上押し問答しても仕方がない、と悟ったのだろうか? それとも、以前にも同じようなことがあったのだろうか?
一方的な真紀からの別れの言葉を、渋々ではあるけれど、あっさりと認めてくれた。
そうして、一方的ではなく、互いの納得のもとに通話終了のボタンを押した。
真紀の家にある、広太の荷物が、急によそよそしく感じられた。
どこかのタイミングで引き取ってもらわなきゃ……。
勝手に、捨てちゃってもいいんだろうけど。
真紀はそう思いながら、この数時間で起こったことを思い返しながら、電話機を見つめていた。ディスプレイが、よわよわしく光っていた。
別れてから数日のあいだ、真紀は、本当は寂しかった。
暖かなぬくもりがいつもそばにあったのに、突然消えてしまったのだから。
けれど、広太を思い出すたびに、あの、受話器を通して聞こえてきた冷ややかな母親の声がずっと耳にこびりついて離れなかった。いつまでも、あの声が響いて、悩まされるくらいなら、別れてよかったのだと、少しずつ思えるようにもなってきた。
イタズラ電話は、あの日を境に、ピタリと鳴らなくたった。
だれが、かけてきていたのかは、分からない。
広太の母親が、様子を探るためにかけてきていたのかもしれない。
ただ偶然がかさなって、鳴らなくなっただけかもしれない。
だけど、深夜に眠りを妨げるものは、もう何もなくなった。
身体も、心もひりひりとした痛みを伴うことも、もうないのだ。
寂しさをはねのけるように、真紀は少しだけ伸びをした。
冬眠から、すっかり目が覚めたリスのように。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/fukuten/33767
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】
天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。