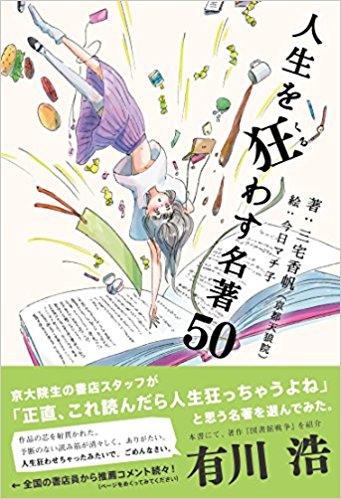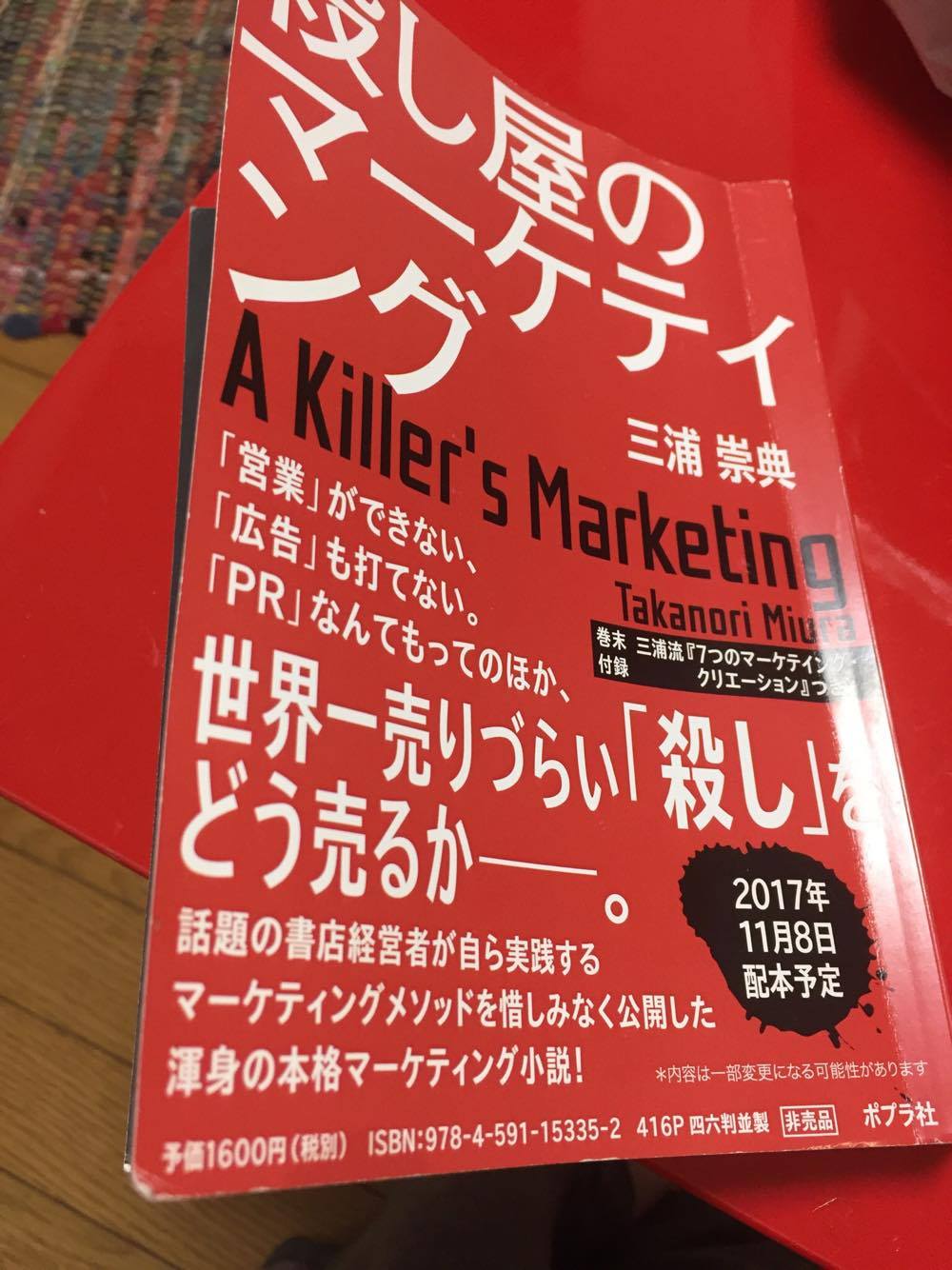失った恋を忘れられないなら、函館にイカを食べに行きなさい《リーディング・ハイ》

記事:おはな(リーディング&ライティング講座)
「で、なんでいまだに引きずってるわけ?」
いつもの行きつけの居酒屋で、親友のミカが、猫のような目をさらに吊り上げて聞いてきた。
「だって、やっぱりさ、わたしのことを分かってくれる人は、彼しかいないと思う。
わたしには、彼じゃなきゃだめなんだよ」
そう言いながらわたしは、とりあえずの一杯目のビールをちびちびと飲み続けていた。
「は? あんたら何年付き合ってたんだっけ?」
「えっと……5年かな。別れた時期もあるけど」
「で、一度でも結婚の具体的な話は出たわけ?」
「そ、それはさー、まだ早いっていうか。タイミングっていうか」
どんどんわたしの声は小さくなる。
「あんたさー」
ついにミカは人差し指を振り、こちらに向けてきた。
「イカの刺身って、何色だと思ってんの?」
「へ?」
凄んでくる勢いと、その質問のちぐはぐさに拍子抜けをした。
「イカ? イカの刺身の色? で、合ってる? 白? 白でしょ?」
「はぁー」
ミカのその怒りに満ちた溜息は、嵐の前兆だ。これから、大変なことになる。
「食感は? イカの食感?」
「え、や、やわらかい、のかな?」
「刺身につける薬味は?」
「え? 薬味? ワサビ? お醤油にワサビ?」
ダンッ!
飲み干した生ビールのジョッキを、ミカがテーブルに叩きつけた。
「あんたもうだめ! 話にならない。
そんな未練たらしくグチグチ言ってないでね、さっさと函館に行ってイカ食べて来なさいよ!」
***
朝の6時。
東京駅はすでに動き出している。
この駅は、眠ることがないのではないかと思うくらい、どの時間でも大きな荷物を引きずった人々があちらこちらへ歩き続けている。
わたしの手には、新函館北斗駅行きの切符。
今年の3月に開業したばかりの北海道新幹線に、こんなにも早く乗る日が来るなんて、思ってもみなかった。
わけがわからなかった。
あの日、親友のミカは完全にぶち切れていた。
二人のお気に入りの居酒屋で女子会飲み食べ放題コースを頼み、
いつものお決まりのチョコバナナを頼もうとしていたとこだったのに。
函館でイカを食べるまでは絶交だと、一方的に言い放って店を去って行った。
あまりにも理不尽な怒られ方をしたから、数日はわたしも彼女に腹を立てていた。
それでも――
「絶交」
そんな昭和の時代に使い古された今時ではない言葉に、胸がズキズキと傷んだ。
この人のためなら何を犠牲にしてもいい。
そう思える男に捨てられたばかりだった。
その上、わたしの良い所もダメなところも全部を理解して、一緒に笑ってくれるミカまで失ってしまったら、本当にわたしはもう、生きていけない。
これは、現実なんだろうか。
まったく理解できない。
ミカはいつだって正しかった。
それに、厳しいことを言っても、いつだってわたしの味方だった。
だから、今回だって、きっと正しいはずなんだ。
でも、なんでイカ? わかんないよ。
窓際の席に着くと、背が高く、つい振り返ってしまうような、美しい顔の男が、
隣に座ってきた。大学生くらいだろうか。おもむろに便箋を取り出し、何かを書こうとしたまま、動かないでいる。
「あ!」と思い、わたしはショルダーバッグを探り、一通の手紙を手にとった。
〈ごめんね。
あの日はごめん。一方的にあんなことを言って、傷つけた。
でも、私は本気だよ。もしあなたが、そのまま彼を思い続けて、過去にしがみついて生きていくというなら、私はつらすぎて、もうそばで見ていることはできない。
お願い。戻ってきて。あなたは、心から人を愛することができる人。
だから、あんな嘘つき男に、もうあなたの人生を奪わせないで。今を生きて。
追伸 この本と、函館のイカが、きっとあなたをここへ帰してくれると信じています。
2016年8月1日 ミカ〉
ミカからの手紙だった。
〈明後日の朝の新幹線で函館に行きます。イカ食べてきます〉
そう彼女にLINEを送った翌日のこと。
アパートに帰ると、郵便受けにB5サイズの封筒が入っていて、
中には、この手紙と一冊の文庫本が入っていた。
『尋ね人』谷村志穂
なんだか、やわらかさと同時にせつなさが共存しているような表紙。
心温まるしあわせな話の予感もするし、胸を締め付けられるような切ないお話な気もする。
ピンク、オレンジ、むらさきに包まれた夕暮れ時、
チェックのシャツを羽織り、自転車を押した女性が、坂の途中から海を見下ろしている。
通り沿いに並んだガラスの街路灯にあかりが灯り、かもめが空を舞い帰ってゆく。
坂を降りた先には路面電車が横断し、その向こうには海が見える。
最後の青函連絡船「摩周丸」は記念館として波止場に留まり続け、
ともえ大橋が湾岸沿いに緩やかなカーブを描き走っている。
今からここに行くんだ。
イカを食べに。
だんだん考えることにも疲れてくると、なんだか笑えてきた。
まぁ、いいや。
キレイな観光地を巡って、美味しいもの食べて、とりあえずイカを食べたら写真を撮ってミカに送ろう。
せっかく海を渡って行くんだもん。楽しまなきゃ。
ミカは待っててくれる。イカさえ食べれば、絶対また笑顔で迎えてくれる。
後ろの席に客がいないことを確認し、リクライニングシートを少し倒した。
ミカから渡された文庫本をめくっていく。
約4時間。
荒波に揺られることなく、新幹線は青函トンネルをくぐり、海底を走りぬけ、本州から北の大地へと渡った。
函館は、薄曇りだった。
せっかくの旅先だというのに、気分までどんよりしていた。
なぜだろう。
愛していた男に裏切られたから? 親友とケンカしたから?
いや、どちらでもない。
それは――
「あ、カモメ」
駅の背中には、函館湾が広がっている。
見上げると、あの小説の表紙のように、真っ白なともえ大橋が空中でカーブを描いている。
釣り場としても人気の中央ふ頭付近には、釣り竿を持つ人が一定の距離を保ち、並んでいる。
魚を狙っているのだろうか。
あちこちに、丸々と太ったカモメが飛んでいる。
「確かに、食べたくなるかも……」
ふるふると、頭を左右に振り回し、そんな考えを吹き飛ばす。
キレイな観光地をめぐるはずだったのに、気づけば一日中、海沿いを歩き続けていた。
不思議な街だった。エメラルドグリーンのペンキに塗られた和洋折衷の建物があったり、トタン屋根を鮮やかなセルリアンブルーに塗った古いのか新しいのかわからない建物があったり。オシャレなカフェに立ち寄っては、地元の人のあたたかくて、くすぐったいような不思議なイントネーションの方言に聞き耳を立てた。
夜になると、路面電車がカーブを描いて走っていくそのエリアは、
ボンヤリと街全体が電球色のオレンジ色に包まれていた。
幻想的でありながら、どこか胸が苦しくなる。
「人恋しくなる街」
今朝、新幹線の中で読んだ小説を思い出す。
本当にそうだ。
なぜだろう。この灯りに包まれていると、じんわりあたたかいようで、寂しくなる。
誰かに、触れたくて仕方がなくなる。
何かを、思い出しそうになる。
吸い込まれるように路面電車に乗り込み、その灯りから離れていった。
ゆっくりと走る車両の底から伝わってくる低音が、体の奥まで響いてくる。
黒にも見えそうな濃い緑色のざらついた座席のカバーが、胸のチクチクを刺激してくる。
昼間に到着した駅まで戻ってくると、夜の街にも少し賑わいが戻ってきた。
LEDの白い光が、気持ちを現実へと引き戻してくれた。
路面電車の線路を挟んで向かい合う通り沿いには、背の低い商店街が広がっている。
少しだけ開いた引き戸から威勢の良い声が聞こえて来る居酒屋に入った。
「ごめんなさいね、今満席なんですよ。何名さんですか?」
のれんをくぐると、山を描くような不思議なイントネーションの店員が話しかけてくる。
「あ、一人なんですけど。あの、イカを食べたくて」
「お、いいねー、姉ちゃん。ここ座っか?ちょっと待ってれや」
真っ赤な顔をした中年の男が嬉しそうに話しかけてくる。
「おい、ここ空けっからよ。なんも狭くたっていっけや。食わしてやれー」
男は怖い人なのか、優しい人なのか、よくわからない。
ぶっきらぼうな言い草だが、その言葉にはあたたかみを感じた。
「函館のイガだっけうめどー。食わねで帰るなんて、なんぼなんでも許されねえもんな」
男の言ってることは半分くらいわからなかったが、
あまりにも強く「なぁ!」と言ってきたので、
「は、はい」と自分でも驚くほど大きな声を出していた。
目尻にシワを寄せて笑いながら帰っていった男の背中に、小さく「ありがとうございます」とつぶやく。
つい先程まで男が座っていたその席は、まだ熱を帯びていて、しっとりとしていた。
「お待たせしましたね。イガだもんね。どって食べる? 刺身? 焼く?」
「あ、お刺身を、お願いします」
店員の言っていることは、かろうじて理解することができた。
なんだろう。この街の人はみんな真顔なのに、その方言がくすぐったい。
真剣に聞いてくれるから、真面目に答えたいのに、不思議と笑ってしまう。
「はい、お待たせー。イガ刺しねー」
目の前に置かれたガラスのお皿に山のように盛られたイカの刺身を見て、息を飲んだ。
細かく線のように刻まれたそれは、クリスタルの様に、輝いていた。
「白くない、全然白くない…」
これは――
***
「で? どうだったの、函館は?」
ブルーのアイシャドウで、よりシャープさを引き立たせた目元をしたミカが、聞いてきた。
「うん、わかった。わかったよ、ミカの気持ち」
腕組みをしたミカがニヤッと笑う。まるで猫がヒゲを動かしているようだ。
「何がわかったって?」
「うん、イカの刺身は白くなかった。
この本に書いてるみたいに、透明で飴色をしていた。本当にべっこう飴のように見える時もあるし、カラメルを煮詰め始めた直後みたいな、キレイな飴色に見える時もあるし。
ただ、白くはなかった。イカなのに、白くなかった。
それに、やわらかくなかった。
パリパリしてて、コリコリしてて、
だけど、ほら、この本の主人公の李恵が言うように、口にネットリ絡みついてきて。
飲み込みたくないっていうか、いつまでも終わりたくないって思うくらい、なんか不思議な食べ物だった。
それにさ、あの、ゴロって言うの? イカの肝があんなに甘くて臭みもないなんて、びっくりした! トロッとしてさ、それとお刺身を一緒に食べるのがまた美味しくてさ。
しかも、ショウガでしょ?
最初、間違えてるのかと思ったよ。なんで黄色なんだ、緑でしょって。
でも、正解だった。新鮮なイカ刺しには、ショウガしか考えられない。
あんなにネットリとして離れたくない、終わりたくないって思うのに、
キリッとしたショウガがさ、はいはい終わり! って手を叩いてるみたいでさ。
でも不思議に終わっちゃうのは寂しくなくて。ありがとうって。
こんなにしあわせな気分にさせてくれてありがとうって、そう思ってた。
びっくりした。
ほんとびっくりしたよ。
イカが、イカがあんなにすごいなんて考えたこともなかった。
まさか自分の視野の狭さを、イカに教わるなんて、考えたこともなかったよ。
いつもの白くてやわらかいイカを、わさび醤油で食べるだけで、イカが好きとか言ってた自分が恥ずかしいよ。
透明でパリパリでネットリと絡みついてきて、それなのにショウガが効いて後味サッパリ。
潔いって言うかさ、いい夢を見たかんじ。
それで思ったんだよ。イカでさえ、こんなに想像もつかないようなイカがいるんだなって。
男だってさ、わたしが知らないだけで、ほんとは色んな人がいるはずなんだよね。
わたしのことをわかってくれる人もいれば、わかってくれない人もいる。
何年一緒にいても前に進まない人もいれば、一瞬で恋に落ちる人もいる。
いるんだよね、本当は。まだ出会ってないだけで。わたしが知らないだけで。
なのに、バカみたい。狭い世界の中だけで彼しかいないって決めつけて、執着して。
危うく白くてやわらかいイカにワサビ付けてさ、イカはやっぱりこれだよなって言って死んでいくとこだったよ。もう新鮮さが無いから、噛みきれなくて、飲み込めないだけなのにね。
ようやくさ、わたしの恋にも、ショウガがはいはい終わり!って手を叩いてくれた気がする」
いけない! ついベラベラと一人でしゃべりすぎてしまった!
そうだ、わたしミカに「絶交」とまで言われてたんだ。どうしよう。
それなのに、イカに人生を学んだみたいな、おかしな話をしてしまった。
慌ててチラリとミカを見やると、
ミカは穏やかな三蔵法師様みたいな顔で笑っていた。
「やるじゃん! それでこそ私が選んだ親友だ!」
そう言ってわたしを抱きしめて、猫を愛でる時の様に、頭をぐしゃぐしゃに撫でてくれた。
「私もさ、この本を初めて読んだ時、胸が苦しくなるほどつらくなった。
こんなつらい恋は絶対にしたくない。誰かを愛するなら、心から愛し抜いて、後悔したくない。いつ自分の身に何が起こっても後悔しないように、絶対愛する男のそばに居て、絶対私の側を離れさせない。そう、思ったんだよ。
なのにさ、あんなにも苦しくてさ、悲しくて気持ちが沈んでいくのにさ、
なぜかイカが頭から離れなかったんだよね。
主人公の李恵がさ、なんであんな時にイカが食べたくなるのか、全然わかんなくてさ。
今は目の前にいる愛した男に集中しろよって思うのにさ、なんかこっちまでイカが食べたくて仕方がなくなったんだよね。
それで、私も行ったの。函館に。わざわざイカ食べにだよ? 笑っちゃうよね。
でも、キレイな夜景とか賑わう観光地の一本外れたところとかさ、ちょっと奥に入るとさ、急に時代がわからなくなるというか、寂しくなるんだよね。
何かよくわかんないけどさ、何かを思い出しそうになって、人恋しくなってさ。
それでハッとして、ちゃんと現実を見なきゃと思って人の賑わう方に行ってさ。
で、居酒屋でおっちゃんに勧められたイカを食べたの。
もう、びっくり。白くないんだもん。パリッパリだし。耳の辺りって言うの?
なのにさ、お腹のあたりは吸い付いてくるみたいに濃厚で甘くてさ。
ほんとそれでてショウガがキリッとしてるから、未練を感じる暇もなくてさ。
あー、私の見てきた世界って、私の当たり前って、全然当たり前じゃないんだって。
私もイカに教えられたよ。いい恋ってなんだろう。いい人生って、なんだろうってね。
もう目からうろこ! あ、イカにうろこはないか!」
ミカも止まらずにしゃべり続けた。
あの街でイカを食べると、なぜかそうなる。
不思議だけど、街が奥に隠しこんだ悲壮感に包まれ、なぜだかわからないが、やるせなくなる。それなのに突然エネルギーが昂ぶり出す。
それは街の人たちの、刺さるほどにまっすぐな誰かを思いやる気持ちに触れたからなのか、
その不思議なイントネーションに笑ってしまうからなのか、それとも、ただイカが美味しいからなのか。理由はわからない。
だけど、ある時突然、よし、またやってやるぞ。そんな気持ちになる。
それは、この小説の中にも、痛いほどに溢れている。
「あ、そうだ!」
髪をボサボサに乱されたわたしはミカの両手をすり抜け、自分のバッグの中に手をいれた。
「これ、ミカにお土産」
そういって、カステラサイズの箱を手渡した。
「え? 開けていい?」
こういう不意打ちの瞬間のミカの表情は、なんでもない普通の女の子の顔だ。
包装紙を丁寧に剥がし、箱のフタを開けたミカが
「キャッ」と小さく高い声を上げた。
「何これ?」そう言いながら箱を鼻に近づけ、眉間にシワを寄せながら、般若のお面みたいな形相でにおいを嗅いでいる。
「いかようかん」そう言ってわたしは思わず噴き出した。
「いかようかーん?!」そう言ってミカも吹き出し、二人でお腹を抱えて笑った。
いかようかんは、函館の老舗の和菓子屋さんが作った一風変わったお土産の一つ。
それはまるで、つい先ほど釣られたばかりのように、新鮮な飴色をしている。
一杯のイカのそのまんまの形で、足の吸盤やギョロっとした目玉がリアルだ。
「ちょっと何よこれー、味は? 普通のようかんなの?」
目頭を押さえて笑い転げながらミカは聞いた。
「それがね。コーヒー味!」
二人でまた吹き出して笑い転げた。
あまりにうるさくて、だけどあまりにも楽しそうだから、
隣の座敷の二人組のサラリーマンが苦笑いでこちらをのぞき込んでいる。
息を整えながら、もう目を線にしながら笑っているミカが言う。
「あー、もうだめだ。あんたさ、やっぱり趣味悪いわ。
なんであんな究極に美味しいイカ刺し食べて、お土産がこれなのよ。
第一さ、缶入りのバター飴とか、摩周丸のポストカードとかさ、
あの本読んでりゃつい買いたくなる物があるでしょ?
それがイカの姿のコーヒー味のようかんを選ぶって、どんなセンスしてんの?
あんたさ、次の男はきっとゲテモノだよゲテモノ。あー、おかしい。
最高。あんたやっぱりわたしの最高の友達だ」
そう言いながら、ミカはまだ笑い出した。
「食べてから言ってよ。美味しいんだから。いろんな賞も取ってるお菓子なんだよ。
でさ、ミカ。そのー、絶交はもう無し?」
上目遣いで恐る恐る聞くふりをする。
「当たり前でしょ! おかえり!!」
そう言って強く抱きしめてくれたミカに、
「生臭い! あなたも私も生臭い!」と、小説のセリフを真似て突き放す振りをする。
「ここで、あの場面はないでしょー? 」
そう言って、二人でお腹を抱えて涙を流して、笑い続けた。
「…っと、ちょっと! おーい」
目の前でミカが手を振ってる。
「あ、びっくりした。遅かったね。」
「うん、トイレ混んでてさ。ごめんごめん」
席に着くなりミカは、ぬるくなったビールをごくごくと飲み、プハーッと気持ちよさそうな吐息をもらした。
「で、いつ函館帰るんだっけ?」
ミカが、トイレに行く前の会話に戻して聞いてきた。
「えっと、月末」
「そっか、楽しんできてね。お母さんとゆっくり楽しんできてね」
「うん、ありがとう。ミカに、おみやげ買ってくるね」
「いいよいいよ。でさ、さっきボーッと何考えてたの?」
ミカが、少し心配そうに聞いてくる。
「あ、うん。イカで失恋を乗り越えられないかなと思って」
「イカ? イカで? 意味分かんないんだけど」ミカが鼻で笑う。
「いや、最近読んだ小説がさ、忘れられない人について書いてるんだけど、
なんかそれを読んでたらさ、函館のイカって、もしかしてすごいんじゃないかって、思えてきたの」
「イカが? なにそれ。どんな話なの?」
「あ、うん。
谷村志穂さんが書いた『尋ね人』って小説でね。
主人公の36歳の李恵が、地元の函館に帰ってくるところから始まるんだけど。
李恵は18の頃に上京して、服飾関係の専門学校で出会った男に恋をして、その人が立ち上げたブランドの協同経営者として、恋人として、彼を支え続けるの。
でも、あっさり若い女にとられちゃってさ。
それに、その頃ちょうど地元にひとりで暮らしているお母さんも末期がんになっちゃって。
それで帰ってきて。そしたらね、お母さんに50年前に突然姿を消した恋人を探してほしいって言われるの。お母さんは、日本史上最悪の海難事故って言われてる洞爺丸台風があった年に結婚しているんだけど、その前に付き合っていて結婚を約束していた人に、どうしても一目会いたいって」
「で、見つかるの?」
ミカが、心配そうに片眉を上げて聞いてくる。
「うん、それで探していくうちに、自分やお母さんやその恋人や、いろんな人の忘れられない恋を通じて、人生と向き合ってくってかんじかな」
「で、イカは? なんでイカで失恋を乗り越えられるの?」
検討もつかないという表情でまっすぐにこちらを見つめてくるミカに、
わたしはゆっくりと、さっき頭の中で考えていたことを、話し始めた――
谷村志穂著『尋ね人』2015年発行、新潮文庫
「読/書部」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、スタッフのOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
また、直近の「リーディング&ライティング講座」に参加いただくことでも、投稿権が得られます。
【リーディング・ハイとは?】
上から目線の「書評」的な文章ではなく、いかにお客様に有益で、いかにその本がすばらしいかという論点で記事を書き連ねようとする、天狼院が提唱する新しい読書メディアです。
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021
福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL 092-518-7435 FAX 092-518-4941
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】