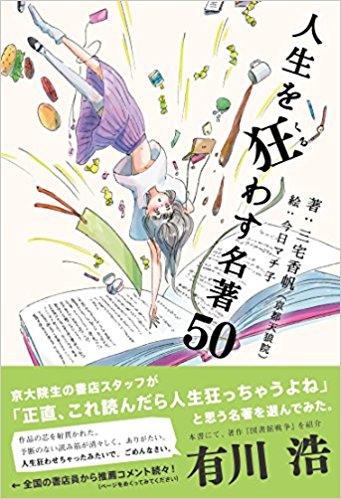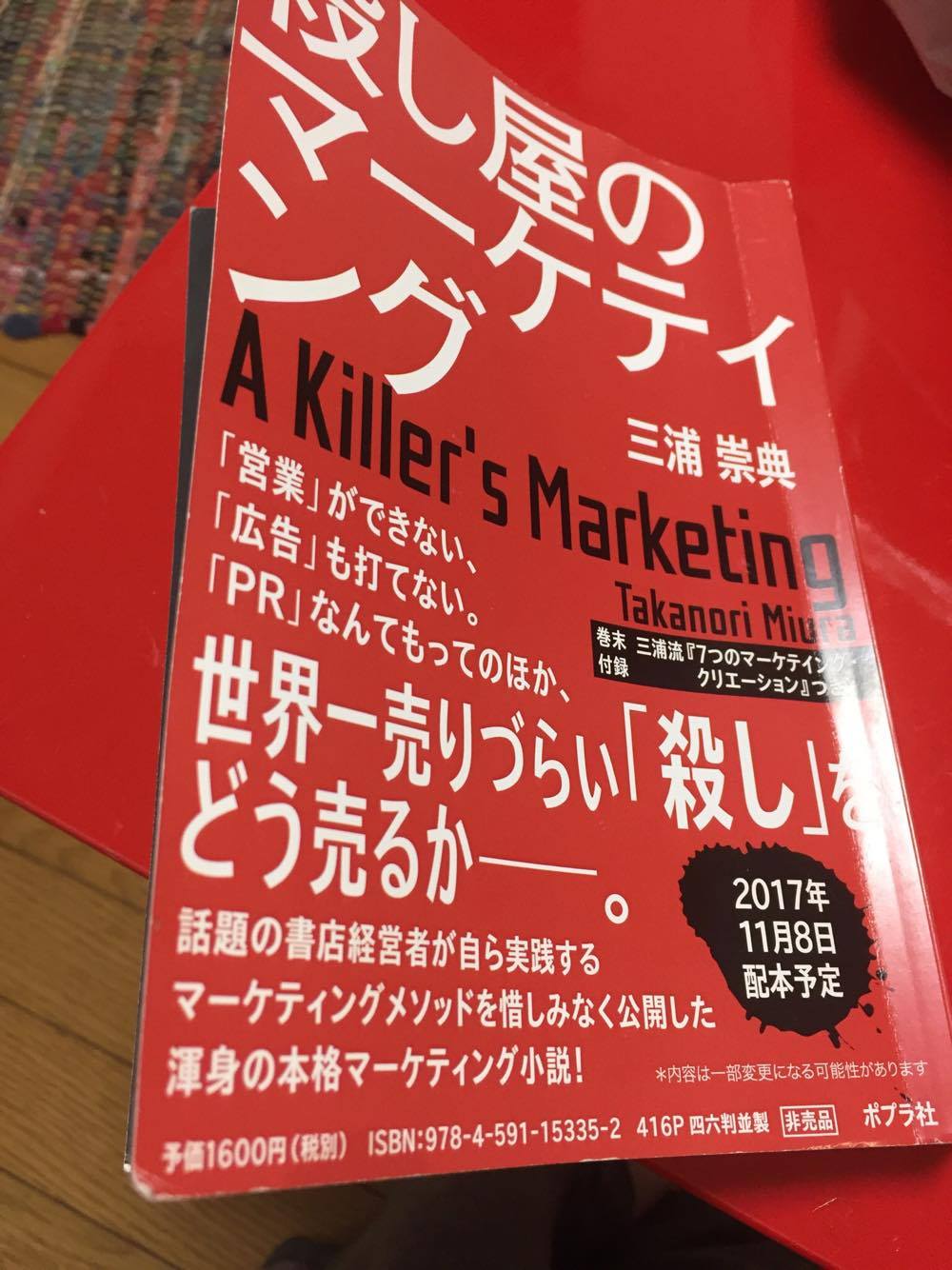恋愛とか結婚に焦っているあなたへ――カツカレーの日《リーディング・ハイ》


記事:西部直樹(リーディング・ライティング講座)
「それで、どうしたいのかな?」
わたしは、ほんのわずかばかり投げやりな思いを匂わせて言った。
俯く彼女を見ながら、返答を待った。
「う~ん、やっぱり、結婚したい」
彼女は顔を上げ、私を見て、断言をした。
「しかし、それは難しいなあ」
わたしは、すこし呆れたようなニュアンスを込めて言った。
「でも、結婚したいんです」
彼女の言い方は、潔かった。迷いはない。
「したいっていっても、結婚は一人じゃできないし……」
「だから、頑張っているんじゃないですか、それを……」
「頑張っているのは、認める。でも、そのがんばりで結婚できるかどうかはわからないよ」
彼女の必死な目を見ながら、どうしたものか、わたしは迷うのだった。
わたしが若かった頃、結婚には3高が条件だと言われたこともある。
高い身長
高い学歴
高い収入
女性たちは、この条件を満たしていない人とは、結婚しないというのだ。
3高を満たした人が、どれだけいるのだろうか。
低い身長――160センチほどしかない。
低い学歴――地方の私大出身だ。
低い収入――食うや食わずだ。
と、その条件をまったく満たしていないわたしは、結婚できるのか、とても不安になったものだ。
が、しかし、である。
3低のわたしも、何の因果か、いまでは二人の子どもがいる。
やれやれ。
連れ合いが、3高を条件にしなかったのか、
あるいは、3低のわたしに3高を凌駕する魅力があったのか、
それは定かではないが……。
わたしが回想にふけっている間に、目の前の女性は、なにか言い募ろうとしている。
「やっと、いい感じの人を見つけたんです。
仕事は安定の公務員だし、真面目だし、趣味は同じ映画なんで、合うし、とっても気を遣ってくれるんですよ」
「それは、いい人なんだね」
「そうでしょう、結婚するなら、真面目で、安定した人がいいし、趣味が違うと面倒だから、同じ趣味の人がいいと思っていたんです。彼はそれにぴったりなんですよ。まあ、ちょっとはっきりしないところがあるけど……」
「条件は、ぴったりですか。はっきりしないところっていうのは?」
「誘うのは、いつも私の方からなんです。押しが弱いというか。一緒にいてくれるんですが、なんかはっきりしないんです」
「そうなんだ、彼がはっきりとした態度を取らないんだな」
「そうなんですよ、結婚したいのかどうなのか……」
「それで、どうしたいの?」
話は、振り出しに戻る。いやはや。
彼女とは、あるイベントで知り合った。
何度か、そのイベントで会ううちに、彼女は婚活中であること、婚活がなかなかうまくいかないことなど、話すとはなしに話され、聞くとはなしに聞いているうちに、相談事になってしまったのだ。
週末の昼下がり、池袋の東口からすぐのビルの中ほどにある、隠れ家のような喫茶店で、わたしたちは向かい合っていた。
彼女はアラサーで、ごく一般的な事務職である。
気がつくと大台に乗り、まわりは結婚した、子供が生まれたという祝い事ばかり、ちょっと焦ってきた、という。
それで、婚活だ。
わたしはごく普通の自営業で、もう還暦も近い。
アラサーの彼女にとっては、叔父さんのようなものだ。
まあ、わたしにとって彼女は、姪のようなものでもある。
彼女は、結婚の理想と結婚相手の条件を並べ、なかなか難しいということを言い続けていた。
しかし、彼女の話を聞くと、結婚に焦るばかりで、何かが欠けているような気がする。
彼女は、そのことに気がついているのか、気づかないふりをしているのか。
わたしはだいぶ投げやりになりつつあった。
「はっきりしない彼と、どうなりたいの?」
「結婚したいんです。彼が一番いいんですよ」
「一番、条件に適っているということ?」
「そうです。あとのは、ちょっとなんだかなんですよ」
「あとのは、というと他にもいるの?」
「キープというか、ちょっと年下で、いい子なんですよ。でも、仕事はフリーナントカだし、本をよく読むんですが、わたしは漫画が好きだし、ちょっとルーズというか、適当なところもあるし、でもね、彼から積極的に誘ってくるんです。でも、条件的には駄目なんで、どうしようかなと」
「はあ、なるほどね。彼と、その年下の彼といると楽しい?」
「楽しいです! 気が合うというかなんというか、話が止まらない感じですね」
「公務員の彼とはどう?」
「結婚したい人のほうは、穏やかですね。映画を見終わったら、静かに語り合うというか」
「静かに語り合う時は、どんな感じ、楽しい?」
「楽しいというか、穏やかですね」
「そうなのか、あのさあ、結婚したいから公務員氏と付き合っているの、それとも公務員氏と結婚したいから付き合っているの」
「え、どっちも同じじゃないですか?」
「う~ん、迷っている君に、ちょっとプレゼントがあるんだ」
わたしは、もしかするとこういう展開になるかも知れない、と思っていた。
婚活に焦る彼女をみて、まわりが見えなくなっているのでは、いや、自分が見えなくなっているのではないか、と思っていた。
しかし、他からいわれても走り出した彼女には届かないかも知れない。
ならばと、カバンから本を取り出し、彼女の前に置いた。
「あら、マンガですか? 『カツカレーの日』って、女性マンガですね。活字はあまり読まないけど、漫画は好きなんですよ」
彼女は、本を手に取り、興味深そうにページを捲る。
「いまの君に、ちょうどいいかなと思ってね」
「どうしてですか?」
「それは、読んでのお楽しみだよ」
「それは、それは……」
彼女は、少し戸惑いながら、微笑んだ。
相談にならない相談を終えて、わたしたちは喫茶店を出た。
後日、彼女から電話があった。メールでもラインでもよかったのに、直接電話をしてきたのだ。
その声は弾んでいた。
・紹介した本 カツカレーの日 西炯子 フラワーコミックス 全2巻
………
「読/書部」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、スタッフのOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
また、直近の「リーディング&ライティング講座」に参加いただくことでも、投稿権が得られます。
【リーディング・ハイとは?】
上から目線の「書評」的な文章ではなく、いかにお客様に有益で、いかにその本がすばらしいかという論点で記事を書き連ねようとする、天狼院が提唱する新しい読書メディアです。