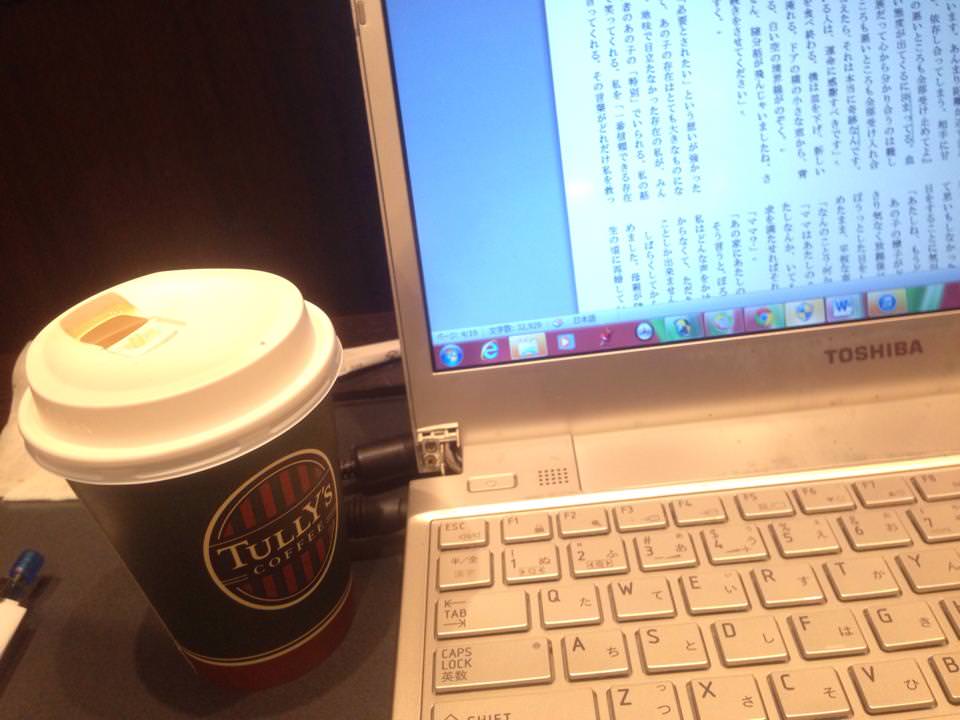書けば書くほど、自分のことが嫌いになった。《川代ノート・雑誌『READING LIFE創刊号』予約受付中》
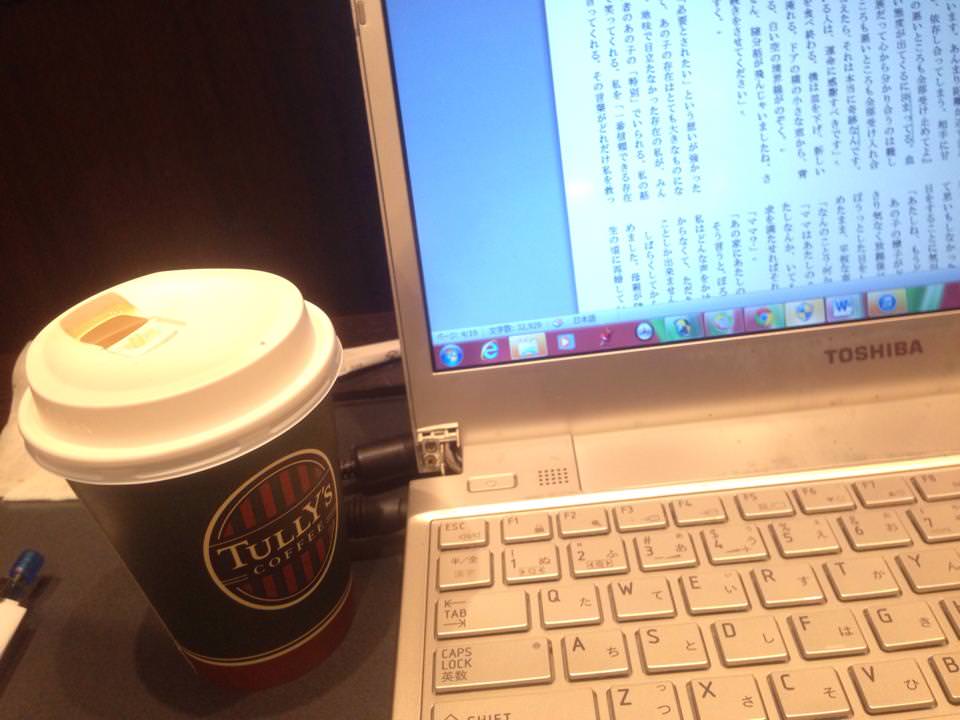
私って何が好きなんだろう。
何をしているときが一番楽しいんだろう。
どんな自分を、心から好きだと言えるだろう。
音楽に、ダンスに、スポーツに、勉強に、国際交流に。大学の同級生みんなが、それぞれに自分の「やりたいこと」を見つけているなか、私には「やりたいこと」がひとつも見つからなかった。
私のことがわからなかった。自分自身を理解しきることが出来なかった。自分の事をわからないということにも気が付いていなかった。本当に心から「やりたいこと」を見つけるのが面倒で、無理矢理なんとなく好きなものを「好き」と言って、その場その場をやりすごしていたのだ。とりあえず目の前に、自分が夢中になるべきものを置いておいて、私がそれに夢中になっているという仮想現実を作り上げた。
それは夢に向かってきらきらと輝いている周りのみんなが羨ましかったからだ。私だけおいて行かれるのが寂しかったからだ。自分ひとりだけがきらきらしていないなんて考えたくもなかった。だからとりあえず、の夢中になれる対象を作って、みんなと同じ「ふり」をした。
そしてみんなと同じがいい、誰にもおいて行かれたくないと恐怖を抱いていながらも、一方で自分は特別な人間なんだと思いたかった。
私は周りの平凡な人間とは違うの。あんたたちみたいに何にも考えていないお気楽な人じゃないの。私は特別。変わってる。人と違うところがある。それを「変」だと言う人もいるけれど。
そう思っていた。さきって変わってるね、とか変なところあるよね、と言われると、そんなことないよお、普通だよ、と言いながらも嬉しそうな顔をしていたのは、間違いなく自分自身だった。非凡でいると認識されることが嬉しかった。その「人とは違うところがある」と意識していることこそが、紛れもなく平凡であるという事実になど一切気が付かずに、自分は特別だと信じ込んだ。
でも心の奥底では気が付いていたのだ。蓋をして見て見ぬ振りをしていただけで、自分には何もないことを知っていた。何も持っていないことを知っていた。何事に対しても情熱を持てないということ。自信が無かった。
何のために大学に入ったんだろう、と何度も思った。私のなかにはどこにも、「熱」なんてものは存在しないのかもしれないと思った。熱を向けられる対象はどこにも無いんじゃないかと思った。
天狼院で、文章を書くようになったのは、今年の6月頃からだった。
文章を書くのはもともと好きだった。作文もどちらかといえばすらすら書ける方だったし、子供の頃から物語を考えるのも好きだったこともあって、ウェブ上で記事を書く、という仕事に、私は強く興味をひかれた。
「潜入捜査官・川代が天狼院書店店主・三浦の本性を暴く」。最初に書いたのはそんな記事だった。お客様にはわからないこと、天狼院の裏側を公開するというものだった。
記事を書くのは面白かった。私の記事を読んでくれたお客様から感想をきくのも面白かった。私はすぐに文章を書く作業にのめり込んだ。
いくつかの記事を投稿してから、店主の三浦に「好きに書いていい」、と言ってもらえるようになった。私は今までに自分が心の奥底で考えていて、でも口にはなかなか出せなかったようなことを思いつくネタから書いていった。
書くたびに、視界が広くなった。目の前の世界がどんどんクリアになっていく。頭の中にもやもやと燻っていることが、具現化される。他人に伝えることが出来る。それが面白くて仕方なかった。
私はもともと口下手で人前では緊張してうまく話せなくなる性質だった。どうしても、伝えたいことをすべて、口頭でわかりやすく説明することができない。言いたいことの半分も伝えられないことがほとんどだった。
もどかしかった。
でも文章では違った。言葉にして書き表せば、私は私自身の世界に入っていくことができる。キーボードを叩くとき、私の可能性は無限に広がっているような気がした。深い海の底にダイブして、すいすいと気持ちよく泳ぐような、そんな感覚。それを味わえるのは、文章を書いているときだけだった。
ああ、「本当にやりたいこと」っていうのは、こういうことなのか。
大学生活も終わろうとしている四年目にしてようやく、私は本当の「好き」を知った。自分が夢中になれるものを知った。それは仮初めの「好き」ではなかった。「何かに夢中になっている自分」に陶酔しているわけでもなかった。
私は本当に、文章を書くのが好き、という、ただの「熱」であり、「狂」だった。書けば書くほど、自分のことがよくわかった。新しい自分に出会うことが出来た。それが面白かったのだ。
でも自分を知るということは、信じられないくらい面白い反面で、とてつもなく苦しい作業でもあった。
どろどろとした感情や、思い出したくない嫌な記憶も深掘りしていく必要があった。目を背けたくなるほど嫌な自分の側面を知ることにもなったし、それ以上知りたくないがために書くのをやめてしまいたくなることもあった。
書いているとき、私は一切の嘘がつけなかった。美しく着飾ることも出来なかった。理想の自分を本当の自分だと勘違いすることも出来なかった。書けば書くほど、自分のことが嫌いになった。
何故なら、書けば書くほど、自分を知れば知るほど、全ての出来事の責任は自分にあるのだと自覚せずにはいられなかったからだ。
今までに苦しかったことや辛かったことや、嫌いになった人や嫌な思い出。そういう記憶をすべて、他人や環境のせいにしてきたのだと気が付かずにはいられなかった。
多くの記事を書く毎に、嫌な部分がひとつ見つかった。でも書かずにはいられなかった。知ることの苦しみよりも、知ることで得る学びや面白さの方が、ずっとずっと大きかったからだ。
「小説、書いてみなよ。雑誌に載せてあげるから」。
店主の三浦にそう言われて、戸惑った。幼い頃に物語を書いていたことはあったけれど、小説なんて書いたことは一度もなかったからだ。
でも挑戦したいと思った。ふと思いついた、想い出があった。
それは自分にとって最も強烈な想い出だった。その出来事が今の私の軸になっているとも言えるようなものだった。
天狼院のウェブではどうしても書けないことだった。それは私にとってあまりにも強烈すぎるということもあったが、思い出すのがあまりにもはばかられるということでもあった。所謂「トラウマ」というやつだ。
だから出来る事なら書きたくはなかった。思い出したくもなかった。でも私が私自身を好きになるには、これを書かずにはいられなかった。私の根幹で、軸の部分を知るためにはその想い出を深掘りするしかなかった。
小説を書く作業は、普通の記事を書くことよりもずっと苦しい作業だった。深掘りし、自分の感情を当時のまま爆発させる必要があった。私はそのとき、完全に当時の自分に戻っていた。
そしてやはり、知ってしまった。「トラウマ」になっていた出来事の責任は、すべて自分にあったのだということを知ってしまった。「あの出来事のせいで」と考えたかった。自分を正当化したかった。だから私はその「嫌な思い出」が必要だったのだ。私の精神を保つために、その「トラウマ」という大義名分が必要だった。
その現実に出会したとき、私は本気で悲しかった。こんなに嫌な人間はいないと思った。私はなんて浅薄で傲慢で自己中心的で不誠実で嘘つきな人間なんだろうと思った。私のことが信じられなかった。
小説は完成した。それは私の心の奥の根幹であり、私自身でもあった。でも最大の反省でもあった。
そして私は気が付いた。「自分自身を嫌いである」と明言することすらも、言い訳なのだと気が付いた。努力しないための言い訳でしかない。かわいそうな自分を守るための、ただの言い訳なのだ。私は、これまですべてのトラウマや想い出や嫌な記憶を、理由付けしてきたことによって、自分を守っていたのだと気が付いた。
小説は苦しいものだった。大好きな作家のように書こうとしてもうまく書けなかった。語彙の無さに絶望した。知識の無さを後悔した。
でもそれでも、私は「今」の私自身を残しておくことが出来た。そして私自身と真正面から向き合うことが出来た。そして「私は自分が嫌いだ」という言い訳をしないという決意も出来た。
私はちっとも特別なんかじゃない。特別になりたかったら、相当の努力をするしかない。その現実とようやく向き合えるようになった。
苦しい。痛い。恥ずかしい。
自分にとっても、そんな思いを抱えてでも、乗り越えたいものがあるのだと知ることが出来た。私がきらきら出来ていたかはわからないけれど、一心不乱になって小説に向き合っていたのはたしかだ。
私にとっては素っ裸になるよりも恥ずかしいものを公開するようなもので、本音で言えばそれをどう評価されるかは恐ろしくてたまらないけれど、それでもここまでやってきて本当に良かったと思う。私の「熱」を、目に見える形に出来て安心した。
雑誌READING LIFEがどうなるかはわからない。そこに確実に存在する「私」が、読者にどんな風にうつるのかわからない。でもこのむき出しの私自身を、多くの人の熱がこもったこの雑誌の一員として迎えてもらえたことに、心から感謝している。
この雑誌が、天狼院にとっての、あらゆる人にとっての「翼」となるように。
私の小説が、どこかの誰かの持つ翼の、少し頼りない「羽」くらいになれるのならば、私はきっと、ああ、嬉しいと声を漏らすだろう。
【雑誌『READING LIFE』予約する際の注意と通信販売について】
雑誌『READING LIFE』編集長の三浦でございます。
『READING LIFE』は3,000部作りますが、造りがかなり複雑になっていますので、最終工程は手作業となっております。それなので、発売日にお渡しできる分の数に限りがございます。確実に手に入れたい方はご予約をおすすめ致します。
また、万が一予約が殺到した場合、予約順でのお渡しとなりますのでご了承くださいませ。
店頭、お電話、メール、下の問い合わせフォーム、Facebookメッセージなど、あらゆる方法で予約受付致します。
雑誌『READING LIFE創刊号』2,000円+税
11月8日(土)10時から発売開始・予約順のお渡し
今回は通信販売も同時に受付開始します。通販での受付も予約受付順の発送となります。PayPalでの決済完了時間が予約受付時間となります。
通信販売の場合、送料・手数料として500円別途頂きますが、その代わりに天狼院書店でご利用頂ける「コーヒーチケット(360円相当)」をおつけしますので、東京に来る際に、ぜひ、天狼院でご利用頂ければと思います。
通信販売分は、11月8日より、予約順に順次発送致します。
《通信販売》
雑誌『READING LIFE創刊号』2,000円+税
送料・手数料 500円(*360円相当コーヒーチケットつき)
11月8日(土)から予約順の発送
【天狼院書店へのお問い合わせ】
TEL:03-6914-3618
【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をして頂くだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。イベントの参加申し込みもこちらが便利です。 

天狼院への行き方詳細はこちら