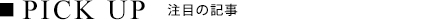

そこはまるで巨大な舞台セットが水に浮かんでいるようような街だった。 想像をはるかにこえる見たことのない景観。 私は一目で恋におちた。 その街の名前はベネチア。
「こんどの週末、愛知県に旅行に行くんだ〜」 もし、友人や知人にそのようなことを言われたらなんと反応するだろう。
少し小ぶりの黒い器が運ばれてきた。待ちきれずに器の中身をのぞき込む。想像していた以上に赤く、こってりとしている。
元気に挨拶、これが一番大事だ。 すーっと息を吸う。行くぞ。毎回何だか緊張する瞬間だ。
朝晩の涼しさが、夏の終わりを告げてきたような、9月上旬のことである。 その日、私は自前のパソコンを持って職場に向かった。
お向かいのお宅は新築で、5年前の11月頃に引っ越してこられた。うちは10月だったからほんの少しだけ早かった。お向かいの完成内覧会の看板を見た時、どんな人が家に入るのかまだわからないし、ちょっと見せてもらおうと思った。
花火大会で、花火の写真を撮ってきた。
悪い夢を見ているようだった。 エアコンの効いた涼しい部屋でPCの画面に向かっているのに、額にじっとりと汗がにじむ。嫌な汗だ。
わたしは、自転車を走らせていた。どこかへ行きたかった。このまま、まっすぐには家へ帰ることができなかった。
「仕事や子育て以外のものがないと、私は死んじゃいそう」 激務と育児の両立で、いつも時間に追われ、由理佳さんは身体も心も疲れていた。
そこそこ器用に仕事をこなし、機転も利いて、情に厚い。 自分をこんな風に評してしまうと図々しいかもしれないけれど、多分、私はそんな人間だ。
「僕は死にましぇん! あなたが好きだから」 これは1991年に放送されたいわゆるトレンディドラマ「101回目のプロポーズ」の有名なセリフだ。
「諦める」というとどういった印象を持つだろうか?
人間は諦めることをあまり善しとしない。 学校では「諦めるな! がんばれ!」と激励され、漫画やアニメの主人公でさえも「諦めなければ夢は叶う!」と、声高に叫ぶ。
「あなたはラーメンを年間どのくらい食べますか?」 とある調査によると、日本人が一年間に食べるラーメンの量はカップラーメンと外食を合わせると30杯近く食べているらしい。つまり月に直すと2~3杯ということになる。
来てほしくはなかったメールがとうとう来た。 予告通りだ。
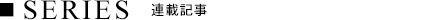
「なんか、私はもう、好きがわからなくなった。好きだった人を気持ち悪いとまで思ってしまうようになったら、わからなくなった。好きってなんなの? どうなったら好きなの?」私の持論であるが、「好きってなんなの?」というワードが出てしまった時点で、こじらせ女子確定なのである。果たして、この世にこじらせ女子はどれくらいいるのだろうか?
たった1時間で仕込んだものが、いつもの食卓をもっとおいしくするとしたら? 味噌や柚子こしょう、干し柿、たくあん、梅干しなど、スーパーに売っている保存食は、自分で作ることができます。日本では「手塩にかける」、韓国では「手の味」という言葉があるくらい、家庭で手づくりすることは、昔から美味しくなるコツだったのです。 時間がない? いえいえ、仕込みは1時間ほど。食べることができるようになるまでに時間がかかるものもありますが、それを待つ時間もドキドキワクワクで楽しいんですよ。 1時間で仕込むコツ、狭いマンションで置くための工夫やお役立ちアイテムなどを紹介しながら、家で簡単に取り組める保存食のつくり方を紹介します。少し時間を作ってぜひトライしてみてください!
「九州の醤油は甘い」と言われます。 確かに九州では、関東圏などと比べると甘味のあるお醤油が好んで使われています。 では、この醤油文化の違いはどのようにして生まれたのでしょう? とても身近な調味料ですが、意外と知らないお醤油のこと。 実は日本で一番お醤油屋さんが多いという福岡県から、奥の深いお醤油の話をお届けします。 普段何気なく買っているお醤油を、いつもとは違うものに変えてみるのは如何でしょう? また新しい味や香りとの出会いが待っているかもしれません。
かつて、人々がまだ純粋で残酷だった時代、そこには天をも統べる広大な大地があった。いくつもの大国が興り、滅び、そして忘れ去られていく。そこでは、生き物の枠を外れた存在だけが、その様を季節の移り変わりのように見続けていた。 この物語は、人ではない何かが、人を愛し、恨み、その果てに破滅を願う、古譚——古き世の物語——である。
「車の街」と言われるように、中部地方は自動車をはじめとする「ものづくり王国」と言われていますが、実は中部地方は自動車産業だけでなく、航空機、陶磁器、繊維などの産業も盛んです。そして、歴史があり、知名度の高い業界トップ企業が多く存在しています。 この連載では、そうした企業の知られざるストーリーや、工場の裏側、ものづくりにかける想いを届け、私たちが普段目にしたり、手にする製品が生まれるまでの努力を伝えていきます。
「トレイルランニング」とは山の中を走る山岳レースです。 その中でも100km以上の距離を走るレースを「ウルトラトレイルランニング」と言います。 おそらくほとんどの人にとって100km走るということは理解ができない行動だと思います。しかも舗装された道ではなく、山の中を走り、完走するのに24時間以上かかることはざらです。
横浜中華街が誕生してから約160年が経ちました。 スタンダードな中華料理から、タピオカに焼き小籠包といったニューフェイスまで、 時代とともに大きく店が変わる中華街。 その中にも、長年変わらず愛され続けるお店やメニューがありました。 外側から見ていただけではわからない、「生き残っていく店の秘訣」は何でしょうか。 もし中華街の「中の人」からの生の声が聞けたら、どんな店を薦めてくれるのでしょうか。 「横浜で生まれ育った華僑4世だからこそ薦める店」を巡っていったら、 素敵な料理と、それを支えた歴史が見えてきました。
声は、印象のおよそ4割をしめるといわれます。自分らしくツヤのある声になりたいと思いませんか。アナウンサーの声がなぜ、よく伝わるようになるのかというと、日々、話している以上に、日々、読んでいるからです。 この記事では、文章を声に出して読むだけで、声だけでなく、話し方や、表現力まで変わるナレーションのさまざまなポイントをお伝えします。 声に出して読めば、伝え方も変わる!「ナレトレ」を、一緒に楽しみましょう!
竜宮城を思わせる造りの片瀬江ノ島駅を降りて、潮風に吹かれながら海岸沿いの道を真っ直ぐ歩くと、大きな建物が見える。 2004年にリニューアルオープンし、湘南・江の島の観光名所としても外すことのできない新江ノ島水族館だ。
ガラパゴス諸島は、珍しい動物が生息する島として知られています。 ダーウィンが進化論を思いつくきっかけになった場所、世界自然遺産第1号としても有名です。 そんなガラパゴス諸島は、生物の教員である私にとって、ずっと憧れの島でした。 2019年8月、コロナ禍直前のタイミングで初めて訪れることができました。見ると聞くとは大違い。現地で知ったこと、驚いたことが沢山ありました。 参加したのは「NPO法人日本ガラパゴスの会(JAGA)」が主催した体験型自然学習ツアーです。JAGA事務局長である奥野玉紀さんと、ガラパゴス訪問49回のベテラン添乗員・波形克則さんがガイドをしてくれたことで、旅の価値は爆上がりになりました。 この得難い体験を、写真を交えてご紹介していきます。 環境保全と観光事業が両立したエコ・ツーリズムのお手本であるガラパゴスの魅力を、ぜひお楽しみください。
ドイツ人の妻である綿島ミリアムさんと、熊本出身の夫である綿島健一郎さんが器づくりをしているのは、「長崎県東彼杵郡波佐見町」という、人口約15,000人の、長崎県では唯一の海なし町である。 そんな波佐見町で陶芸家として活動している綿島夫妻が、2人の工房「studiowani(スタジオワニ)」を構えたのは、わずか3年半ほど前の2017年9月だ。 元々、イタリアンレストランで料理人をしていた健一郎さんと、ドイツの美術大学でプロダクトデザインを学んでいたミリアムさんが、違う分野から、どんなきっかけで器づくりの道へと進むことになったのか? なぜ、陶芸の場所として、出身地ではない「波佐見」を選んだのか? 自然豊かな町で育まれた400年の歴史のある波佐見焼という伝統工芸の中で、独自の道を切り開いていく夫妻の姿を追ってみたい。
神奈川有数の観光スポットである鎌倉は、文学の街でもあります。その由来は、多くの作家や文学者が移住をしてきたことにあります。 その鎌倉に所縁のある作家・文学者のエピソードを鎌倉文学館館長であり、文芸評論家としても第一線で活躍している富岡幸一郎氏にお話を伺い、皆さまにお伝えをする企画です。 是非、鎌倉で文学の香りを味わってください。
湘南って、海でしょ? 湘南って、レジャーでしょ? そんなことはない。 湘南って、見た目ほどチャラチャラしてはいないのです。 湘南だけど、野菜を作っている。 湘南だけど、土に根付いた暮らしがある。 しっかりと、そこには、生活が息づいているのです。
2020年春、ついに屋久島に移住しました。 大学の仕事があるパパを東京に残して、私と子供たちだけが屋久島に引っ越し、屋久島での暮らしが始まったのです。 目の前は海、後ろは山、亜熱帯の木々に囲まれた大自然の中で暮らす日々。 子供たちも地元の小学校や保育園に通いはじめ、わたしも自然の中に生まれた知恵や伝統文化に触れ、四季折々の集落行事に少しずつ関わり始めました。
人生100年時代と言われる時代になりました。 世界一の長寿国である日本人は、女性で89歳、男性で81歳が平均寿命といわれているぐらい、日本人の人生は長くなりました。 50歳はその中間地点。 それまでの50年食べてきたもので、これからの残り50年の生き方が変わります。 あなたは、どんな食べ物を、どんな風に食べてきましたか?
「連立方程式」「平方根」「三平方の定理」…… 中学校の数学で習う単元。 「いったい何の役に立つの?」「必要ないし、使わないし」一度は口にしたことがある人もいるのではないだろうか。そして結局の所、やっぱり何の役に立つのか、必要なのか、いつ使うのか……? 30歳に数学の免許を取り、そこから現役の中学生教師である筆者が、日々中学生と接し、授業をしながら数学について感じたことを徒然と書く。教材研究や、授業を通して、数学が世の中でどう役に立っているのか、はたまた役に立っていないのか? 難しい数式や考え方はなし。 みんなが経験した中学数学の各単元はいったい何だったのか? を考えていく数学エッセイ!
「ママであろうと、関係ない!」 アラフォーの子持ち主婦だったライター・ギール 里映。「私、このままでいいのかな」という不安に襲われ、一念発起して起業。 なぜ、「起業」という選択をしたのか? どうやって事業を伸ばしてきたの? 「ママ起業」のリアルって? 自分がやりたいことをやるのに、性別も、肩書も関係ない! ライター自身の経験をもとに、「ママ起業」のエッセンスをお届けします!
子どもが1歳のときに、定期検診で言葉の発達に遅れあるかもと医者に言われた。検査とは発達障害の傾向があるかをみるものである。 検査の結果「発達障害グレー」と診断をうけた。 発達障害の子どもにもつ親に会ったり、 成人を迎えた発達障害の当事者に会ったり、 療育サービスを提供している人たちに会ったりして、 これから我々のような親子が落ちうる穴を聞いていって、先人たちの失敗談から反省点を抜き出して、うちの家庭に当てはめ実践していったところ、家庭も子どももとても落ちていった。 その経緯を書いていきたい。
コミケ=コミックマーケットがその存在を知られるようになってから久しい。だがその実態は、時たま驚嘆する一場面だけがニュースなどで取り上げられ、実情は把握しにくい状態にある。そう言った状態だが、コミケに興味が湧き、自らも行ってみたいと思う人々は増えてきているはずだ。
スマホがあればいつでもどこでも映画が観られる時代。 そんな中私たちは一体どうして、劇場まで足を運び、2000円近いお金を払い、暗闇に2時間も拘束されてまで映画を観るのだろう?
時代は令和である。 都内をラッピング電車が走り、コンビニでキャラクターファイルが配られ、人々はアニメーション映画に夢中になる。そんな時代である。
インターネットが普及してスマホなどのガジェットを使う人が増えてきた。筆者の若い頃はパソコンが家に一台あれば進歩的だったが、今はひとり一本あるいはそれ以上スマホを持ち歩いているのが当たり前。
さあさあさあ、どうぞ一席お付き合いください。こな落語の開演でございます。
京都は先斗町の路地裏に、食べるだけで人生が変わる割烹があるらしい──
まっすぐな恋愛って何ですか?
天狼院書店店主・三浦による、公式の「天狼院通信」です。
天狼院書店スタッフ川代が綴る「川代ノート」は、女子の本音を綴ります。
「宇宙一わかりやすい科学の教科書」は、増田明氏による寄稿記事です。 どこよりもわかりやすく丁寧に、科学のひみつをお伝えします。
大人なら知っておきたい「お酒」についてのお勉強、はじめてみませんか?
「死にたてのゾンビ」というワードをきいたとき、何を思い浮かべますか?
店主三浦が「ワークトリップ」として利用した宿と、仕事の記録。
人は狂に酔いしれ、狂に踊る。
東京から日帰りで、非日常な景色と体験、食を愉しむ旅ガイド
おっさんがおっさんを借りてみた!
アプリやソフト、Webサービス……。初心者でも普段使いできるよう、わかりやすく丁寧に解説!
下関在住ライター・安光伸江が、両親から相続した資産で株や国債、外貨預金などに挑戦していくさまを現在進行形で描く投資レポート!
近未来の日本で、最新科学技術で作り出した自分そっくりのアンドロイドを使用する人たちの群像劇。
京都天狼院書店の大学生アルバイトスタッフが贈る書店員物語。一冊の本が、あなたの心に鮮やかな絵を描いてくれるかもしれません。
「滋賀にはものすごく臭い“すし”があるらしい」鮒ずし愛、滋賀県愛に溢れた熱狂レポート!
1964年の東京オリンピックを体験したあの頃の記憶を、2020年を盛り上げる世代へ届ける。
近未来の日本で、最新科学技術で作り出した自分そっくりのアンドロイドを使用する人たちの群像劇。